- 定義
- 栃木県の北東部に位置する広大な平地とそれに続く、ゆるやかな丘陵・高原をいいます。
- 広義には、箒川以北、福島県境までの山地を除いた地域の約7万haです。
- 狭義には、このうちの南半分の箒川と那珂川に挟まれた木の葉形の地域の約4万haです。
- このうち明治初年までは那須東原、那須西原と言われた約1万haの広漠たる原野がありました。
- 歴史への登場
- 鎌倉時代の「吾妻鏡」で初めて文献に登場
建久4年(1193年)4月、那須野ヶ原一帯において、時の将軍源頼朝による大規模な巻狩が行われました。
「もののふの矢並つくろう籠手のうへに霰たばしる那須の篠原」
(源実朝…「金槐和歌集」) - 江戸時代
- 那須野ヶ原一帯は、主に、黒羽藩、大田原藩及び幕府領に属し百数十の村が散在していました。
地域の飲用水や新田開発のため蟇沼(ひきぬま)用水などが開削されました。 - 那須東原・那須西原(約1万ha)の大半は村々の入会まぐさ場として利用され、毎年春先に焼かれたために、広漠たる原野でした。 ―― 明治の開拓の舞台。
- 明治の開拓 ―― 大農場の展開と那須疏水
- 地域の飲用水、かんがい用水確保のため那須疏水本幹水路(約16km)が1日当たり100mという驚異的なスピードで開削され(明治18年)、大農場の展開を支えました。
- 明治新政府の殖産興業政策に沿って、那須東原・西原の原野を中心に華族や民間有志による大農場が展開されました。
- 大農場の先がけ(明治13年)
肇耕社(ちょうこうしゃ)
(約1000ha)―― 三島通庸の指導による華族農場第1号
―― 後に三島が引き継ぎ三島農場那須開墾社(約3400ha) ―― 印南丈作・矢板武ら民間有志による
―― 後に松方正義の千本松農場などに分割引き継がれる - その後
- 大農場の一部は大正から昭和10年代にかけて、残りのほとんどの戦後に解体
千本松農場 ―― 約800haが今にその面影を残しています。 - 那須疏水は、昭和40年代に着手した国営那須野原開拓建設事業により全面改修され、約4300haの農地を潤しています。
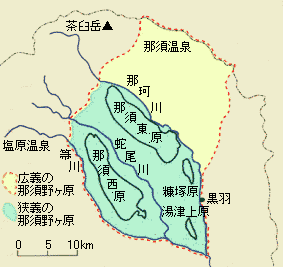
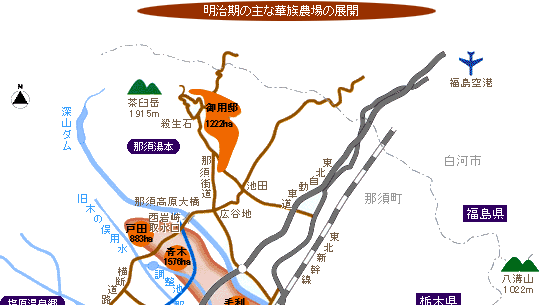 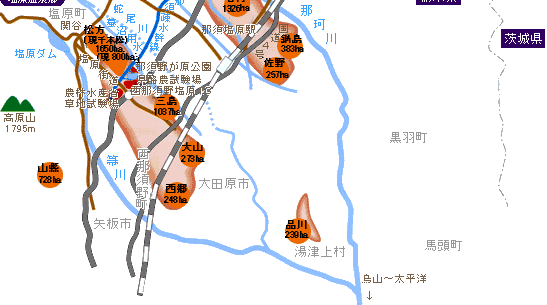 |
| 明治 | 農 場 | 開 設 者 | 爵位 | 代表的地位 | 面積(約ha) | ||||||||||
| 14 年 |
|
佐野 常民 青木 周蔵 (大山・西郷) 大山 巌 西郷 従道 |
伯 子 公 侯 |
農商務大臣 外務大臣 陸軍大臣 海軍大臣 |
| ||||||||||
| 16 | 傘松農場 | 品川弥二郎 | 子 | 農商務大臣 | 257 | ||||||||||
| 18 | 毛利農場 | 毛利 元敏 | 子 | 旧豊浦藩主 | 1326 | ||||||||||
| 19 | 三島農場 | 三島 道庸 | 子 | 警視総監 | 1037 | ||||||||||
| 20 | 戸田農場 | 戸田 氏共 | 伯 | 旧大垣藩主 | 883 | ||||||||||
| 21 | 千本松牧場 | 松方 正義 | 公 | 総理大臣 | 1650 | ||||||||||
| 26 | 鍋島農場 | 鍋島 直大 | 侯 | 旧佐賀藩主 | 383 | ||||||||||
隣接地
| ||||||
| 出典「那須野ヶ原開拓のあらまし」(磯 忍氏著) |