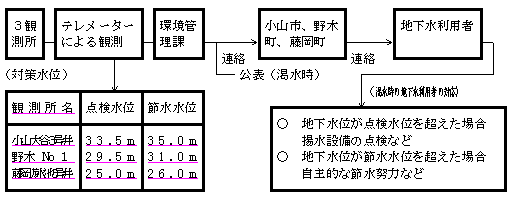トップ > 環境 > 環境保全・温暖化対策 > 環境保全 > とちぎの環境 > 計画・報告書等(環境資料アーカイブ) > 環境の状況及び施策に関する報告書(環境白書) > 平成12年度環境の状況及び施策に関する報告書(要約)
土壌環境・地盤環境保全対策
| 1 土壌環境保全対策 | |||||||||||||||||
(1) 農用地土壌保全対策 農用地に使用される再生有機質資材(特殊肥料)については、「肥料取締法」により規制値が設定されています。 (2) 土砂等適正処理事業 平成11年4月施行の「土砂等の埋め立て等による土砂の汚染及び災害の防止に関する条例」に基づき、県内に行ける土砂等の埋め立ての適正処理を推進します。 (3) 土壌環境調査 平成11年度に引き続き、「土壌環境保全実態調査」を実施します。
|
|||||||||||||||||
| 2 地盤沈下対策 | |||||||||||||||||
(1) 経 過 昭和62年3月、栃木県公害対策審議会から、「地盤沈下の基本的施策について」次の主旨の答申が出されました。
地盤沈下防止の総合的な対策を講じるため、平成3年、国が本県南部地域(13市町)を含む関東平野北部を対象に「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」を策定しました。
地盤沈下対策は多岐にわたることから、平成9年度に庁内関係各課室から構成する「地盤沈下対策検討会」を設置し、地下水利用者への地下水保全意識の啓発、観測体制の充実など連携を図りながら地盤沈下対策の推進に努めています。 (2) 対策の現状
図2-2-3 地盤沈下の情報提供のフロー(概要)
|