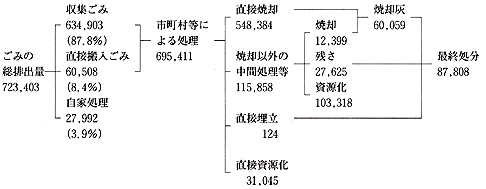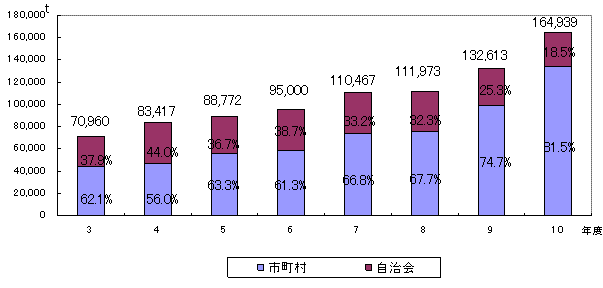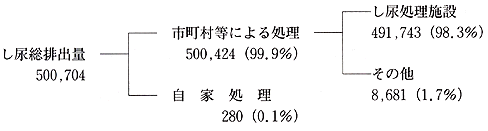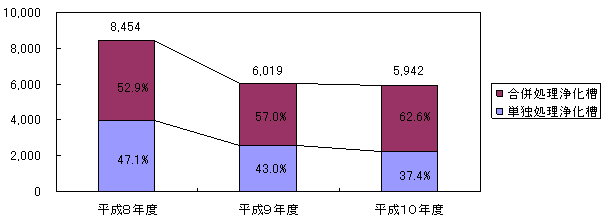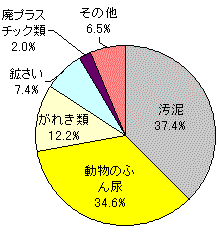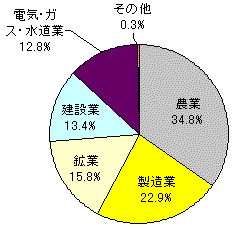トップ > 環境 > 環境保全・温暖化対策 > 環境保全 > とちぎの環境 > 計画・報告書等(環境資料アーカイブ) > 環境の状況及び施策に関する報告書(環境白書) > 平成12年度環境の状況及び施策に関する報告書(要約)
廃棄物・リサイクルの状況
| 1 一般廃棄物処理の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) ごみ処理 ごみの総排出量は、年間約72万3千tにのぼり、自家処理される約2万8千tを除く約69万5千tが市町村等により処理されています。(図2−5−1) 図2−5−1 ごみ処理の状況(10年度) (単位:t/年) 市町村等がごみ処理に要した年間の経費は、総額約326億円でした。 (2) リサイクルの状況 ごみのうち、資源化が可能なごみは、次のとおり年間16万4,939tがリサイクルされており、リサイクル率は22.7%となっています。 表2−5−1 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量(10年度)(10年度、単位:t/年)
図2−5−2 資源回収の状況
(3) し尿処理 平成10年度に収集されたし尿及び浄化槽汚泥の量は50万0,424kLで、このうち49万1,743kL (98.3%)が市町村の設置するし尿処理施設で処理されました。(図2−5−3) 図2−5−3 し尿処理の状況(10年度) (単位:kL/年)
し尿処理に要した年間の経費は総額約61億円でした。 (4) 浄化槽の設置状況 浄化槽による水洗化も進み、毎年6〜8千基程度の浄化槽が設置されています。 図2−5−4 新設浄化槽設置状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 産業廃棄物処理の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) 排出量 県内における10年度の推計総排出量は、年間約650万tです。 図2−5−5 栃木県内から排出された産業廃棄物の推計量(10年度) (種類別)
(業種別)
(2) 処理の状況 県内で排出された産業廃棄物で、処理業者が委託を受けて処理処分した平成10年度の総量は、約118万4千tです。 (3) 再生利用の状況 排出事業者及び産業廃棄物処理業者は、それぞれの立場において産業廃棄物の減量化、安定化、安全化及び再生利用の努力を重ねているところです。 (4) 産業廃棄物処理施設設置状況(宇都宮市許可分を除く) 平成4年7月4日施行の法律改正により許可制となった「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設の設置数は223施設、その他の産業廃棄物の処理施設(施行令第7条各号に該当しない施設で、かつ処理業者が設置した施設)は200施設であり、総数は423施設となります。 (5) 産業廃棄物処理業の許可状況 産業廃棄物の収集・運搬、中間処理(焼却、乾燥等)及び最終処分(埋立)の業を行おうとする者は、知事の許可を受けなければなりません。 表2−5−2 産業廃棄物処理業者の許可状況
(注)1 「県内」とは、主たる事務所が県内にある処理業者をいい、それ以外を「県外」という。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||