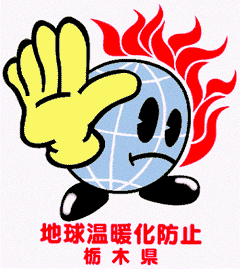|
(1) 地球温暖化対策地域推進計画の策定
県では、12年(2000年)3月、本県の地球温暖化対策を計画的、総合的に推進するため、「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」を策定しました。
この計画では、県内の温室効果ガスの排出実態と排出特性を踏まえ、本県の温室効果ガスの削減目標を掲げるとともに、その目標を達成するための県の施策と、県民、事業者及び行政の各主体が地球温暖化防止に向けた取組を実践する際の行動指針を具体的に示しました。
削減目標は、「22年度(2010年度)における本県の温室効果ガスの排出量を、2年度(1990年度)に比べ6%削減する」こととしましたが、これを達成するには22年度の排出量を約1,500万トンに抑制する必要があります。
12年度には、従前からの各種対策に加え、地球温暖化防止キャンペーンとして、「地球温暖化防止対策推進シンボルマーク及びキャッチフレーズの募集」と「地球温暖化防止ラジオキャンペーン」を実施しました。
|
ア 地球温暖化防止対策推進「シンボルマーク」及び「キャッチフレーズ」の募集
|
|
「地球温暖化防止月間」をはじめとした県が行う各種の啓発事業において活用する「シンボルマーク」及び「キャッチフレーズ」を一般に募集したところ、シンボルマーク
375点、キャッチフレーズ(高校生以上の部)1,309点、同(小中学生の部)79点の応募がありました。
応募作品の中から、次の作品を最優秀賞として採用し、啓発パンフレット等に印刷するなどの活用を図っています。
|
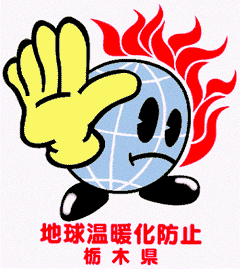
地球温暖化防止対策推進「シンボルマーク」 |
キャッチフレーズ(高校生以上の部)
|
| キャッチフレーズ(小中学生の部)
|
|
イ 地球温暖化防止ラジオキャンペーンの実施
|
|
地球温暖化問題について県民意識を高め、環境に配慮したライフスタイルへの転換を図るため、特に20歳代を中心とする青年層向けに20秒間のFMラジオスポットCMを、地球温暖化防止月間である12月に20日間にわたり合計120回放送しました。
|
(2)
栃木県庁環境保全率先実行計画の推進
県は、県の事業者・消費者としての立場から自らの活動による環境への負荷を低減するため、9年度に「県の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組のための行動指針」を策定し、全庁的な取組を行ってきました。
一方、国においては、10年10月に「地球温暖化対策推進法」を制定し、国、地方公共団体、事業者、国民の自主的、積極的な温暖化対策を推進することとしました。
本県においてもこれを受け、これまでの取組をさらに強力に推進するため、12年3月に「栃木県庁環境保全率先実行計画」を策定しました。
こ の計画は、県自らが行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、温室効果ガスの排出抑制などについて率先して行動することとしており、県のすべての組織が行う事務・事業(病院、企業庁、県立学校、警察を含みます。)を対象としています。
計画期間は、12年度から16年度までの5年間とし、計画の推進に当たっては、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の考え方であるPDCAサイクルを導入し、環境の継続的な改善を行うこととしています。
12年度は、計画の初年度として「電気使用量を抑制する」、「廃棄物の減量化に努める」を全庁重点取組事項として温室効果ガス削減の取組を行いました。
また、地球温暖化を防止するための具体的な取組について解説した職員啓発用のパンフレットを作成し、全職員に配布して取組の浸透を図りました。
表4−1 計画に掲げる数値目標
|
項目 |
目標及び目標値 |
| 電気使用量 |
庁舎等における単位面積当たりの電気使用量を7%削減する。 |
| 水道使用量 |
庁舎等における単位面積当たりの水道水使用量を5%削減する。 |
| 庁舎燃料使用量 |
庁舎等における単位面積当たりの燃料の使用量を5%削減する。 |
| 用紙使用量 |
コピー用紙・印刷機用紙の総使用枚数を10%削減する。
印刷物を含めた用紙の古紙利用率を90%以上とする。 |
| グリーン購入の推進 |
常用物品に占める環境配慮型製品の購入率を70%以上(金額ベース)とする。 |
| 公用車燃料使用量 |
公用車燃料の総使用量を10%削減する。 |
| 廃棄物 |
庁舎等からのごみの排出量を20%削減する。 |
| 建設副産物 |
建設廃棄物の利用率を94%、建設発生土利用率を90%とする。
(目標年度 17年度) |
また、これらの取組を行うことにより、温室効果ガスを次のとおり削減することとしています。
|
県の活動による温室効果ガスの総排出量を6%削減する。
温室効果ガス総排出量(二酸化炭素換算)
10年度 59,883トン → 16年度 56,300 トン(約3,600トンの削減) |
(3)
エコライフ推進事業の実施
二酸化炭素の削減など地球環境保全に関する問題について、消費者が環境家計簿の記入を通し、消費生活面から環境保全を考え、地球環境にやさしいライフスタイルの確立を支援するための講座等を実施しています。
13年度は、「地球にやさしい生活講座」と「省資源・省エネルギー交流研修会」を実施し、消費者の地球環境にやさしいライフスタイルの確立を支援していくこととしています。
|
ア 地球にやさしい生活講座
|
|
各種広報を通して一般県民から受講生を募集し、8回の講座(うちスクーリング3回、通信講座5回)を実施しました。(12年度受講生36名)
13年度も28名の受講生に対し、6回の講座を実施します。
|
|
イ 二酸化炭素(CO2)体験講座
|
|
消費生活センターにおいて、二酸化炭素の視認等を簡易な実験により実施し、二酸化炭素削減の意識づけを図りました。
13年度も要望に応じて実施することとしています。
|
|
ウ 省資源・省エネルギー交流研修会(エコライフフォーラム)
|
|
省資源・省エネルギーや地球温暖化防止等の環境問題について、エコライフネットワーク「とちぎ」と共催により、一般県民を対象として講演やエコライフ啓発展等を通し啓発を行いました。
13年度も同様に、エコライフネットワーク「とちぎ」・栃木県コミュニティ協会との共催で研修会を開催します。
|
|
エ ルリちゃんのエコカレンダーの配布
|
|
地球温暖化防止のためのエコライフスタイルを定着させるためにルリちゃんのエコカレンダー2001年度版を3,000部作成し、県民に配布しました。
|
|
オ エコライフネットワーク「とちぎ」の活動充実と支援
|
|
地球環境に負荷の少ない永続性のある生活(エコライフ)を、県民、団体、企業、行政等が一体となり広く普及し、全県的に確立することを目的として設立されたエコライフネットワーク「とちぎ」に対し、各種啓発事業を実施するための支援を行いました。
|
|
|
(1) 地域新エネルギービジョンの策定
我が国は、エネルギーの8割以上を輸入に依存するとともに、その約6割を石油に依存しており、石油をはじめとするエネルギーの安定供給の確保や石油依存度の低減等の努力が求められています。
また、我が国の温室効果ガスの約9割を占める二酸化炭素のうち、約8割以上が石油をはじめとした化石エネルギーに起因していることや、9年12月の「地球温暖化防止京都会議」の結果等を踏まえると、エネルギー施策における環境対策は必要不可欠な状況となっています。
これらの課題に対応するものとして、近年、太陽光発電や風力発電、廃棄物発電等の新エネルギーが注目されています。(表4−2)
本県では、こうした新エネルギーの導入促進を図るため、13年3月、本県におけるエネルギーの需給構造の実態や地域特性、各種の新エネルギーに関する現状と課題を把握した上で、行政、県民、事業者が新エネルギーを導入する際の指針となるものとして「栃木県地域新エネルギービジョン」を策定しました。
ビジョンでは、国の目標に準じ、本県の自然的、社会的地域特性を踏まえ、2010年度における新エネルギーの導入見通しを設定しました。(表4-3)
また、本県の各新エネルギーの利用可能量や導入適性、技術動向等を考慮し、「重点的に導入を図るエネルギー」として、太陽光発電、太陽熱利用、クリーンエネルギー自動車を位置づけました。
表4−2 新エネルギーの種類
|
再生可能エネルギー
|
| 太陽熱利用 |
| 太陽光発電 |
| 風力発電 |
| 温度差エネルギー |
| 中小水力発電 |
| 地熱エネルギー |
| |
リサイクルエネルギー
|
| 廃棄物発電 |
| 廃棄物熱利用 |
| 廃棄物燃料製造 |
| その他排熱利用 (工場排熱等) |
| バイオマスエネルギー |
| |
従来型エネルギーの新利用形態
(広義の新エネルギー)
|
| 天然ガスコージェネレーション |
| 燃料電池 |
| クリーンエネルギー自動車 |
|
表4−3 栃木県の2010年における新エネルギー導入見通し
新エネルギーの種類 |
導入見通し |
現状値 |
太陽光発電 |
95,000kw |
1,792kw |
太陽熱利用 |
85,500kl |
不明 |
クリーンエネルギー自動車 |
71,100台 |
406台 |
廃棄物エネルギー(廃棄物発電) |
22,900kw |
0kw |
風力発電 |
1,800kw |
6kw |
中小水力発電 |
231,300kw |
222,580kw |
バイオマスエネルギー |
22,200kl |
0kl |
その他排熱利用(工場排熱) |
36,000kl |
不明 |
天然ガスコージェネレーション |
18,300kw |
1,860kw |
燃料電池 |
44,000kw |
200kw |
(2)
新エネルギーの率先的導入
県民や事業者の新エネルギーに対する理解を促進するため、県が率先して太陽光発電施設やクリーンエネルギー自動車などの新エネルギーを導入することとしています。
|