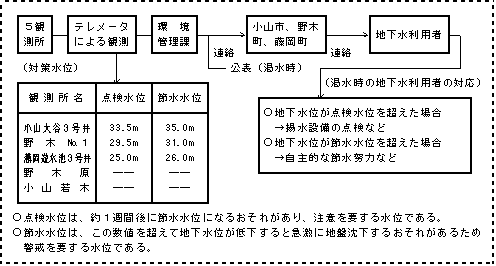|
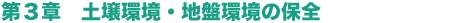
(1) 土壌汚染対策
15年2月施行の「土壌汚染対策法」に基づき、特定有害物質による土壌汚染の対策を推進する。
17年度は、昨年度に引き続き特定事業場に対する「土壌汚染対策実態調査」(15年度実施)を基に「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に新たに規定された土壌の汚染の未然防止のための施設等の構造や管理の基準を遵守することを含め、特定有害物質の適正管理等を立入検査時や講習会等により周知指導し、事業者の自主的な対策を進めていく。
(2) 農用地土壌保全対策
「土壌機能モニタリング調査」を実施して、県内農用地土壌における重金属等の含有量など、土壌の実態を正確に把握していく。
(3) 土砂等適正処理事業
11年4月施行の「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づき、県内における土砂等の埋立ての適正処理を推進する。
(1) 経 過
昭和62年3月、栃木県公害対策審議会から「地盤沈下の基本的施策について」答申が出された。これを受けて、2年12月に県南県央地域の16市町を対象とした「栃木県地下水採取の届出に関する指導要領」を策定した。
5年7月には「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」を策定し、対象地域を県内全域に広げるとともに、一定規模以上の施設について事前協議制を導入した。その後、同要綱は8年7月及び16年2月に一部が改正され、現在に至っている。
一方、国は地盤沈下防止の総合的な対策を講じるため、3年に県南部地域(13市町)を含む関東平野北部を対象にした「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」を策定した。
同要綱においては、本県の対象地域は、以下のように区分されている。
| 保全地域 |
地下水採取に係る目標量を設定し、その達成のための措置を講じる地域 |
小山市の一部、野木町、藤岡町 |
| 観測地域 |
観測及び調査等に関する措置を講ずる地域 |
足利市、佐野市佐野地区、小山市の一部、真岡市、上三川町、南河内町、二宮町、石橋町、国分寺町、大平町、岩舟町 |
地盤沈下対策は多岐にわたることから、9年度に庁内関係各課室から構成する「地盤沈下対策検討会」を設置し、地下水利用者への地下水保全意識の啓発、観測体制の充実など連携を図りながら地盤沈下対策の推進に努めている。
(2) 対策の現状
ア 本県における対策
地盤沈下が懸念される小山市・野木町・藤岡町において、迅速な対策を図るため、地下水位及び地盤沈下の状況をテレメータシステムによりリアルタイムで観測している。
テレメーターを設置している観測所は、小山大谷、野木№1、藤岡遊水池、野木原、小山若木の5か所で、このうち、小山大谷、野木№1及び藤岡遊水池の観測所において観測した地下水位が対策水位(点検水位・節水水位)を超えた場合、「小山市・野木町・藤岡町地盤沈下防止連絡協議会(11年3月設立)」の地下水利用者に対し、点検要請・節水要請を行っている。(図2-3-3)
16年度は、地下水位が野木1号観測井及び小山3号観測井で点検水位を超えて低下したため、7月7日から野木町、7月13日から小山市の地下水利用者に対して点検要請を行った。その後も、野木1号観測井では地下水位の低下傾向は続き、節水水位を超えて低下したため、7月15日に点検要請を節水要請に切り替えた。点検要請、節水要請は、地下水位が回復傾向を示した9月2日まで継続させた。
県民の生活水準の向上や産業の進展に大きく貢献している貴重な水資源である地下水を、将来にわたり有効かつ適切に保全、利用するため、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、県内全域を3地域に分割し、揚水機の規模に応じて届出を提出させ、地下水の採取量、揚水機の規模など、適正な施設となるよう指導している。
特に、同要綱のA地域においては、大規模地下水採取者に対して、事前協議制度により、節水や代替水源への転換等の指導を行っている。
図2-3-3 地盤沈下の情報提供のフロー(概要)
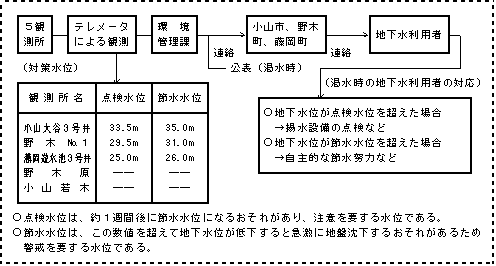
イ 国における対策
国土交通省は、17年3月に「地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡会議」を設置し、現在の地盤沈下状況等の確認、これまでの地盤沈下防止の取組等について検討を行った結果、今後とも「関東平野北部地盤沈下対策防止等対策要綱」の取組を継続し、地盤沈下防止等の総合的な対策を推進することとした。
|