|
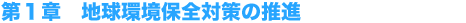
私たちを取り巻く地球の環境は、一方では人間の活動に対し原材料を提供し、また一方では人間の活動から出る不用物や汚染物質を受け入れて同化する役割を果たしてきた。ところが、人間の活動が急激なスピードで拡大した結果、環境から多くの物質が資源として利用され、他方では、容易に分解されない汚染物質が環境へ捨てられるなど、地球の環境にも大きな影響が現れて、地球環境問題として認識されるに至った。
地球環境問題には様々なものがあるが、典型的なものとしては次の9つがある。
①地球の温暖化 ②オゾン層層の破壊 ③酸性雨
④森林(特に熱帯林)の減少 ⑤野生生物の種(生物多様性)の減少
⑥砂漠化 ⑦海洋汚染 ⑧有害廃棄物の越境移動
⑨開発途上国における環境問題
地球環境問題は60年代から本格的な議論が始まっていたが、4年(1992年)に世界の首脳レベルが集まり「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」が開催され、「持続可能な発展」を実現するための21世紀に向けた具体的な行動計画として「アジェンダ21」を採択して、以後の地球環境問題への取組の出発点となった。また、この年には、地球温暖化を防止するための「気候変動枠組条約」と生物多様性を保全するための「生物多様性条約」が採択され、すでに採択されていたオゾン層保護のための「ウィーン条約」等と併せて地球環境問題に対処するための主要な国際的枠組が整備された。
9年(1997年)12月に、京都で開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において、先進国の温室効果ガスの削減目標を定めた「京都議定書」が採択され、13年(2001年)11月のモロッコのマラケシュでのCOP7 では、その運用細則が決定(マラケシュ合意)された。これを受け、我が国でも、14年6月に「京都議定書」の締結を閣議決定し、国連に受諾書を寄託した。
17年(2005年)2月には、ロシアが京都議定書を批准したことにより、京都議定書が発効した。
我が国でも、地球サミット以降、地球環境保全の取組が活発になってきた。5年(1993年)には、それまでの国内の公害対策を目的とした「公害対策基本法」に変わって、地球環境保全も含め、より総合的に環境対策を行うための「環境基本法」が制定された。
10年(1998年)10月には、「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」が制定され、その中で、地球温暖化対策のための国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれの責務が明確化された。この法律において、国と地方公共団体は、自らの事務・事業について温室効果ガスの発生抑制のための実行計画を策定し、公表することとされている。
さらに、14年(2002年)3月には「地球温暖化対策推進大綱」の改訂、同年6月には「地球温暖化対策推進法」の改正を行い、17年(2005年)2月の京都議定書発効に受けて、同年4月に「京都議定書目標達成計画」を策定した。
オゾン層保護については、昭和63年(1988年)5月に制定された「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」により生産規制が行われてきたが、13年(2001年)6月には、業務用冷凍空調機器及びカーエアコン中に含まれる冷媒用フロン類の廃棄時の回収・破壊を規定した「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定された。
この法律では、フロン類の大気への放出が禁止されており、フロン類の回収・破壊は、都道府県等に登録されたフロン類回収業者等及び国の許可を受けた破壊業者により、適正に実施されることとなった。
|