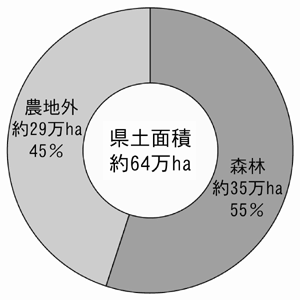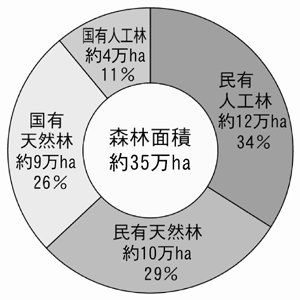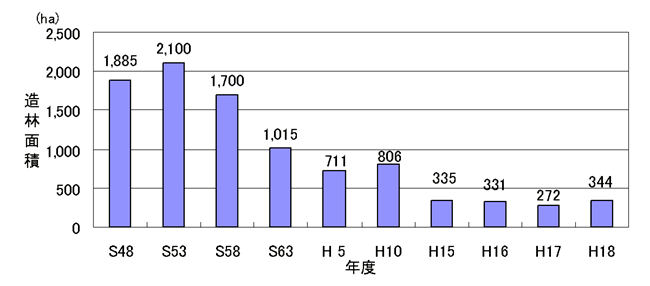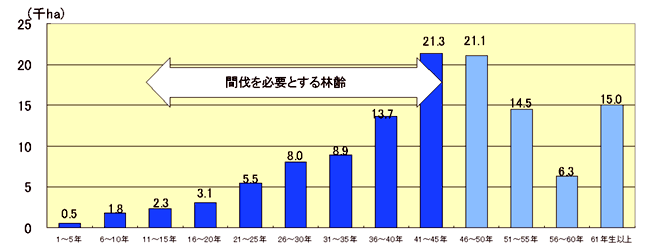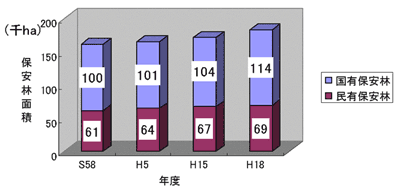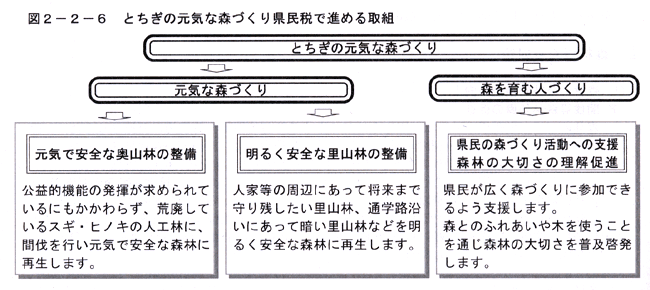|
�@�������́A���R�̒����琶���邽�߂ɕK�v�ȋ�C�␅�A�H���Ȃǂ̕����I�Ȍb�݂Ă������ł͂Ȃ��A���R�ɐڂ����Ƃ��Ɋ�������炬�⏁���Ȃǐ��_�I�ɂ��傫�Ȍb�݂��Ă���B
�@���̎��R�̌b�݂������ɂ킽���Ď����邽�߂ɂ́A�l�����R�����Ԍn���\���������ł���Ƃ����F���ɗ����āA���R���̔����ȋύt�Ȃ�Ȃ��悤�A���R�ɑ��ēK�ɓ���������ƂƂ��ɁA�������p���Ă����K�v������B
�@���ɁA�{���́A�������������ɑ�\�����悤�ȗD�ꂽ���R�����n�����̐g�߂Ȏ��R�A���l�����Ԍn�Ɍb�܂�Ă���A�S���Ɍւ����������R�i�ς�ۂ��Ă���B�܂��A���y�̖�55�����߂�X�т́A�����̂���{�A��_���Y�f�z���@�\�Ȃnj��v�I�@�\��L���Ă���A�����̋@�\�̍��x������}���Ă����K�v������B
�@���̂��߁A�����x����X�тÂ����i�߂�ƂƂ��ɁA���l�Ȏ��R��������l����ۑS���A�l�X�Ȏ��R�Ƃ̂ӂꂠ���̏��@����m�ۂ��邱�Ƃɂ��u�l�Ǝ��R���������鏁���̂���n��Â���v��ڕW�Ƃ���B
��P�߁@�����x����X�тÂ���
(1) �{���̐X�т̊T�v
�@
18�N�x���ɂ�����{���̐X�іʐς́A���y�ʐϖ�64��ha��55���ɂ������35��ha�ƂȂ��Ă���B���y�ʐςɂ�����X�іʐς̊����i�X�ї��j�͑S���ő�27�ʂɂ�����B�i�}�Q�|�Q�|�P�j
�@
�X�т̏��L�ʓ���́A���L�т���13��ha�i�{���X�т�37���j�A���L�т���22��ha�i�{���X�т�63���j�ƂȂ��Ă���B�܂��A���L�тɂ��������ʖʐϊ����́A�X�M��31���A�q�m�L��20���A���̑��j�t�����X���A�L�t�����̑���40���ƂȂ��Ă���A�X�M�E�q�m�L�𒆐S�Ƃ����l�H�іʐς͖�12��ha�i���L�іʐς�55���j�ƂȂ��Ă���B�i�}�Q�|�Q�|�Q�A�\�Q�|�Q�|�P�j
�}�Q�|�Q�|�P�@���y�ʐςɂ�����X�т̊���
�i18�N�x���j |
�}�Q�|�Q�|�Q�@�������L�ʁE�l�H�V�R�ѕ�
�X�іʐς̊����i18�N�x���j |
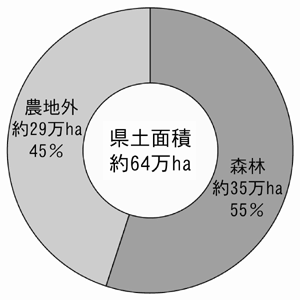 |
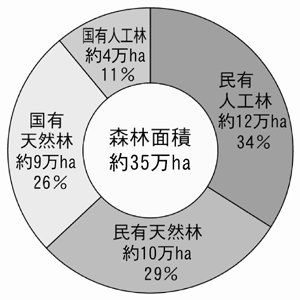 |
�\�Q�|�Q�|�P�@���L�тɂ��������ʖʐϊ���
| �敪 |
���� |
����i�S�̂ɐ�߂銄���j |
| �j�t�� |
60�� |
�X�M�i31���j�A�q�m�L�i20���j�A���̑��j�t���i�X���j |
| �L�t�� |
40�� |
�N�k�M�i�Q���j�A���̑��L�t���i38���j |
(2) �X�т̐�����
�A ���іʐς̐���
�@���іʐς͏��a53�N�x��2,100ha���s�[�N�Ɍ����X���������A18�N�x�ɂ́A�s�[�N���̂Q���������344ha�ɂ܂ŗ�������ł���B�i�}�Q�|�Q�|�R�j
�C ���L�l�H�т̗�ʍ\���`�Ԕ���K�v�Ƃ���X�т̏`
�@�{���̖��L�l�H�ёS�̖̂�T�����A�Ԕ���K�v�Ƃ���i�V�`�\��i11�`45�N���j�j�X�тɂȂ��Ă���i�ʐ�62.8��ha�j�B���̔����߂����Ԕ��̒x�ꂽ�X�тł���A�r�p�̊댯�������܂��Ă���B���ɉ��n�ȂǏ����̈����ӏ��̒x�ꂪ�����ő��}�ȑK�v�ł���B�{���ł́A�����𒆐S��14�N�x����18�N�x�܂ł̂T�N�ԂŖ�Q��ha���Ԕ������{���A���S�ȐX�тÂ���ɓw�߂Ă������A�����Ɏ����̍s���͂��Ȃ��X�т������c����Ă���B(�}�Q�|�Q�|�S)
�}�Q�|�Q�|�R�@���іʐς̐���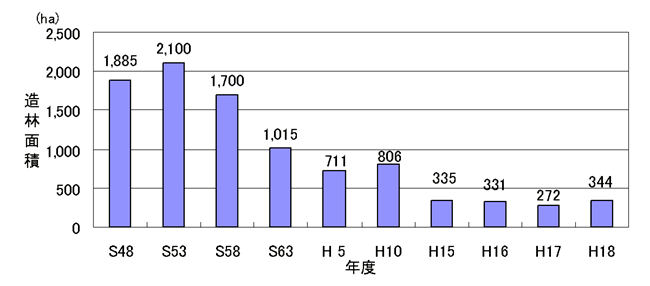
�}�Q�|�Q�|�S�@�������L�l�H�тɂ�����X�M�E�q�m�L���ї��ʖʐρi18�N�x���j
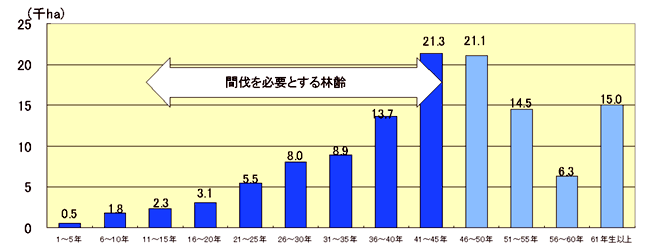
(3) �X�т̗L���鑽�ʓI�@�\
�@
�X�т͑��ʓI�ȋ@�\��L���Ă���A�����̐����Ɛ[����������Ă���B12�N�ɔ_�ѐ��Y��b������{�w�p��c�ɑ��āu�n�����E�l�Ԑ����ɂ������_�Ƌy�ѐX�т̑��ʓI�ȋ@�\�̕]���ɂ��āv���₳��A���̓��\�i13�N11���j�ł́A�X�тɂ͎��̂悤�ȋ@�\������Ƃ���Ă���B
�@�@
�@�������l���ۑS�@�\
�@�@
�A�n�����ۑS�@�\
�@�@
�B�y���ЊQ�h�~�@�\�E�y��ۑS�@�\
�@�@
�C��������{�@�\
�@�@
�D���K���`���@�\
�@�@
�E�ی��E���N���G�[�V�����@�\
�@�@
�F�����@�\
�@�@
�G�������Y�@�\
�@
�ߔN�A��_���Y�f���z���E�Œ肷�铭������A�n�����ۑS�@�\�����ۓI�ɏd�v������Ă���B
(4) �ۈ����̖ʐςƐ���
�@
��������{��y�����o�h���ȂǐX�т̌��v�I�@�\����荂�x�ɔ��������Ă������Ƃ�ړI�Ɏw�肷���ۈ����ɂ��ẮA���L�сA���L�тƂ��ɒ����ɑ������Ă���A18�N�x�����݂̎w��ʐς͖�18���R��ha�ŁA���̓���͍��L�т�62���i���L�іʐς̖�W���j�A���L�т�38���i���L�іʐς̖�R���j�ƂȂ��Ă���B�i�}�Q�|�Q�|�T�j
�}�Q�|�Q�|�T�@�ۈ����ʐς̐���
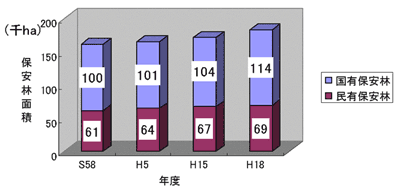
(5) �K���ȐX�ѐ����̐��i
�@
�X�т́A���L�ғ��ɂ��A�т��田�̂܂ł̗ыƐ��Y������a���b�Q�̖h���E�X�щЂ̖h�~�Ȃǂ̓K���ȊǗ���ʂ��A���̑��ʓI�@�\���ێ����コ���A�����̐����������Ƃ����d�v�Ȗ�����S���Ă����B
�@
�������A�������؍މ��i�̒����Y�R�X�g�̏㏸���ɂ��ыƍ̎Z���̒ቺ�A�S����̍���Ȃǂɂ��A���S�ȐX�т��琬�����Ԕ����̓K���Ȏ{�Ƃ��i�݂ɂ����ɂ���A�ыƐ��Y������ʂ����X�т̎����v�I�@�\�̎����I�Ȕ����ɂ��x��������������ꂪ�����Ă���B
�@
���̂悤�Ȓ��A�X�т��������L�̍��Y�Ƃ��Ď��̐���Ɉ����p�����߁A������l�ЂƂ肪�X�т̑����F�����A�ʂ����ׂ��������l���A�ł��邱�Ƃ�����g�ސV���Ȏd�g�݂̍\�z���ۑ�Ƃ���Ă���B
(6) �X�т��x����ыƂ̐U��
�@
�؍ސ��Y���n�߁A��_���Y�f�z���␅������{���̐X�т̎����ʓI�@�\�̔����ɂ́A�l�H�тɂ����鎝���I�ȗыƐ��Y�������s���ł���A���̂��߂ɂ́u��A���A��āA�����ė��p���A�܂��A����v�Ƃ����X�ю����̏z���p�𐄐i���邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@
�����ŁA�ыƒS����̊m�ہE�琬��ѓ��E��Ɠ����̊�Ր����̑��i�ȂǂɎ��g��ł���B�������Ȃ���A�؍މ��i�̒�����ɂ��ыƍ̎Z���̈����f���āA�X�я��L�҂̎{�Ǝ��{�ɑ���ӗ~�����ނ��Ă���A�ϋɓI�ɒ�R�X�g���Y�Ɏ��g��ł���ꕔ�̐X�я��L�ғ��������A�Ԕ����̐X�ю{�Ƃ��ˑR�Ƃ��ď��K�́E���U�^�ŃR�X�g���̌X���ōs���Ă��邱�ƂȂǂ���A�؍ސ��Y������I�ɍs���ɂ����ƂȂ��Ă���B
�@
���̂��߁A�v��I�������I�ȐX�ю{�Ƃ̑��i�ɂ�鎖�ƋK�͂̊g���X�ю{�ƃR�X�g�̒ጸ��}��ȂǗыƍ̎Z���̌��オ�ۑ�ƂȂ��Ă���B
(1) �X�т̌��v�I�@�\�̌���
�A �Ԕ����X�ѐ����̑��i
�@
�X�т̎�����_���Y�f�̋z���E�Œ���͂��߂Ƃ�����v�I�@�\�������I�ɔ��������邽�߁A�X�я��L�҂ւ̎x���⌧�E�X�ѐ������Ђɂ����I�X�ѐ����ɂ���Ԕ����̐X�ѐ����𑣐i���Ă���B18�N�x�͖�4,900ha���Ԕ����܂߁A���сA�����蓙�̐X�ѐ������7,000ha���{�����B
�@
���̂����A���R�ЊQ�Ȃǂɂ����v�I�@�\�̒ቺ�����ۈ����ɂ����ẮA�������{��̂ƂȂ�A�ۈ����������Ɠ��ɂ��X�ѐ����𐄐i���Ă���B�܂��A�ѓ����牓���Ȃǂ̏����ɂ�菊�L�҂ɂ��{�Ƃ�����ȉ��n���ۈ����ȊO�̐X�ѓ��ɂ����Ă͐X�ѐ������Ђ����{��̂ƂȂ�A�X�M�E�q�m�L���Ԕ���L�t���A�͓��̐X�ѐ����𐄐i���Ă���B18�N�x�͌��A�X�ѐ������ЂŖ�1,400ha���Ԕ���L�t���A�͓��̐X�ѐ��������{�����B
�C ���l�ȐX�т̈琬
�@
�X�т̎����v�I�@�\�������I�����x�ɔ��������邽�߂ɂ́A�Ԕ��̑��i�ƂƂ������w���{�Ƃ��������{���A�琬�V�R�ю{���A�L�t���ѐ������ɂ��A���l�ȐX�т̈琬���d�v�ł���B
�@
18�N�x�͖�100ha�����w�������A��680ha�̍L�t���ѐ������܂߁A���l�ȐX�т̈琬��}��ړI�ŁA��2,200ha�̐X�ѐ��������{�����B
�E �����Q���̐X�тÂ���̐��i
�@
�X�т̑���ɂ��ď����s���ƂƂ��ɁA�X�Â���̌��u���̊J�Â����ɂ��X�Â��芈���̎��{�ȂǁA�̌�������ʂ��ĐX�ъ��̕ۑS�ɑ��錧���ӎ��̏�����}�����B�@
�@
�܂��A�X�у{�����e�B�A�̑��𗬂�[�߂��g���͂��߁A�{�����e�B�A��m�o�n�A��Ɠ��̏㉺���𗬂ɂ�鋦�������̐X�Â��萄�i���Ƃ����{����ȂǁA�����Q���ɂ��X�ѐ��������̑��i��}�����B
�G �Ƃ����̌��C�ȐX�Â��茧���ł̓����Ɍ����Ă̎�g
�@
�X�т̗L������v�I�@�\�̌���Ɍ����āA���������̐X�Â����ړI�Ƃ����{���Ǝ��̐Ő��x�ɂ��āA�K�v���A�g�r�A�d�g�ݓ��̌������s�����߁u���������X�Â���Ɋւ���L���҉�c�v�i�w���o���ғ����ψ��j��18�N�x�ɂS��J�Ái�v�V��j�����B���̗L���҉�c����V��31���ɒm���֒�o���ꂽ�̓��e�́w���v�I�@�\�����X�т��������L�̍��Y�Ƒ����A�Љ�S�̂Ŏx����V���Ȏ�g���K�v�ł���A���̍����Ƃ��Č����̍��ӂ���Łu�X�ъ��Łi���́j�v�̑n�݂��K���ł���B�܂��A���������ɂ��X�Â����i�߂Ă������߂ɂ́A����茧���̗��𑣐i���K�v�ł���B�x�Ƃ�����̂ł������B
�@
���̒܂��A���ł͐ł̓����y�ь��������ɂ��X�Â���̎�g�ɂ��Č�����i�߂��ق��A�Ƃ������C�t�H�[������Ƃ������������Ȃǂ�ʂ��āA�X�т̑����Љ�S�̂ŐX�т�����ĂĂ������Ƃ̕K�v���ɂ��čL���E�L�������{�����B�����āA�Ƃ����̌��C�ȐX�Â���V���|�W�E����A�����e�n�Ō��������X�Â���t�H�[�����i�e�і����������Ɂj���J�Â��A����2,500�l�̎Q���āA�V���Ȑł̕K�v�����ɂ��āA�ӌ��������s���A���������̑��i��}�����B�i�}�Q�|�Q�|�U�j
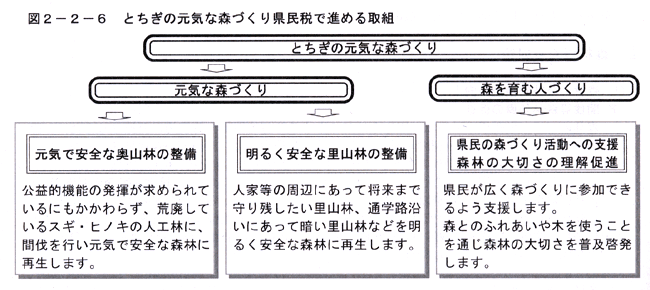
�I �X�ю����̏z���p�̐��i
�@
�X�ю����̏z���p�𐄐i���邽�߁A�X�ю{�Ƃ̒��j��S���X�ёg�����ыƎ��Ƒ̂̐V�K�A�ƎҊm�ۈ琬�x����o�c���P�w�����s���ƂƂ��ɁA��R�X�g�ыƂ̊�ՂƂȂ�ѓ����Ɠ��̐����𑣐i�����B�܂��A�؍ނ̍������H�ɕs���Ȑl�H�����{�ݓ��̓����x����u�Ƃ����̌����i�^���v�̓W�J���ɂ��A���i���Ȍ��Y�ނ̈��苟���Ɨ��p�g��ɓw�߂��B
(2) �X�т̓K���Ǘ�
�A �X�ьv�搧�x�ɂ��X�ъǗ��̐��i
�@
�X�ьv�搧�x�͐X�і@�ɂ����đ̌n�t�����Ă���A�������肷��S���X�ьv��ɑ����āA�����n��X�ьv����A�s�����͒n��X�ьv��ɓK�������s�����X�ѐ����v������肵�Ă���B
�@
�n��X�ьv��́A���L�т�ΏۂƂ���10�N���P���i�O���E����j�Ƃ���v��ł���A�{���ł͌�����߉ϐ�E�S�{��E�n�ǐ���̂R�̐X�ьv���ɋ敪���Ă���B
�@
18�N�x�ɂ����ẮA19�N�x�����N�x�Ƃ���n�ǐ���n��X�ьv������肵�A�߉ϐ�y�ыS�{��n��X�ьv��̈ꕔ�ύX���s�����B
�@
�܂��A�v��I�ȐX�ѐ�����}�邽�߁A�X�ьv��}��X�ѕ�A�{�Ɨ����Ȃǖ��L�тɊւ���l�X�ȏ��ɂ��Ĉꌳ�I�ɊǗ��E���͂���u�X�тf�h�r�v�������B
�C �ۈ����E�ђn�J�������x�ɂ��X�т̕ۑS
�@
�ۈ����w��̊g�哙�ɂ��A�X�т̎����v�I�@�\�̍��x�����ƐX�т̕ۑS�𐄐i�����B
�܂��A�{�����L�т��ۈ��������i�w��A�X�ѐ����A�Ǘ��j�̓K���Ȑ��i��}�邽�߁A17�N�x�ɍ��肵���u�Ȗ،��ۈ���������{�v��v�Ɋ�Â��A��̓I�s���v��ł���u�Ȗ،���P���ۈ����������{�v��v�̍����i�߂��B
�@
����ɁA�X�т̗L������v�I�@�\����Ƃ̒��a�Ȃ����ƂȂ��A��������J���s�ׂ𑣂����߂̗ђn�J�������x�Ɋ�Â��A�K�ȋ��Ǝw���Ɏ��g�B
�E �X�є�Q��̐��i
�@
�X�т̕a�Q������Q�𑁊��ɔ������A�K�ȑ�����{���邽�߁A�s������W�c�̓��ƘA�g���Ĕ�Q���}���Ă���B�@
�@
18�N�x�͏���������Q�h����Ƃ���200ha�̐X�тŖ�U�z�����{�����ق��A3,800���R�̔�Q�̔��|�쏜�������{�����B
�@
�܂��A�M�d�Ȍ������L�̍��Y�ł���X�т���u�ŏĎ����Ă��܂��X�щЂ�h�~���邽�߁A�R�Ύ��h�~�̕��y�[�����������{���Ă���B
�@
18�N�x�́A�R�Ύ��h�~�̕��y�[�������Ƃ��čL��Ԃɂ�鏄��������S��ōs�����ق��A�e���r�E���W�I�ɂ��R�Ύ��h�~�b�l�̕�����[�t���b�g�z�z���̍L�������{�����B
|