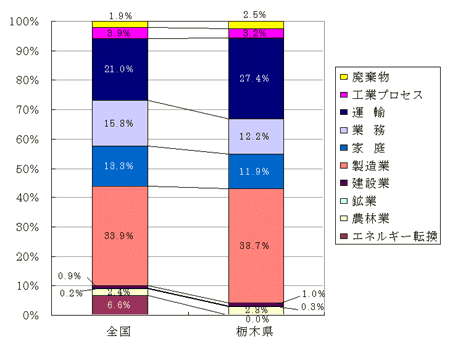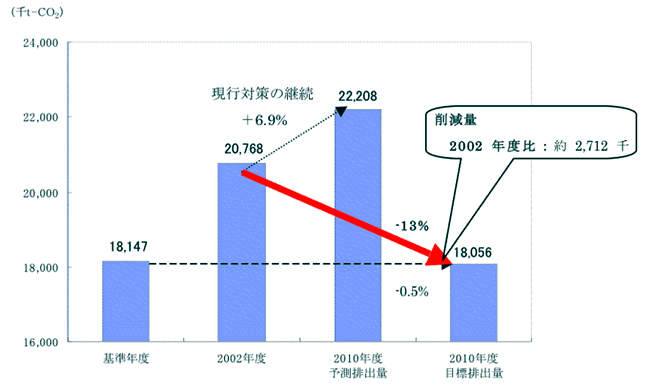|
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題は、人の社会経済活動による環境への負荷が長年にわたって蓄積されたことによって生じたものであり、私たち一人ひとりの行動に深く関わる人類共通の課題である。 第1節 地球温暖化防止対策の推進
(1) 地球温暖化の仕組み私たちが住んでいる地球を覆っている大気中には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが含まれており、これらのガスの濃度上昇に伴い温室効果が増大して地球の気温が全体として上昇することを「地球温暖化」と呼んでいる。 (2) 地球温暖化の影響19年2月に公表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」第4次報告書によると、気候システムに温暖化が起こっていると断定するとともに、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定し、過去100年に世界平均気温が0.74℃上昇したと報告されている。また、21世紀末までに、平均気温が最大6.4℃上昇し、平均海水面が最大59cm上昇すると予測している。 (3) 国際的な取組
地球温暖化問題は昭和60年代から本格的な議論が始まっていたが、4年(1992年)にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」が開催され、地球温暖化を防止するための「気候変動枠組条約」が採択された。これは、「気候系に対して危険な人為的な影響を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガス濃度を安定化させること」を目的とした条約であり、6年(1994年)3月に発効した。 (4) 我が国の取組
10年(1998年)10月に、「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」が制定され、その中で、地球温暖化対策のための国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれの責務が明確化された。この法律において、国と地方公共団体は、自らの事務・事業について温室効果ガスの発生抑制のための実行計画を策定し、公表することとされている。
(1) 温室効果ガス排出量の概要
本県では、18年3月に「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」を改定し、県内の温室効果ガスの排出実態等を踏まえ、本県の温室効果ガスの削減目標を掲げるとともに、その目標を達成するための県の施策と、県民、事業者及び行政の各主体が地球温暖化防止に向けた取組を実践する際の行動指針を具体的に示した。
栃木県における排出源別のCO2排出量の占める割合を全国と比較すると、製造業、運輸部門の占める割合が全国と比べて大きく、家庭、業務部門は小さくなっている。(図2−3−1) 図2−3−1 排出源別のCO2排出量の占める割合 なお、18年度における温室効果ガス排出量の簡易推計を行った結果、約20,199千t-CO2であり、基準年比11.3%増であった。 (2) 温室効果ガス排出量の将来予測
栃木県における22年度(2010年度)の温室効果ガス総排出量は、今後、このままの状況で推移すると仮定した場合、CO2及びHFCSが基準年に比べ大幅に増加することにより、約22,208千t-CO2と予測され、基準年(2年度、1990年度)比4,061千t-CO2(22.4%)の増加が見込まれ (3) 温室効果ガス排出量の削減目標
我が国は、京都議定書において、20年(2008年)から24年(2012年)の第1約束期間に、温室効果ガス総排出量を基準年(2年、1990年)比で6%削減することとしている。京都議定書目標達成計画においては、温室効果ガス排出量の削減目標として、基準年比−0.5%を掲げ、不足分となる量(5.5%)は、森林での吸収量(3.9%)と京都メカニズム(1.6%)で補うとしている。 図2−3−2 温室効果ガス排出量の将来予測と削減目標
(1) 地球温暖化防止対策の総合的な推進「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、以下のとおり、地球温暖化防止対策を総合的に推進した。 ア 地球温暖化防止活動推進センター事業「地球温暖化対策推進法」第24条の規定に基づき指定した栃木県地球温暖化防止活動推進センターの自主事業との連携を図りながら、地球温暖化防止に向けた県民への普及啓発事業を委託により実施した。 (ア) エコテックとちの環2007の開催
企業や団体によるリサイクル製品・省エネ機器など環境への負荷の少ない製品や技術の展示、活動の紹介、及び講演会の開催等を通して地球温暖化対策や循環型社会の構築を啓発する環境イベントを開催した。 (イ) 地球温暖化防止キャンペーン「エコライフフォーラム」の開催
地球温暖化の現状や影響、さらに、防止するためには一人ひとりの取組が必要不可欠であることを普及啓発し、県民の環境にやさしいライフスタイルへの転換を促すため、講演会を開催した。 (ウ) 環境情報誌「とちぎエコ通信」の発行一般県民向けに、地球温暖化対策など環境に関する様々な情報をわかりやすく提供する環境情報誌「とちぎエコ通信」を年2回(6月、12月)発行(各15,000部)し、県民利用施設や公民館、金融機関等に配布した。 イ とちの環県民会議事業県民、民間団体、事業者、行政の各主体が相互に連携・協力するパートナーシップを確立し、県民総ぐるみで環境保全に取り組む組織「とちの環県民会議」は、「地球温暖化対策推進法」第26条の規定に基づく地球温暖化対策地域協議会を兼ねており、地域の特性に応じた地球温暖化対策の検討・実践活動を行った。 (ア) とちの環県民会議総会記念講演会の開催
異常気象や気候変動に関するメカニズムに関する講演会を開催した。 ウ 地球温暖化防止活動推進員の活動地球温暖化対策の取組を推進するため、「地球温暖化対策推進法」第23条の規定に基づき、栃木県地球温暖化防止活動推進員(18年度)34名を委嘱し、合計74名の推進員が県内各地域で、地球温暖化の現状や対策の重要性についての普及啓発を実施した。 エ 地球温暖化対策計画普及事業「栃木県生活環境の保全等に関する条例」で義務づけられた「地球温暖化対策計画」の作成・届出に係る事務を円滑に執行するための相談窓口を開設した。 オ 広報媒体を活用した普及啓発事業地球温暖化防止啓発、省エネルギーキャンペーン等の周知を新聞、ラジオ等スポットCMにより行った。 カ 環境演劇の開催事業地球温暖化や循環型社会等の環境をテーマとした演劇を県内の小・中学校へ巡回公演し、次世代を担う子どもの意識の高揚を図った。 キ 栃木県庁環境保全率先実行計画の推進
県では、県自らの活動による環境への負荷を低減するため、「県の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組のための行動指針」を9年9月に策定し、さらに、本指針の内容に地球温暖化防止の視点を加えた「栃木県庁環境保全率先実行計画」を12年3月に策定し、全庁的に取り組んできた。
(2) 省エネルギー・エネルギー有効利用の推進ア 省エネチャレンジ大作戦
“もったいない”を基本とした省エネライフの普及・推進を図るため、家庭、学校、事業所単位による県民総ぐるみで省エネ実践活動に取り組み、その成果を顕彰する省エネチャレンジ大作戦を実施した。学校及び事業所部門では、削減率のほかに、「周知・啓発度」「定着度」「ユニークさ」「実行可能性」についても審査し受賞者を決定した。 イ 地球温暖化対策支援事業
事業者の地球温暖化対策を推進するため、温室効果ガス排出量削減に関する知識や技術を指導・助言できるESCO事業者等省エネルギー関連事業者や専門家をアドバイザーとして県が登録し、県内事業者の要請に応じ派遣した。 ウ ESCO導入推進事業県内の総合的・効率的な省エネルギー対策を推進するため、市町及び民間事業者を対象とするESCO事業導入に関するセミナーを3回開催した。 エ 省エネルギー住宅の普及拡大省エネルギー性能を含む「住宅性能表示制度」の普及・促進により、適切な熱環境計画を行った省エネルギー住宅の普及拡大を図った。また、住宅の省エネルギー化技術者の養成を推進するため、(財)建築環境・省エネルギー機構との共催で、住宅建設業者等向けの「省エネルギー住宅の設計・施工技術講習会」(19年1月)を実施した。 オ ESCO事業の推進県自らの省エネルギー化に向けた率先行動の一環として、新たな省エネルギー対策であるESCO事業の県有施設への導入可能性調査を実施するとともに、その導入推進のための指針となる「栃木県ESCO推進マスタープラン」(18年2月)を策定し、モデル的にがんセンターにて18年度からESCO事業を導入している。 カ 省エネラベリング商品購入促進事業消費者が家電機器の購入時に省エネ型製品を容易に選択できるよう、省エネ性能を比較しやすい「省エネラベル」の普及啓発のため、セミナーを開催し、家電の普及拡大を図った。 キ 栃木県グリーン調達の推進「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」及び「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、「栃木県グリーン調達推進方針」を13年7月から毎年度策定している。18年度は、17分類220品目について判断基準及び調達目標を定め、取組を実行した。 (3) 新エネルギー・未利用エネルギーの利用の推進ア 一般住宅用太陽光発電システム資金貸付
一般住宅用太陽光発電システムの設置に必要な資金の融資制度を17年6月から開始し、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及促進を図っている。(表2−3−3)
イ 太陽光発電の率先導入県自らの活動によるCO2の排出抑制に取り組むとともに、太陽光発電システムの導入促進を図るため、学校や県民利用施設に大規模太陽光発電システムの整備を進めている。 ウ 新エネルギーに関する普及啓発
県民や事業者の新エネルギーに対する理解を促進するため、県が導入した太陽光発電施設やクリーンエネルギー自動車などを活用して積極的に普及啓発を行った。 (4) 自動車からの二酸化炭素排出量削減の推進ア エコドライブ普及啓発事業
11月を「栃木県エコドライブ月間」として、エコドライブキャンペーンやエコドライブ講習会を11月3日に宇都宮市内で開催し、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るためのエコドライブの普及啓発を図った。 イ クリーンエネルギー自動車普及促進事業運送事業者の貨物車等への天然ガス自動車の普及促進を図るため、天然ガス燃料供給施設の設置可能性等を調査した。その結果、22年度(2010年度)における天然ガス自動車の導入見通しとして770台とし、天然ガス燃料供給施設の設置見通しを4〜5カ所とした。 ウ クリーンエネルギー自動車の率先導入
県として二酸化炭素(CO2)の排出抑制や大気環境の保全に取り組むとともに、クリーンエネルギー自動車の普及啓発を図るため、公用車にハイブリッド自動車を8台導入した。 エ 自動車交通需要の調整県と関係市町が策定した各都市圏の総合都市交通計画に基づき、都心部でのレンタサイクル(宇都宮市)や循環バス運行(栃木市)など、自動車交通需要の低減に寄与する交通需要マネジメント施策が展開されている。 オ 公共交通ネットワークの整備本県は、自動車普及率や自動車免許保有率が全国第2位にあるなど、「くるま社会」化が顕在化しており、県民の日常生活は自家用車に依存する傾向がますます強まる一方で、公共交通の利用者の減少に歯止めがかからない状況にある。この状況を改善するため、以下の取組を進めている。 (ア) バス・鉄道利用デーの取組毎月1日と15日を「バス・鉄道利用デー」と定め、通勤等で日常的に自家用車を利用している県民に対し、ラジオスポットによる呼びかけを行い、バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進を図っている。 (イ) 公共交通の利便性向上18年度に設置した「とちぎ公共交通確保対策協議会」において、全県的な視点で公共交通の利便性の向上並びに利用促進策等の検討を行っている。また、宇都宮市が17年度に設置した「県央地域公共交通利活用促進協議会」にも参加し、公共交通の利便性向上や自家用車から公共交通への転換を図るなど、広く公共交通の利活用を促進するための検討等を行っている。 (ウ) 新交通システムの導入検討17年度に宇都宮市と共同で設置した「新交通システム導入課題検討委員会」において、新交通システムを導入するとした場合の課題を抽出するとともに、今後の検討の方向性をとりまとめた。 カ 交通渋滞の解消、緩和による自動車交通の円滑化体系的な道路ネットワークの整備や道路の拡幅、バイパスの整備、交差点の立体化等を推進し、渋滞の解消、緩和によるCO2の排出抑制を行っている。 (5) 森林整備・緑化の推進と木材利用の推進ア 森林整備、緑化の推進
森林は、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を光合成により吸収し、木材として炭素を長期間貯蔵、また、蒸散作用により気候を緩和するなど、地球温暖化を防止する上で大きく期待されており、これらの機能を高く発揮するため、森林の保全・育成や木材資源の有効利用を促進することが求められている。また、都市部の緑化は、大気の浄化や気温上昇の抑制などの効果が期待されている。 イ 木材利用の推進木材の持つ炭素の貯蔵効果を発揮するため、「県有施設の木造・木質化に関する基準」に基づき、県発注の建築工事や土木工事において積極的に県産材を利用したほか、市町村・学校法人等の施設整備や県民の住宅建築における県産材利用を促進した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||