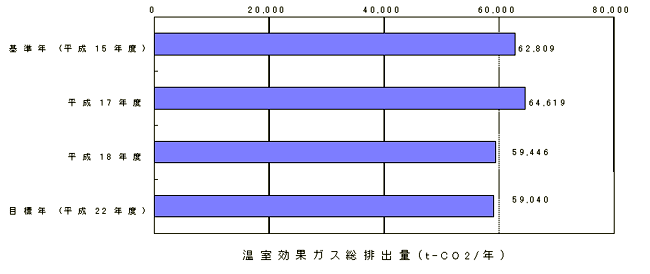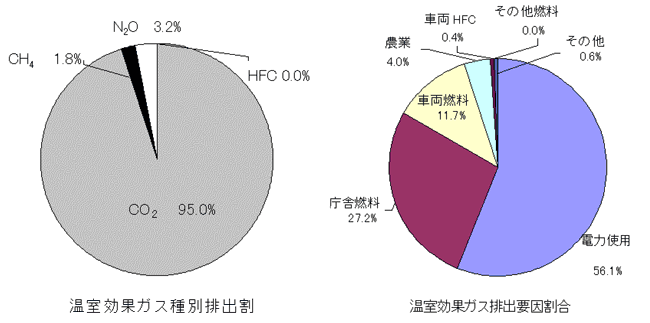|
県庁では、温室効果ガスの排出量削減を図るため、「地球温暖化対策推進法」に基づき策定した「栃木県庁環境保全率先実行計画」(以下「率先実行計画」という。)により、全庁的に取組を進めているところである。
率先実行計画は、12~16年度までの5年間を〈一期計画〉、17~22年度までの6年間を〈二期計画〉とし、15年度(基準年)に対し温室効果ガス6%削減を目標に取り組んでいるところである。
(1) 温室効果ガス総排出量について
ア 温室効果ガス総排出量は、17年度に対し8%の大幅な減少となった。
イ 減少した要因は、二期計画から各課所に率先実行計画推進員を置き、各課所の計画推進マニュアルの作成や四半期ごとの推進状況評価を行うなどの取組成果と、暖冬であったという気象的要因、施設の統廃合などが考えられる。
(2) 平成18年度重点事項の取組結果について
ア 「①用紙類の合理的な使用の推進」については、文書学事課の「紙の消費削減の取組」、広報課の「記者発表資料の両面コピー化」などの全庁的な取組により用紙使用量が11%の減少となった。
イ 「②ガソリン使用量を抑制する」については、エコドライブの推進やクリーンエネルギー自動車の導入などを進めてきたが、走行距離の増大によりガソリン使用量は増加となった。
(3) その他の取組成果について
ア 前年度との比較では、7項目が改善された。項目別では、電気使用量、水道使用量、庁舎燃料使用量、用紙使用量、軽油使用量、廃棄物の排出量が減少し、古紙利用率はやや改善された。
イ 22年度の目標値との比較では、目標達成項目は4項目で、水道使用量、庁舎燃料使用量、公用車燃料使用量(軽油)、建設副産物利用率(建設廃棄物)である。
栃木県庁環境保全率先実行計画実績一覧表
| 項目 |
単位 |
17年度 |
18年度 |
22年度目標値 |
| 実績値 |
実績値 |
数値目標 |
基準年との比較 |
温室効果ガス総排出量
(二酸化炭素換算) |
t-CO2 |
64,619 |
59,446 |
59,040 |
6%削減 |
| 1 |
電気使用量 |
千kWh |
90,928 |
86,616 |
83,192 |
6%削減 |
| 2 |
水道使用量 |
千m3 |
1,567 |
1,429 |
1,578 |
5%削減 |
3
|
庁舎燃料使用量
(二酸化炭素換算) |
t-CO2 |
20,138 |
16,195 |
18,358 |
6%削減 |
4
|
用紙使用量
使用枚数
古紙利用率 |
千枚
% |
74,554
85.2% |
66,426
86.3% |
64,353
90%以上 |
10%削減 |
5
|
公用車燃料使用量
ガソリン
軽油 |
kl
kl |
2,654
260 |
2,728
240 |
2,405
307 |
7%削減
7%削減 |
6
|
廃棄物の排出量
県庁全体 |
t |
2,263 |
2,070 |
1,985 |
20%削減 |
7
|
建設副産物利用率
建設廃棄物
建設発生土 |
%
% |
(16年度)
98.3%
87.5% |
(17年度)
97.3%
65.8% |
90%以上
90%以上 |
|
18年度における温室効果ガスの総排出量は59,446(t-CO2/年)で、17年度と比較して8%減少した。基準年(15年度)と比較しても5.4%減少している。
また、温室効果ガスの割合は、二酸化炭素(CO2)が全体の95.0%と最も多い。排出要因は、電力使用が56.1%と最も大きく、次いで、A重油・天然ガスなどの庁舎燃料が27.2%、車両燃料が11.7%であった。
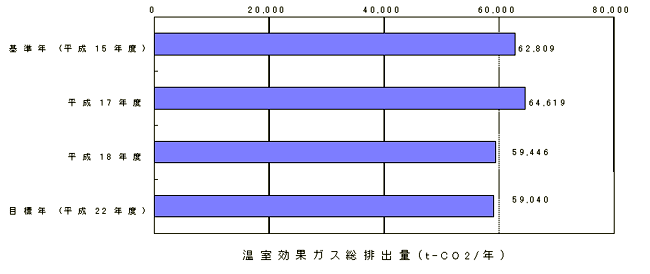
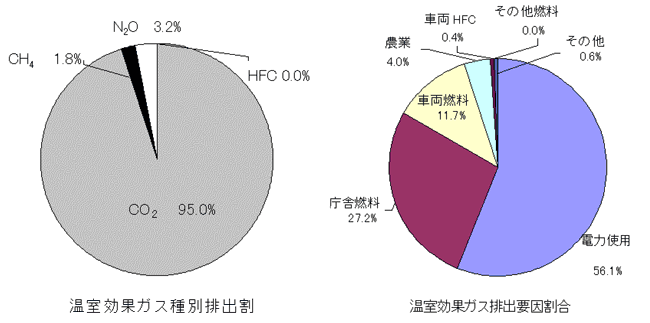
(注)1
車両HFC…車両エアコンに封入されている代替フロン。エアコンの使用に伴い排出される。
2 農業…家畜の飼養、畑作への施肥、水田の耕作から発生する一酸化二窒素、メタン。
3 その他…病院で使用する笑気ガス(一酸化二窒素)など。
率先実行計画〈二期計画〉3年目である19年度の「全庁重点取組事項」は、次の2項目に決定し目標達成に向けた取組を行う。
|
① 電気使用量を抑制する
【徹底事項】
(1) 昼休みの消灯、残業時の不必要な照明の消灯。
(2) 冷房使用時の室温を28℃以上とする。
(3) 暖房使用時の室温を19℃以下とする。
(4) 長時間席を離れる時及び昼休みは、パソコンの主電源を切る。
(5) 退庁時にはパソコン、プリンタ、コピー機のプラグをコンセントから抜く。
② ガソリン使用量を抑制する
【徹底事項】
(1) 急発進、急加速をしない(ふんわりスタート)。
(2) 無用なアイドリングをしない(アイドリングストップ)。
(3) タイヤ圧を点検・調整し、燃料消費の向上を図る。
(4) 効率的なルート選択、出走台数の削減に努める。
(5) 自動車更新時には、低燃費・低公害車の購入に努める。
(6) 公共交通機関利用により自動車の走行量を抑制する。 |
|