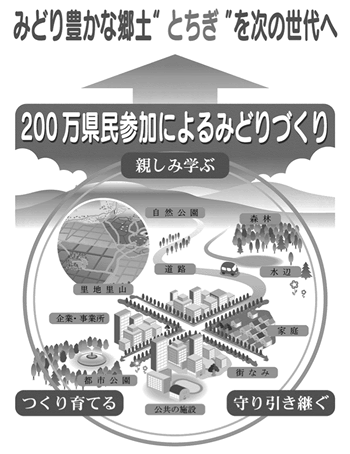1 みどりづくり活動推進の背景
本県は森林と農地が県土の約75%を占めるなど、豊かなみどりに恵まれているが、いずれも減少傾向にあるとともに、手入れの行き届いていない森林や遊休農地の増加など、質の低下も懸念される。
都市部においては、人々の暮らしに密着したみどりの量と質の確保を図ることにより、自然と共生した、安全で住みよい都市環境の整備が求められているなど、今後、みどりづくりはますます重要になってきている。
また、県民の緑化の必要性や緑化活動への参加意識も高まっていることに加え、地球温暖化を始めとする地球規模の環境問題が深刻化する中、森林をはじめとするみどりが有する公益的機能への期待も高まっている。
このような中、森林整備や身近なみどりづくりのためのボランティア、NPOや企業・住民等の活動が活発化しつつある。
2 みどりづくり活動の推進
(1)県土緑化の推進
- ア 第4次栃木県緑化基本計画による緑化の推進
- 「みどり豊かな郷土“とちぎ”を次の世代へ」引き継いでいくため、18年3月に策定した「第4次栃木県緑化基本計画」に基づき、県民やボランティア、NPO、企業、行政等が連携した“協働”によるみどりづくりを進め、「みどりに親しみ学ぶ」「みどりをつくり育てる」「みどりを守り引き継ぐ」を柱として、多様な緑化施策を総合的かつ計画的に実施し、県土緑化の推進を図った。(図2−2−16)
図2−2−16 みどりづくりのイメージ
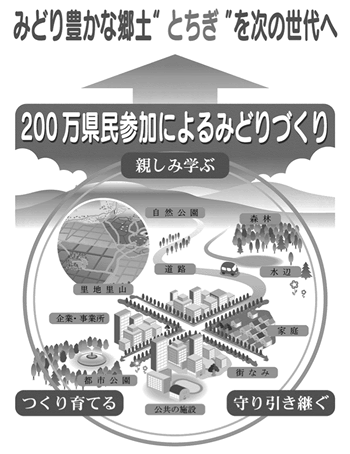
- イ 普及啓発によるみどりづくり活動の促進
- 春・秋季緑化運動期間を中心として、さくら市での県植樹祭(参加者約800名)や苗木配布会(県内48会場)の開催、みんなの森づくり活動(3回、参加者延べ143名)などを実施し、みどりづくりに関する普及啓発を行った。
また、学校環境緑化などのコンクールを実施し、緑化意識の高揚を図るとともに、みどりづくり活動への参加を促進した。なお、19年度の緑づくり活動の参加人数は7,668人であり、18年度から449人増加した。(表2−2−27)
表2−2−27 緑づくり活動参加人数の推移
| 年度 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 参加人数(人) |
6,829 |
6,888 |
7,219 |
7,668 |
- ウ 都市緑化対策
- 都市における緑は、大気の浄化、騒音等公害の緩和に寄与するとともに、住民に安らぎと憩いをもたらし、都市生活上欠くことのできない重要な役割を担っている。
このため、都市緑化推進の重要性に鑑み、県(5か所)、宇都宮市及び足利市でそれぞれ「緑の相談所」を設置し、植栽樹 種の設定、植栽方法、病虫害防除等に関する相談、各種緑化催し物の開催を行い、都市緑化意識の高揚、植物知識の普及・啓発を図っている。(表2−2−28)
表2−2−28 緑の相談所の利用状況(19年度)
| 団体名 |
都市公園名 |
相談 |
講習会 |
展示会 |
| 回数 |
利用者 |
| 栃木県 |
井頭公園 |
911件 |
39回 |
766人 |
42回 |
| 中央公園 |
450 |
51 |
2,233 |
43 |
| 那須野が原公園 |
126 |
27 |
587 |
46 |
| みかも山公園 |
263 |
31 |
429 |
29 |
| 日光だいや川公園 |
397 |
40 |
1,471 |
35 |
| 宇都宮市 |
平出工業団地公園 |
1,772 |
51 |
2,313 |
3 |
| 足利市 |
有楽公園 |
824 |
28 |
7,589 |
2 |
| 合計 |
4,743 |
267 |
15,388 |
200 |
(2)緑化推進体制の充実
- ア 緑づくり人材バンク事業
- 森林や緑づくりについて専門的な知識・技術を有する人材や、ボランティア活動を実践する人材などを登録・紹介する緑づくり人材バンク(19年度末現在の登録者178名)の活用を図り、みどりづくり活動の活性化を進めるとともに、みどりに関する様々な分野の指導者や活動グループのリーダー的人材の育成のため、グリーンスタッフ養成講習会を実施した。(表2−2−29)
表2−2−29 グリーンスタッフ登録者数の推移
| 年度 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 登録者数(人) |
55 |
63 |
72 |
98 |
- イ 森林ボランティアネットワーク化の促進
- より多くの県民がみどりづくり活動に容易に参加できる環境を整えるため、ボランティア団体の相互連携を高め、情報発信する仕組みとして森林ボランティアのネットワーク化を促進し、みどりづくり推進体制の充実を図っている。
- ウ 緑の少年団の育成
- 森林での学習活動や地域の奉仕活動、レクリエーション活動を通して、自然や人を愛する心豊かな人の育成を目的とした緑の少年団が192団、39,218名で組織され、自主的な活動が展開されている。19年度は、とちぎグリーンキャンプ(参加者57名)などの交流会や緑の少年団の活動助成などを実施した。