(1) 我が国のエネルギー需要の推移
我が国のエネルギー需要(最終エネルギー消費)は、高度成長期と言われた1960(昭和35)年から1970(昭和45)年にかけて、高い経済成長率を背景に、年率12.5%と極めて高い伸び率で推移しました。
しかし、二度のオイルショックを契機に産業部門においてエネルギー利用の効率化が進展したこと等を背景に、1979(昭和54)年度以降1986(昭和61)年度までの7年間では、最終エネルギー消費全体で年平均マイナス0.4%の伸び率で推移しました。しかしながら、1987(昭和62)年度以降の内需主導型の経済成長、さらに低水準で推移するエネルギー価格等を背景にエネルギー需要は増大し、1986(昭和61)年度から1990(平成2)年度の4年間で年率4.4%の伸び率で推移しました。1990(平成2)年度以降は、景気の停滞等を背景に伸び率は鈍化しましたが、民生部門、運輸部門を中心に、依然として増加傾向にあります。
部門別に見ると、快適性や利便性を追求するライフスタイルの浸透を背景に、民生・運輸部門の伸びが顕著であり、1990(平成2)〜1998(平成10)年度の産業部門の伸び率が年平均約1%であるのに対し、民生・運輸部門では年平均約3%の伸びを示しています。
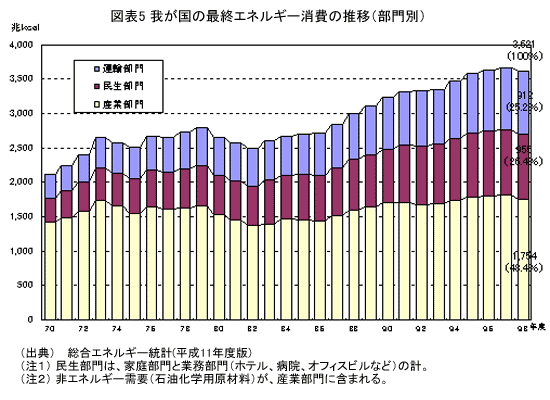
(2) 我が国のエネルギー供給構造
1998(平成10)年度の日本の一次エネルギー総供給に占める割合をエネルギー源別に見てみると、石油(52.6%)が最も高く、次いで石炭(16.4%)、原子力(13.7%)、天然ガス(12.3%)と続いています。エネルギーの石油依存度は年々低下しているものの、主要先進国に比べれば依然として高い水準にあると言えます。また、日本はエネルギーの約8割を海外に依存しており、特に石油は中東への依存度が約8割と供給国にも偏りがあります。新エネルギーについては、一次エネルギー総供給に占める割合が約1.1%(1998年度)とまだまだ低い水準にあります。このように日本のエネルギー供給構造は国際的に見ても極めて脆弱なものとなっており、エネルギーの消費抑制とエネルギー源の多様化が、他の主要先進国以上に重要な課題となっています。
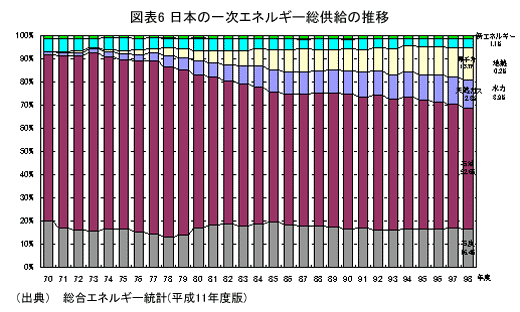
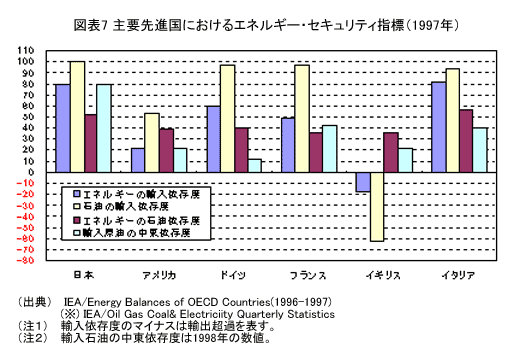
(3) 「長期エネルギー需給見通し」によるエネルギー需給見通し
ア.最終エネルギー消費の見通し
総合エネルギー調査会需給部会が1998(平成10)年6月に発表した「長期エネルギー需給見通し」※1によれば、2%程度の経済成長と既定の施策の実行を前提とした基準ケースとして、最終エネルギー消費量(原油換算)は、1996(平成8)年度の3.93億klから2010(平成22)年度には16%増の4.56億klになると予測しています。
今後、省エネルギー基準の強化等の追加的な対策を講じた場合の対策ケース(図表12参照)では、1996(平成8)年度比で約1.8%増の4.00億klになると予測しています。対策ケースは、基準ケースよりも5,600万klのエネルギーの削減を見込んでおり、特に高い伸びが予想される民生、運輸部門において一層の省エネルギーが求められます。
| 年度
項目 |
1996年度 |
2010年度 |
|
基準ケース |
対策ケース |
| |
構成比 |
年平均
伸び率
1996年
〜
2010年 |
|
構成比 |
年平均
伸び率
1996年
〜
2010年 |
| |
構成比 |
| 産 業 |
億kl
1.95 |
%
49.6 |
億kl
2.13 |
%
46.7 |
%
0.6 |
億kl
1.92 |
%
47.9 |
%
▲0.1 |
| 民 生 |
1.02 |
26.0 |
1.31 |
28.7 |
1.8 |
1.13 |
28.3 |
0.8 |
| 運 輸 |
0.96 |
24.5 |
1.12 |
24.6 |
1.1 |
0.95 |
23.7 |
▲0.1 |
| 合 計 |
3.93 |
100.0 |
4.56 |
100.0 |
1.1 |
4.00 |
100.0 |
0.1 |
イ.一次エネルギー供給の見通し
一次エネルギー供給量は、既定の施策の実行を前提とした基準ケースで、1996(平成8)年度の5.97億klから2010(平成22)年度には16%増の6.93億klになると予測しています。追加的な対策を講じた場合の対策ケースでは、1996(平成8)年度比で約3.2%増の6.16億klになると予測しています。
対策ケースでは、1996(平成8)年度における石油依存度(55.2%)を原子力や天然ガス、新エネルギー等の割合を高めることにより、2010(平成22)年度までに47.2%まで引き下げるとしています。
図表9 一次エネルギー供給の見通し
年度
項目 |
1990年度
|
1996年度
|
2010年度 |
基準ケース
|
対策ケース
|
| 一次エネルギー総供給 |
5.26億kl |
5.97億kl |
6.93億kl |
6.16億kl |
エネルギー別区分
|
実 数
|
構成比(%) |
実 数
|
構成比(%) |
実 数
|
構成比(%) |
実 数
|
構成比(%) |
| 石油 |
3.07億kl |
58.3 |
3.29億kl |
55.2 |
3.58億kl |
51.6 |
2.91億kl |
47.2 |
| 石油(LPG輸入除く) |
2.88億kl |
54.8 |
3.10億kl |
51.9 |
3.37億kl |
48.6 |
2.71億kl |
44.0 |
| LPG輸入 |
1,430万t |
3.5 |
1,520万t |
3.3 |
1,610万t |
3.0 |
1,510万t |
3.2 |
| 石炭 |
11,530万t |
16.6 |
13,160万t |
16.4 |
14,500万t |
15.4 |
12,400万t |
14.9 |
| 天然ガス |
3,790万t |
10.1 |
4,820万t |
11.4 |
6,090万t |
12.3 |
5,710万t |
13.0 |
| 原子力 |
2,020億kWh |
9.4 |
3,020億kWh |
12.3 |
4,800億kWh |
15.4 |
4,800億kWh |
17.4 |
| 水力 |
910億kWh |
4.2 |
820 億kWh |
3.4 |
1,050億kWh |
3.4 |
1,050億kWh |
3.8 |
| 地熱 |
50万kl |
0.1 |
120万kl |
0.2 |
380万kl |
0.5 |
380万kl |
0.6 |
| 新エネルギー等 |
679万kl |
1.3 |
685万kl |
1.1 |
940万kl |
1.3 |
1,910万kl |
3.1 |
(出典) 総合エネルギー調査会需給部会中間報告(1998年6月)図表10 新エネルギー供給の見通し
■新エネルギー
|
年度
項目 |
1990年度
|
1996年度
|
2010年度 |
基準ケース
|
対策ケース
|
| 太陽光発電 |
0.9万kW
(0.2万kl) |
5.7万kW
(1.4万kl) |
23万kW
(6万kl) |
500万kW
(122万kl) |
| 太陽熱利用 |
126万kl |
104万kl |
109万kl |
450万kl |
| 風力発電 |
0.3万kW
(0.1万kl) |
1.4万kW
(0.6万kl) |
4万kW
(2万kl) |
30万kW
(12万kl) |
| 廃棄物発電 |
48万kW
(44万kl) |
89万kW
(82万kl) |
213万kW
(282万kl) |
500万kW
(662万kl) |
| 廃棄物熱利用 |
3.7万kl |
4.4万kl |
12万kl |
14万kl |
| 温度差エネルギー |
1.8万kl |
3.3万kl |
9万kl |
58万kl |
| 黒液・廃材等 |
503万kl |
490万kl |
517万kl |
592万kl |
合 計
[一次エネルギー総供給に占める割合] |
679万kl
[1.3%]
|
685万kl
[1.1%]
|
940万kl
[1.3%]
|
1,910万kl
[3.1%]
|
(注) ( )内は原油換算
■従来型エネルギーの新利用形態
コージェネレーション
(スチームタービンを除く) |
199万kW |
385万kW |
813万kW |
1,002万kW |
| クリーンエネルギー自動車 |
0.1万台 |
1.2万台 |
28万台 |
365万台 |
| 燃料電池 |
0.9万kW |
1.6万kW |
55万kW |
220万kW |
(注) 燃料電池のうちコージェネレーションタイプのものはコージェネレーションの内数としても計上
(出典) 総合エネルギー調査会需給部会中間報告(1998年6月)
|
![]()