1 発生源対策
(1) 生活排水対策
課 題
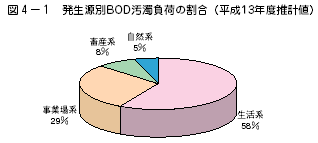
施策の内容
1.汚水処理施設の整備
2.生活排水対策の普及啓発
*1 市町村自らが浄化槽の設置主体となり、その後の維持管理も行っていく制度。
(2)工場・事業場対策
課 題
-
工場・事業場排水に起因する河川への有機性汚濁負荷は、全体の29%を占めている。また、水質汚濁防止法等や県公害防止条例に基づく排水基準適合率は平成14年度は93.9%*1と前年度より3ポイント高くなっているが、今後は、規制基準の適用を受けない小規模な事業場等からの排水水質についても汚濁負荷の低減に取り組むことが重要である。
-
家畜排せつ物の素堀り、野積みによる貯留等は、河川や地下水等の汚染を引き起こすおそれがある。
施策の内容
1.工場・事業場に対する監視、指導
-
水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び県公害防止条例に基づく立入検査を実施する。
-
ダイオキシン類対策特別措置法及び工場・事業場排水等自主管理要領に基づき、工場・事業場に対し、排出水の水質測定及び結果の報告を求めることなどにより、排水処理施設等の適切な維持管理を指導する。
-
廃棄物処理施設の安全性を確保するため、廃棄物処理業者等に対する指導監督を強化する。また、産業廃棄物の管理型最終処分場については、公共関与により安全性と信頼性の高い施設の整備を計画的に進める。
-
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の円滑な運用を図り、家畜排せつ物処理施設の整備を計画的に進める。
2.工場・事業場の自主的な取組の促進
-
環境保全に関する講習会の開催や、公害防止や環境管理についての専門知識を有する者を工場・事業場に派遣することにより、事業場の環境保全に関する取組を支援する。
-
工場・事業場の自主的な環境管理を促し、水環境への負荷を低減していくため、ISO14001や環境活動評価プログラム(エコアクション21)*2の導入促進を支援する。
-
中小企業者等に排水処理施設の整備や環境保全事業等の実施に必要な資金を融資する。
*1 資料:「平成15年度環境の状況及び施策に関する報告書」(栃木県)
*2 環境活動評価プログラムは、中小事業者等の幅広い事業者に対して、自主的に「環境との関わりに気づき、目標を持ち、行動する」ことができる、環境マネジメントの簡易な方法である。
(3)その他の汚染源対策
課 題
施策の内容
1.森林地域対策
2.農業地域対策
3.都市地域対策
4.不法投棄対策
*1 望ましい森林の姿は、下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射し込み、落葉などの有機物が土壌に豊富に供給され、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し、土壌を保持する能力や水を蓄える土壌中のすき間が十分に形成され保水する能力に優れた森林である。
2 河川・湖沼の浄化
課 題
-
全県的に河川水質の状況を概観すると、人の健康の保護に関する項目については、数地点で環境基準を超過する年もあるものの、ほとんどの地点で環境基準を達成している。また、生活環境の保全に関する項目のうち、BODの環境基準達成状況を経年的にみると、水質は改善傾向にある。今後も環境基準の達成率の向上が課題である。
-
市街地を流れる河川や水路等では、さらに水質の改善が必要な地域もみられる。
-
湖沼においては、流域から窒素、りんなどの栄養塩類が流入することにより、植物性プランクトンが増殖し、水質が悪化する富栄養化の進行が懸念されている。
施策の内容
1.浄化施設の設置
2.自然浄化機能の活用
3.地域住民による取組の促進
*1 県、日光市が、関係団体等の協力を得ながら、湯ノ湖、湯川、中禅寺湖の水質保全対策を総合的かつ計画的に推進することを目的に設立された。
3 有害化学物質等による汚染の防止
(1)化学物質対策
課 題
-
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)では、化学物質による環境への影響の未然防止の観点から、事業者が、有害性を持つ化学物質の環境中への排出量を把握し、届出を行うこととされており、本法の趣旨を踏まえ、化学物質の適正管理を推進していく必要がある。
-
内分泌攪乱化学物質*1については、人体への影響等科学的に解明されていない点も多いものの、将来にわたる影響が懸念されている。
-
農薬の安全かつ適正な使用及び適切な保管管理の徹底は、農業生産の安定のみならず、県民の健康の保護及び生活環境の保全の観点からも重要である。
施策の内容
1.汚染防止対策の推進
-
PRTR法の円滑な施行のため、制度の普及啓発に努め、工場・事業場における有害な化学物質の排出量の抑制を図る。
-
ダイオキシン類については、環境汚染状況を把握・監視するための調査を行う。
-
現在、県内では水環境中に内分泌攪乱化学物質が著しく検出されるような状況にはないが、今後も引き続き監視を行い、県内の状況を把握していく。
-
環境に配慮した農業生産を確立するため、農業生産を安定化させながら、農薬や化学肥料の使用量を削減する等、環境保全型農業を推進する。
2.化学物質についての情報の共有
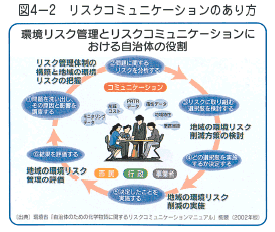
*1 環境ホルモンともいわれ、外部から体内に入って、生体内で営まれている正常なホルモン作用(内分泌)に影響を与えている化学物質をいう。
(2)水道水等の水質保全
課 題
施策の内容
1.水道水の安全確保
2.飲用井戸の安全確保
3.水源の保護
-
市町村(水道事業者等)が行う水道原水の水質保全のための行動計画の策定、普及啓発活動を支援する。
-
水源地域の森林を保全するため、保安林の指定、森林計画に基づく適切な森林整備、治山事業を推進する。
-
大規模開発に対しては、環境影響評価制度や各種開発関係法令等を厳格に運用し、適切な開発あるいは開発規制を行う。
*1 腸管寄生性原虫のひとつであり、人間が感染した場合下痢や腹痛を起こすことがある。
4 水質の監視
(1)水質監視体制の充実
課 題
施策の内容
1.公共用水域の水質監視
2.異常水質対策
(2)環境基準類型指定の見直し
課 題
施策の内容
*1 水質汚濁防止法の規定に基づき、県内の公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定計画である。
*2 水質汚濁に関する環境基準については、国において類型別に基準値が示され、これに基づき都道府県が河川等の状況を勘案し、具体的に地域に当てはめ、指定していくことをいう。(資料編参照)

