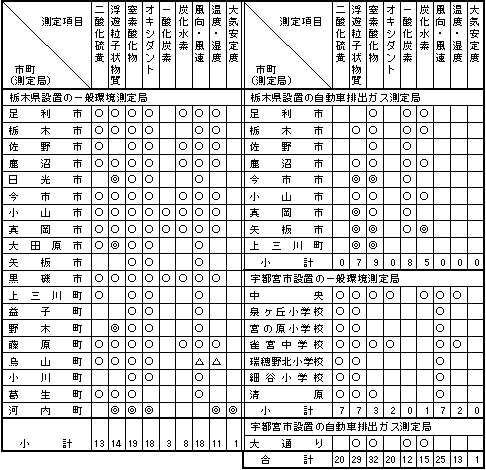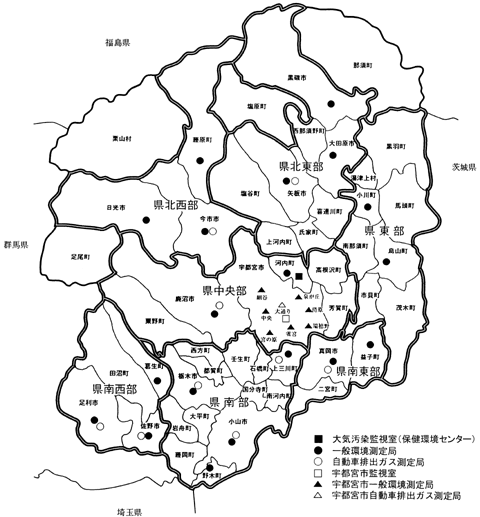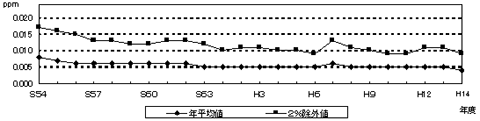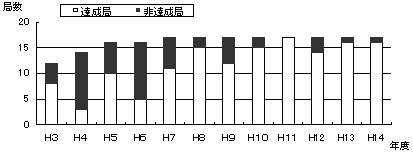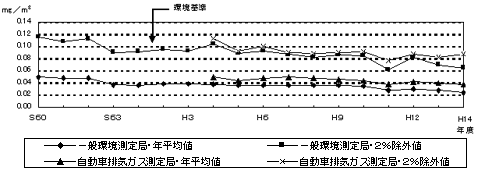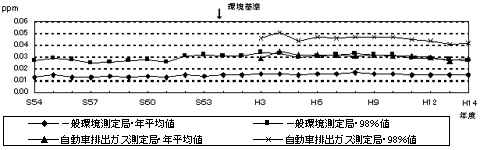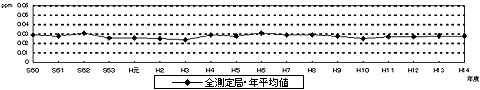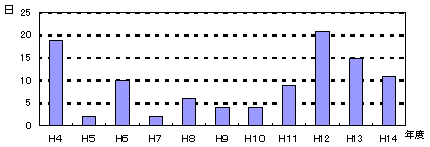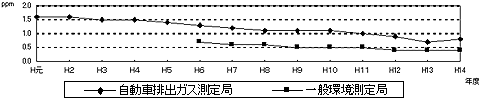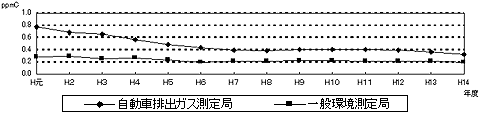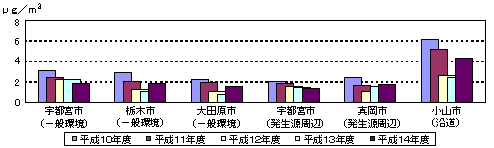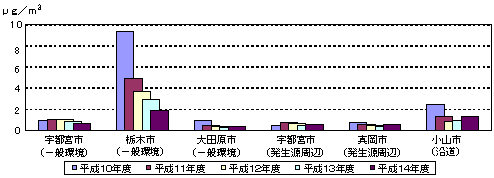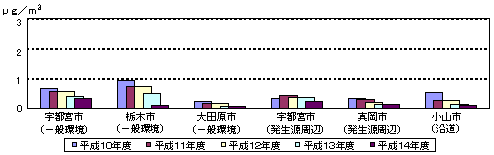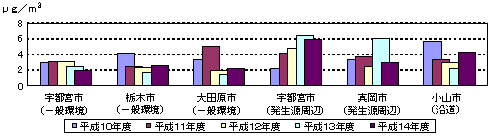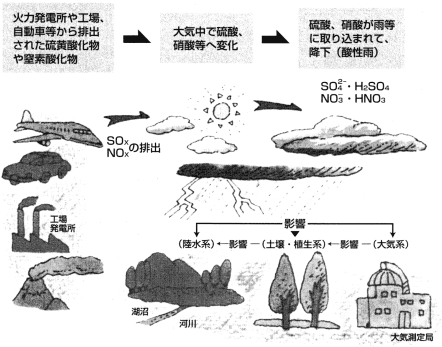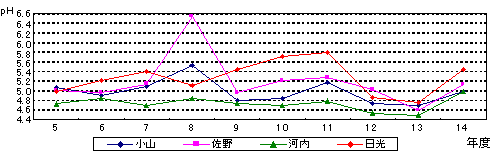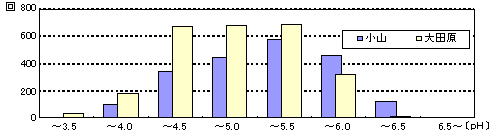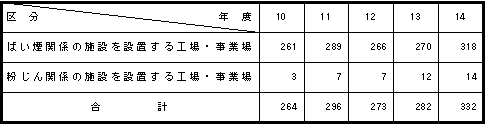|

�@��C�̉����ɌW������́A�u����{�@�v�ɂ��A����̏����ɂ��Đl�̌��N��ی삷���ňێ����邱�Ƃ��]�܂�����Ƃ��Ē�߂��Ă���B��_�������A��_�����f�A��_���Y�f�A�����w�I�L�V�_���g�A���V���q���A�x���[���A�g���N�����G�`�����A�e�g���N�����G�`�����A�W�N�������^���̂X�����ɂ��Ē�߂��Ă���B
�@�܂��A12�N1���Ɏ{�s���ꂽ�u�_�C�I�L�V���ޑ����ʑ[�u�@�v�ɂ��A�_�C�I�L�V�����ɂ��Ċ������߂�ꂽ�B
�@���̂ق��A�Y�����f�ɂ��ẮA�����w�I�L�V�_���g�̊����B�����邽�߁A�s����̖ڕW�Ƃ��āA�Z�x�w�j����߂��Ă���B
�\�Q�|�P�|�P�@��C�����ɌW������
| ���� |
����̏��� |
|
��_������ |
�P���Ԓl�̂P�����ϒl��0.04ppm�ȉ��ł���A���A�P���Ԓl��0.10ppm�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
��_�����f |
�P���Ԓl�̂P�����ϒl��0.04ppm����0.06ppm�܂ł̃]�[�������͂���ȉ��ł��邱�ƁB |
|
��_���Y�f |
�P���Ԓl�̂P�����ϒl��10ppm�ȉ��ł���A���A�P���Ԓl�̂W���ԕ��ϒl��20ppm�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
�����w�I�L�V�_���g |
�P���Ԓl��0.06ppm�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
���V���q�� |
�P���Ԓl�̂P�����ϒl��0.10mg/m�R�ȉ��ł���A���A�P���Ԓl��0.20mg/m�R�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
�x���[�� |
�P�N���ϒl��0.003mg/m�R�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
�g���N�����G�`���� |
�P�N���ϒl��0.2mg/m�R�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
�e�g���N�����G�`���� |
�P�N���ϒl��0.2mg/m�R�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
�W�N�������^�� |
�P�N���ϒl��0.15mg/m�R�ȉ��ł��邱�ƁB |
|
�Y�����f |
�ߑO�U������X���܂ł̔^���Y�����f�̂R���ԕ��ϒl��0.20ppm�b����0.31ppm�b�܂ł͈͓̔����͂���ȉ��ł��邱�ƁB |
�i���j�_�C�I�L�V���ނɌW�����ɂ��ẮA�������Ɏ����B
(1) ��C�����펞�Ď�
�@�{���ł́A�u��C�����h�~�@�v�Ɋ�Â���C�����̏��Ď����邽�߁A36�����̑���ǁi��ʊ�26�ǁA�����Ԕr�o�K�X10�ǁj�ŏ펞�Ď������{���Ă���B����́A����28�ǁi��ʊ�19�ǁA�����Ԕr�o�K�X9�ǁi14�N�x�Ɉ�ʊ��ǁA�����Ԕr�o�K�X�ǂ��ꂼ��1�ǐV�݁j�A�F�s�{�s��8�ǁi��ʊ�7�ǁA�����Ԕr�o�K�X1�ǁj�̑���ǂōs���Ă���B�i�\�Q�|�P�|�Q�j
�@�����̑���f�[�^�͌��ی����Z���^�[���̑�C�����Ď����ŏW���Ď����Ă���A��C�����̔c���A�����w�X���b�O���ӕ�̔��ߓ��A�ً}���̑��v���ɍs���Ă���B�i�}�Q�|�P�|�P�j
�\�Q�|�P�|�Q�@��C�����Ď��̐��@�@�@�@�@�i15�N3�������݁j
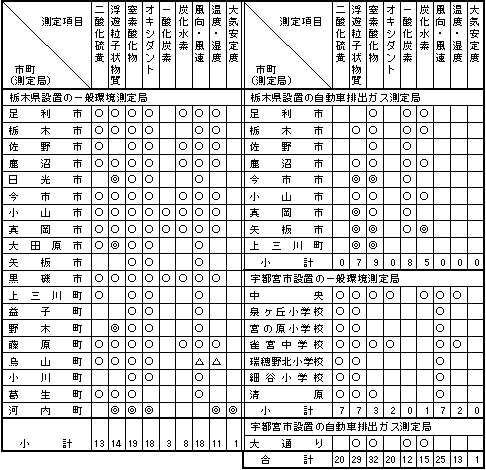
�i���j���F�N�ԗL�����莞�ԁi6,000���ԁj�����Ă��Ȃ��B
�@�@�@���F15�N�R�����瑪��J�n
�@�@�@���̂����A��ʋǂ̍���s�i�Y�����f�A���x�E���x�j�A�����s�i�Y�����f�j�A���s�s�i�Y�����f�j�A��c���s�i��_�������j�A�������i���f�_�����A�Y�����f�j�y�ю��r�ǂ̎����s�i��_���Y�f�j�ɂ��ẮA15�N�R���ɔp�~�����B
�}�Q�|�P�|�P�@��C�����펞�Ď���
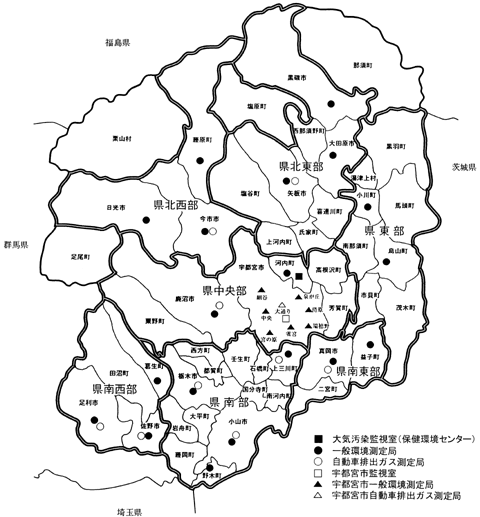
(2) ������̒B���i�\�Q�|�P�|�R�j
|
�� |
�@��_�������ɂ��ẮA�����I�]���ł́A���ׂĂ̑���ǂŊ����B�����A�Z���I�]���ł́A20����ǒ�17����ǂ��B�����Ă���A��N�x�ɔ�חǍD�ȏł���B |
|
�� |
�@���V���q���ɂ��ẮA�����I�]���ł́A21����ǒ�17����ǂ̒B���ł��������A�Z���I�]���ł́A21����ǒ�4����ǂ̒B���ł���B |
|
�� |
�@��_�����f�ɂ��ẮA���ׂĂ̑���ǂŊ����B�����Ă���B |
|
�� |
�@�����w�I�L�V�_���g�ɂ��ẮA���ׂĂ̑���ǂŊ�����B������Ă��Ȃ��B |
|
�� |
�@��_���Y�f�ɂ��ẮA���ׂĂ̑���ǂŁA�����I�]���A�Z���I�]���Ƃ��Ɋ����B�����Ă���B |
�\�Q�|�P�|�R�@��C�����ɌW�����B����
| ���荀�� |
�]�����@ |
�敪 |
�P�S�N�x |
�P�R�N�x |
| ��ʋ� |
���r�� |
��ʋ� |
���r�� |
��_������
�i�r�n�Q�j |
�����I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
20/20 |
�| |
20/20 |
�| |
|
�B�����i���j |
100.0 |
�| |
100.0 |
�| |
�Z���I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
17/20 |
�| |
9/20 |
�| |
|
�B�����i���j |
85.0 |
�| |
45.0 |
�| |
���V���q��
�i�r�o�l�j |
�����I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
16/17 |
1/4 |
16/17 |
2/3 |
|
�B�����i���j |
94.1 |
25.0 |
94.1 |
66.7 |
�Z���I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
4/17 |
0/4 |
4/17 |
0/3 |
|
�B�����i���j |
23.5 |
0 |
23.5 |
0 |
��_�����f
�i�m�n�Q�j |
�����I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
21/21 |
7/7 |
21/21 |
7/7 |
|
�B�����i���j |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
�����w�I�L�V�_���g
�i�n�w�j |
�Z���I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
0/19 |
�| |
0/19 |
�| |
|
�B�����i���j |
0 |
�| |
0 |
�| |
��_���Y�f
�i�b�n�j |
�����I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
3/3 |
9/9 |
3/3 |
9/9 |
|
�B�����i���j |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
�Z���I
�]�� |
�B���ǐ��^�L������ǐ� |
3/3 |
9/9 |
3/3 |
9/9 |
|
�B�����i���j |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
�i���j�P |
�����I�]���Ƃ́A�N�Ԃɂ킽�鑪�茋�ʂ��I�Ɋώ@������ŕ]��������@�������B |
|
�Q |
�Z���I�]���Ƃ́A�A�����āA�܂��͐����ɍs�������茋�ʂɂ��A������s���������͎��Ԃɂ��ĕ]��������@�������B |
|
�R |
�L������ǂƂ́A���莞�Ԃ�6,000���Ԉȏ�̑���ǂ������B |
|
�S |
��ʋǂƂ͈�ʊ�����ǁA���r�ǂƂ͎����Ԕr�o�K�X����ǂ������B�i�\�Q�|�P�|�Q�A�}�Q�|�P�|�P�Q�Ɓj |
(3) ��_������
�@��_�������́A20�����ő��肵�Ă��邪�A���̌��ʂ́A�S����ǂ̔N���ϒl��0.004ppm�ł���A�ߔN�����ł���B�i�}�Q�|�P�|�Q�j
�@����܂ł̖@�K���A�R���̒ᗰ�����A�H��w�����ɂ��A�H��E���Əꂩ��̉��������̔r�o�ʂ͒����ɍ팸���}���Ă������̂ƍl������B
�}�Q�|�P�|�Q�@��_�������̌o�N�ω�
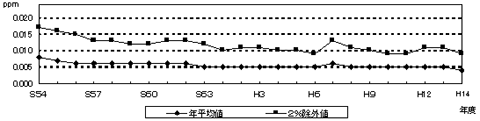
(4) ���V���q��
�@���V���q���́A��ʊ�����ǁi17�����j�Ǝ����Ԕr�o�K�X����ǁi4�����j�ɂ����ď펞�Ď������{���Ă���B���̌��ʂ́A��ʊ�����ǂ̔N���ϒl��0.025mg/m3�A�����Ԕr�o�K�X����ǂ̔N���ϒl��0.038mg/m3�ł���A�������N�����X���ɂ���B
�@���V���q���̎�Ȕ������͍H��E���Ə�⎩���Ԃł���B
�i�}�Q�|�P�|�S�j
�}�Q�|�P�|�R�@���V���q���̊���B����
�@�@�@�@�@�@�@�@�i��ʊ�����ǁj
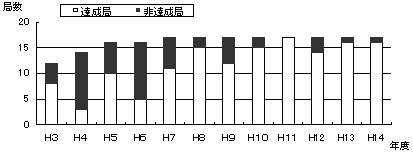
�}�Q�|�P�|�S�@���V���q���̌o�N�ω�
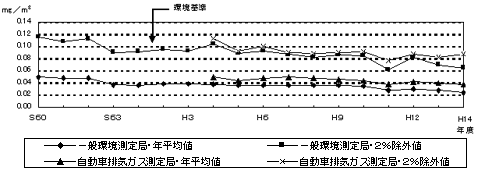
(5) ��_�����f
�@��_�����f�́A��ʊ�����ǁi21�����j�Ǝ����Ԕr�o�K�X����ǁi7�����j�ŏ펞�Ď������{���Ă���A��ʊ�����ǂɂ�����N���ϒl��0.015ppm�A�����Ԕr�o�K�X����ǂœ�0.029ppm�ł���B�����Ԕr�o�K�X�̉e���ɂ��A�����Ԕr�o�K�X����ǂ̔Z�x�͈�ʊ�����ǂ̂ق�2�{�ƂȂ��Ă���B�i�}�Q�|�P�|�T�j
�}�Q�|�P�|�T�@��_�����f�Z�x�̌o�N�ω�
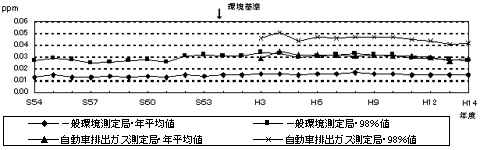
(6) �����w�I�L�V�_���g
�@�����w�I�L�V�_���g�́A����19�����ŏ펞�Ď������{���Ă���B���̌��ʂ́A���ԁi5�`20���j�̔N���ϒl��0.028ppm�ł���A�������N�����̌X���ɂ���B�i�}�Q�|�P�|�U�j
�@�����w�I�L�V�_���g�ɂ��ẮA���ׂĂ̑���ǂŊ����B�����Ă��炸�A���ɉĊ��ɂ����Ă͋C�ۏ������ɂ�荂�Z�x�ɂȂ邱�Ƃ�����A�����w�X���b�O�̔������₷���ɂ���B
�}�Q�|�P�|�U�@�����w�I�L�V�_���g�̌o�N�ω�
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�T���`20���̔N���ϒl�j
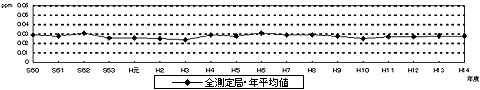
�@���ł́A�����w�X���b�O�����\��Ɩ����A4��1������9��30���܂ł�183���Ԏ��{���Ă���B���̌��ʂ́A���ӕ�̔��ߓ�����11���ł������B
�@�n��ʔ��ߏ́A���쐼����9���A���암��9���A���쓌����2���A����������9���A��������2���A���k������3���A���k������3���ł������B�i�}�Q�|�P�|�V�j
�@�Ȃ��A���N��Q�̔����͂Ȃ������B
�}�Q�|�P�|�V�@�����w�X���b�O���ӕߓ����̌o�N�ω�
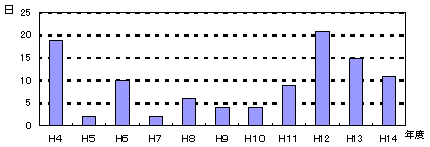
(7) ��_���Y�f
�@��_���Y�f�́A��ʊ�����ǁi3�����j�Ǝ����Ԕr�o�K�X����ǁi9�����j�Ŏ��{���Ă���B���̌��ʂ́A��ʊ�����ǂ̔N���ϒl��0.4ppm�A�����Ԕr�o�K�X����ǂ̔N���ϒl��0.8ppm�ŁA������̋ǂ������Ԕr�o�K�X�K���̋����ɔ����A�����X���ɂ���B�i�}�Q�|�P�|�W�j
�}�Q�|�P�|�W�@��_���Y�f�̌o�N�ω�
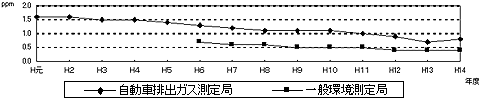
(8) �Y�����f
�@�Y�����f�́A��ʊ�����ǁi9�����j�Ǝ����Ԕr�o�K�X����ǁi5�����j�ŏ펞�Ď������{���Ă���B�^���Y�����f�̌��ʂ��݂�ƁA6�`9���ɂ�����N���ϒl�́A�Y�f���Z�ň�ʊ�����ǂ�0.19ppm�A�����Ԕr�o�K�X����ǂ�0.32ppm�ł���A��ʊ�����ǁA�����Ԕr�o�K�X����ǂƂ������̌X���������Ă���B�i�}�Q�|�P�|�X�j
�@���ׂĂ̑���ǂ��A�����w�I�L�V�_���g�̊����B�����邽�߂̖ڕW�l�Ƃ��Ē�߂��Ă���Z�x�w�j�߂��Ă���B
�}�Q�|�P�|�X�@�^���Y�����f�̌o�N�ω�
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�U�`�X���̕��ϒl�̔N���ϒl�j
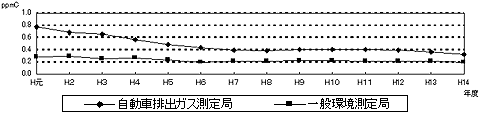
(9) �L�Q��C��������
�@���N���X�N�������ƍl�����D��I�ɑ�Ɏ��g�ނׂ��Ƃ���Ă����L�Q��C��������(22�����j�̂����A������@�̊m������Ă���18�����ɂ��āA��C�����h�~�@��18����23�̋K��Ɋ�Â���ʊ��R�n�_�A�Œ蔭�������Ӂi�H�ƒc�n���Ӂj�R�n�_�A�����P�n�_�̍��v�V�n�_�ŁA���P��24���Ԃ̍̎�ɂ��N�Ԃ�ʂ��ă��j�^�����O�����{�����B
�@������ݒ肳��Ă���S�����i�x���[���A�g���N�����G�`�����A�e�g���N�����G�`�����y�уW�N�������^���j�́A�x���[���ɂ��ĂP�n�_�Ŋ���߂������A���̑��͊�������Ă����B
�@10�N�x����p�����Ē������Ă���U�n�_�̃x���[���A�g���N�����G�`�����A�e�g���N�����G�`�����y�уW�N�������^���̔Z�x��}�Q�|�P�|10�A�}�Q�|�P�|11�A�}�Q�|�P�|12�y�ѐ}�Q�|�P�|13�Ɏ����B
�}�Q�|�P�|�P�O�@�p�������n�_�̗L�Q��C��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�x���[���j�̑��茋�ʁi�N���ϒl�j
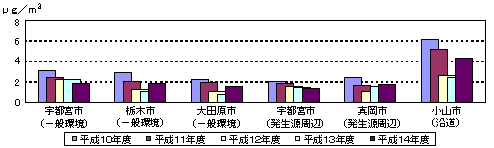
�}�Q�|�P�|�P�P�@�p�������n�_�̗L�Q��C��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g���N�����G�`�����j�̑��茋�ʁi�N���ϒl�j
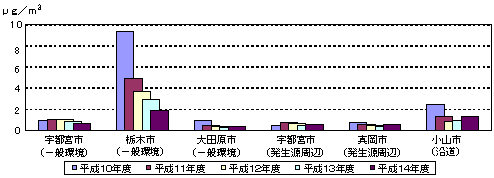
�}�Q�|�P�|�P�Q�@�p�������n�_�̗L�Q��C��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�e�g���N�����G�`�����j�̑��茋�ʁi�N���ϒl�j
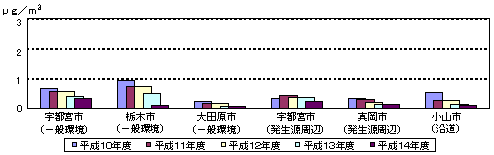
�}�Q�|�P�|�P�R�@�p�������n�_�̗L�Q��C��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�W�N�������^���j�̑��茋�ʁi�N���ϒl�j
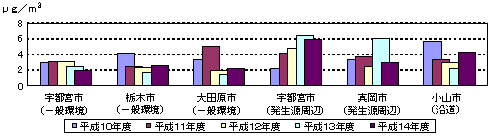
(10) �_���J
�@���B��k�ē��ɂ����ẮA�_���J�������Ƃ݂���Ώ��̎_������X�є�Q�Ȃǂ��L��I�ɔ������A�n���K�͂̊����̈�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B�i�}�Q�|�P�|�P�S�j
�@��ʂɁA���g��5.6�ȉ��̉J�͎_���J�Ƃ����Ă���A�H�ꓙ�̂����⎩���Ԕr�o�K�X����������_���������f�_��������C���ɕ��o����A���_�C�I����Ɏ_�C�I���ɕω����A�J�����Ɏ�荞�܂�邽�߂ɐ�������̂ƍl�����Ă���B
�@�_���J�����̈�Ƃ��āA��ߎ��̎摕�u�ɂ��1�����P�ʂ̎_���~�����ʂ̒�����4�n�_�ŁA�܂��A�_���J�������葕�u�ɂ��~����0.5mm���Ƃ����g�A�d�b�i�d�C�`���x�j�̏펞�Ď���3�n�_�ŁA���ꂼ����{���Ă���B
�@��ߎ��̎摕�u�ɂ�钲�����ʂł́A4�n�_�̂��g�̔N���ϒl��4.98�`5.45�i13�N�x4.50�`4.72�j�͈̔͂ł���A�O�N��荂���l�ƂȂ����B�܂��A�_���J�������葕�u�ɂ�钲�����ʂł́A2�n�_�̂��g�̔N���ϒl�́A���R��4.6�ŁA��c����4.3�i13�N�x4.4�j�ł������B�i�}�Q�|�P�|�P�T�C�}�Q�|�P�|�P�U�j
�@�܂��A�_���J���L��I�ȉ����ł����邱�Ƃ���A�W�s���Ƃ̋��������i�֓��n���������i�{���̎_���J���������j�ɐϋɓI�ɎQ������ȂǁA�����E���������p�����Ď��{���Ă���B
�}�Q�|�P�|�P�S�@�_���J�����̎d�g��
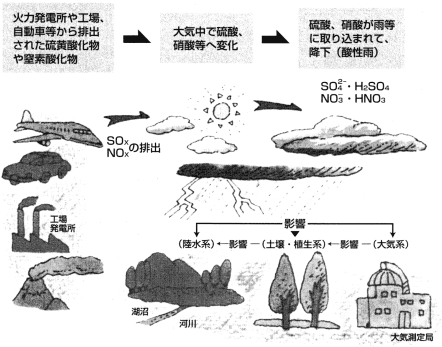
�}�Q�|�P�|�P�T�@��ߎ��̎摕�u�ɂ��J�̂��g�̌o�N�ω�
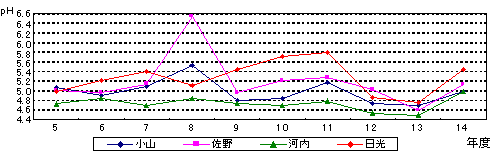
�}�Q�|�P�|�P�U�@�~����0.5mm���Ƃ̂��g�p�x���z�}
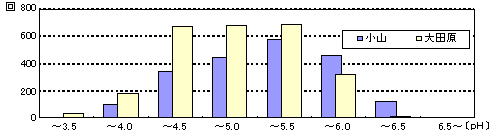
�@�_���J�ɔ�אA�����ւ̉e�����傫���Ƃ����Ă���_�����ɂ��āA6�N�x��������s�����i�����������j�ɖ������̎摕�u��ݒu���A�������s���Ă���B14�N�x�̌��ʂł́A���g�̍ő�l��6.60�A�ŏ��l��4.45�A���ϒl��5.37�ł������B
(11) �������ɂ������~���������ʒ���
�@14�N�x�́A�����𒆐S��3�n�_�Œ��������{�����B
�@���̌��ʂ͔N���ϒl��4.9�`15.8t/km2/���i13�N�x4.8�`16.1t/km2/���j�ł���A�����̌X���ł������B
�@��C���̕ۑS��}�邽�߁A�u��C�����h�~�@�v�y�сu�Ȗ،����Q�h�~���v�Ɋ�Â��H��E���Ə�ւ̗������������{���Ă���B
�@�܂��A�u�H��E���Ə����������Ǘ��v�́v�Ɋ�Â��A�����ʓ��̎��呪��y�ь��ʂ̕����߂�Ȃǂɂ��A�{�݂̓K�Ȉێ��Ǘ���}��悤�w�����Ă���B
(1) �K���
�@�{���ł́A�u��C�����h�~�@�v�Ɋ�Â��ꗥ��ɉ����āA���@��S���P���̋K��Ɋ�Â��A�L�Q�����i�ӂ��f�y���������f�j�ɂ��ď��ł�茵������悹�r�o����߂Ă���B
�@�܂��u�Ȗ،����Q�h�~���v�ł́A�S��ނ������ɌW�����{�݂��߁A�r�o���ݒ肵�Ă���B�������ɂ��ẮA�R��ނ̓���{�݂��߁A�{�݂̊Ǘ�����K�肵�Ă���B
(2) �����W�{�y�ѕ�����W�{�݂̓͏o��
�@�u��C�����h�~�@�v�A�u�Ȗ،����Q�h�~���v�Ɋ�Â��A�����y�ѕ�����W�{�݂̓͏o�́A�\�Q�|�P�|�S�A�\�Q�|�P�|�T�̂Ƃ���ƂȂ��Ă���B
�\�Q�|�P�|�S�@�����W�{�ݓ��͏o�i15�N�R��31�����݁j
�@�@��C�����h�~�@
| ���������{�� |
�{�@�݁@���@�i���j |
| ���� |
�F�s�{�s�� |
�v |
|
�{�C���[ |
3,019 |
652 |
3,671 |
|
�n��F |
242 |
16 |
258 |
|
�������M�F |
228 |
38 |
266 |
|
�Đ��F�y�їn�Z�F |
27 |
1 |
28 |
|
�����F |
180 |
26 |
206 |
|
�p�����ċp�F |
110 |
27 |
137 |
|
���̑��̎Y�ƘF |
56 |
108 |
164 |
|
�{�ݍ��v |
3,862 |
868 |
4,730 |
|
�͏o�H��E���Əꐔ |
1,610 |
310 |
1,920 |
�A�@�Ȗ،����Q�h�~���
| �����ɌW�����{�� |
�{�@�݁@���@�i���j |
| ���� |
�F�s�{�s�� |
�v |
|
�������ͱ��Ƴт̑���B�̗p�ɋ�����n��F |
37 |
1 |
38 |
|
�������i�̐����̗p�ɋ�����\�ʏ����{�y�ю_��{�� |
3 |
0 |
3 |
|
���̑� |
0 |
0 |
0 |
|
�{�ݍ��v |
40 |
1 |
41 |
|
�͏o�H��E���Əꐔ |
16 |
1 |
17 |
�\�Q�|�P�|�T�@������W�{�ݓ��͏o�i15�N�R��31�����݁j
�@�@��C�����h�~�@�i��ʕ�����j
| ��ʕ������{�� |
�{�@�݁@���@�i���j |
| ���� |
�F�s�{�s�� |
�v |
| �͐Ϗ� |
205 |
15 |
220 |
| �R���x�A |
688 |
16 |
704 |
| �j�Ӌ@�E���Ӌ@ |
314 |
9 |
323 |
| �ӂ邢 |
142 |
0 |
142 |
|
�{�ݍ��v |
1,349 |
40 |
1,389 |
|
�͏o�H��E���Əꐔ |
231 |
12 |
243 |
�A�@��C�����h�~�@�i���蕲����j
| ���蕲�����{�� |
�{�@�݁@���@�i���j |
| ���� |
�F�s�{�s�� |
�v |
| ��ȗp�@�B |
3 |
0 |
3 |
| �����@ |
9 |
0 |
9 |
| �ؒf�@ |
5 |
0 |
5 |
| �����@ |
6 |
0 |
9 |
| �؍�p�@�B |
7 |
0 |
7 |
| �j�Ӌ@�E���Ӌ@ |
2 |
0 |
2 |
| �v���X |
8 |
13 |
21 |
| ���E�@ |
1 |
0 |
1 |
|
�{�ݍ��v |
41 |
13 |
54 |
|
�͏o�H��E���Əꐔ |
5 |
1 |
6 |
�B�@�Ȗ،����Q�h�~���
| ������ɌW�����{�� |
�{�@�݁@���@�i���j |
| ���� |
�F�s�{�s�� |
�v |
|
�������͗L�@�엿�̗p�ɋ����镲�ӎ{�y�тӂ邢 |
16 |
0 |
16 |
|
�q�Ɠy�Ζ��͍z���̗p�ɋ�����{�� |
�j�Ӌ@�E���Ӌ@ |
98 |
8 |
106 |
| �ӂ邢 |
91 |
8 |
99 |
| �����{�� |
23 |
0 |
23 |
| ��{�� |
56 |
0 |
56 |
| �͐Ϗ� |
62 |
5 |
67 |
|
�����Y���͒Y�f���i�̗p�ɋ�����{�� |
�����Y�����{�� |
22 |
0 |
22 |
| ���Y�A���Y�����{�� |
1 |
1 |
2 |
| �f�D�����{�� |
8 |
0 |
8 |
|
�{�ݍ��v |
377 |
22 |
399 |
|
�͏o�H��E���Əꐔ |
121 |
13 |
134 |
(3) �H��E���Ə�ɑ��闧��������
�@14�N�x�́A����332�H�ꓙ�ɂ��ė������������{�����B�i�\�Q�|�P�|�U�j
�@���̌��ʁA�����������̎w�������̎�ȓ���́A�͏o�̕s��33��(40.2%)�A���啪�̖͂����{18��(22.0%)�ł������B�i�\�Q�|�P�|�V�j
�\�Q�|�P�|�U �����������{��
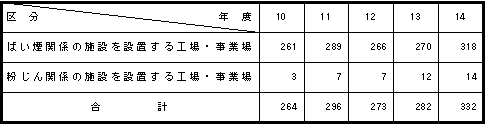
(��) �P�@14�N�x�̂����W�̗����������{���́A����281���A�F�s�{�s�ϔC��37��
�@�@�@�Q�@14�N�x�̕�����W�̗����������{���́A���� 12���A�F�s�{�s�ϔC�� 2��
�\�Q�|�P�|�V�@���������w�����e�i14�N�x�j
| �w������ |
�{�ݐ��i���j |
| �����{�� |
�F�s�{�s���{�� |
���v |
| �w�������H��E���Əꐔ(����) |
67 |
15 |
82(75) |
�w
��
��
��
�e |
�r�o��E�Ǘ���̏��� |
4 |
1 |
5(5) |
| ���啪�͂̎��{ |
14 |
4 |
18(15) |
| �\���͏o |
27 |
6 |
33(43) |
| �{�ݓ��̓_���E�Ǘ� |
5 |
0 |
5(4) |
| �����{�ݓ��̐ݒu�E���P |
5 |
0 |
5(6) |
| �Ǘ��g�D�̐� |
5 |
3 |
8(2) |
| �L�^�̐��� |
1 |
0 |
1(0) |
| ���̑� |
6 |
1 |
7(0) |
(��)�@���v���́i�@�j�����l�́A13�N�x���ђl
(�S) �A�X�x�X�g��
�@���N12���Ɂu��C�����h�~�@�̈ꕔ����������@���v���{�s����A�A�X�x�X�g���u���蕲����v�Ƃ��ċK���������Ƃɔ����A�W��Ƃ̊Ď��E�w���ɓw�߂Ă���B
�@�܂��A����A�X�x�X�g���g�p����Ă��錚���̉�̂��������邱�Ƃ��\�z����邽�߁A9�N4���ɐ��t���Ζ����g�p����Ă��錚���̉�̓���Ƃ��u���蕲����r�o����Ɓv�Ƃ��ċK�肳�ꂽ���A���̉�̍�Ƃɂ��Ă��K���E�w�������{���Ă���B
(5) �������ɂ����镲�����
�@�������́A���{�L���̐ΊD�z�R���̖��W�n��ł���A���ɉ������������ʂ��������߁A�~�����������������{����ƂƂ��ɁA������������{���Ă���B
(1) �����Ԕr�o�K�X��
�@�A�@�����Ԕr�o�K�X��
�@�����Ԕr�o�K�X��́A���ɂ����ăf�B�[�[���Ԃ̔r�o�K�X��𒆐S�ɑ�C�����h�~�@�⎩����NOx�@�����������A�u������NOx�EPM�@�v�ɂ��A�����K���̋������}���Ă���B
�@���ł́A�����Ԍ�ʌ��Q��̈�Ƃ��āA�����Ԕr�o�K�X�ɂ��e����c�����邽�߁A14�N�x�ɂP�����V�݂��A10�ǁi�����P�ǂ͉F�s�{�s�ݒu�j�̎����Ԕr�o�K�X����ǂŁA��C�����̏펞�Ď����s���Ă���B
�@�܂��A�u�A�C�h�����O�E�X�g�b�v�^���v�i�����Ԃ̒���Ԏ��ɂ�����s�K�v�ȃG���W���g�p�̒��~�j�̕��y��}�邽�߁A�����ւ̌[���p�X�e�b�J�[�̓\�t��^�A�W�ƊE�ւ̌Ăъ|�����s���Ă���B
�@�C�@����Q�Ԃ̕��y���i
�@�d�C�����ԁA�V�R�K�X�����ԓ�������Q���̓����͎����ԑ��s�ɋN�������C�����i�m�n�w�A�������j����̉��P�A��_���Y�f�i�b�n�Q�j�팸���ɑ��A�ɂ߂ėL���ł���B���ł́A�������œd�C�o�X��n�C�u���b�h�o�X���^�s����ق��A���p�ԂɓV�R�K�X�Ԃ�n�C�u���b�h�����Ԃ����Ă������ƂƂ��Ă���A14�N�x�́A�n�C�u���b�h������16��������B
(2) �����ԑ�����
�@���ł́A�u�����K���@�v��18���Ɋ�Â��A��v�Ȋ������H280�q�ɂ��Ď����ԑ����̏펞�ā@�����s���Ă���B
�@�܂��A�W�@�ւɂ��u�Ȗ،���ʌ��Q���A����c�v��ݒu���A���H��ʑ�����̐��i�@��}���Ă���B
(3) �X�p�C�N�^�C�������ɔ������H�������
�@�u�X�p�C�N�^�C��������̔����̖h�~�Ɋւ���@���v�Ɋ�Â��A�R�N�T���ɉF�s�{�s�Ȗk��17�s�����X�p�C�N�^�C���g�p�֎~�n��Ƃ��Ďw�肳��A�T�N�Q���ɓ����s���lj��w�肳�ꂽ�B�i�\�Q�|�P�|�W�j
�\�Q�|�P�|�W�@�X�p�C�N�^�C���g�p�֎~�n��
| �V�s |
�F�s�{�s�A�����s�A�����s�A���s�s�A��c���s�A��s�A����s |
| 11�� |
��͓����A�͓����A�F�꒬�A�������A���J���A���ƒ��A�����A��A�쒬�A�ߐ{���A���ߐ{�쒬�A������ |
�@
(1) �����w�X���b�O
�@�����w�X���b�O�́A���f�_������Y�����f�Ȃǂ����O���̍�p���Đ�������h�����K�X�i�����w�I�L�V�_���g�j�ɂ��N������̂ŁA�ڂ̎h���A�̂ǂ̒ɂ݁A���ꂵ���Ȃǂ̌��N��Q���B
�@���ł́A��Q�𖢑R�ɖh�~���邽�߁A�u�Ȗ،������w�X���b�O���v�j�v�����肵�A�����w�X���b�O�\����A�W����s�����A�s���@�ցA�@�y�ыً}�����͍H�ꓙ�ɒʕĂ���B
�@�܂��A�ً}���ɂ́A���ӕ߂��A�s�����ւ̒ʕ�A�ً}�����͍H�ꓙ�ɑ�������r�o�ʂ̍팸�[�u�̗v�����s���A��Q�̖��R�h�~�ɓw�߂Ă���B14�N�x�ɂ́A�z�[���y�[�W�u�Ƃ����̐�v���J�݂��A�����ւ̏��̐������������B
�@�����w�X���b�O�̔����\��Ɩ��́A��C�����V�X�e���ɂ����W���������w�I�L�V�_���g�Z�x���ƋC�ۂɊւ�����@�ւ������锭���\���C�ۏ��y�ъ��Ȃ̑�C���������L��Ď��V�X�e�����瓾��ꂽ�֓��n��̍L��I�ȏ���c�����A�����I�ɉ�͂��邱�Ƃōs���Ă���B
�\�Q�|�P�|�X�@�����w�X���b�O���ߑΏےn��
| �ԍ� |
�Ώےn�� |
�s������ |
�s���� |
| �P |
�������� |
�Q�s�S�� |
�F�s�{�s�A�����s�A�͓����A���쒬�A�F�꒬�A������ |
| �Q |
���암 |
�Q�s11�� |
�Ȗ؎s�A���R�s�A��O�쒬�A��͓����A�������A�p�����A�����A���������A��ؒ��A�啽���A�������A��M���A�s�꒬ |
| �R |
���쐼�� |
�Q�s�Q�� |
�����s�A����s�A�c�����A������ |
| �S |
���쓌�� |
�P�s�Q�� |
�^���s�A��{���A�v�q�� |
| �T |
���k���� |
�R�s�T�� |
��c���s�A��s�A����s�A��͓����A���J���A���ƒ��A��A�쒬�A���ߐ{�쒬 |
| �U |
���k���� |
�Q�s�P�� |
�����s�A���s�s�A������ |
| �V |
������ |
�V���P�� |
�Ζؒ��A�s�L���A���Ï㑺�A���H���A��ߐ{���A�G�R���A�n�����A���쒬 |
�\�Q�|�P�|�P�O�@�����w�X���b�O�ً}���̔��ߋy�щ����̊
| ��@�@�� |
���@�߁@�́@��@�� |
���@���@�́@��@�� |
| �\�� |
�C�ۏ����y�уI�L�V�_���g����l�����������A���O���Ɍf���邢���ꂩ�̈�̏�Ԃ���������Ɨ\�������Ƃ��B |
���Ɍf�����Ԃ��Ȃ��Ȃ����ƔF�߂���Ƃ����͓��v�ɂȂ����Ƃ��B |
|
���ӕ� |
��̑���n�_�ɂ����āA�I�L�V�_���g����l��0.12ppm�ȏ�ɂȂ�A���A���̏�Ԃ��C�ۏ�������݂Čp������ƔF�߂���Ƃ��B |
���ߒn����̑���n�_�ɂ����āA�I�L�V�_���g����l��0.12ppm�����ɂȂ�A���A�C�ۏ�������݂Ă��̏�Ԃ��������邨���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ƔF�߂���Ƃ����͓��v�ɂȂ����Ƃ��B |
|
�x�� |
��̑���n�_�ɂ����āA�I�L�V�_���g����l��0.24ppm�ȏ�ɂȂ�A���A���̏�Ԃ��C�ۏ�������݂Čp������ƔF�߂���Ƃ��B |
���ߒn����̑���n�_�ɂ����āA�I�L�V�_���g����l��0.24ppm�����ɂȂ�A���A�C�ۏ�������݂Ă��̏�Ԃ��������邨���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ƔF�߂���Ƃ��B |
|
�d��ً}�� |
��̑���n�_�ɂ����āA�I�L�V�_���g����l��0.40ppm�ȏ�ɂȂ�A���A���̏�Ԃ��C�ۏ�������݂Čp������ƔF�߂���Ƃ��B |
���ߒn����̑���n�_�ɂ����āA�I�L�V�_���g����l��0.40ppm�����ɂȂ�A���A�C�ۏ�������݂Ă��̏�Ԃ��������邨���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ƔF�߂���Ƃ��B |
(2) �X�^�[�E�H�b�`���O�E�l�b�g���[�N
�@��l�ЂƂ肪�g�߂ȑ�C�̏�c�����A��C�ۑS�̏d�v���⎩�R�ώ@�ɂ��Ă̋����ƊS��[�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���a62�N�x������Ȃ̎�ÂŎ��{���Ă���B
�@14�N�x���A����ɂ��u�V�̐�v�̊ώ@�A�o�ዾ�ɂ��Ċ��y�ѓ~���̑�\�I�Ȑ����ł���u���ƍ��v�y�сu���鐯�c�i�v���A�f�X���c�j�v���A�ǂ̓����̐��܂Ō����邩�̊ώ@�����Ȃ���A�{���ł́A�S�s�Q��15�c�̉���680�����Q�������B
|