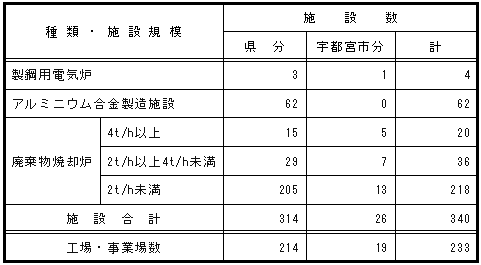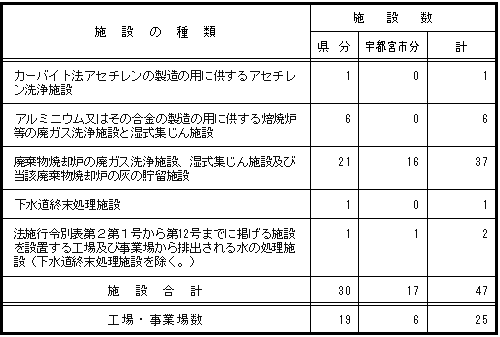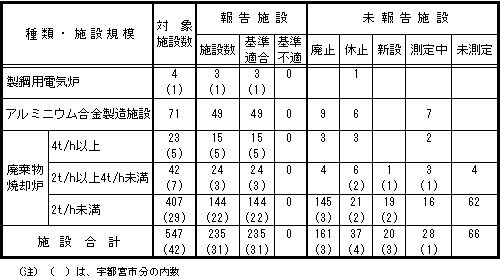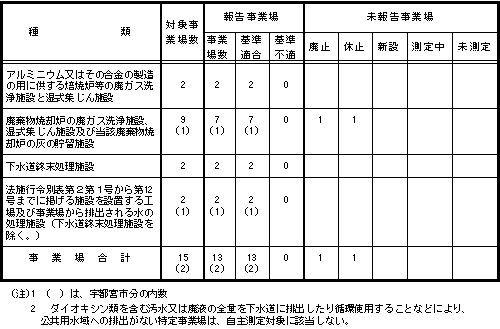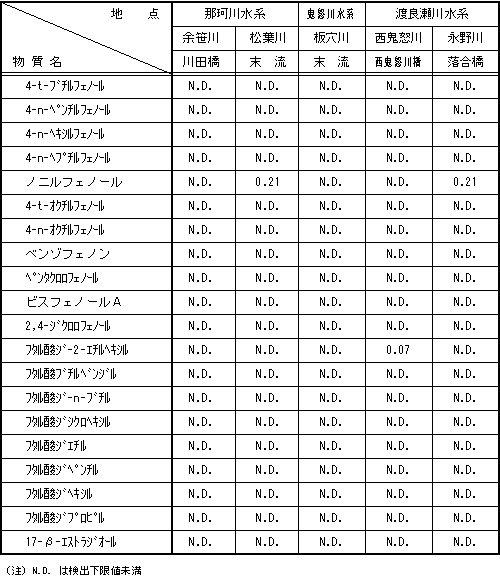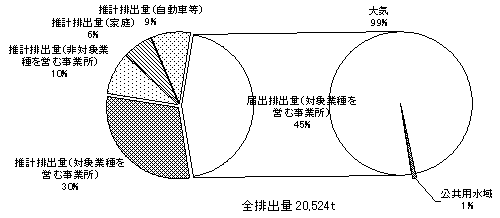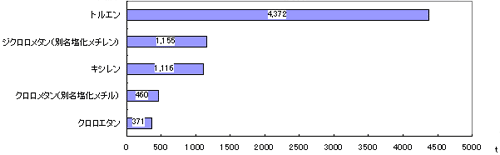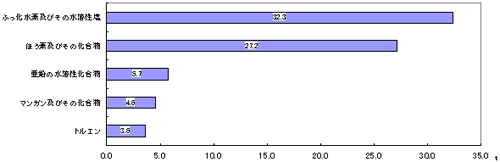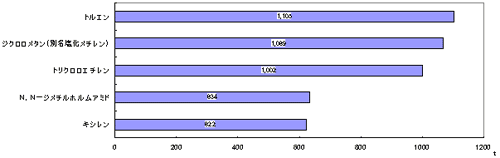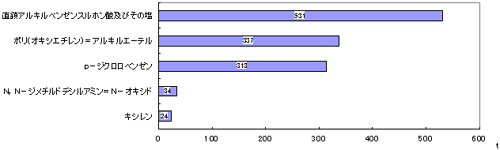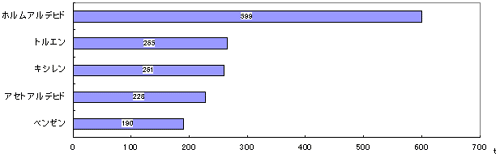|

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」により、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められている。
また、同法において、ヒトが生涯にわたって摂取し続けても許容される摂取量(TDI)は、1日当たり体重1㎏当たり4pg-TEQ/kg/日と定められている。
表2-6-1 ダイオキシン類の汚染に係る環境基準
| 媒体 |
基準値 |
| 大気 |
年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 |
| 水質 |
年平均値 1pg-TEQ/l以下であること。 |
| 水底の底質 |
150pg-TEQ/g以下であること。 |
| 土壌 |
1,000pg-TEQ/g以下であること。 |
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気、水質及び土壌の汚染の状況について、常時監視を行っている。
14年度においては、大気17地点、水質(公共用水域(河川・湖沼)・地下水)122地点、河川底質8地点及び土壌(一般環境・工場事業場周辺)64地点でダイオキシン類の測定を行った。
表2-6-2 ダイオキシン類に係る常時監視結果
| 調査対象 |
区分 |
調査地点数 |
測定結果 |
| 最低値 |
最高値 |
平均値 |
中央値 |
|
大気 |
|
17 |
0.055 |
0.35 |
0.12 |
0.10 |
|
水質 |
河川 |
53 |
0.065 |
0.86 |
0.22 |
0.12 |
|
湖沼 |
3 |
0.065 |
0.066 |
0.065 |
0.065 |
|
地下水 |
66 |
0.065 |
0.071 |
0.065 |
0.065 |
|
底質 |
河川 |
8 |
0.40 |
4.6 |
1.7 |
0.83 |
|
土壌 |
|
64 |
0.018 |
130 |
8.1 |
3.0 |
(1) 大気
一般環境11地点、固定発生源周辺(工業団地周辺)6地点の合計17地点で、年4回24時間の採取によるモニタリングを実施した。各調査地点の年平均値は、0.055~0.35pg-TEQ/m3であり、全ての調査地点で環境基準を達成している。
10年度から継続して調査している6地点の濃度を比較したものを図2-6-1に示す。
図2-6-1 継続調査地点のダイオキシン類の測定結果(年平均値)
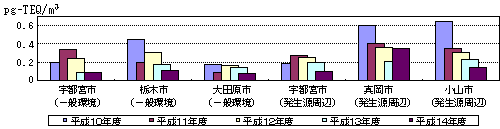 (注)10年度は、大気環境指針0.8pg-TEQ/m3で評価 (注)10年度は、大気環境指針0.8pg-TEQ/m3で評価
(2) 水質
① 河川
53地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.065~0.86pg-TEQ/lであり、全ての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成している。
② 湖沼
中禅寺湖、湯の湖及び深山ダム湖において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.065~0.066pg-TEQ/lであり、全ての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成している。
③ 地下水
66地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.065~0.071pg-TEQ/lであり、全ての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成している。
(3) 底質
河川8地点において底質の調査を実施した。各調査地点の濃度は0.40~4.6pg-TEQ/gであり、全ての地点で水底の底質に係る環境基準(150pg-TEQ/g以下)を達成している。
(4) 土壌
一般環境55地点、固定発生源周辺9地点の合計64地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は0.018~130pg-TEQ/gであり、全ての調査地点で土壌の汚染に係る環境基準(1,000pg-TEQ/g以下)を達成している。
ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、常時監視と並行して「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく工場・事業場への立入検査を実施している。
(1) 規制基準
本県では、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく特定施設について、その種類ごとに定 められた規制基準により規制を行っている。
(2) 特定施設の届出状況
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく特定施設の届出状況は、表2-6-3に示すとおりである。なお、14年12月から排出基準が強化されたため、施設の休廃止が増加した。
表2-6-3 ダイオキシン類対策特別措置法に規定される施設数(14年度末)
① 大気基準適用施設
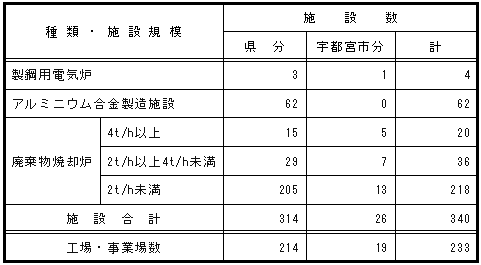
② 水質基準適用施設
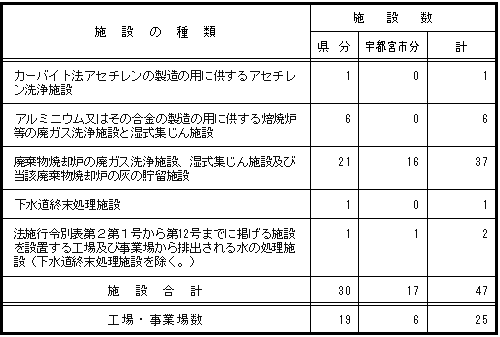
(3) 工場・事業場に対する立入検査状況
14年度は延べ217工場・事業場(県分204工場等、宇都宮市分13工場等)について立入検査を行い、ダイオキシン類の排出削減等について指導を行った。(表2-6-4)
県では12年度に県保健環境センターに測定施設を設置し、ダイオキシン類の検査体制を整備し、13年度から工場・事業場の行政分析を計画的に実施している。
行政分析の結果、14年度については、排出基準不適合施設はなかった。(表2-6-5)
表2-6-4 立入検査実施数
| 区分 |
14年度 |
| 大気関係の特定施設を設置する工場・事業場 |
194 |
| 水質関係の特定施設を設置する工場・事業場 |
23 |
| 合計 |
217 |
(注) 1 大気関係の立入検査実施数は、県分182件、宇都宮市分12件
2 水質関係の立入検査実施数は、県分 22件、宇都宮市分 1件
表2-6-5 行政分析結果(14年度)
|
区分 |
施設数(件) |
| 県 |
宇都宮市 |
合計 |
| 大気実施数 |
39 |
12 |
51 |
| 不適合数 |
0 |
0 |
0 |
| 水質実施数 |
10 |
1 |
11 |
| 不適合数 |
0 |
0 |
0 |
(4) 事業者の自主測定結果
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者は毎年1回以上自主分析を行い報告をすることが義務づけられている。
14年度の事業者の自主測定結果報告状況は、14年4月1日~15年3月31日の間に設置されていた施設(この間に廃止された施設も含む。)のうち、大気関係対象547施設(宇都宮市分42)に対し235施設(宇都宮市分31)、水質関係対象15事業場(宇都宮市分2)に対し13事業場(宇都宮市分2)の報告があった。
14年度の報告結果については、排出基準不適合施設はなかった。(表2-6-6)
また、測定を行っていない事業者に対しては、速やかに測定を行うよう指導しているところである。
表2-6-6 ダイオキシン類自主測定結果の報告状況
① 大気関係対象施設
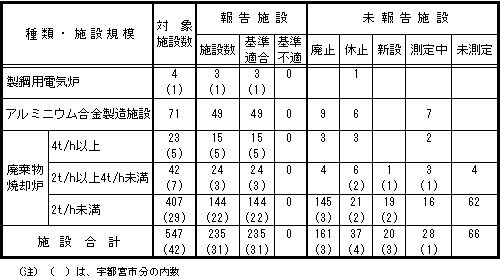
② 水質関係対象事業場
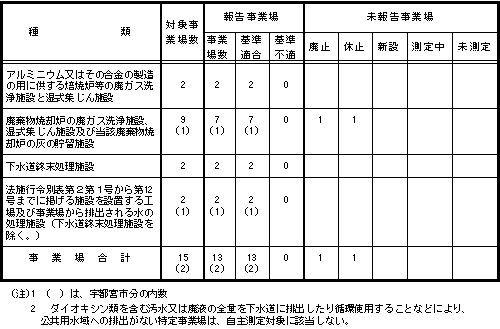
内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)については、野生生物の生殖異常などの報告がなされているが、その環境中における挙動や健康影響・生態影響については、科学的に未解明な部分が多い。
しかし、環境ホルモンは、ヒトや野生生物の内分泌作用を攪乱し、生殖機能障害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある物質であって、生物の生存の基本的条件に関わるものであり、世代を超えた深刻な問題を引き起こすおそれがあることから、これに対する環境保全対策が重要となってくる。
環境省では、9年3月に「外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班」を設置し、既存の知見の収集整理及び今後の課題についての検討を行い、同年7月に中間報告書をとりまとめた。
そして、10年5月「外因性内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について」(いわゆる環境ホルモン戦略計画SPEED'98)を策定し、内分泌攪乱作用が疑われる約70種の化学物質について、基本的な考え方並びに実態調査、試験研究及び情報提供の推進等の具体的な対応方針を示し、さらに12年11月には、新しい知見等を追加・修正した「環境ホルモン戦略計画SPEED'98
2000年11月版」を公表した。
環境ホルモンについては、科学的に未解明な部分が多いことから、化学物質対策連絡会議において、情報収集及び情報交換等により情報の共有化を図ってきた。
14年度は13年度に引き続き、水質の環境ホルモンの調査を次の5河川において実施した。その結果は表2-6-7のとおりで、ほとんどが検出限界値未満であり、検出された物質の濃度も、全国の調査結果と比較すると低い値であった。なお、現在のところ、いずれの物質も環境基準等は設定されていない。
表2-6-7 環境ホルモン実態調査結果(14年度) (単位:μg/l)
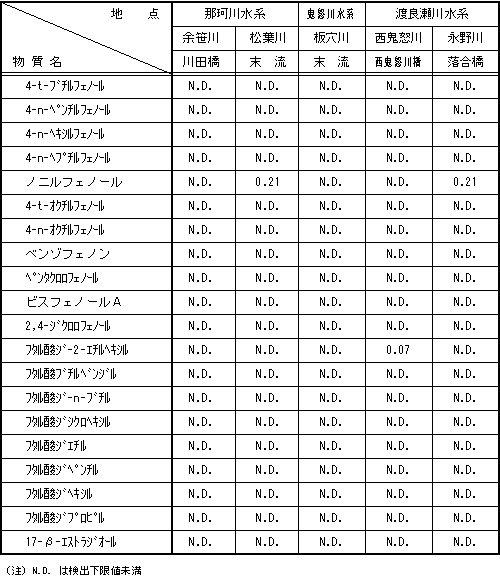
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的として、11年7月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法)が公布された。
化学物質排出把握管理促進法で定められたPRTR制度では、政令で定める354種類の化学物質(第一種指定化学物質)を取り扱い、かつ、政令で定める届出要件(業種、従業員数、取扱量)を満たす事業者が、1年間にどのような物質をどれだけ環境中へ排出したか、あるいは廃棄物としてどれだけ移動したかを行政機関に届け出ることとなっている。
国はそれを集計し、家庭や農地、自動車などから排出される化学物質の量を推計し、合わせて公表することとなっている。
事業者は、自らが排出している化学物質の量を把握することによって、化学物質排出量の削減への自主的な取組が促進されることが期待される。
法に基づき、有害性の恐れのある354種類の化学物質について、事業者から14年4月1日から14年7月1日の期間に第1回目の届出がなされた。国においては、15年3月にそのデータを都道府県ごとに集計し公表した。県においては、その結果を地域ニーズに応じて加工し、公表することができることとなっている。
この制度により、化学物質の適正な管理を進めるためには、県民と企業及び行政の担当者が、それぞれの立場の違いを十分に認識しながら、化学物質のリスクについての情報を共有し、互いに理解と信頼関係を築き、効果的にリスク低減を図っていくための「リスクコミュニケーション」を進めることがきわめて重要になってきている。
本県では、化学物質の情報の開示及び「リスクコミュニケーション」のあり方について、事業者、県民及び学識経験者等により、検討を行うこととしている。
(1) 届出件数
栃木県内における対象事業所からの14年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出は、727件である。全国での届出件数は34,830件であり、栃木県は全国の約2%を占めている。
(2) 環境への排出量
栃木県内の事業所からの届出排出量と推計量をあわせた合計排出量は、20,524tである。届出排出量は全体の45%を占め、それ以外から排出される推計排出量は55%を占める。届出排出量の内訳は、大気への排出99%、公共用水域への排出1%であった。(図2-6-2)
発生源別の内訳をみると、事業所(製造、販売、サービス業等)からの排出割合が85%、家庭から6%、自動車等から9%であった。
図2-6-2 発生源別・排出先別割合(届出・推計)
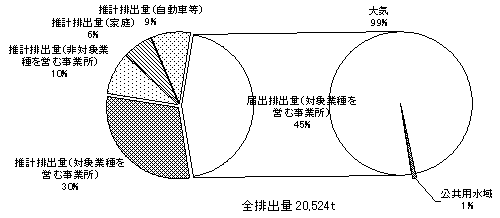
ア 届出排出量
(ア) 大気への排出量
栃木県内の事業所から届出のあった大気への排出量(合計9,160t)の上位5物質を図2-6-3に示す。排出量の多い物質の主な用途は次の通りである。
○トルエン :塗料やインキの溶剤、ガソリン成分、合成原料
○ジクロロメタン(別名 塩化メチレン) :金属脱脂の洗浄剤
○キシレン :塗料の溶剤、ガソリン・灯油成分、合成原料
図2-6-3 大気への排出量(届出)
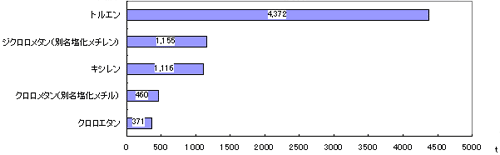
(イ) 公共用水域への排出量
栃木県内の事業所から届出のあった公共用水域への排出量(合計83t)の上位5物質を図2-6-4に示す。排出量の多い物質の主な用途は、次のとおりである。
○ふっ化水素及びその水溶性塩 :金属・ガラスの表面処理剤
○ほう素及びその化合物 :ガラス添加剤、消毒剤
○亜鉛の水溶性化合物 :乾電池、金属表面処理剤
図2-6-4 公共用水域への排出量(届出)
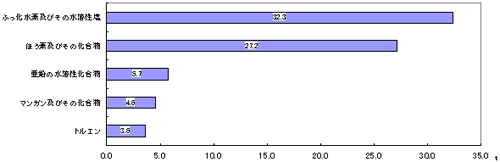
(ウ) その他
土壌への排出は合計31kg、届出事業所における埋立はゼロであった。
イ 推計量
(ア) 届出の必要のなかった事業所からの推計排出量
届出要件(業種、従業員数、取扱量)を満たしていないために、届出をする必要のなかった事業所からの推計排出量(8,122t)の上位5物質を図2-6-5に示す。主な用途は、次のとおりである。
○トリクロロエチレン :洗浄剤、溶剤
○N,N-ジメチルホルムアミド :有機合成溶剤
図2-6-5 届出の必要のなかった事業所からの推計排出量(推計)
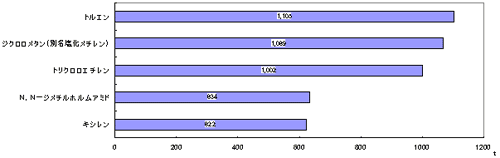
(イ) 家庭からの排出量
栃木県内の家庭からの推計排出量(合計1,336t)の多い上位5物質を図2-6-6に示す。排出のあった物質の主な用途は、次のとおりである。
○直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 :界面活性剤(洗剤成分)
○ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル :界面活性剤(洗剤成分)
○p‐ジクロロベンゼン :衣類用防虫剤
○N,N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド :洗浄剤(シャンプー、台所洗剤)
図2-6-6 家庭からの排出量(推計)
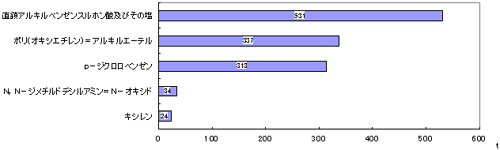
(ウ) 自動車等からの排出量
栃木県内の自動車等(自動車・二輪車・特殊自動車等)からの排ガスに含まれる推計排出量(合計1,823t)の多い上位5物質を図2-6-7に示す。
図2-6-7 自動車等からの排出量(推計)
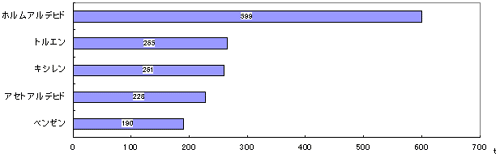 |
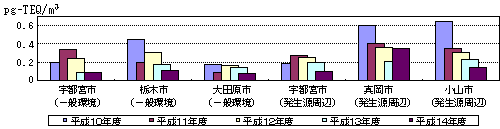 (注)10年度は、大気環境指針0.8pg-TEQ/m3で評価
(注)10年度は、大気環境指針0.8pg-TEQ/m3で評価