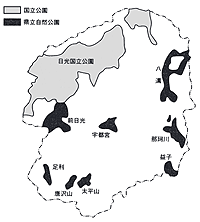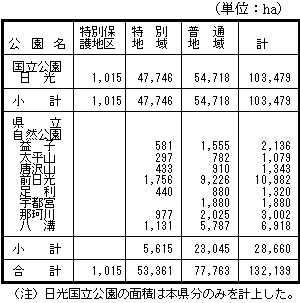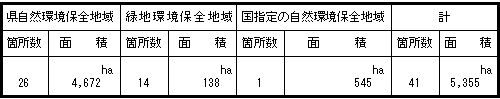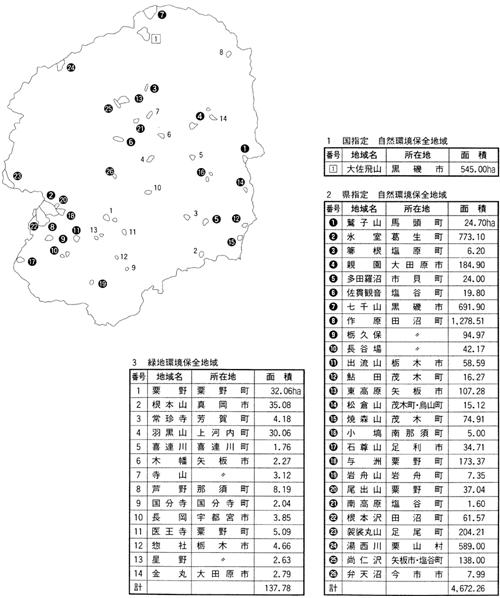|

�@�{���́A���k���ɓ����A�����A�ߐ{�ΎR�Q����Ȃ�R�x�n�т��`������A�Ώ��A�k�J�A�e�z�⍂�w�������������тƒ��a�������R�i�ς��Ȃ��Ă���B�܂��A�n�`�A�n���A�C�ۂȂǗ��n�����̓��ِ��ɂ���āA����n�A�k���n�A�������݂��ĕ��z���A�X�͎��ォ��̓��A�����������������A���َ��M�d�Ȃ��́A�������������������̓��ω��ɕx���R����悵�Ă���B
�@����A�������y�ѓ암�̕��n�т́A�o�ϊ����̏�Ƃ��Ď���ƂƂ��ɕω����Ă������A�l�ԂƎ��R�Ƃ̒���������荇���̒��ő������Ă��镽�n�ѓ��́A�h���A�h�A�e���̏ꓙ��������v��m��Ȃ����p�����g�߂Ȏ��R�Ƃ��ďd�v�ȈӋ`�������Ă���B�Ȃ��A���̒n�т́A�ޗǎ��ォ��̓��������̒��S�n�ł���A�Õ����Փ��̗��j�I�A�����I�Ȉ�Y�����������݂��Ă���B
�@�{���̐X�т́A���y�̖�55�����߁A�؍ޓ��̗юY���̐��Y�@�\�Ɛ���������{�A���y�̕ۑS�A�ό������Ƃ��Ă̗D�ꂽ���R���̒ȂǁA���������Ɛ[���ւ��������A���ʓI�Ȍ��v�I�������ʂ����Ă���B
�@�s�s�y�т��̎��ӂł́A��n�����̐i�W�ɔ������n�����̋M�d�ȗ���������X���ɂ���A����A����w�̗Ή����i���K�v�ȏɂ���B
�@�{�������R�����̖ʐς́A��13��ha�ł��茧�y�̖ʐς̖�21�����߂Ă���B���k�����̎R�x�n�т𒆐S�Ƃ����n��́A�䂪���̑�\�I�Ȏ��R�����ł���������������ɂ���Đ�߂��A�܂��A�����e�n�ɂ́A�n��̓��������W�̌������R�����������āA���ꂼ��ω��ɕx���R�i�ς�L���Ă���B�i�}�R�|�P�|�P�j
�@�����̎��R�����ɂ́A���̓��O����A���R�����߂đ����̐l�X���K��Ă���B
�}�R�|�P�|�P�@���R�����̌���
�@
(1) ���R���ی쎖��
�@���R���ۑS�y�ю��R�ی�ӎ��̍��g�̂��߂̕��y�[���A�����������{�����B
(2) ���R���ۑS�n�擙�̎w��
�@�u���R���ۑS�@�v�y�сu���R���̕ۑS�y�їΉ��Ɋւ�����v�Ɋ�Â��A�D�ꂽ���R�������n������R���ۑS�n���ɁA�܂��A�s�X�n���Ӓn�y�ї��j�I�E�����I��Y�ƈ�̂ƂȂ����Βn���Βn���ۑS�n���Ɏw�肵�Ă���B
�@14�N�x�܂łɍ��w��̎��R���ۑS�n��1�������܂߁A41����5,355ha�̎w����s�����B(�\�R�|�P�|�P�j
�\�R�|�P�|�P�@���R���ۑS�n�擙�w����@�i15�N4��1�����݁j
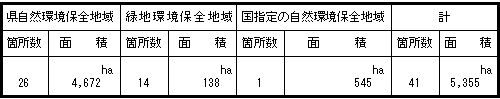
(3) ���R�i�Βn�j���ۑS�n��̐���
�@���R�i�Βn�j���ۑS�n��Ɏw�肳��Ă���n��i�}�R�|�P�|�Q�j�̈ē��W���������āA�D�ꂽ���R���̕ۑS�ɓw�߂��B
�@��c���s�̐e�����R���ۑS�n��ɂ́A���̓V�R�L�O���y�э����쐶���A����Ɏw�肳��Ă���~���R�^�i�S�̕ی�n������A���̕ی�Ǘ������{�����B
(4) �����n���ی��̎w��
�@�u��ł̂�����̂���쐶���A���̎�̕ۑ��Ɋւ���@��<�W�p��F�u��Ŋ뜜���v�u��Ŏ��v�u���b�h�f�[�^�u�b�N�v>�v�Ɋ�Â��A��c���s�H�c�n��̃~���R�^�i�S�����n�i60.6ha�j��6�N12���ɑS���ŏ��߂������n���ی���Ɏw�肳�ꂽ�B
�@���n��ł́A�~���R�^�i�S�������̈ێ��Ǘ��y�ѕی쑝�B���Ƃ����{����Ă���B
(5) ���R����b����
�@���R���ۑS�@��T���Ɋ�Â����R���ۑS��b���������{����ƂƂ��ɁA�{���̎��R���c���̂��߂Ɏ��{������b�����̎��܂Ƃ߂��s�����B
(6) ���n�т̕ۑS
�@���n���́A�ΖL���Ȃӂ邳�ƓȖ��\����i�ςł���A��C�̏A�h���A�h�����̌��v�I���p�Ɛ����ɏ�����^����g�߂ȗ̋����n�Ƃ��Ă��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���A14�N�x�����݂̖ʐς́A��70��ha�ƂȂ��Ă���B
(7) �ۈ��т̎w��
�@�ۈ��т́A�����̂���{�A�ЊQ�̖h�~�A���R���̕ۑS�E�`���y�ѕی��x�{�̏�̒��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���A14�N�x�����݂̎w��ʐς́A��16��9��ha�ƂȂ��Ă���B
�@�ۈ��т̎w��́A�ۈ��ѐ����v��Ɋ�Â��v��I�ɐ��i���Ă��邪�A14�N�x�́A��������{�ۈ��т�y�����o�h����ۈ��ѓ��Ƃ��āA��219ha�̕ۈ��т��w�肵���B
�@�܂��A���v�I�@�\���ቺ�����ۈ��тɑ��ẮA�Ԕ����̕ۈ��Ƃ��s���ȂǓK���ȊǗ��ɓw�߂��B
(8) �����̐X�ѐ���
�@���R�̉��Q�ɂ��A�����͎����A���n�������r�p�n�̕�����}�邽�߁A�A�͂�w���R�v�^�[�ɂ����d�Ȃǂ̎��R���Ƃ��s���A�Ή���i�߂Ă���B
�܂��A�{�����e�B�A�ɂ��A�ъ������s���Ă���B
(9) �����̕ۑS
�@�������l���̊ϓ_����d�v�Ȓn��ł��鎼����ۑS���邽�߁A�����A�C�̒����y�ю�������{���m�ۑ����̕ۑS����s���Ă���B
(10) ���R�Ƃ̂ӂꂠ���̐��i
�@�L���Ȏ��R�Ƃ̂ӂꂠ����ʂ��āA���R�̂����݂����𗝉����邽�߂Ɏ��R�ώ@���쒹�ώ@����J�Â���ق��A���R�̌��v���O�����̕��y��A�l�ނ̈琬�������{���Ă���B
(11) �Ƃ����ӂ邳�ƊX����������
�@2�N4���Ɂu�Ƃ����ӂ邳�ƊX���i�Ϗ��v���{�s���A���N6���ɏ��Ɋ�Â��ߐ{�E�����X��
�i�ό`���n����w�肵�A12�N12���Ɏw��n����g�������B�����ł́A�X���i�ό`����Ɋ�Â�
�w�����s���A�u�݂ǂ�L���ȓȖ،��v�̃C���|�W�ɂӂ��킵���X���i�ς̌`����}���Ă���B
�@13�N�x�ɂ́u�Ƃ����ӂ邳�ƊX���i�ϗ��e���x�v��n�݂��A3�c�̂𗢐e�Ƃ��Ďw�肵�����A�@14�N�x�͐V����1�c�̂��w�肵���B
�@�܂��A�i�ϕۑS�̂��߂̓y�n���̍w�����x�ɂ��A���ʓI�Ȏ{��̐��i��}���Ă���B
�}�R�|�P�|�Q�@���R�i�Βn�j���ۑS�n��̎w����i15�N4��1�����݁j
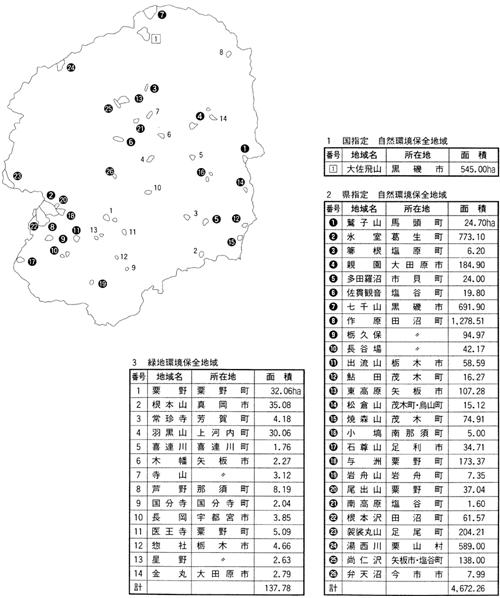
�@���R�����i�������������y��8�̌������R�����j�̗D�ꂽ���i�n��ی삷�邽�߁A�e��s�ׂ̋K�������s���ƂƂ��ɁA���K�ȗ��p���m�ۂ��邽�߂̎{�ݐ����A���p�҂ɑ���K�����p�̎w�������s���Ă���B
�@14�N�x�̎�Ȏ�g�͎��̂Ƃ���B
(1) ���R�����Ǘ�����
�@�����v��Ɋ�Â����ʒn��Ȃǂ̒n��w��ɂ��e��s�ׂ̋K�������{����ƂƂ��ɁA���p�҂ɑ���K�����p�̎w�������s�����B�v�q�������R�����̌����v��̕ύX���s���A�����������n�y�э��َR�k�Ζʂ��1����ʒn��ւ̎w��ύX���s�����B
(2) �������R�����t���b�V���A�b�v����
�@�v�q�������R�������c�y�W�c�{�ݒn��̍Đ����Ƃ��āA���n��̗��p���_�ƂȂ�g���C���Z���^�[���Ӊ��n�̐����i�����H���j�A�{�ݐ����y�ѐX�ѐ��������{�����B
(3) ���R�������{�ݐ�������
�@���R�����̉��K�ȗ��p���i��}�邽�߁A�����A���n���̐������s�����B
�@�@�����ӏ��@�������������R�������O20����
�@�@�������e�@������C�A�W���ݒu�A�ؓ��E��O��ݒu�A�h���A���n������
(4) �ߐ{�E�����G�R�A�b�v����
�@�������������ߐ{�E�����n��ɂ����āA�u�l�Ǝ��R�Ƃ̖L���Ȃӂꂠ���v�u�l�Ǝ��R�Ƃ̋����̊m�ہv��}�邽�߁A�D�ꂽ���R��ۑS����ƂƂ��ɁA���R�̌��̏�������B
�@�@�����ӏ��@�ߐ{���������O4����
�@�@�������e�@����������
(5) ���R�������^�{�ݐ�������
�@�����������̗D�ꂽ���R���̕ی�Ɨ��p�̑��i�̂��߁A���R�Ƃӂꂠ���{�݂̐����ɓ�����A���R�i�ς�Ԍn�ɔz�������{�ݐ����𐄐i�����B
�@�@�����ӏ��@��胖�l���n�O3����
�@�@�������e�@�g�C�������A���n�����A�W���ݒu�A���ԏꐮ����
(6) ���ۊό��n�u�����v��������
�@�䂪�����\���鍑�ۊό��n�u�����v�̊�������}�邽�߁A�����s���{�K�n��ɂ����Ċ�Ր��������s�����B
�@�@�����ӏ��@�咹�����n�O2����
�@�@�������e�@���H���ǁA���������A�W���ݒu��
(7) ���������ۑS��
�@���ۊό��n�u�����v���������ƂŐ��������A�������{�K�n��̌��c���ԏ�A�Δȉ��n�A�C�^���A��g�ٕʑ��L�O�������̊Ǘ��^�c���s�����B
�@�쐶���b�́A���R�����\������d�v�ȗv�f�̂P�ł���A���R����L���ɂ�����̂ł���Ɠ����ɁA�_�ѐ��Y�Ƃ̐U���y�ѐ����������K�ɂ����ŁA�������Ƃ̂ł��Ȃ��������ʂ������̂ł���B���������āA���b�̐����A���������l�����Čv��I�A���ʓI�Ȓ��b�ی�̎{���i�߁A���R���̕ۑS�𐄐i����B
�@���ɂ����ẮA14�N�x����18�N�x�܂ł�5�N�Ԃ�ΏۂƂ��č��肳�ꂽ�u��X�����b�ی쎖�ƌv��v�Ɋ�Â��A���b�̕ی�ɐB�̂��߂����b�ی�����̐ݒ�A�쐶���b�ɂ���Q�h�~�A��̓K������}�铙�����I�Ȓ��b�ی쎖�Ƃ��s���Ă����B�i�\�R�|�P�|�Q�j
�@14�N�x�́A���b�ی�y�ю�̓K������}�邽�߁A���v��Ɋ�Â��A���b�ی��̐ݒ�A�����A���y�[�������s�����b�ی쎖�ƁA�쐶���b��Q��A�쐶���b�̕ی�Ǘ������{�����B
�\�R�|�P�|�Q�@���b�ی�擙�̐ݒ�@�@�@�@�i15�N3��31�����݁j
�i�P�ʁFha�j
| �敪 |
�ӏ��� |
�ʐ� |
���l |
| ���b�ی�� |
112 |
83,861 |
�������ʕی�n�� 18���� 6,407ha |
| �x�� |
6 |
6,312 |
�@ |
| �e�֎~��� |
209 |
109,425 |
�@ |
| �v |
327 |
199,598 |
�@ |
�@�{���̗Βn�i�_�p�n���܂ށB�j�́A���y�̖�80�����߁A�S���I�ɂ��Ɍb�܂ꂽ���ɂ��邪�A���̌���́A�l���̏W������s�s���̐i�W�ɔ����̌����A�Ύ����̑啔�����߂�X�т̎����s�����A����芪�����́A�K�������y�ς������Ȃ��ɂ���B
�@����A�L���ȗ̂Ȃ��ŐS�̂�Ƃ��_�I�L���������߂錧���̈ӎ��͍��܂��Ă���A���y�Ή��̐��i�������v������Ă���B
�@�{���ł́A���������v���ɂ�������ƂƂ��ɁA�������v��u�Ƃ���21���I�v�����v�̂T�̊�{�ڕW�̂P�ł���u���K�ň��S�ȕ�炵��z���v�̒����Ȏ�����}�邽�߁A�u���R���̕ۑS�y�їΉ��Ɋւ�����v�Ɋ�Â����肵���u��R���Ȗ،��Ή���{�v��v�ɂ��A�e��Ή��{���W�J���Ă���B
�@�{��̕����Ƃ��ẮA�n��̎��R�I���������A�l�ƗƂ����a�����A�w�R�x�w���x�w�X�x�̗Â����i�߁A
�@(1) �݂ǂ���Ă�
�@(2) �݂ǂ�����
�@(3) �݂ǂ���w��
�@���Ƃ𒌂ɁA���l�ȗΉ��{��𑍍��I���v��I�Ɏ��{���A���y�̗Ή����i��}���Ă���B
�@���̈琬�́A���������R���̒��Œ����Ԃɂ킽���čs���邽�߁A�e��̕a���Q�ɂ�����ꍇ������A�������A�ЂƂ��є�Q����ƁA���̉����ɍ���ł���B���ɁA���������̔�Q�́A���a55�N�x�Ƀs�[�N�ƂȂ�A���̌��Q��̌��ʓ��ɂ�茸�����Ă��Ă��邪�A�������N�Ċ��̍������J�̉e���Ŏ�����X���ɂ���A�ˑR�Ƃ��Ĕ�Q���������Ă��邽�߁A�n�悪��̂ƂȂ�A�n��̎���ɉ������A���߂ׂ̍�����Q���ʂ��ď��̗���邱�Ƃ��d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B
�@�{���̖��L�т̏��іʐς͖�2��4��ha����A���L�ё��ʐς̖�11�����߂Ă���B�����́A�ۈ��тɎw�肳��铙�A���v�I�@�\�����x�ɔ������A�M�d�ȐX�ю����ł��邾���łȂ��A�ЊQ�̖h�~����̕ۑS���̏ォ��A���������Ƃ��ł��Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B
�@15�N3�������݂̏���������Q�́A��Q�����s������45�A��Q���іʐϖ�6��9�Sha�A��Q�ސϖ�1��8��m3�ɋy��ł���B
�@���������̔�Q�\�h�[�u�Ƃ��āA��܂̍q��U�z��n��U�z���v��I�Ɏ��{����ƂƂ��ɋ쏜�[�u�Ƃ��Ĕ�Q��K���ɔ��|�쏜���邱�Ƃɂ���Q�̖h�~�ɓw�߁A�����āu���������h�������^���v�𐄐i���āA�h���ӎ��̍��g�ɓw�߂Ă���B
�@�܂��A�і�Б�Ɋւ��ẮA�������@�ނ̐�����}��ƂƂ��ɁA�R�Ύ��\�h�̌[���ȂǗ\�h���������{���Ă���B
�@
�@
|
�P |
���邨���̂��鐅�Ӌ�Ԑ������� |
�@�͐�ɐ����Ɛ������Ăі߂��A�L���Z���ɐe���܂��e���̏�Ƃ��ĉ͐�̗L�����p��}�邽�߁A�����炬�̂��鐅�ӁA�e���A�L���Ȑ�Â�������{���Ă���B
�@�܂��A�����̕ۑS����P��}�邽�߂̉͐���Ƃɂ��ẮA12�N�x�������i�����s�j�ɂ����Ď��{���Ă���B�i�\�R�|�P�|�R�j
�@���Ɨ̍L����m�ۂ��A�Βn�A���ړI�L��A�^����A�h�Ћ�ԂƂ��ĉ͐�~�̗L�����p��}�邽�߁A�ᐅ�H�̐����⍂���~�̑����Ȃǂ��s���͓������ɂ��ẮA�߉ϐ�i����s�E�ߐ{���j�A�s����i�^���s�j��10�N�x�ɁA������i�I�R���j��12�N�x�Ɋ����A14�N�x��13�N�x���璅�肳�ꂽ�H�R��i����s�j�ɂ����Ĉ����������{���Ă���B
�\�R�|�P�|�R�@���ɕ⏕�����ꋉ�͐쐮�����Ɓi�͐�������j
| �͐얼 |
�n�於 |
���H�N�x |
�S�̌v��T�v |
14�N�x���ƊT�v |
���l |
| ���� |
�����s |
12 |
�͓����ց@�{��
���Ɣ�@651,000��~ |
�{�ݍH��
���Ɣ�@210,000��~ |
�p�� |
| �H�R�� |
����s |
13 |
�͓������@�ᐅ���
���Ɣ�@450,000��~ |
����݂̐���
��� �`=1,560�u
���Ɣ� 60,000��~ |
�p�� |
�@
|
�Q |
���L���Ȃӂ邳�ƂÂ��莖�� |
�@�n��Z����s�����A��������̂ƂȂ��āA�n��̊��͂⎩�R�A���j�A���������������I�Ŗ��͓I�Ȓn��Â�����x�����邽�߂ɁA���ӂ̌i�ςƒ��a�������Ӌ�ԂÂ�����܍s��i���ƒ��j�Ŏ��{�����B
�@���a45�N�ɁA�s�s���̐i�W�ɔ����͐���̈������ɂ�茧�͐숤��A����������A�e�s�����ɉ͐숤���u���ꂽ�B����ɂ��A�n��Z����W���c�̂̋��͂ɂ���āA�͐�̐��|���̎��H�����������ɍs����悤�ɂȂ�A�͐�����̌���Ɖ͐숤��̌[���ɑ傫�Ȍ��ʂ��グ�Ă���B
�@14�N�x�Ɏ��{�������Ƃ̊T�v�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�Ȗ،��͐숤��A����̎���
|
�A |
�@7��1���`7��31���܂ł�1�������͐숤�쌎�ԂƂ��A7��7���́u��̓��v�𒆐S�Ƃ��āA�e�s�����͐숤����̂ƂȂ��ĉ͐�̐��|�������{�����B�܂��A�S������̓����ԗp�̃|�X�^�[�y�у`���V���e�s�������ɔz�z���A�͐숤��v�z�̕��y��}�����B |
|
�C |
�@�͐숤�앁�y�|�X�^�[���W���A�D�G��i�̕\�����s�����B�܂��A��ʓ��I��i�ŃJ�����_�[���쐬���A�e�s�������ɔz�z�����B |
|
�E |
�@�͐숤�앁�y�p�p���t���b�g��z�z�����B |
|
�G |
�@�͐숤����J�c�̂�\�������B |
|
�I |
�@�e���r�ʼn͐숤��b�l����f���邱�Ƃɂ��A�͐숤��v�z�̍��g��}�����B |
�@���ӂ��r�I�g�[�v������ɂ����āA�r�I�g�[�v�̕ۑS�ɌW�镁�y�[����}�邽�߁A�u���ӂ̃r�I�g�[�v�u����v���J�Â����B
|