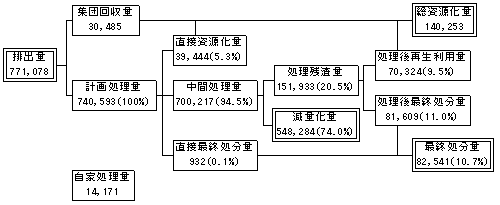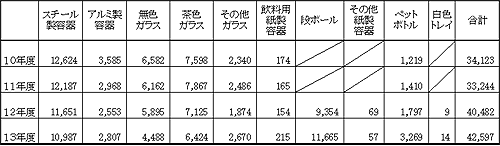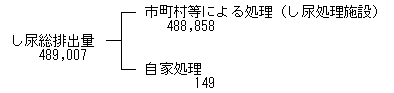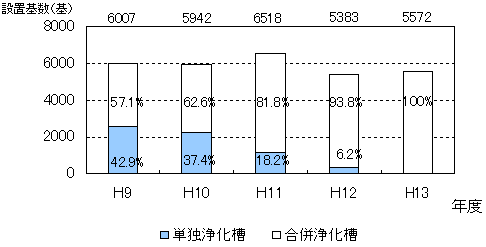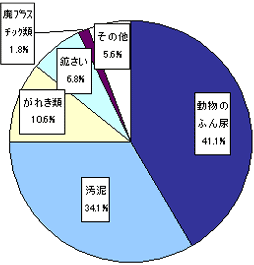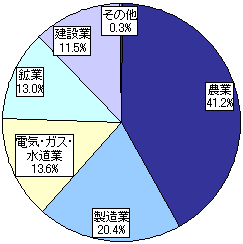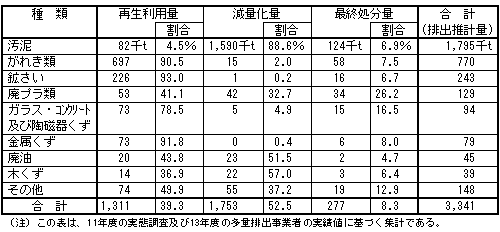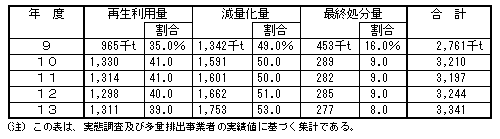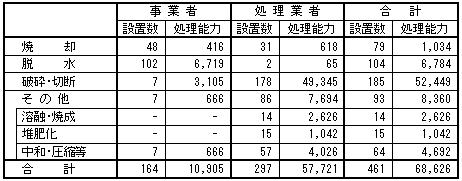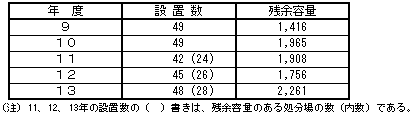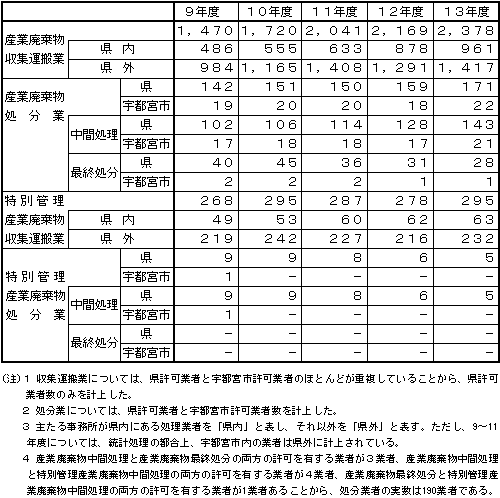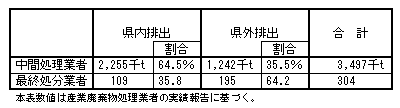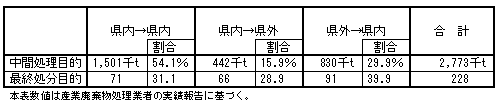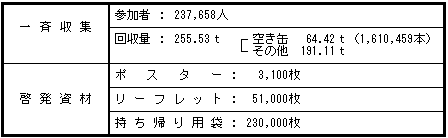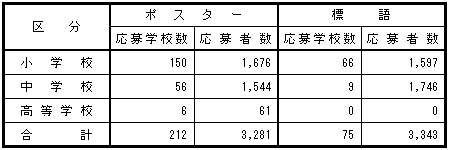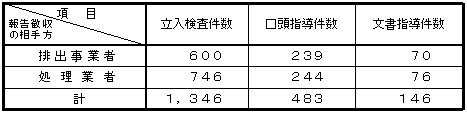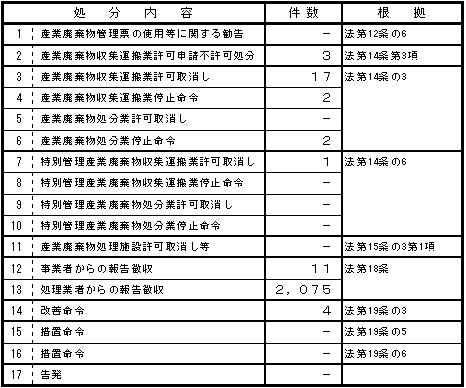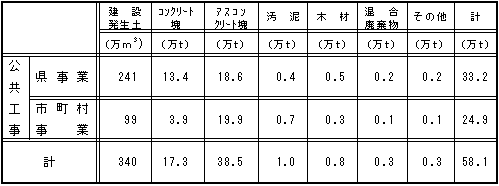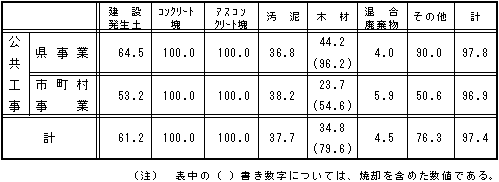|
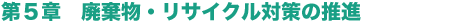
�@21���I���}�������݁A����܂ł̑�ʐ��Y�A��ʏ���A��ʔp���ɂ��Ζ��Ȃǂ̓V�R�����̌͊��A�p����������̕s���A�s�@������_�C�I�L�V���ނȂǂ̗L�Q�����̔����ȂǁA�[���ȎЉ�o�ϖ�肪�����Ă���B����ɁA�n�����g����̂��߂̉������ʃK�X�̍팸�Ɏ��g�ނ��Ƃ����߂��Ă���A�܂��A�ŏI�������̂Ђ�����V�R�����̏���}���̂��߁A�z�^�Љ�̌`�����}���Ƃ���Ă���B
�@���ł́A���f���[�X�i�����}���j�A�����[�X�i�Ďg�p�j�A���T�C�N���i�Đ����p�j�̂������R�q�����{���O�Ƃ���z�^�Љ�̌`�����A����̔p�����E���T�C�N����̊�{�I�����ƈʒu�t���A�u�z�^�Љ�`�����i��{�@�v���͂��߂Ƃ��āu�H�i���T�C�N���@�v�A�u���݃��T�C�N���@�v�ȂǁA���T�C�N���֘A�@�������B�i�}�Q�|�T�|�P�j
�@������A���ɂ����Ă��z�^�Љ�̌`���Ɋւ���{��𑍍��I���v��I�ɐ��i���邽�߁A�e���ǂ���̂ƂȂ����Ȗ،��z�^�Љ�i�{����12�N�x�ɐݒu�����B
�@�܂��A�z�^�Љ�̌`���Ɍ����L�������̐��f�����邽�߁A�w���o���ҁE����ҁE���Ǝғ��ō\������z�^�Љ�i���k���13�N7���ɐݒu�����B
�}�Q�|�T�|�P�@�z�^�Љ�`�����i��{�@���̐���

�@
|
�Q |
�z�^�Љ�i�w�j�̍��� |
�@�{���ɂ�����z�^�Љ�̌`���Ɋւ���{��𑍍��I���v��I�ɐ��i���邽�߁A�z�^�Љ�`���̊�{�����A�������S�A��̓I�Ȏ{��Ȃǂ������u�Ȗ،��z�^�Љ�i�w�j�v��14�N�x�ɍ��肵���B
�@15�N�x�́A�����E���ƎҁE�s�����A�g��}��Ȃ���A�n�����g�����z�^�Љ�̍\�z�Ɏ��g�ނ��߁A�u�Ƃ��̊�����c�v��ݗ����邱�ƂƂ��Ă���B
�@
|
�R |
���T�C�N���֘A�@�ւ̎�g |
(1) �e�����T�C�N�����ʎ��W�ւ̎�g
�@�A�@�e���p�����̃��T�C�N���̐ϋɓI���i�Ɍ����A�s���������{����e���̕��ʎ��W�𑣐i���邽�߂ɁA15�N4�����n���Ƃ���5�N�Ԃ��v����ԂƂ����u�Ȗ،����ʎ��W���i�v��i��3���v��j�v��14�N7���ɍ��肵���B
�@�C�@�e���p�����̕��ʎ��W���v��I�ɐ��i���邽�߂ɁA���y�[�����̎��Ƃ����{����s�����ɑ��ĕ⏕�����{�����B
�@���e�����T�C�N�����i����
�@�@ �⏕��z�@3�C000��~
�@�@ �� �@�� �@���@1/2
�@�@ 14�N�x��6�s���ɑ��ĕ⏕���s�����B
(2) �Ɠd���T�C�N���ւ̎�g
�@�Ώۋ@��ƂȂ�p�Ɠd�i�̓K�Ȕr�o��}�邽�߁A���i���Ƃ����{����s�����ɑ��ĕ⏕�����{�����B
�@���Ɠd���T�C�N�����i����
�@�@ �⏕��z�@3�C000��~
�@�@ �� �@�� �@���@1/2
�@�@ 14�N�x��3�s���ɑ��ĕ⏕���s�����B
(3) �H�i���T�C�N���ւ̎�g
�@�H�i���T�C�N���Ɋւ��{��̑����I�����ʓI�Ȑ��i��}�邽�߁A�H�i���T�C�N�������V���|�W�E�����J�Â���ƂƂ��ɁA�H�i���T�C�N�����f���������Ƃ����{�����B
�@�A �H�i���T�C�N������̊J��
�@�@�@��1��@�H�i���T�C�N���Ɋւ��Đ����p���̎�g�ۑ�ɂ���
�@�@�@��2��@�H�i�֘A���Ǝ҂̐H�i�p�����������ɂ���
�@�C ���ƒ��a�����_�Ɛ��Y�V���|�W�E���̊J��
�@�@�@�e�[�}�@�u�z�^�Љ�̌`���Ɍ��������ۑS�^�_�Ƃ̖����v
�@�@�@���@�e�@�@���ᔭ�\�A�p�l���f�B�X�J�b�V����
�@�E �H�i���T�C�N�����f���������Ƃ̎��{
�@�Ȗ،�����ݒn�������s��ɂ����đ�ʂɔ�������H�i�p������͔쉻���A�Đ����p���邽�߂̃��T�C�N���{�݂��s����ɐݒu�����B
(4) �G�R�X���O�̗L�����p���i�ւ̎�g
�@��ʔp�����y�щ������D���琻������n�Z�X���O�i�G�R�X���O�j�̗L�����p�𑣐i���邽�߁A14�N9���ɗn�Z�X���O�L�����p���i�����ݒu���A�u�Ȗ،��G�R�X���O�L�����p���i�w�j�v��15�N3���ɍ��肵���B
�@�A �n�Z�X���O�L�����p���i����̊J��
�@�@�@��1��@�Ȗ،��ŗ��p���i�w�j�i�āj�̌���
�@�@�@��2��@�Ȗ،��ŗ��p���i�w�j�i�āj�̌����A�ӌ��W��
�@�@�@��3��@�G�R�X���O�̗L�����p�Ɋւ��镁�y�[���ɂ���
�@�C�@�Ȗ،��G�R�X���O�L�����p���i�w�j�̍���
�@���y�ь����̎s�����i�ꕔ�����g�����܂ށB�j����������G�R�X���O�̗L�����p�𑣐i���邽�߁A���̕i���m�ۂ̔��f���A�G�R�X���O���E�g�p����ۂ̔z�����ׂ������Ȃǂ��߂��B
(5) ���݃��T�C�N���ւ̎�g
�@���݃��T�C�N���@�̊��S�{�s�i14�N5��30���j�ɓ�����A�@�̓K���Ȏ��s��}�邽�߁A�e�������̊J�Ëy�ѕ��y�[�����������{����ƂƂ��ɁA�@�̎{�s��ɂ́A�K���Ȏ{�H�̎w����}�邽�߁A�ΏۍH������̃p�g���[�������{�����B
�@�A �u���݃��T�C�N���@�Ɋւ��鎖�������̎�����v�̍쐬
�@�@�̓K���Ȏ��s��}�邽�߁A�s���������������̎�������쐬���A�W�@�ւɔz�z�����B
�@�C�@���݃��T�C�N���@�̊��S�{�s�Ɍ������e�������̎��{
�@�����݃��T�C�N���@�u�K��̊J�Ái�ΏہF��̍H�������Ǝғ��j
�@���͏o��t�����Ɩ��S���҂ɑ��������̊J�Ái�ΏہF�y�؎������A����s�����j
�@�E�@���y�[�������̌p�����{
�@���݃��T�C�N���@�̎��m�O���}�邽�߁A�e��[�������i���L��f�ځA�e���r�b�l�A���[�@�t���b�g�z�z�A���݃��T�C�N���@�[���V�[���z�z�A�u�K��j�����{�����B
�@�G ����p�g���[���̎��{
�@���͏o�H������ɂ����镪�ʉ�̂̎w��
�@�����͍H���̊Ď�
�@
|
��Q�߁@�p�����E���T�C�N���̏� |
�@��ʔp�����̏����́A�u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�ɂ��A�s�����̌ŗL�����ƂȂ��Ă���B
�@��ʔp�����́A�ƒ납��r�o���ꂽ���y�т��A����̂ł���A���W���ꂽ���y�т��A�̑啔���́A�s�������͈ꕔ�����g���i�ȉ��u�s�������v�Ƃ����B�j�̏����{�݂ʼnq���I�ɏ�������Ă���B
�@13�N�x���ɂ����邱���̏����\�͂́A���ݏ����{�݂ɂ����Ă�2,898t/���ł���A���A�����{�݂ɂ����Ă�2,182kl/���ł���B
(1) ���ݏ���
�@���݂̑��r�o�ʂ́A�N�Ԗ�77��1��t�ɂ̂ڂ�A�W�c������ꂽ��3��t��������74��1��t���s�������ɂ�菈������Ă���B�i�}�Q�|�T�|�Q�j
�}�Q�|�T�|�Q�@���ݏ����̃t���[�i13�N�x�j�@�@�@�@ �i�P�ʁF���j
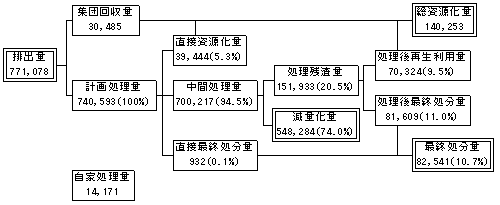
�@�s�����������ݏ����ɗv�����N�Ԃ̌o��́A���z��360���~�ŁA���̓���́A���݁E���ǔ��149���~(41.4%)�ł���A�����y�шێ��Ǘ���͖�199���~
(55.1%)�ƂȂ��Ă���B
(2) �������E�ŏI�����̏�
�@���݂̔r�o��771,078t�̂������������ꂽ�ʂ́A�s���c�̓��ɂ�����Ŏs�������֗^���Ă���W�c�����30,485t�A�s����������Đ��Ǝғ��֒��ڔ������ꂽ���ڎ�������39,444t�A�s�������̒��ԏ����{�݂ɂ����鎑������70,324t�̍��v�N��140,253t�ł������B���������ꂽ���̂̑唼�͎��ށA�����ށA�K���X�ނŁA�S�̖̂�9�����߂�B
�@�Ȃ��A�r�o�ʂɐ�߂鎑�����ʂ̊����i�Đ����p���j��18.2���ŁA�������N���ł��̏ɂ���B
�@�ŏI�����ʂ�82,541t�ŁA�r�o�ʂɐ�߂銄���i�ŏI�������j��10.7%�ŁA���̊����͔N�X�������Ă���B�i�\�Q�|�T�|�P�j
�@�u�e�����T�C�N���@�v�Ɋ�Â����ʎ��W�́A���ʑΏەi�ڂ̍��͂�����̂̌����S�s�����Ŏ��{����Ă���A42,597t�����ʎ��W���ꂽ�B�X�`�[�����e��△�F�K���X���e��̌����ɑ��A�y�b�g�{�g���̑����X���������ł���B�i�\�Q�|�T�|�Q�j
�\�Q�|�T�|�P�@�������E�ŏI�����̏��@ �@�@ �@�@�@�i�P�ʁF���^�N�j
| �N�x |
�X |
�P�O |
�P�P |
�P�Q |
�P�R |
| ���r�o�� |
710,231 |
725,987 |
731,053 |
757,362 |
771,078 |
| �@ |
���ڎ������� |
�| |
�| |
39,599 |
40,020 |
39,444 |
| ���ԏ�����Đ����p�� |
99,039 |
103,318 |
63,935 |
69,323 |
70,324 |
| �W�c����� |
33,573 |
30,576 |
27,885 |
29,100 |
30,485 |
| ���������ʁi���j |
(18.7%) |
(18.4%) |
(18.0%) |
(18.3%) |
(18.2%) |
| 132,612 |
133,894 |
131,419 |
138,443 |
140,253 |
|
�ŏI�����ʁi���j |
(12.4%) |
(12.1%) |
(11.7%) |
(11.5%) |
(10.7%) |
|
88,085 |
87,808 |
85,490 |
86,989 |
82,541 |
�i���j�P�O�N�x�ȑO�́A���ڎ������ʂ͒��ԏ�����Đ����p�ʂɊ܂܂��B
�\�Q�|�T�|�Q�@�e�����T�C�N���@�Ɋ�Â����ʎ��W��
�i�P�ʁF���^�N�j
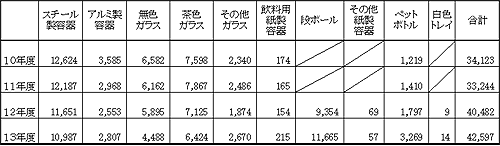
(3) ���A����
�@13�N�x�̂��A�y�я����D�̑��r�o�ʂ�489,007kl�ł���A���̂���488,858kl���s�����̐ݒu���邵�A�����{�݂ŏ�������Ă���B�i�}�Q�|�T�|�R�j
�}�Q�|�T�|�R�@���A�����̏i13�N�x�j�@�@�@�@�i�P�ʁFkl�^�N�j
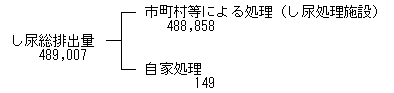
�@���A�����ɗv�����N�Ԃ̌o��́A���z��64���~�ŁA���̓��A���݁E���ǔ��9���~(14.3%)�ł���A�����y�шێ��Ǘ���͖�49���~(76.4%)�ƂȂ��Ă���B
(4) ���̐ݒu��
�@���́A���N5�`6���ݒu����Ă��邪�A13�N4������A���A�Ɛ����G�r�����ď������鍇���������̐ݒu���`���Â����A���A�݂̂���������P�Ə������̐V�݂��ł��Ȃ��Ȃ����B�i�}�Q�|�T�|�S�j
�}�Q�|�T�|�S�@�V�ݏ��ݒu��
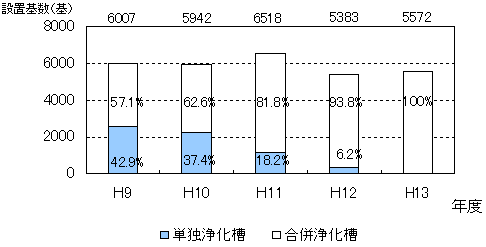
�@�Y�Ɣp�����̏����́A�u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�ɂ��A�r�o���ƎҎ���̐ӔC�ɂ����ēK���ɏ������邱�ƂƂ���Ă���B
�@�Y�Ɣp�����́A���Ɗ����ɔ����Ĕr�o�����p�����̂����A���D�A�p�v���X�`�b�N�ޓ�20��ނł���B�����̔p�����́A�r�o���Ǝ҂̐ӔC�ɂ����ēK���ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����Ǝ҂ɂ��s�K���ȏ����̎����������̂ŁA�X�ɓK�������̐��i�ɂ��Ďw���E�Ď��̋�����}��K�v������B
(1) �r�o�ʂƏ����̏�
�@�A �r�o��
�@1�N�ԂɎY�Ɣp������1000t�ȏ�A���ʊǗ��Y�Ɣp������50t�ȏ�r�o���鑽�ʔr�o�Ǝ҂��璥���������ѕ�����ɐ��v���������ɂ�����13�N�x�̑��r�o�ʂ́A��729��t�ł���B
�@��ޕʂł́A�����̂ӂ�A����300��t(41.1��)�ōł������A�����ʼn��D��249��t(34.1��)�A���ꂫ�ޖ�77��t(10.6��)�A�z������50��t(6.8��)�A�p�v���X�`�b�N�ޖ�13��t(1.8��)�̏��ɂȂ��Ă���B
�@�Ǝ�ʂł́A�_�Ƃ���301��t(41.2��)�ōł������A�����Ő�����149��t(20.4��)�A�d�C�E�K�X�E�����Ɩ�99��t(13.6��)�ƂȂ��Ă���B�i�}�Q�|�T�|�T�j
�}�Q�|�T�|�T�@�Ȗ،�������r�o���ꂽ�Y�Ɣp�����̐��v�ʁi13�N�x�j
| �i��ޕʁj |
�i�Ǝ�ʁj |
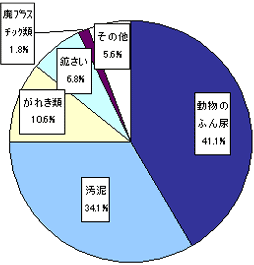 |
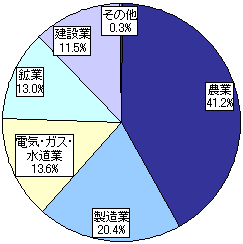 |
�@�C �����p��
�@�i�ږ��̍Đ����p�́A��������91.8���A���ꂫ��90.5�����������l���������ʁA�p�v���X�`�b�N��41.1���A����36.9���̍Đ����p�����Ⴂ�B�i�\�Q�|�T�|�R�j
�@�_�ƁE�z�ƂɌW����̂��������S�̂̐��l�́A10�N�x�ȍ~�قړ������ڂ������Ă���B�i�\�Q�|�T�|�S�j
�@�Ȃ��A���ɔr�o�ʂ̑��������̂ӂ�A�ɂ��ẮA�]������엿�i�͔쓙�j�Ƃ��Ă̍Đ����p���s���Ă����Ƃ���ł��邪�A�ꕔ�ŕs�K���ȕۊǁA�������s���Ă���B11�N11���Ɂu�ƒ{�r�����̊Ǘ��̓K�����y�ї��p�̑��i�Ɋւ���@���v���{�s���ꂽ���Ƃɂ��A����A�͔�Ƃ��Ă̗��p�ƓK����������w���i�������̂Ɗ��҂����B
�@�E �ŏI������
�@��ޕʂł́A�قƂ�ǂ�10�����������A�p�v���X�`�b�N��26.2���A�K���X�����A�R���N���[�g�����y�ѓ����킭��16.5���ɂ��Ă͍������ƂȂ��Ă���B�i�\�Q�|�T�|�R�j
�@�S�̓I�ɂ́A10�N�x�ȍ~�������Ő��ڂ��Ă���B�i�\�Q�|�T�|�S�j
�\�Q�|�T�|�R �Y�Ɣp�����̎�ޕʏ����i�_�ƁE�z�ƂɌW����̂������j
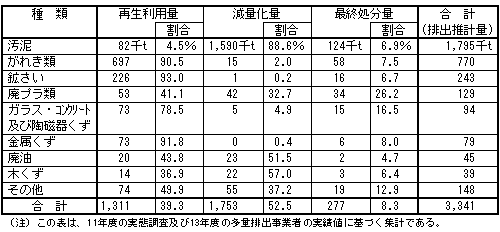
�\�Q�|�T�|�S �Y�Ɣp�����̔N�x�ʏ����i�_�ƁE�z�ƂɌW����̂������j
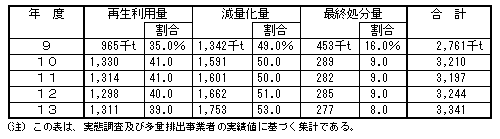
(2) �Y�Ɣp���������{�݂̐ݒu��
�@�ݒu�������ԏ���461�{�݁A�ŏI����48�{�݂ł���B����͏����Ǝ҂ɂ��{�݂����ԏ���297�{�݁A�ŏI����47�{�݂ł���A����ȊO�̎��Ǝ҂ɂ��ݒu���́A���ԏ���164�{�݁A�ŏI�����P�{�݂ł���B
�@���ԏ����{�݂́A�����Ǝ҂ł͔j�Ӂi178�{�݁j�Əċp�i31�{�݁j�őS�̂�7���ȏ���߂Ă���B���Ǝ҂ł͒E���i102�{�݁j�Əċp�i48�{�݁j�ƂőS�̂�9���ȏ���߂Ă���B�i�\�Q�|�T�|�T�j
�@�ŏI������48�{�݂�13�N�x���ɂ�����c�]�e�ʂ�����{�݂�28�{�݂ł���A�c�]�e�ʂ̍��v�́A�����Ǝғ��̕ɂ��Ζ�226�����R�ł���A12�N�x���̖�176�����R���50�����R���������B�i�\�Q�|�T�|�U�j
�@�Y�Ɣp���������Ǝ҂̎Y�Ɣp���������{�ݓ��̐ݒu�ɂ������ẮA�u�Ȗ،��p���������Ɋւ���w���v�j�v�Ɋ�Â����O���c�y�єp���������{�ݓ����c��ɂ����āA�Z�p�I�ȐR���y�ъW�@�߂̒������s���Ă���B
�\�Q�|�T�|�T ���ԏ����{�݂̐ݒu�� �@ �@�@�@�@�@�@�@�@(�P��:t/��)
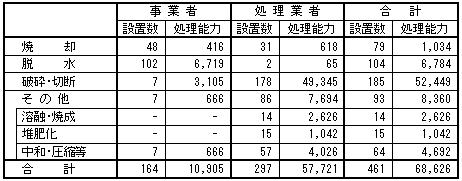
�i���j���Ǝ҂̐ݒu���͔p���������@�̋��Ώێ{�݂݂̂̐��A�����Ǝ҂̐ݒu���́A���ΏۊO�̎{�ݐ����܂ށB
�\�Q�|�T�|�U ����^�ŏI������̐ݒu���@�@�@�@(�P�ʁF�炍�R)
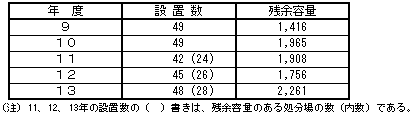
(3) �Y�Ɣp���������Ƃ̋���
�@�Y�Ɣp�����̎��W�E�^���A���ԏ����i�ċp�A�j�ӓ��j�y�эŏI�����i�����j�̋Ƃ��s�����Ƃ���҂́A�m���i�F�s�{�s���j�̋����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ���Ă���B
�@14�N3�������݂̎Y�Ɣp�������W�^���Ƃ̋���L����҂�2,673�Ǝ҂ŁA���̂���1,024�Ǝ�(38���j�́A�����Ɏ傽�鎖������L����Ǝ҂ł���B�i�\�Q�|�T�|�V�j
�@�Y�Ɣp���������Ƃ̋���L����҂�198�Ǝ҂ŁA���̂���29�Ǝ҂��ŏI���������Ƃ͈̔͂Ƃ��ċ����Ă���B
(4) �Y�Ɣp���������Ǝ҂̏�������
�@�Y�Ɣp���������Ǝ҂�13�N�x�̏������т͎��̂Ƃ���ł���B
�@�@ �Y�Ɣp���������ƎҎ���
�@�����̒��ԏ����Ǝ҂����������Y�Ɣp�����͖�350��t�ł���B���̓���́A�����̎��Ǝ҂���̎���ʂ���226��t�A���O�̎��Ǝ҂���̎���ʂ���124��t�ƂȂ��Ă���B
�@�����̍ŏI�����Ǝ҂����������Y�Ɣp�����͖�30��t�B���̓���́A�����̎��Ǝ҂���̎���ʂ���11��t�A���O�̎��Ǝ҂���̎���ʂ���19��t�ƂȂ��Ă���B�i�\�Q�|�T�|�W�j
�@�A �Y�Ɣp�������W�^���ƎҎ���
�@�Y�Ɣp�������W�^���Ǝ҂ɂ���Č��O����������ꂽ�Y�Ɣp�����͖�92��t�i���ԏ����ړI��83��t�A�ŏI�����ړI��9��t�j�A����A�������猧�O�ɔ��o���ꂽ�Y�Ɣp�����͖�51��t�i���ԏ����ړI44��t�A�ŏI�����ړI7��t�j�ł���B�i�\�Q�|�T�|�X�j
�\�Q�|�T�|�V�@�Y�Ɣp���������Ǝ҂̋���
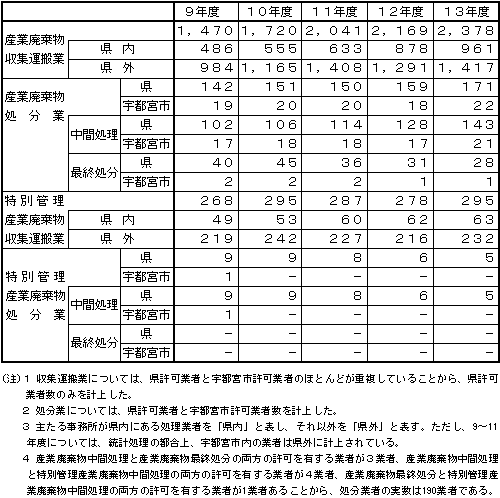
�\�Q�|�T�|�W �����Ǝ҂̔r�o�n��ʏ�������
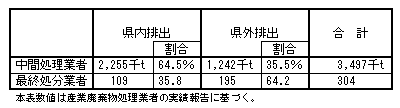
�\�Q�|�T�|�X ���W�^���Ǝ҂̉^���n��ʏ�������
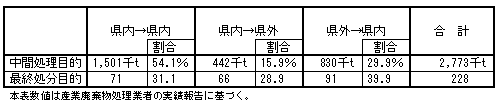
�@
|
��R�߁@�p�����E���T�C�N���� |
�@��ʔp�����̎��̑��l���Ɨʂ̑���ɑΉ����邽�߂ɂ́A���݂̌��ʉ��E�Đ����p�𑣐i����ƂƂ��Ɏ{�݂̐������i�y�шێ��Ǘ��ʂ̎w������������K�v�����邱�Ƃ���A���̂��Ƃ��d�_�I�Ɏw�������B
(1) ���݂̌��ʉ��E���T�C�N���̐��i
�@�u�Ȗ،��p���������v��v�Ɋ�Â��āA���݂̌��ʉ��E���T�C�N���ɂ��Ă̈ӎ��̍��g�Ⓖ�ړI�ȍs���A����ɂ͊��Â���𑍍��I�������I�ɐ��i���Ă������߁A14�N�x�́A�R�q���i���ԁi10���j���}�C�E�o�b�O�E�L�����y�[����W�J�����ق��A���̎��Ƃ����{�����B
���@�N���[���A�b�v�t�F�A�̊J��
�@������l�ЂƂ肪�n�������ւ̔F����[�߁A�p���������͂��߁A���̕ۑS�ւ̕��L�������Ƌ��͂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�N���[���A�b�v�t�F�A���J�Â����B
�@���@�ԁF14�N10��26���i�y�j�`10��27���i���j��2����
�@��@��F�Ȗ،��q�ǂ������Ȋw��
�@��@�ÁF�Ȗ،��E�Ȗ،��N���[���A�b�v�t�F�A���s�ψ���
�@����ҁF10,500�l
�@15�N�x��10���ɁA�����ɂ����āA�N���[���A�b�v�t�F�A���J�Â���B
���@�����ʉ��E���T�C�N�������J�Î���
�@�������S���q�������y�ш�ʌ����̂��ݖ��ɑ���ӎ��̍��g��}�邽�߁A�����ʉ���T�C�N�����e�[�}�ɂ��������������ŏ㉉�����B
�@�������F�u�ӂ��낤��l�ƂȂd���v
�@��������i�����w���Ώہj�F111��@ 32,683�l
�@��ʌ����i��ʌ����Ώہj�F 17�� 6,850�l
�@15�N�x�́A�������100��̃��T�C�N�������J�Â�\�肵�Ă���B
���@�����ʉ��A���T�C�N���L������
�@�e���r�E���W�I�X�|�b�g�b�l���Ō����ɂ��݂̌��ʉ��A���T�C�N���̐��i�ɂ��ČĂт������B
(2) ���ݏ����̓K�����̐��i
�@�A�@���݂̓K�������̎w��
�@���ݏ����{�y�эŏI������̐����ɂ��Ďw������ƂƂ��ɁA�K���Ȉێ��Ǘ��̐��i��}�����B
�@�C�@���ݏ����̍L�扻�̐��i
���@�L�扻�̌v��̊T�v�i�Ȗ،��p���������v��j
�@�E�L��s��������b�Ƃ���10�̒n��u���b�N��ݒ肵��
�@�E�ݒ肵���n��u���b�N���̊����{�݂̉ғ���X�V�������܂��A����������3�O���[�v������
���@�s�������̔p���������{�݂̍L�扻�̐��i
�@�E�n��u���b�N�L�扻��{�v��̍쐬
�@�L�扻�̒����Ȑ��i��}�邽�߁A���ݏ����{�y�эŏI������̓K���Ȏ{�ݐ����ƈێ��Ǘ����w������ƂƂ��ɁA�e�n��u���b�N���Ƃ̍L�扻��{�v��쐬�ɑ��A�x�����s�����߁u�n��u���b�N�L�扻��{�v��쐬��⏕���Ɓv��11�N�x�ɑn�݂����B
�@14�N�x�@�n��u���b�N�L�扻��{�v��쐬���Ǝ��{�c��
�@�@�@�@�@�@ �F�s�{�n�悲�ݏ����L�扻���i���c��
�@�E�s�����U�������ݕt��
�@�s���������{����_�C�I�L�V���ލ팸�̂��߂̎{�݂̉����ɗv����o��ɂ��Ďs�����U�������̒��Ƀ_�C�I�L�V���ޑ����ʘg��݂��Ďs�������x�������B
(3) �U�����ݑ�
�@���H��ό��n�ɂ����邲�ݓ��̎U���́A�n��̊��Ȃ�����łȂ��A���W�E�^���̖ʂł��p�����s���̑傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B���̂��߁A�֓��n���m������\������11�s���ł́A���a57�N���疈�N5��30���i���݃[���̓��j�𒆐S�ɓ��ꂵ���������L�����y�[����W�J���Ă���B
�@14�N�x���S�s�����y�ъW���c�̂̋��͂āA�����S��ł̎U�����݂̈�Ď��W�E�[�������y�я��E���E���Z����ΏۂƂ����|�X�^�[�E�W��̕�W�����{�����B�i�\�Q�|�T�|�P�O�A�\�Q�|�T�|�P�P�j
�@15�N�x�����������A���l�̊������L�����y�[����W�J���A���y�[���ɓw�߂�B
���@14�N�x���݂̎U���h�~�ƍĎ�������i�߂邽�߂̕W��R���e�X�g
�@�@�ŗD�G��i
�@�@�i���w�Z��w�N�j�݂�����@������Ɓ@�Ƃ܂��ā@���݂Ђ낢
�@�@�i���w�Z���w�N�j������@����炢���@�S�~�̎R
�@�@�i���w�Z�j�@�@�@�@ �ǐS���@�ꏏ�Ɏ̂ĂĂ����̂���
�\�Q�|�T�|�P�O�@5��30���i���݃[���̓��j�𒆐S�Ƃ�����Ď��W�E�[���̌��ʁi14�N�x�j
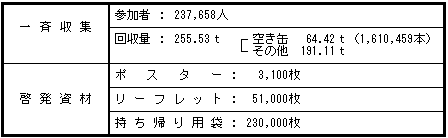
�\�Q�|�T�|�P�P�@�|�X�^�[�E�W��̉���i14�N�x�j
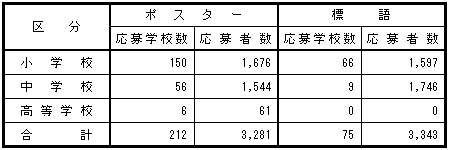
(4) ���A�����{��
�@���A�����{�݂̐����y�э��x�����ւ̉��P�ɂ��Ďw������ƂƂ��ɁA�K���Ȉێ��Ǘ��̐��i��}�����B
�@���Ɋւ��ẮA�u���@�v�y�сu�Ȗ،����ێ�_���Ǝ҂̓o�^�Ɋւ�����v�Ɋ�Â��A�ێ�_���Ǝ҂̗��������y�я��ێ�_���Ǝ҂ɑ���u�K������{���A���̓K���Ȉێ��Ǘ��̐��i��}�����B
�@
|
�Q |
�Y�Ɣp�����i�F�s�{�s���������B�j |
�@�{���ł́A���̕ۑS��}��A�z�^�Љ�̌`���𐄐i���邽�߁A�Y�Ɣp�����̓K���������A�������D�̎������A�؍ނ̎c�p�ނ⌚�ݕ��Y���̍ė��p�ȂNJe��̎{����s���Ă���B
(1) �Y�Ɣp�����K��������
�@�A�@�����ɗ��n���Ă��鎖�Ə��̗�������
�@�Y�Ɣp���������{�݂�ݒu���Ă���r�o���Ǝ҂Ȃnj����ɗ��n���Ă��鎖�Ə��i���Џ�������܂ށB�j��Ώۂ�600���̗������������A�Y�Ɣp�����̔����A�ۊǏA���������y�шϑ��̕��@���ɂ��ĊĎ��w�����s�����B
�C�@���ԏ����E�ŏI�����Ǝ҂̗�������
�@�����Ǝ҂̐ݒu���Ă���ċp�{�ݓ��̒��ԏ����{�y�эŏI�������ΏۂɁA����746���̗������������{���A�K���Ȉێ��Ǘ��̊m�ۂɂ��ĊĎ��w�����s�����B
�E�@�w����
�@���Ə��y�юY�Ɣp���������Ǝ҂ɑ�1,346���𗧓��������w���������ʁA���̂���146���̕����w���i�����j���������A4���̉��P���߁A2,086���̒̕��������߂��B�܂��A18���̎Y�Ɣp���������Ƌ��̎�����y��4���̎Y�Ɣp���������ƒ�~�𖽂����B
�@������A�r�o���ƎҁA�����Ǝґo���ɎY�Ɣp�����̓K���ȏ����A�����ɂ��Ďw�����Ă����B�i�\�Q�|�T�|�P�Q�A�\�Q�|�T�|�P�R�j
�\�Q�|�T�|�P�Q�@�Y�Ɣp�����W�����������ʁi13�N�x�j
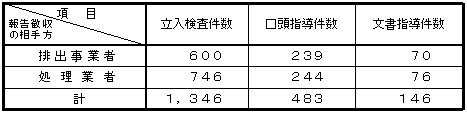
�\�Q�|�T�|�P�R�@�s�������̏i13�N�x�j
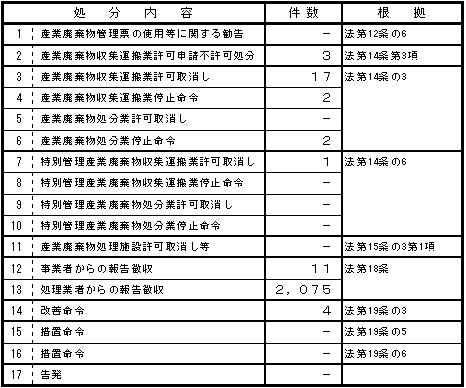
|
(��)�P |
�@�Y�Ɣp�������W�^���Ƌ�����������Ǝ҂̂����A1�Ǝ҂ɂ��Ă͓��ʊǗ��Y�Ɣp�������W�^���Ƌ�������������߁A����������Ǝ҂�17�Ǝ҂ł���B |
|
2 |
�@�Y�Ɣp�������W�^���ƒ�~���߂���2�Ǝ҂́A���ꂼ��Y�Ɣp���������ƒ�~���߂������߁A��~���߂����Ǝ҂�2�Ǝ҂ł���B |
|
3 |
�@�����Ǝ҂���̕����ɂ́A�S�����Ǝ҂�ΏۂƂ������ѕ��܂ށB |
�@�G �u�Ȗ،��p���������Ɋւ���w���v�j�v�ɂ��K���E�w��
�@�Y�Ɣp�����̓K�������𐄐i���������̕ۑS��}�邽�߁A�u�Ȗ،��p���������Ɋւ���w���v�j�v�ɂ��A�Y�Ɣp���������{�݂�ݒu����ۂ̎��O�葱���ɂ��Ďw�����s���Ă���B
�@�Ȃ��A10�N6���A�u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�̉����ɑΉ�����ƂƂ��ɁA�@�����L���ɋ@�\���邽�߂̍s���w���̂�������K�肷�邽�߁A�w���v�j�����������B
�@���@���ɂ�邠�����x�̓���
�@���@���I�m����L����҂���̈ӌ�����葱�̓���
�@���@�ݒu���K�v�{�݂̎葱�̊ȗ���
(2) �s�@�������A�s�K��������
�@�A�@�p���������s������t��
�@�s�@�����A�s�K�������̖h�~�y�эŏI������̓K���Ȉێ��Ǘ����m�ۂ��邽�߁A�p�����Ď�����ݒu����s�����ɑ��A���̌o��̈ꕔ��⏕����p�����Ď����s������t���ɂ��s�K�������E�����̖h�~����u���Ă���B14�N�x�́A�v29�s���Ɍ�t�����B
�@�C�@�s�@�����̊Ď��ϑ���
�@�s�@���������������ԁA�x���̊Ď��p�g���[���A�w���R�v�^�[�𗘗p�����X�J�C�p�g���[�������{���邱�Ƃɂ��A�s�@�����̖��R�h�~�y�ь����҂̓���̉~������}���Ă���B
�@�܂��A13�N�x�ɂ́A�Ď��J�����̐ݒu�A�g�я��[���𗘗p�����Ď��A�g�V�X�e���������B
�@�E�@�Ȗ،����ۑS�����̑���
�@�Y�Ɣp�����̓K�������𑣐i����ƂƂ��ɁA�Y�Ɣp�����̏����ɋN�����鑹�Q�ɑ��⏞���s�����߁A�i�Ёj�Ȗ،��Y�Ɣp��������ɑn�݂��ꂽ�Ȗ،����ۑS�����̑����͎��̂Ƃ���ł���B
��������z�i15�N3�����݁j��3�D9���~
�@�G�@�Y�Ɣp�����s�@�����ً}��
�@�Y�Ɣp�����̕s�@�������ɂ�鐶�����ۑS��̎x��̖��R�h�~�̂��߂ɁA12�N�x���}�I�ً}�I�[�u�����{���邽�߂̊�����i�Ёj�Ȗ،��Y�Ɣp��������ɑ��������B
�@�����z�@�P���~�i��5�疜�~�A����5�疜�~�j
(3) �������E�ė��p��
�@�A �������D�̎�����
�@�������D�̗L�����p�𑣐i���邽�߁A�������������H��������B
���̍H��́A�����̗��扺�����y�ь����������̏I�������ꂩ�甭�����鉺�����D���W�߁A�ċp�n�Z�{�݂ɂ��X���O�����A���ݎ��ޓ��ɓ]�����āA�L�����p��i�߂���̂ł���A14�N10���ɋ��p���J�n�����B
�@�C�@�؍ނ̎c�p�ނ̍ė��p
�@�����̗ыƥ�؍ގY�Ƃ����Y�����̒��Ŕ�������c�p�ނ̍ė��p�𑣐i����B
�@�c�p�ނ́A�X�ѓ��Ő��Y�����f�ށi�ۑ��j�ޕi�i���A�ޓ��j��؍ރ`�b�v�ɉ��H����ߒ��Ŕ������鋘���A�[�ޓ��̖؎��n�c�p�ނ���ł���B
�@�����̖؎��n�c�p�ނɂ��ẮA�e���Ƒ̂��ƂɎ��Ћy�шϑ��ɂ�菈������Ă���A���؎s��E���ލH��ɂ������ȏ����E���p�́A�\�Q�|�T�|�P�S�̂Ƃ���ł���B
�@�Ȃ��A14�N�x�Ɂu�Ȗ،��؎������z���p���i�w�j�v�����肵�A15�N�x����͂��̎w�j�ɏ]�����؎��n�c�p�ނ̏z�����p����������n�抈���ɑ��āA�x�����J�n����B
�\�Q�|�T�|�P�S�@���؎s��E���ލH�ꓙ�ɂ����鏈���E���p��
�P�ʁF��m3/�N
| ��� |
�r�o�� |
�����E���p���@ |
| �`�b�v���� |
���`�R�� |
�R�� |
�ƒ{�~�� |
������ |
�ċp |
�s�� |
| ���� |
24 |
0 |
1 |
0 |
19 |
0 |
1 |
3 |
| ���� |
56 |
0 |
0 |
0 |
16 |
15 |
2 |
23 |
| ��L�ȊO |
11 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
| �v |
91 |
6 |
1 |
0 |
35 |
15 |
6 |
28 |
�i���j�P�����E���p�ʂ����ʂ̍��ڂ��g�O�h�Ɋ܂܂��B
�@�@�@�Q�w�j���莞�̃A���P�[�g�����ɂ�鐄�v�l�ł���B
�@�E�@���ݕ��Y���̍Ď�����
�@���ݍH�����甭������A�X�t�@���g�E�R���N���[�g�̌��ݕ��Y���̍Ď������E�ė��p�𑣐i����B
�@13�N�x�ɂ�����Ȗ،��������H���i���E�s�����j�̌��ݕ��Y���̔r�o�ʋy�у��T�C�N�����͕\�Q�|�T�|�P�T�A�\�Q�|�T�|�P�U�̂Ƃ���ł���B
�\�Q�|�T�|�P�T�@���ݕ��Y���r�o�ʁi13�N�x�j
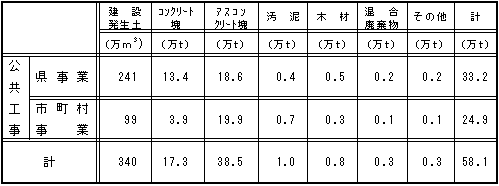
�\�Q�|�T�|�P�U�@���ݕ��Y�����T�C�N�����i13�N�x�j�@�@�@ (�P�ʁF��)
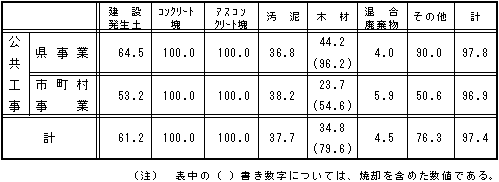
(4) �_�C�I�L�V���ލ팸��
�@�Ȗ،����ۑS�����̗Z���ΏۂɎY�Ɣp���������{�݂�lj����āA�����Ǝ҂��ݒu����ċp�{�݂̉��������x�����Ă���B
�@
(5) �|�������r�t�F�j���i�o�b�a�j��
�@13�N7�����|�������r�t�F�j���̓K���ȏ����̐��i�Ɋւ�����ʑ[�u�@���{�s����A�|�������r�t�F�j���p������ۊǂ��鎖�Ǝ҂́A�|�������r�t�F�j���p�����̕ۊNjy�я����̏�s���{���m�����ɓ͂��o��ƂƂ��ɁA15�N�ȓ��ɂ����K���ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ����B
(6) �y�����K��������
�@���ݎc�y���̏����ɔ����L�Q�����̍����△�����Ȗ����ē��ɑ���s��������A���ݎc�y���̓y���ɂ�閄���Ăɂ��Ď��ӏZ���Ƃ̃g���u�����������Ă����B
�@���̂悤�ȏ܂��A�����̐����̈��S�̊m�ۂƐ������̕ۑS�̂��߁A11�N4���Ɂu�y�����̖����ē��ɂ��y��̉����y�эЊQ�̔����̖h�~�Ɋւ�����v���{�s���A�����ɂ�����y�����̖����Ă̓K�������𐄐i���Ă���B
�@�Ȃ��A�����̋K���Ώۖʐϖ����i3,000���R�����j�̖����Ăɂ��Ă�47�s���������𐧒肵�Ă���B
(7) �Y�Ɣp�����W���c��
�@�Y�Ɣp������K���ɏ������邽�߂ɁA�Y�Ɣp���������Ǝ҂̎����̌���A�Y�Ɣp�����Ɋւ���m���̕��y�E�[�����тɎY�Ɣp�����̓K�������y�эĐ����p�Ɋւ��钲�������A���C�A���̎��W���𐄐i����B
�@�����̏���������ړI�Ƃ��āA�i���j�Ȗ،����ۑS���Ћy�сi�Ёj�Ȗ،��Y�Ɣp��������g�D����Ă���A���ꂼ�꒲�����������⌤�C��ɂ��A�Y�Ɣp�����̓K���ȏ����y�эĐ����p���Ɍ����Ċ�����W�J���Ă���B���͗��c�̂̉^�c�Ǘ��ɂ��ēK���Ȏw���ē��s���ƂƂ��ɏ����Ƃɂ��ĕK�v�ȉ������s���Ă���B
|