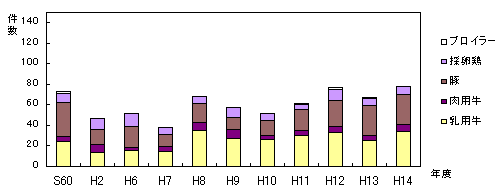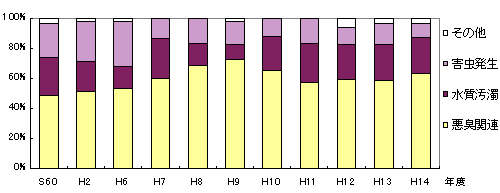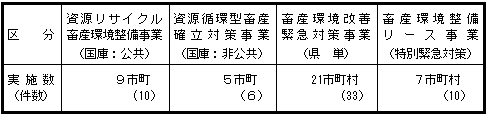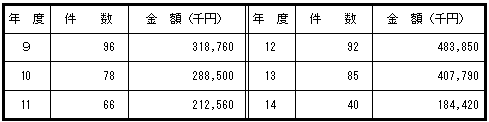|
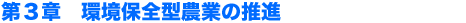
化学肥料・農薬の過度の使用、家畜ふん尿の過剰施用や不適切な処理等により、周辺環境への悪影響が生じている。
このため温室効果ガスの一種であるメタン・亜酸化窒素の削減に向けた施肥や家畜飼養管理技術の改善、2004年末に全廃が決定している臭化メチルの代替防除技術の確立が求められている。
一方、消費者の健康・安全志向等から、有機農産物や減農薬農産物等を求める声が高まっている。
堆肥等を利用した土づくりと化学肥料、化学農薬の低減を一体的に行う農業生産方式を導入する生産者(エコファーマー)は、15年3月末現在3,924名が認定されている。
14年度末現在、環境保全型農業推進方針を策定した市町村数は、31市町村(策定率63%)である。(関東平均:59%)
発生数を経年的にみると、昭和60年度以降、60件前後で推移しており、過去3か年は11年度61件、12年度77件、13年度67件の発生となり、14年度は78件とやや増加した。
家畜別では、乳用牛が全体の44%を占め、次いで豚(37%)、採卵鶏(10%) 、肉用牛(9%)という結果であった。(図3−3−1)
図3−3−1 畜産環境苦情の発生状況(家畜別)
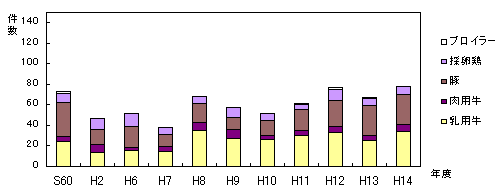
苦情の種類別では、悪臭関連(64%) が特に多く、次いで水質汚濁関連(24%)
となっている。苦情が悪臭、水質汚濁、害虫発生に集中している傾向が認められる。(図3−3−2)
図3−3−2 苦情の種類別発生状況
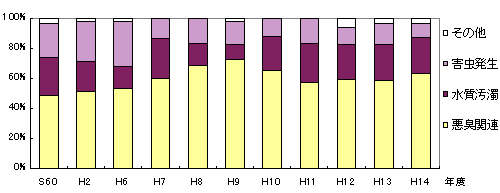
6年3月に「栃木県環境保全型農業推進基本方針」を策定し、次の4項目を柱に環境に調和した農業を積極的に推進する。
○ 土づくりの推進
○ 環境への負荷を軽減するための効率的な施肥及び防除の推進
○ 未利用有機物資源のリサイクルの推進
○ 環境保全型農業技術の開発促進
環境保全型農業の普及啓発を図るため、生産者・農業団体等の取組の支援、消費者に対するPRを実施する。
(1) 県推進指導事業
ア エコファーマーの育成、実証展示ほの設置、土壌診断の実施、技術資料の作成等を通じた普及啓発
堆肥等を活用した土づくりと化学肥料、化学農薬の使用低減を一体的に行う農業生産方式を導入する生産者(エコファーマー)を育成する。また、濃密指導地区、実証展示ほ等の設置及び啓発資料の作成や広報活動をとおして普及啓発を行う。
イ 農薬・化学肥料使用低減の推進
性フェロモン剤の活用による効率的防除の推進、土壌診断に基づく適正施肥の推進等の運動を展開するとともに、作物病害虫の生物的防除法の開発、耐病性品種の開発等の試験研究にも取り組む。
ウ 消費者交流事業の開催等
県民の日(6月)、農業試験場公開デー(8月)、ふるさとフェアー(10月)等において、環境にやさしい資材、パネルの展示等を実施するなど、消費者・生産者双方の意識高揚と相互理解を促進する。
また、エコファーマーと消費者を交えたシンポジウムを開催し、環境保全型農業や食の安全等についての理解を促進する。
(2) 市町村等推進事業
ア 地域に適した先導的生産方式の実証等実践活動の強化
イ 家畜排泄物や生ごみ等の地域循環システムの構築の支援
(3) 農業団体推進事業
ア 環境保全型農業の普及啓発等
イ 堆肥利用定着のための活動支援
(4) 堆肥の流通・利用促進
畜産部門と耕種部門の連携のもと堆肥の流通・利用の促進を図るため、県関係機関、市町村、農協、堆肥センター等を構成員とする「栃木県堆肥利用促進協議会」を設立し、堆肥の生産技術の改善及び品質向上、堆肥の流通・利用の促進、耕種農家のニーズの把握、堆肥の広域的な需給調整等の活動を行っている。
畜産経営による環境汚染問題は、経営の存続や畜産業の発展に重大な影響を与えることから、家畜ふん尿の適切な処理・利用により環境汚染を未然に防止し、畜産経営の健全な発展を図るため、「環境保全型畜産確立基本方針」に沿って、次のような畜産経営における環境対策の推進に努めている。
○ ふん尿の適正な処理と畜産農家・耕種農家の有機的連携による農地還元の推進
○ 家畜ふん尿処理機械・施設等の家畜飼養施設環境整備の推進
○ 適地への経営移転の推進
各農業振興事務所ごとに県関係機関、市町村、農協等の関係団体を構成員とする「地方協議会」を開催し、次のような指導等を行っている。
○ 環境問題の発生状況等の実態調査
○ 畜産農家に対する環境保全意識の啓発
○ 畜産公害苦情・紛争処理に対する助言指導
○ 水質・臭気調査等の実施と調査結果に基づく農家指導
(1)
資源リサイクル畜産環境整備事業(国庫:公共)、資源循環型畜産確立対策事業(国庫:非公共)、畜産環境改善緊急対策事業(県単)、畜産環境整備リース事業
適正な家畜ふん尿の処理・利用を推進するために、畜産農家が組織化し、または畜産農家と耕種農家が連携して施設・機械等を整備するため各種事業を実施した。(表3−3−1)
表3−3−1 畜産環境対策の施設、機械整備に対する事業実施状況
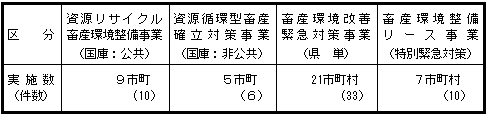
(2) 農業近代化資金の融資
畜産経営による環境汚染防止を推進するため、家畜ふん尿処理施設や機械の整備に対し、農業近代化資金の融資を実施している。(表3−3−2)
表3−3−2 農業近代化資金(畜産関係公害防止機械・施設)の融資状況
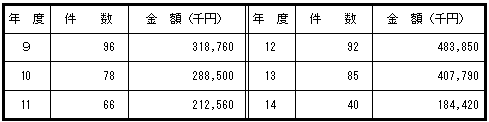
|