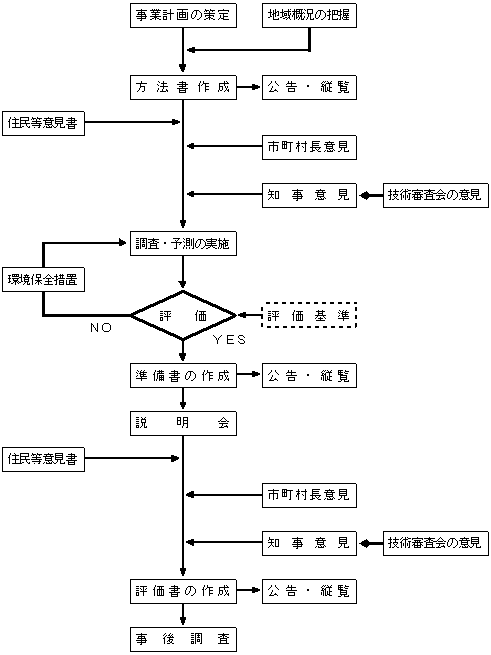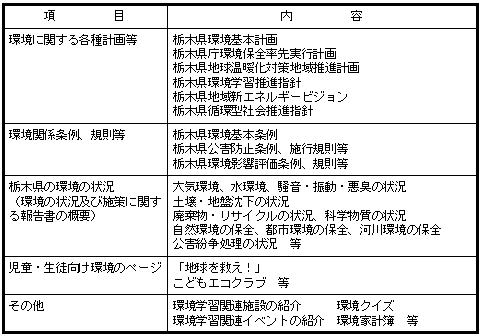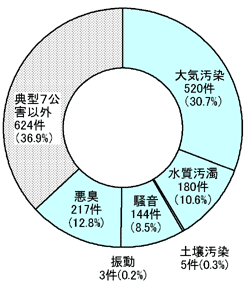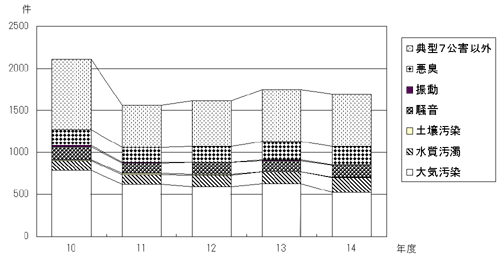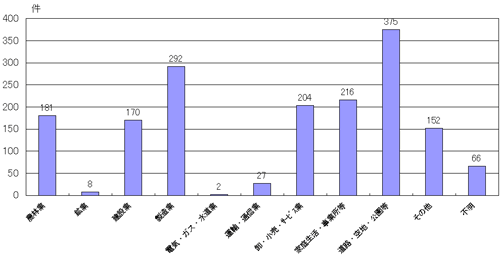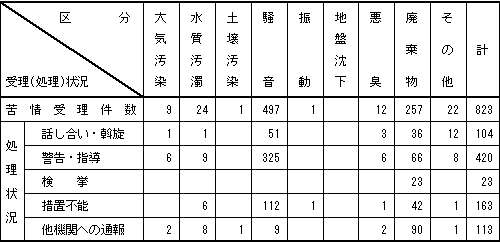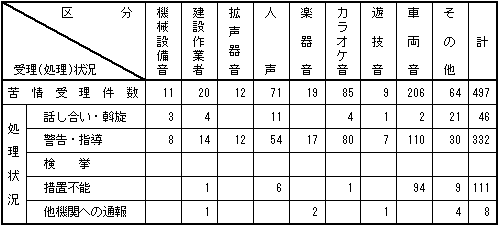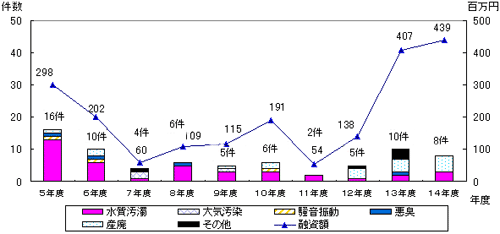|
�@���e���]���Ƃ́A�H�ƒc�n��Z��c�n�̑������A��K�͂ȊJ�����Ƃ��s���ۂɁA���Ƃ̎��{�����ɋy�ڂ��e�������Ǝ҂����炩���ߒ����A�\���y�ѕ]�����A���̌��ʂ����Ɠ��e�̌��ʂɔ��f�����邱�Ƃɂ��A���̕ۑS�ɓK���ɔz�����悤�Ƃ�����̂ł���A9�N6���Ɍ��z���ꂽ�u���e���]���@�v�y��11�N3���ɐ��肳�ꂽ�u�Ȗ،����e���]�����v�̓K�ȉ^�p�ɓw�߂Ă���B
(1) �{���̊��e���]�����x�̕���
|
���a50�N 3�� |
�J�����Ƃɑ�����e���]���̎��{�Ɋւ�����j�̍��� |
|
���� 3�N 4�� |
�Ȗ،����e���]�����{�v�j�̎{�s�i���x���e�ʂ̏[���j |
|
9�N 6�� |
���e���]���@�̐���i�@�����E���x���e�ʂ̏[���j |
|
10�N 1�� |
�Ȗ،����R�c��֎���i�u����̊��e���]�����x�݂̍���ɂ��āv�j |
|
11�� |
�Ȗ،����R�c��̓��\ |
|
11�N 2�� |
��252��Ȗ،��c�����ɏ��Ă���� |
|
3�� |
�Ȗ،����e���]�����̐��� |
|
6�� |
���e���]���@�̎{�s
�Ȗ،����e���]�����̎{�s |
(2) �{���̊��e���]�����x�̓���
�@�A�@�Ώێ��Ƃ̊g��
�@�Ώێ��Ƃ��A����܂ł̖ʓI�ȊJ�����Ƃ̂U��ނɓ��H�A�_���A�p���������{�ݓ��̎��Ƃ�lj����A18��ނɊg�債���B
�@�C�@���@���̎葱�̓���
�@���Ǝ҂����������s���O�ɑΏێ��ƂɌW����e���]�����s�����@�i���e���]���̍��ڂ⒲���A�\���y�ѕ]���̎�@�j���L�ڂ������@�������J���A�Z���A�s�������y�ђm���̈ӌ����āA���e���]���̍��ځA��@��I�肷��葱��V���ɓ��������B
�@�E�@�]�����ڂ̊g��
����܂Ŋ��e���]���̑ΏۂƂ��Ă����T�^�V���Q�̍��ڋy�ю��R���T�v�f�ɐ��Ԍn�A�p�����A�������ʃK�X���̍��ڂ�lj������B
�@�G �Z���Q���@��̊g��
�@�@�@���̕ۑS�̌��n����ӌ����q�ׂ邱�Ƃ̂ł���҂̒n��I�Ȍ�����Ȃ����A�N�ł��ӌ����q�ׂ邱�Ƃ��ł���悤�ɂ����B
�@�A�@���@���̎葱�ɂ����āA�ӌ����q�ׂ�@���V���ɓ��������B
�@�B �K�v�ɉ����Č�������J�Â��A�������ɂ��Ċ��̕ۑS�̌��n����̈ӌ��ڏq�ׂ邱�Ƃ��ł���悤�ɂ����B
�@�I ���㒲���̓���
�@�H�������̊��̏�c�����邽�߂́A�����鎖�㒲���Ɋւ���v���]�����̋L�ڎ����Ƃ��A���Ǝ҂͂���ɏ]���čH�������ɒ������s���A�������ʂ�m���ɕ��邱�ƂƂ����B
�@�J�@���e���]���Ɋւ���Z�p�I�������R�c���邽�߂ɁA�w���o���҂���\�������Ȗ،����e���]���Z�p�R�����ݒu���A�m�������@���y�я������ɂ��Ĉӌ����q�ׂ�ۂɐR����̈ӌ������ƂƂ����B
(3) ���e���]���̎w�����̏�
�@�葱���̎��Ă̓_���V�z�ɌW�鎖�Ƃ�1�����邪�A12�N�x�ɏI���������@���葱���Ď��Ǝ҂������������{���Ă���B
�@���̑��A14�N�x�ɂ����ẮA���ƒ����̎��Ƃɂ��āA��o���ꂽ���㒲������R�����A���ۑS��K�v�Ȏw�������s�����B
�}�U�|�P�@���e���]���̎菇
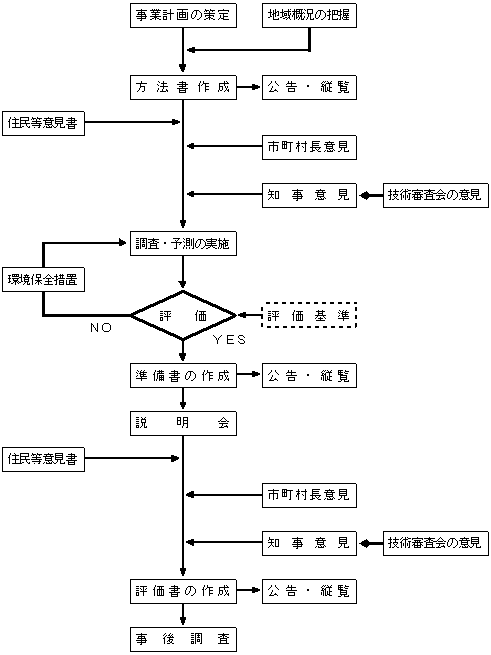
�@
|
��Q�߁@�����y�ь����̎��{ |
�@
|
�P |
�ی����Z���^�[�ɂ����钲������ |
�@�������̎��Ԕc���Ɩ��R�h�~��}�邽�߁A�ȉ��̉ۑ�ɂ��Ē����������s���Ă���B
(1) ��C���W
�@�A�@�Ȗ،��ɂ��������V���q���iSPM�j�̋����ɂ���
�@13�N�x��C�����펞�Ď����茋�ʕ��ɂ��A�Z���I�]����SPM��������B���ł���B
�@�Ȗ،��ł́A7����12����SPM�������X���ɂ���A���̌��������邽�߁A�l�������ɍ���A���R��2�n�_�ŃT���v�����O���s�����B����ɁA������SPM�f�[�^�A�C�ۃf�[�^��p���ĉ�͂��s�����B���R�Ƃ̑��W���Ō���ƁA�ȖA�^���A�����A�G�R�A�F�s�{�A����A�����A�����̏��ɍ��������B
�@�ď��SPM�Z�x�̍������ɂ́A�V�C�}�̌^�A�ǒn���^�A��C����x�ȂNj��ʂ̌^�����邱�Ƃ����������B
�@�C�@�_���J�y�ѕ��V���q������
�@�֓��n�������{����C������ƂƂ��āA�֓��b�M�Â̊e�n�������@�ւƋ����ŁA�~�J���e�������A�N�Ԓ����ʎ��Ԓ����A�y��e���y�ы������H�������s�����B�܂��ċG�A�~�G�ɕ��V���q���̃T���v�����O�H�����A��ʊ��ōs�����B
�@�S�������������c���R���_���J�����ɎQ�����A�����~�������̎�A���͂����B
�@�E�@��C���Ɋւ���s���˗�����
�@��C�������Ƃ��āA�L�Q��C�������������A�������ɂ�����ċG�_���������A�_���~�����ʒ����A�~��������ʒ����A�����Ȋw�Ȉϑ��ɂ������˔\�����y�ъ��Ȉϑ��ɂ�鍑�ݓ����_���J���菊���������{�����B
�@�܂��A�O�L�����̑��A�L�C�w�����������A���ɂ�鑛���A�U�������A���������{�ݒ������s�����B15�N�x�����l�̒��������{����B
(2) �����W
�@�A�@���̌E���T���̃R�J�i�_���Ɋւ��钲��
�@���̌ɂ������R�J�i�_���̔ɖ͌i�ς̈����������ȂǑ����̖�������Ă���B14�N�x�́A�R�J�i�_���̔ɐB�͈́A�����ʋy�щh�{���ށi���f�E���j�̌Œ�ʂ�c�������B�܂��A���Ǘ��ۂɂ����Ď��{�������������ɂ��ΐ��ւ̉e���������Ē������A���f�E���̌ΊO�����o���ʂ�c�������B
�@15�N�x�́A�R�J�i�_���̊�����Ɛ����Ƃ̊W�ɂ��Č�����i�߂�B
�@�C�@�����Ɋւ���s����������
�@�H��E���Ə�r���A�S���t��r���y�эz�R�r���̐������́A�_���̐��������A�������������A�������̐��������̂ق��n���������������ɂ������ً}���A�ُ펞�̐����̕��͌������s�����B
�@15�N�x�ɂ����Ă��A�����p�����H��E���Ə�r���A�������̖��K�����w�����A�ُ퐅�����������A�������Ȃǂ̐�������A���͂��s���B
(3) �p�����W
�@�A�@�p�����ŏI������ɂ����鐅���x�Ɨn�o�����Ɋւ��錤��
�@������̓K�Ȉێ��Ǘ��Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���ߗ��Ċ��Ԓ��̐����x�y�ѐZ�o�����̉��w�����̗n�o���������A����x�̕]����@���\�z���邽�߂̌�����14�N�x����J�n�����B
�@�C�@�p�����̗L�����p�Ɋւ��钲������
�@�n�Z�X���O�͏ċp�D�̖��Q���E���ʉ����}��邱�Ƃ���A�e�s�����ɂ����ėn�Z�����{�݂̐ݒu���i�߂��Ă���B�����ʂɔr�o�����n�Z�X���O�̗L�����p�ɑΉ����邽�߁A12�N�x������S���̊m�F�����y�ъ��ʂł̗��p���@�̌������s���Ă���B
�@�E�@�p�����Ɋւ���s����������
�@�u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v��u�Ȗ،��Y�Ɣp���������Ɋւ���w���v�j�v��u�Ȗ،��y�����̖����ē��ɂ��y��̉����y�эЊQ�̔����̖h�~�Ɋւ�����v���Ɋ�Â�������̐Z�o���E�r���A���Ӓn�����̐��������y�єp�����E�y��̗n�o�������s���Ă���B
(4) ��ISO�W
�@�p���I�Ȋ��ۑS�����𐄐i���邽�߁A�܂��A�����ɂ����郂�f���P�[�X�Ƃ��ĕی����Z���^�[�ɂ����Ċ��Ɋւ��鍑�ۋK�i�ł���ISO14001�̎�g�𐄐i���Ă���B
�@11�N�x�͊��}�l�W�����g�V�X�e�����\�z�����B12�N�x�͐R���@�ւɂ��R�����A10����ISO14001�K�i�ɓK�����o�^�A13�N10���Ɉێ��R�����A�ύX�o�^���ꂽ�B�iJSAE282�F(��)�Ȗ،����Z�p����y�сi���j�Ȗ،��ی��q�����ƒc���{�����H�i���������܂ށB�j
�@13�N�x����́A�o�^�̃m�E�n�E�����p�����Ǝ҂ɑ��鑊�k�Ɩ��A�A�h�o�C�X���Ƃ����{���A14�N�x�͑��k�Ɩ����p�����Ȃ���������쐬�����B
�@
|
�Q |
������Z���^�[�ɂ����钲������ |
(1)�@���[�_�[�{���u��
�@�A�@�����Ăƕ��ʕĂ̊����ׂɂ���
�@�����ẮA�����ƌ����`�ɂ������ׂ̒ጸ�ɂȂ��邱�Ƃ���A�}���ɕ��y���i��ł���B
�@�������A�A���P�[�g�̌��ʂł�25���̐l�������Ă������ł���Ƃ̌��ʂ������̂ŁA�������ꍇ�ł��A�����Ă͐����������ׂ̒ጸ�ɂȂ��邩�ǂ����ׂ��B
�@���̌��ʁA�����Ă͌������ꍇ�ł������`�ɂ�鐅���������ׂ́A1/2����1/3�ɒጸ�����Ƃ������ʂ�����ꂽ�B�܂��A�A���P�[�g�̌��ʂł́A�������������Ƃ������Ƃł������B
�@�C�@���O�����l����
�@���O���ɂ��čl���邱�Ƃ́A���₯�₵�݂Ȃǂ̔��e��̖���畆����ȂǑ̂ւ̉e�������łȂ��A�����̈�ł���I�]���w�̔j��ɂ��čl�����ł��d�v�ł���B
�@�����ŁA�g�̉��̕i���≻�ϕi�ɂ��āA���̎��O���J�b�g���𑪒肵���B
�@���肵���̂́AUV�J�b�g��搂������ϕi�╁�ʂ̉��ϕi�A�T���O���X�A�P�A�n���J�`�A�X�J�[�t�A���K�l�A�s�V���c�Ȃǂł���B
�@���̌��ʁA���ʂ̉��ϕi�╁�ʂ̃��K�l�ł����̃J�b�g�����������B�܂��A����̂s�V���c�ł����Ȃ莇�O�����J�b�g�ł��邱�Ƃ��킩�����B
�@�u����{�@�v��43���̋K��Ɋ�Â��A�s���{���́A���̓s���{���̋��ɂ�������̕ۑS�Ɋւ��Ċ�{�I�������R�c�����邽�߁A���̕ۑS�Ɋւ��w���o���҂��܂ގ҂ō\�������R�c��̑��̍��c���̋@�ւ�u�����ƂƂ���Ă���B
�@�{���ł́A�u�Ȗ،����R�c����v�ɂ��A�Ȗ،����R�c��i�ȉ����̐߂ɂ����āu�R�c��v�Ƃ����B�j��ݒu���Ă���B
�@�R�c��́A30�l�̈ψ��i�w���o���ғ��j��4�l�̓��ʈψ��i���̒n���s���@�ւ̒����͐E���j�őg�D����Ă���B�ψ��A���ʈψ��Ƃ��C����2�N�ƂȂ��Ă���B
�@14�N�x�́A8����2���ɉ�c���J�Â��A�m�����u�Ȗ،����Q�h�~���̌������v�ɂ��Ď�����s�����ق��A�m�����玐�₪�����������ɂ��ē��\���s�����B
�@15�N�x�ɂ����Ă��A���̕ۑS�Ɋւ���d�v�Ȏ����ɂ��āA�R�c��Œ����R�c���s���\��ł���B
�@�������~���������A�~�������ɁA���m�ɁA�����Ă킩��₷���`�Œ��邱�Ƃ́A�����𐳂����F�����A���ۑS�Ɋւ���l�̐ӔC�Ɩ����𗝉������ł��d�v�Ȃ��Ƃł���B
�@�����̗l�X�ȏ�ʂɂ����āA����I�ŐϋɓI�Ȋ��ۑS�����𑣂��悤�ȓK�Ȋ����̐����Ə��̐��̋����A�̌n�����K�v�Ƃ���Ă���B
�@���̂��߂ɂ́A���̍L��}�́i�u���������v�A�u�L�Ƃ����v�A�u���������v���j�͂��Ƃ��A���������A�e��p���t���b�g�Ȃǂɂ��K���A�K�Ȋ����̒ɓw�߂�ƂƂ��ɁA���������A�C���^�[�l�b�g�����p�������̐�������B
(1) �s�������̒�
�@�{���̊��S�ʂɊւ���s�������u���̏y�ю{��Ɋւ�����i�������j�v�̊T�v�Łu�Ȗ̊��v���쐬�E����ƂƂ��ɁA��C�A���A�n�Պ��ȂNJĎ�����E�����������ʂɂ��ēK�����\���A���ۑS�����𑣂��B
�@�܂��A12�N�x�ɊJ�݂����C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�u�Ƃ����̊��v�ɂ��ẮA�����������e�̏[���ɓw�߂�B�i�\�U�|�P�j
�\�U�|�P �z�[���y�[�W�u�Ƃ����̊��v�o�ڍ��ړ�
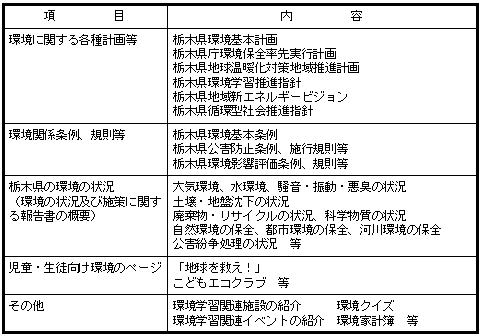
(2) ���w�K�Ɋւ�����̒�
�@�]���A���w�K�Ɋ֘A����C�x���g���f�ڂ������q�u���w�K�K�C�h�u�b�N�v�Œ��Ă��������A14�N�x����́A�z�[���y�[�W�u�Ƃ����̊��v�Ɍf�ڂ��邱�ƂŁA���̂��߂��܂��ȍX�V�ɓw�߂��B
�@�܂��A���w�K�֘A�{�݂̏Љ��A���N�C�Y�̌f�ړ��A�C���^�[�l�b�g�ɂ����@�\�����p�����V�N�Ŏg���₷�����̒ɓw�߂��B
�@
|
��S�߁@�y�n���p�ʂ���̊��z�� |
�@���y�́A�����̐�����Y�����̋��ʂ̊�Ղł���A���A����ꂽ�����ł���B
�@���̗��p�ɓ������ẮA�u���͂Ɣ������ɖ��������y�g�Ƃ����h�v�̑n���ɂӂ��킵���Z�݂悢�A�L���Ȓn��Љ�ƂȂ�悤�A�Ȗ،��y�n���p��{�v�����{�Ƃ��āA�e��̓y�n���p�W�@�̓K�ȉ^�p��}��A���̕ۑS�ɔz�����A���A�n��̓���������������������y�n���p�𑣐i���邽�߁A���̂悤�Ȏw�������{���Ă���B
�@
|
�P |
�y�n���p�Ɋւ��鎖�O�w�� |
(1) ��K�͊J�����ƂɊւ���y�n���p�̎��O�w��
�@���y�̑����I���v��I�ȗ��p��}�邽�߁A5ha�ȏ�̓y�n�i�Ď����i��c���s�Ȃ�5�s���j�@���̓y�n�ɂ����Ă�2ha�ȏ�j�A2ha�ȏ�̔_�n���܂ޓy�n����2ha�ȏ�̎��R���������܂ޓy�n�ɂ��ĊJ�����Ɠ����s�����Ƃ���ꍇ�́A�u�s�s�v��@�v�A�u�_�n�@�v�A�u�X�і@�v���̌ʋK���@�Ɋ�Â��J���s�ׂ̋��\�����̑O�ɁA�u�y�n���p�Ɋւ��鎖�O�w���v�j�v�ɂ�莖�ƌv��̊T�v�̒�o�����߁A�y�n���p�Ɋւ��鑍���I�Ȍ��n����w���������s���Ă���B
�@���̎��O���c�ɂ����ẮA��K�͊J���ɔ������ӊ��ւ̉e�����d�����A�J�������̗Βn�m�ہE�i�ς̈ێ���A�܂��A�r�o���������������̗ʂ�r�o��ɋy�ڂ��e���ɂ��Ă��������A�K�Ȋ����ۑS�����悤���v�̎w�����s���Ă���B
(2) �u���y���p�v��@�v�Ɋ�Â��y�n����ɌW�闘�p�ړI�̐R��
�@���ł́A�K���������I�ȓy�n���p���m�ۂ��邽�߁A�u���y���p�v��@�v�Ɋ�Â��͏o���x�ɂ��A���K�͈ȏ�̖ʐςɌW��y�n�������Ɋւ��āA�y�n�̗��p�ړI���̐R���E�w�����s���Ă���B
�@���p�ړI�̐R���ɂ��ẮA���R���̕ۑS���ɌW��e��y�n���p�Ɋւ���v��ւ̓K�������̔��f���s���A�K�v�ɉ����A�����E�������̑[�u���u���邱�ƂƂ��Ă���B
�@
|
�Q |
��K�͌��z���Ɋւ��鎖�O�w�� |
�@��K�͂Ȍ��z����]�[�g�}���V�����Ȃǂ̌��z�v��ɂ��āA�{���̗D�ꂽ���R�i�ς������ۑS���邽�߁A�s�s�v����ȊO�y�є�������s�s�v����̗p�r�n��ȊO�̒n��i�W29�s�����j�ɂ����āA����13�����錚�z�����͌��z�ʐ�1,000��2�ȏ�̌��z�������z���悤�Ƃ���ꍇ�A�u��K�͌��z���̌��z�Ɋւ��鎖�O�w���v�j�v�ɂ��A���z��y�n���p�Ɋւ���@�ߓ��̈�̓I�ȉ^�p�Ƃ����܂��āA���O�Ɍ��z�v��̒�o�����߁A�w�����s���Ă���B
�@���̎��O�w���ɂ����ẮA���z���̍����A�Βn�т̕��A�ӏ��A�r�������Ȃǂɂ��Ďw�����݂��A���R�i�ς�����ɔz���������z�v��ƂȂ�悤�w�����Ă���B
(1) ���y�юs�����ɂ��������Q���̎戵��
�@�A�@���Q���̎���
�@14�N�x�Ɍ��y�юs����������������1,693���ŁA���̂����A��C�����A���������A�y�뉘���A�����A�U���A�n�Ւ����y�ш��L�̂�����u�T�^7���Q�v�̋�����1,069���i�S���Q������63.1���j�ŁA�O�N�x�ɔ�ׂ�63�����������B
�@�܂��A�p�����̕s�@�����A�Q�����̔����A�����̎��[���u�ȂǁA�u�T�^�V���Q�ȊO�v�̋�����624���i�S���Q������36.9���j�ŁA�O�N�x�ɔ�ׂ�8�����������B�i�}�U�|�Q�A�}�U�|�R�j
�}�U�|�Q�@���Q������
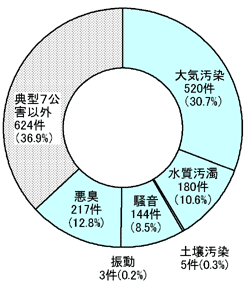
�}�U�|�R�@���Q�̎�ޕʋ����̐���
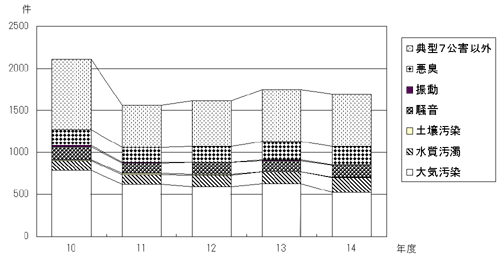
�@�C�@�������ʂ̋���
�@14�N�x�̌��Q���������i�ꏊ�j�ʂɂ݂�ƁA���H�E��n�E���������ł������A�����Ő����ƁA�ƒ됶���E���Ə����A���E�����E�T�[�r�X�ƁA�_�ыƂ̏��ƂȂ��Ă���B�i�}�U�|�S�j
�@�܂��A��������r�I�����������̒��ł́A�ƒ됶���E���Ə����̑����X���������Ă���A10�N�O�i4�N�x�j�̖�3�{�ɒB���Ă���B
�}�U�|�S�@�������ʋ����i14�N�x�j
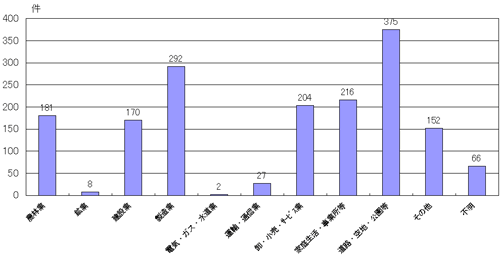
�@�E�@���Q���̏�����
�@14�N�x�ɏ�������������1,728���ł���B���̓���́A14�N�x�ɐV�K�Ɏt����������1,693���A�O�N�x����J��z���ꂽ������35���ł������B
�@���̏������݂�ƁA��t�@�ւ����ڏ�������������1,548���A�x�@�⍑���̑��̋@�ւֈڑ�����������54���A���N�x�J��z����������99���ł������B�i�\�U�|�Q�j
�\�U�|�Q�@���Q���̎�t�����y�я��������i14�N�x�j�@�@�i�P�ʁF���j
| ��t�̏� |
�����̏� |
����
(��t����) |
���Y�N�x��t |
�O�N�x
����J�z |
����
(��������) |
���ڏ��� |
���ֈڑ� |
���N�x
�J�z |
���̑� |
| ���v |
���ڎ�t |
������
�ڑ� |
| 1,728 |
1,693 |
1,645 |
48 |
35 |
1,728 |
1,548 |
54 |
99 |
27 |
�@����A�T�^7���Q�̂����A���ڏ����������ɂ��āA���̏����̂��߂ɍs�����̂����[�u�i���ɗ͂���ꂽ��i�j�ʂɂ݂�ƁA����������ɑ���s���w���v��787���i�T�^7���Q�̒��ڏ���������80.5���j�ƍł������A�����ŁA������̒����v��89���i��9.1���j�A������ҊԂ̘b�����v��19���i��1.9���j�A��\���l�ɑ�������v��12���i��1.2���j�Ȃǂł������B�i�\�U�|�R�j
�\�U�|�R�@�T�^�V���Q�̋����̂��߂ɍs�����̂����[�u����
| �@ |
���� |
��������
�ɑ���
�s���w�� |
������
���� |
�����Ҋ�
�̘b���� |
�\���l��
����
���� |
���̑� |
| ��������(��) |
978 |
787 |
89 |
19 |
12 |
71 |
| �\����(��) |
100 |
80.5 |
9.1 |
1.9 |
1.2 |
7.3 |
�@�܂��A�T�^�V���Q�̂����A���ڏ����������ɂ��āA���̏����̂��߂̖h�~��̗L�����݂�ƁA�u�h�~����u�����v��653���i�T�^�V���Q�̒��ڏ���������66.8���j�u�u���Ȃ������v��177���i��18.1���j�ƂȂ��Ă���B�i�\�U�|�S�j
�\�U�|�S�@�T�^�V���Q�̋����̂��߂̖h�~��̗L���ʌ���
| �@ |
���� |
�h�~����u���� |
�u����
������ |
�s�� |
| ���v |
�������� |
�s���@�� |
��Q�� |
���̑� |
| ��������(��) |
978 |
653 |
568 |
76 |
5 |
4 |
177 |
148 |
| �\����(��) |
100 |
66.8 |
58.1 |
7.8 |
0.5 |
0.4 |
18.1 |
15.1 |
(2) �x�@�ɂ�������Q���̎戵��
�@�A�@14�N�x���ɓȖ،��x�@�{���y�ѓȖ،����e�x�@���Ŏ������Q�W�����́A823���i�O�N�x�䁢128���j�ŁA���������Ɋւ�����̂�497���i�O�N�x�䁢149���j�ƍł������A�S�̖̂�60�����߁A�����Ŕp�����Ɋւ�����̂�257���i�O�N�x��{22���j�őS�̖̂�31�����߂��B�i�\�U�|�T�j
�@�C�@�������̔���������ޕʂɌ���ƁA�ԗ�����206���i�O�N�x�䁢188���j�ƁA�S�̖̂�41�����߂��B�i�\�U�|�U�j
�\�U�|�T�@�x�@�ɂ�������Q�������i14�N�x�j
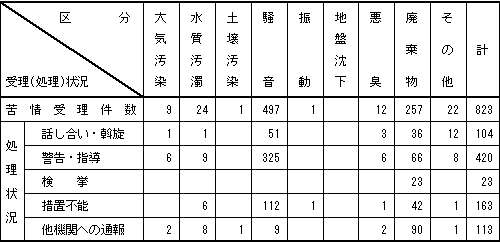
�\�U�|�U�@�����������ʎ����i14�N�x�j
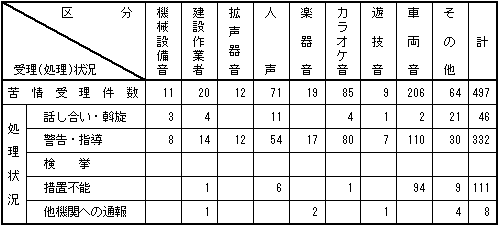
�@�T�^�V���Q�i��C�����A���������A�y�뉘���A�����A�U���A���L�A�n�Ւ����j�ɌW�镴���ɂ��āA��������A����y�ђ��ق��s�����߁A�u�Ȗ،����Q�����������v��Q���Ɋ�Â��A�Ȗ،����Q�R����i�ψ�15�l�j���ݒu����Ă���B
�@�Ȃ��A���a45�N�x�̓Ȗ،����Q�R����ݒu�ȗ�14�N�x�܂ł�8���i�Q���\�����܂ށB�j�̒���\�����Ȃ��ꂽ�B
�@
|
��U�߁@�H��E���Ə��̐��i |
�@
|
�P |
�H��E���Ə�ɑ���K���I�[�u |
(1) ���H�ꓙ�ɑ���K��
�@���Q�W�@�ߓ��ɂ����Č��Q�����̂�����̂���{�݂��u����{�ݓ��v�Ƃ��Ē�߁A�{�݂̎�ށE�\��������̎����ɂ��ē͏o���`���Â��Ă���B�u�Ȗ،����Q�h�~���v�ł͂����̎{�݂̂����A�r���ʂ̑������̍H��E���Ə���u���H�ꓙ�v�ƒ�߁A�����x�ɂ��K�����s���Ă���B
�@14�N�x�ɂ����鋖�H�ꓙ�̐ݒu�y�ѕύX�������́A65���ł���B�i�\�U�|�V�j
�\�U�|�V�@�Ȗ،����Q�h�~���Ɋ�Â�������
| �敪 |
�ݒu |
�ύX |
���v |
| �P�R�N�x |
�P�S�N�x |
�P�R�N�x |
�P�S�N�x |
�P�R�N�x |
�P�S�N�x |
| ���� |
3(0) |
8(0) |
26(4) |
43(8) |
29(4) |
51(8) |
| ���� |
0 |
0 |
7(2) |
14(2) |
7(2) |
14(2) |
| �v |
3(0) |
8(0) |
33(6) |
57(10) |
36(6) |
65(10) |
(��)�i �j�́A�F�s�{�s���̓���
(2) �V�K���n���Ə�̎��O���c
�@���Q�̖��R�h�~�y�ъ��̕ۑS��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���a60�N6���u�V�K���n���Ə���Q�h�~���O�w���v�j�v���߂��B
�@���̗v�j�́A9,000��2�ȏ�̕~�n�ʐς�L����H�ꖔ�͉Ȋw�Z�p�Ɋւ��鎎���������s�����Ə��V���ɐݒu���悤�Ƃ��鎖�Ǝ҂ɑ��A���炩���ߌ��Q�h�~�{�ݐ����v�擙�ɂ��Ď��O���c���s�����Ƃ��`���Â��Ă���B
�@14�N�x�̎��O���c�����́A3���i�H��3���j�ł���A�����X���ɂ���B�i�\�U�|�W�j
�\�U�|�W�@���O���c�����y�ї��n��Ɛ�
| �N�x |
���O���c���� |
| �H�� |
�Ȋw�Z�p�Ɋւ��鎎
���������s�����Ə� |
���v |
| 10 |
15 |
1 |
16 |
| 11 |
7 |
1 |
8 |
| 12 |
9 |
1 |
10 |
| 13 |
6 |
0 |
6 |
| 14 |
3 |
0 |
3 |
�i���j ���O���c�����͓��Y�N�x�ɋ��c�I���ƂȂ�������
(3) ���Q�h�~����
�@���Q�h�~�����́A���Q�W�@�ߓ��̋K���Ƃ͕ʂɁA�s�������邢�͒n��̎�����ƐV���ɗ��n���悤�Ƃ���H�ꖔ�͊����̍H�ꓙ���A�����ҊԂ̍��ӂɊ�Â����Q��h�~���邽�ߒ���������̂ł���B
�@�u�Ȗ،����Q�h�~���v�ł́A���Ǝ҂ɋ�������̓w�͋`���킹�Ă���B���Q�h�~����̉~���Ȓ����ɂ��ẮA�u���Q�h�~����̎���v�ɂ��w�����s���Ă���B
�@
|
�Q |
�H��E���Ə�ɑ���o�ϓI�[�u |
(1) ���ۑS�����̗Z��
�@���Ǝ҂ɂ́A�u�Ȗ،�����{���v�ɒ�߂�悤�ɁA���̎��Ɗ����ɔ����Đ�������Q��h�~���A���͎��R����K���ɕۑS���邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u����Ӗ�������B�������A���Q�h�~�̂��߂̎{�ݐ�����H��ړ]�ɂ͑��z�̎�����K�v�Ƃ��邱�Ƃ���A���Ɍo�c��Ղ̎ア������Ǝғ��ɂƂ��Ă͂��Ȃ�̕��S�ƂȂ�B
�@���̂��߁A���ł́A������Ǝ҂⒆����ƒc�̂����Q�h�~�̂��߂̎{�ݐ�����H��ړ]�����鎑���̒��B���~���ɂ��邽�߁A���a45�N�x�ɗZ�����x�i���Q�h�~�����j��n�݂��A�Z�����s���Ă����B�܂��A9�N�x����́u�Ȗ،����ۑS�����v�Ɖ��̂��A�����14�N�x����̓f�B�[�[�����@�q���������u�i�c�o�e�Ɍ���j�̑����ɌW��o���Ώۂɉ������B
�@�Ȗ،����ۑS�������x�̊T�v�i14�N�x�j�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�A�@�ݕt���i�V�K���j�@10���~
�@�C�@�@�@�@�ہ@�@�@�@�@�@������ƎҁA������ƒc��
�@�E�@���[�����@�@�@�@�@�@�N1.70���i15�N4��1�����݁j
�@�G�@�ݕt���ԁ@�@�@�@�@�@10�N�ȓ��i���������̐��u����2�N�ȓ��j
�@ �@�@�@�@�@�������A1�疜�~�����ɂ��Ă�7�N�ȓ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������̐��u����1�N�ȓ��j
�@�I�@�ݕt���x�z
�@�@�E�@�{�݂̐ݒu���F�o���90���ȓ��� 100���~�ȏ�1���~�ȉ�
�@�@�E�@���ۑS���ƁF�o���90���ȓ��� 100���~�ȏ�1���~�ȉ�
�@�@�E�@�H�ꓙ�̈ړ]�F�o���90���ȓ��� 200���~�ȏ�1��5�疜�~�ȉ�
�@�J�@�a����@�@�@�@�@�Ȗ،��M�p�ۏ؋���
�@14�N�x�̗Z���i�F��z�̎��сj�́A�\�Z�g10���~�ɑ��ĔF�茏��8���A�F��z4��3930���~�ł���B�Ȃ��A����8���̓���͐�������3���A�p�����ċp�{��5���ł���B�i�\�U�|�X�A�}�U�|�T�j
�@15�N�x�ɂ����Ă��A�V�K�ݕt���Ƃ���10���~��\�Z�����A�Z�����s���B
�\�U�|�X�@���ۑS�����Z���k14�N�x�F����сl �@�i�P�ʁF��~�j
| �Ώێ�� |
�ݒu�i���P�j |
�ړ] |
���v |
| ���� |
���z |
���� |
���z |
���� |
���z |
| �������� |
3 |
116,300 |
�@ |
�@ |
3 |
116,300 |
| ���L |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
| �Y�Ɣp�����i�p�����ċp�{�݂��܂ށj |
5 |
323,000 |
�@ |
�@ |
5 |
323,000 |
| �ȃG�l���M�[�ݔ� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
| ����Q�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
| ���Ǘ����єF�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
| ���v |
8 |
439,300 |
�@ |
�@ |
8 |
439,300 |
�}�U�|�T�@���ۑS�����̎�ޕʗZ�������y�єF��z
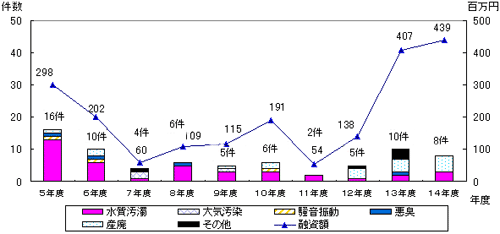
(2) �u�K��̊J��
�@���ۑS�Ɋւ��镁�y�[���̂��߁A�H��E���Ə�ɑ��A�u�K������{�����B�i�\�U�|�P�O�j
�@15�N�x�����������A�H��E���Ə�ɂ�������ۑS�ւ̎�g�𐄐i���邽�߂̍u�K������{����B
�\�U�|�P�O�@�u�K��̎��{��
| ���{�N���� |
�Ώہi�o�ȎҐ��j |
�J�Ïꏊ |
���e |
| 14�N 6��26�� |
�H��E���Ə�W��(162��) |
�F�s�{�s |
(1)�_�C�I�L�V���ނ̔r�o�K���ɂ���
(2)�o�q�s�q�@�ɌW��͏o�ɂ���
(3)�ȃG�l���M�[��Ǝ��{��ɂ��� |
(3) ���ۑS����
�@���̎��Ƃ́A���Q�����{�݂ȂNjZ�p�I�ɖ��̂��閔�͊��Ǘ��V�X�e���̓�����}�낤�Ƃ��Ă��钆����Ǝғ��ɑ��āA���Ƃ�h�����ʓI�ȋZ�p�w�����s�����̂ł���A14�N�x�́A���L�W�P���̓��e�ɂ��Ď��{�����B
�@15�N�x�ɂ����Ă��A�Z�p�I�ɖ��̂���Ȃǂ̒�����Ǝғ��ɑ��A���ۑS���Ƃ����{����B
(4) ���Ǘ��𗬉��
�@���̎��Ƃ́A���Ǘ��V�X�e���̍\�z�i���͊��h�r�n�̔F�؎擾�j��ڎw���Ă��鎖�Ǝғ���ΏۂɃZ�~�i�[�����������J�Â��A���Ǘ��V�X�e���\�z�ւ̎�g���x��������̂ł���B
�@14�N�x��34�l���Q�����A�Z�~�i�[��2��A���������3��J�����B
|