|

内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)については、野生生物の生殖異常などの報告がなされているが、その環境中における挙動や健康影響・生態影響については、科学的に未解明な部分が多い。
しかし、環境ホルモンは、ヒトや野生生物の内分泌作用を攪乱し、生殖機能障害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある物質であって、生物の生存の基本的条件に関わるものであり、世代を超えた深刻な問題を引き起こすおそれがあることから、これに対する環境保全対策が重要となってくる。
環境省では、9年3月に「外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班」を設置し、既存の知見の収集整理及び今後の課題についての検討を行い、同年7月に中間報告書をとりまとめた。
そして、10年5月「外因性内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について」(いわゆる環境ホルモン戦略計画SPEED'98)で内分泌攪乱作用が疑われる約70種の化学物質がリストアップされ、基本的な考え方並びに実態調査、試験研究及び情報提供の推進等の具体的な対応方針を示し、さらに12年11月には、新しい知見等を追加・修正した「環境ホルモン戦略計画SPEED'98 2000年11月版」が公表された。
17年3月には、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について−ExTEND2005−」が公表され、内分泌攪乱作用が疑われる化学物質のリストが廃止されたが、今後も引き続き人体や生態系に影響を与えるおそれのある物質について、環境中濃度の実態把握及びリスク評価等を進めることとしている。
環境ホルモンについては、科学的に未解明な部分が多いことから、化学物質対策連絡会議において、情報収集及び情報交換等により情報の共有化を図ってきた。
16年度は15年度に引き続き、水質の環境ホルモンの調査を次の5河川において実施した。その結果は表2−6−7のとおりで、ほとんどが検出限界値未満であり、検出された物質の濃度は全国の調査結果の範囲内であった。なお、現在のところ、いずれの物質も環境基準等は設定されていない。
表2−6−7 環境ホルモン実態調査結果(16年度)
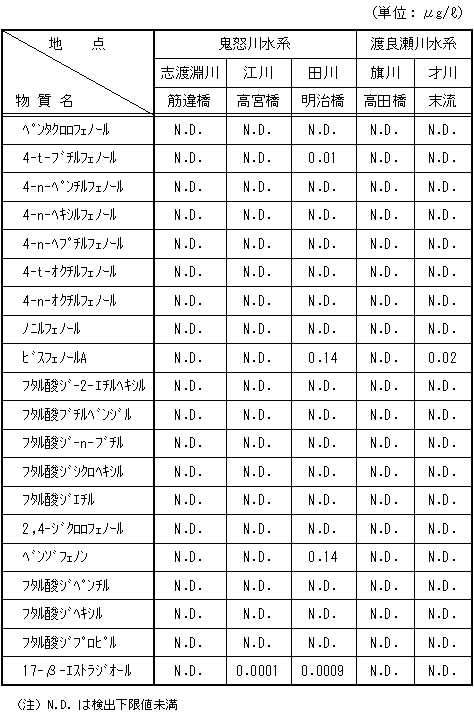
|