|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) 自然環境保護事業 自然環境保全及び自然保護意識の高揚のための普及啓発、調査等を実施している。 「自然環境保全法」及び「自然環境の保全及び緑化に関する条例」に基づき、優れた自然環境を持つ地域を自然環境保全地域に、また、市街地周辺地及び歴史的・文化的遺産と一体となった緑地を緑地環境保全地域に指定している。16年度までに国指定の自然環境保全地域1か所を含め、41か所5,355haの指定を行った。 (表3−1−1)
(3) 自然(緑地)環境保全地域の整備 自然(緑地)環境保全地域に指定されている地域(図3−1−2)の案内標識等を整備して、優れた自然環境の保全に努めている。 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(「種の保存法」)に基づき、6年12月に全国で初めて指定された大田原市の「羽田ミヤコタナゴ生息地保護区」において、環境省、大田原市、羽田ミヤコタナゴ保存会等と連携し、ミヤコタナゴの生息環境の保全を図っているほか、水産試験場において、ミヤコタナゴの増殖等を行っている。 本県の自然環境に関する情報発信と普及啓発を図るため、人と自然が共生していくための共通の指標としての活用を目的として、14・15年度に実施した掲載種選定のための調査を基に県版レッドリストを作成した。さらに、そのリストに生息・生育状況等の解説を加えた、県版レッドデータブック「レッドデータブックとちぎ」を作成した。 平地林は、緑豊かなふるさと栃木を代表する景観であり、大気の浄化、遮音、防風等の公益的効用に加え、生活に潤いを与える身近な緑の供給地としても重要な役割を果たしており、13年度末現在(13年度に実態調査実施)の面積は、約70千haとなっている。 保安林は、水源のかん養、災害の防止、自然環境の保全・形成及び保健休養の場の提供等重要な役割を果たしており、16年度末現在の指定面積は、約17万8千haとなっている。 生物多様性の観点から重要な地域である湿原を保全するため、水文、気候等の調査及び湿原かん養水確保対策等の保全対策を行っている。 (9) 自然とのふれあいの推進 豊かな自然とのふれあいを通して、自然のしくみや大切さを理解するために自然観察会や野鳥観察会を開催するほか、自然体験プログラムの普及や人材の育成等を実施している。 2年4月に「とちぎふるさと街道景観条例」を施行し、同年6月に条例に基づき那須・塩原街道景観形成地区を指定し、12年12月に指定地区を拡張した。ここでは、街道景観形成基準に基づく 指導を行い、「みどり豊かな栃木県」のイメ−ジにふさわしい街道景観の形成を図っている。 農村地域における水田等の農地・水路・ため池等の二次的自然は、有機的に連携して多くの生物相を育み、多様な生態系や自然環境を形成している。これら田園自然環境の保全・再生を行う ための地域の自主的な活動を支援している。 度重なる山火事、銅山の煙害等により植物が枯死し、裸地化した荒廃地の復旧を図るため、治山事業により山腹基礎工、緑化工、植栽工を行い、森林造成を進めている。
自然公園(日光国立公園及び8つの県立自然公園)の優れた風景地を保護するため、各種行為の規制等を行うとともに、快適な利用を確保するための施設整備、利用者に対する適正利用の指導等を行っている。 (1) 自然公園管理事業 公園計画に基づく特別地域などの地域指定により各種行為の規制を実施するとともに、利用者に対する適正利用の指導等を行った。 自然公園の快適な利用促進を図るため、歩道、園地等の整備を行った。 日光国立公園那須・塩原地域において、「人と自然との豊かなふれあい」「人と自然との共生の確保」を図るため、優れた自然を保全するとともに、自然体験の場を整備した。 国立公園等の優れた自然環境の保護と利用の促進のため、自然とふれあう施設の整備に当たり、 我が国を代表する国際観光地「日光」の活性化を図るため、日光市中宮祠地区において基盤整備等を行った。 国際観光地「日光」活性化事業で整備した日光中宮祠地区の県営駐車場、湖畔園地、イタリア大使館別荘記念公園、中禅寺湖畔ボートハウス等の管理運営を行うとともに、日光市道1002号線における交通規制の代替交通手段として低公害バスを運行した。
野生鳥獣は自然生態系を構成する重要な要素であるが、一方で、生活環境や農林業、生態系に被害をもたらす場合がある。このため、野生鳥獣の生息状況や生態系等に配慮した計画的・科学的な保護管理を行い、もって自然環境の保全を推進する必要がある。 表3−1−2 鳥獣保護区等の指定状況(16年度末)
本県の緑地(農用地を含む。)は、県土の約80%を占め、全国的にも緑に恵まれた環境にあるが、その現状は、人口の集中化や都市化の進展に伴う緑の減少、緑資源の大部分を占める森林の手入れ不足等、緑を取り巻く環境は、必ずしも楽観を許さない状況にある。
樹木の育成は、厳しい自然環境の中で長期間にわたって行われるため、各種の病虫害にかかる場合があり、しかも、ひとたび被害を受けると、その回復が非常に困難である。特に、昭和50年に発生した松くい虫の被害は、昭和55年にピークとなったものの、その後被害対策の効果により減少し被害量は、ピーク時の約2割まで減少した。しかしながら、ここ数年横ばいで推移しており、依然として被害が発生しているため、地域が主体となり、地域の実情に応じた、きめの細かい被害対策を通じて松の緑を守ることが重要な課題となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
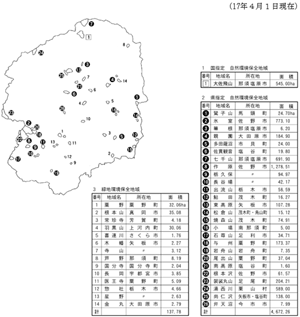 ≪拡大図はこちら≫
≪拡大図はこちら≫