|
今日の環境問題は、工場・事業場の産業活動に起因する公害に加えて、日常生活に伴う都市・生活型の公害や有害化学物質による環境汚染の問題、地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題に至るまで広範多岐にわたっている。
このような新たな環境問題に対応するため、主として産業型公害を防止することを目的として昭和41年に制定(昭和47年に全部改正)された「栃木県公害防止条例」(以下本節において「旧条例」という。)の全部を改正した「栃木県生活環境の保全等に関する条例」(以下本節において「新条例」という。)を制定し、16年10月14日に公布した。
(1) 条例の目的及び構成
ア 目的
新条例は、栃木県環境基本条例第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、公害の防止その他事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置に関し必要な事項を定めることにより、他の法令と相まって、生活環境の保全等に関する施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康の保護及び快適な生活環境の確保に寄与することを目的としている。
イ 構成
新条例は、5章72条で構成されている。(図6−1)
そのうち、旧条例に規定されていた工場・事業場に係る規制等については、公害関係法令との整合を図るため所要の規定の整備を行うとともに、新たな項目(特定有害物質管理基準の遵守義務、悪臭の防止のための措置、化学物質の適正な管理のための措置、事故時における措置等)を追加した上で、「公害の防止のための工場等に関する規制等」として第2章に規定している。
また、広く事業者や県民等を対象とした「事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置」(地球温暖化の防止、フロン類の排出の抑制、自動車排出ガスの排出の抑制、生活排水対策の推進、日常生活等に伴う騒音等の防止及び環境物品等の調達の推進)については、今回、新たに第3章に規定している。
(2) 新たに追加した規定の内容
ア 公害の防止のための工場等に関する規制等
(ア) 特定有害物質管理基準の遵守
水質汚濁防止法及び新条例に定める汚水に係る特定施設で、特定有害物質の製造・使用・処理施設を設置している事業者は、特定有害物質を使用等する特定施設や、これに係る配管や排水処理施設などにおいては、次の構造や管理に関する基準を遵守しなければならないこととした。なお、この基準を満たさない施設を使用している事業者に対しては、新条例第22条に基づく改善命令等のほか罰則を適用することとした。
a 特定有害物質を使用等する施設やその周辺の床は、十分に強度のあるもので、表面は不浸透性、耐薬品性を有する材質であること。
b 薬液や汚水等が地下に浸透したり、屋外に飛散・流出しないように、不浸透性、耐薬品性を有する防液堤など必要な設備を設けること。
c 特定有害物質を使用等する施設や配管、排水処理施設等は、床面から離して設置するなど、容易に点検できる構造とすること。ただし、これにより難い場合は、漏洩等の有無を確認できる措置を講じること。
d 配管は、耐薬品性の材質で、汚水の系統ごとに区分し、識別できるものとすること。
e 特定有害物質を使用等する施設や配管、排水処理施設等は、薬液の漏洩の有無、薬品の使用量、排水処理及び排出水の状況等を1日1回以上点検し、その結果を記録しておくこと。
f 特定有害物質を含む原料、廃液等の保管については、地下に浸透したり、周辺に飛散・流出しないよう対策を講じ、適切な管理を行うこと。
【平成17年10月1日施行。ただし、平成17年4月1日現在設置(工事中を含む。)されている施設については、平成20年10月1日から適用】
(イ) 悪臭の防止のための措置
工場や事業場においては、次の構造や管理に関する基準を遵守しなければならないこととし
た。
a 悪臭を発生する原料や製品などは、悪臭がもれにくい容器に収納したり、覆いをかけて保管すること。
b 工場や事業場は、作業場所を清潔に保ち、又は建物の気密性を高めるなどの措置を行うこと。
c 悪臭を発生する作業は、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合には、屋外では行わないこと。
d 強度の悪臭を発生する工場や事業場には、有効な脱臭装置を設置すること。
【平成17年10月1日施行。ただし、平成17年4月1日現在設置(工事中を含む。)されている工場・事業場については、平成18年10月1日から適用】
(ウ) 化学物質の適正な管理のための措置
a 指定化学物質等に関する情報の収集等
県は、指定化学物質等に関する情報の収集及び整理に努め、県民・事業者に対し、これらの情報の提供を適切に行うものとした。 【平成17年4月1日施行】
b 指定化学物質等の管理に関する計画の作成・公表
PRTR法(化学物質管理促進法)に定める第一種指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等の管理に関し、ア管理の方針、イ自主管理目標及び目標達成のための措置、ウ管理体制、エ取扱状況、オ事故時の措置及びカその他適正管理に必要な事項を盛り込んだ計画を自ら作成し、これを公表するよう努めなければならないこととした。 【平成17年10月1日施行】
(エ) 事故時における措置
ばい煙又は汚水に係る特定工場等や特定有害物質を使用等する施設の設置者、PRTR法に定める指定化学物質等取扱事業者は、特定工場等などにおいて、施設の故障や破損などの事故が発生し、人の健康や生活環境への被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、事故についての応急の措置を講じ、速やかに復旧するよう努めなければならないこととした。(応急の措置が講じられていないときは、知事は措置を命ずることができることとした。)
また、これらの施設の設置者と第一種指定化学物質等取扱事業者は、速やかに、事故の状況と講じた措置の概要を知事に報告しなければならないこととした。【平成17年4月1日施行】
イ 事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置
(ア) 地球温暖化の防止
a 地球温暖化対策の推進
県・事業者・県民は、地球温暖化の防止のため、事業活動や日常生活において、省エネルギーの推進、新エネルギーの利用など温室効果ガスの排出抑制等に努めなければならないこととした。また、県は、温室効果ガスの排出抑制等に関する技術的な助言、情報提供等に努めるとともに、森林の整備・保全や木材の利用に関し、事業者や県民の理解を深めるよう努めるものとした。 【平成17年4月1日施行】
b 地球温暖化対策計画の作成・提出
燃料及び熱の使用量が原油換算で年間1,500kl以上の工場等又は電気の使用量が年間600万kWh以上の工場等を設置している事業者は、ア地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制、イ温室効果ガスの排出状況及びウ温室効果ガスの排出抑制に係る目標及び措置を記載した温室効果ガスの排出抑制等のための計画(地球温暖化対策計画)を原則として3年ごとに作成し、計画期間の初年度の6月末までに知事に提出しなければならないこととした。
(計画を変更したときには、速やかに、変更後の計画を提出することが必要)。
なお、知事は、地球温暖化対策計画の提出がないときは、計画の提出を勧告することができることとした。 【平成17年10月1日施行】
(イ) フロン類の排出の抑制
a フロン類の回収・破壊の促進
県は、フロン類の排出抑制を図るため、フロン類の回収・破壊の促進に関する知識の普及、情報の提供等を行うものとした。 【平成17年4月1日施行】
b フロン類の放出防止
冷媒としてフロン類が充てんされている機器の修理や廃棄をするときなどには、大気中にフロン類を放出することがないように努めなければならないこととした。 【平成17年4月1日施行】
(ウ) 自動車排出ガスの排出の抑制
a 自動車排出ガス抑制のための知識の普及、低公害車の普及促進県は、自動車排出ガスの排出抑制のための知識の普及や情報の提供などを行うものとした。
また、率先して低公害車(排出ガスが排出しないか、より少ない自動車)を使用することなどにより、低公害車の普及促進に努めることとした。 【平成17年4月1日施行】
b 低公害車の購入等
自動車を購入しようとするときや使用するときには、できるだけ低公害車を選ぶように努めなければならないこととした。
また、自動車販売事業者は、自動車を購入しようとしているお客様が低公害車を的確に選択できるよう、取り扱う自動車の排出ガスの量などの情報を適切に提供するよう努めなければならないこととした。 【平成17年4月1日施行】
c 自動車の走行量の抑制
自動車を使用する際には、自動車排出ガスによる環境への負荷荷を低減するため、効率的なルートの選択、配送計画の見直しによる出走台数の削減、公共交通機関の利用などにより自動車の走行量を抑制し、排出ガス量の削減に努めなければならないこととした。 【平成17年4月1日施行】
d アイドリングストップの励行
自動車を運転するときは、駐車中などには不要なアイドリングをやめるよう努めなければならないこととした。
また、自動車を事業用に使用している事業者は、従業員の皆さんへの教育や車両の管理規程の見直しなどにより、アイドリングストップが励行されるよう努めなければならないこととした。
駐車場の設置者・管理者においても、看板の掲示や、駐車券への印刷、館内放送などにより、お客様へのアイドリングストップの徹底に努めなければならないこととした。 【平成17年4月1日施行】
(エ) 生活排水対策の推進
a 生活排水の処理施設の整備方針の策定等
知事は、生活排水の排出による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、生活排水の処理施設の整備に関する方針を定めるものとした。
また、県は、生活排水の排出による公共用水域の水質汚濁を防止するための知識の普及や情報の提供などを行うものとした。 【平成17年4月1日施行】
b 公共用水域の水質汚濁の防止
家庭での家事や、キャンプなどの野外活動においては、調理くず、廃食用油などの処理や洗剤の使用を適正に行うよう努めなければならないこととした。
また、キャンプ場の設置者等においても、浄化槽を設置したり、利用者に注意を喚起するなど、野外活動に伴って排出される水で公共用水域の水質を悪化させないよう努めなければ
ならないこととした。 【平成17年4月1日施行】
(オ) 日常生活等に伴う騒音等の防止
日常生活や事業活動に伴う騒音や振動により周辺の生活環境を損なうことのないように、音量を下げたり、作業場所や設置場所、作業時間帯を変更するなどして静穏の保持に努めなければならないこととした。 【平成17年4月1日施行】
(カ) 環境物品等の調達の推進
知事は、毎年度、県が行う物品や役務の調達に関し、環境物品等の調達推進方針を作成・公表し、県は、その方針に基づき物品や役務の調達を行うものとした。
また、県は、市町村が行う環境物品等の調達状況を把握し、必要な助言を行うよう努めるとともに、事業者や県民が環境物品等を容易に選択することができるよう、環境物品等に関する情報提供等を行うものとした。 【平成17年4月1日施行】
(3) 許可工場制度の廃止
これまで旧条例に規定されていた許可工場制度(特に著しい公害を発生するおそれのある工場等を対象とした工場設置等の許可)については、環境技術の向上、環境法令の充実などにより、今回の条例改正で廃止した。
図6−1 栃木県生活環境の保全等に関する条例の構成
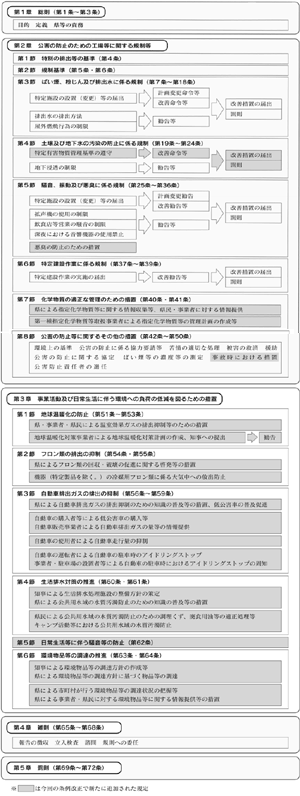 ≪拡大図はこちら≫ ≪拡大図はこちら≫
|
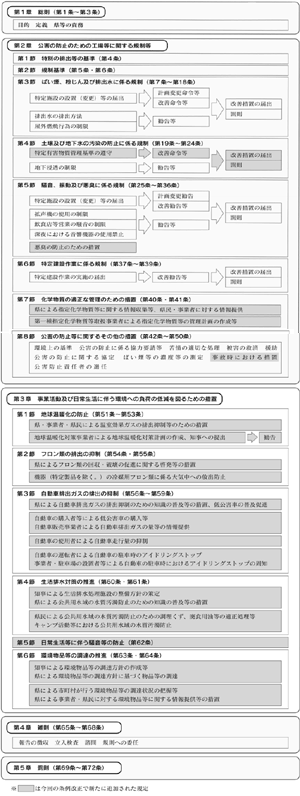 ≪拡大図はこちら≫
≪拡大図はこちら≫