第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策
第2章 人と自然が共生する潤いのある地域づくり
| 第1節 | 環境を支える森林づくり |
1 森林の整備・保全の現状
(1)本県の森林の概要
- ア 本県の森林の概要
- 19年度末における本県の森林面積は、県土面積約64万haの55%にあたる約35万haとなっている。県土面積における森林面積の割合(森林率)は全国で第35位にあたる。(図2-2-1)
森林の所有別内訳は、国有林が約13万ha(本県森林の37%)、民有林が約22万ha(本県森林の63%)となっている。また、民有林における樹種別面積割合は、スギが32%、ヒノキが21%、その他針葉樹が9%、広葉樹が38%となっており、スギ・ヒノキを中心とした人工林面積は約12万ha(民有林面積の55%)となっている。(図2-2-2、表2-2-1)
| 図2-2-1 県土面積における森林の割合 (19年度末) |
図2-2ー2 県内所有別・人工天然林別 森林面積の「割合」(19年度末) |
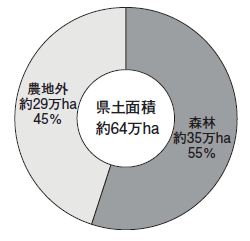 |
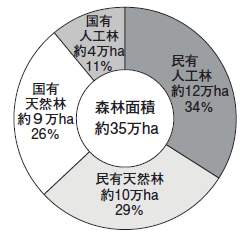 |
| 区分 | 割合 | 樹種(全体に占める割合) |
|---|---|---|
| 針葉樹 | 62% | スギ(32%)、ヒノキ(21%)、その他針葉樹(9%) |
| 広葉樹 | 38% | クヌギ(2%)、その他広葉樹(36%) |
- イ 森林の有する多面的な機能
- 森林は多面的な機能を有しており、県民の生活と深くかかわっている。12年に農林水産大臣から日本学術会議に対して「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」諮問され、その答申(13年11月)では、森林には次のような機能があるとされている。
(1)生物多様性保全機能 (5)快適環境形成機能 (2)地球環境保全機能 (6)保健・レクリエーション機能 (3)土砂災害防止機能・土壌保全機能 (7)文化機能 (4)水源かん養機能 (8)物質生産機能
近年、二酸化炭素を吸収・固定する働きから、地球環境保全機能が国際的に重要視されている。
また、森林は、所有者等による植林から伐採までの林業生産活動や病虫獣害の防除・森林火災の防止などの適正な管理を通じ、その多面的機能を維持向上させ、県民の生活環境を守るという重要な役割を担っている。
(2)森林の整備状況
- ア 民有林造林面積の推移
- 民有林の造林面積は昭和53年度の2,100haをピークに減少傾向を示し、19年度には、ピーク時の約13%に当る278haにまで落ち込んでいる。(図2-2-3)
図2-2-3 民有林造林面積の推移
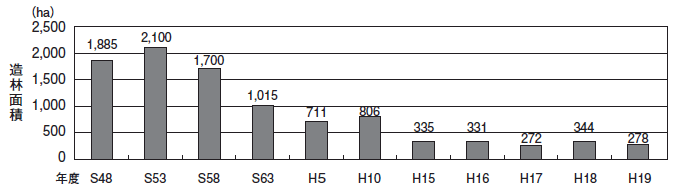
図2-2-4 民有林樹種別造林面積の割合(19年度実績)
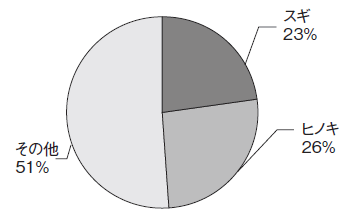
- イ 民有人工林の齢級別構成(間伐を必要とする森林の状況)
- 本県の民有林のうち10万2千ha(全体の約8割)が、間伐を必要とする森林(Ⅳ~ⅩⅡ齢級(16~60年生))になっているが、その半数近くが間伐の遅れた森林であり、荒廃の危険性が高まっている。特に奥地など条件の悪い箇所の遅れが顕著で早急な対策が必要である。
本県では、これらを中心に15年度から19年度までの5年間で約2万haの間伐を実施し、健全な森林づくりに努めてきたが、いまだに手入れの行き届かない森林が多く残されている。(図2-2-5)
図2-2-5 県内民有人工林におけるスギ・ヒノキの林齢別面積(19年度末)
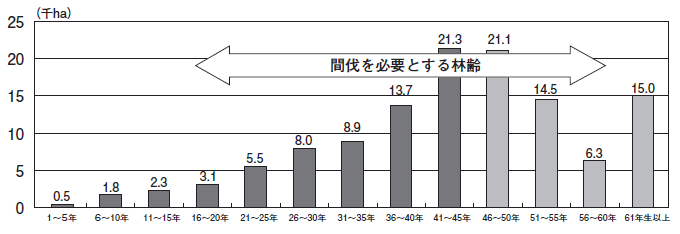
(3)保安林の指定状況
水源かん養や土砂流出防備など森林の公益的機能をより高度に発揮させていくことを目的に指定する保安林について、「栃木県保安林配備基本計画」に基づき指定を行っている。
指定面積は、国有林、民有林ともに着実に増加しており、19年度末現在の指定面積は約18万4千haである。
その内訳は国有林が62%(国有林面積の約8割)、民有林が38%(民有林面積の約3割)となっている。(図2-2-6)
図2-2-6 保安林面積の推移
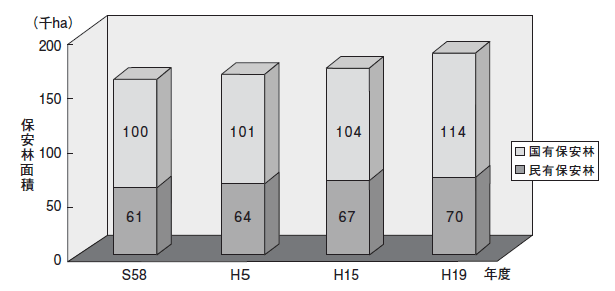
| 項目 | 民有林 | 国有林 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保安林種 | 兼種 | 兼種 | 兼種 | |||
| 水源かん養保安林 | 50,023 | 91,714 | 141,737 | |||
| 土砂流出防備保安林 | 18,888 | 21,675 | 40,563 | |||
| 土砂崩壊防備保安林 | 79 | 51 | 130 | |||
| 防風保安林 | 24 | 24 | ||||
| 水害防備保安林 | 65 | 65 | ||||
| 干害防止保安林 | 437 | 120 | 557 | |||
| 落石防止保安林 | 2 | 2 | ||||
| 保健保安林 | 301 | 8,523 | 68 | 6,450 | 369 | 14,973 |
| 風致保安林 | 70 | 70 | ||||
| 計 | 69,819 | 8,523 | 113,628 | 6,520 | 183,447 | 15,043 |
| 森林面積 | 221,566 | 127,965 | 349,531 | |||
| 保安林率 | 31.5% | 88.8% | 52.5% | |||
(4)森林を支える林業・木材産業の現状
ア 林業の現状
- (ア)木材価格の状況
- 19年の木材価格は、素材ではスギ小丸太が13,200円/m3、ヒノキ小丸太が21,500円/m3、製材品ではスギ正角(柱材)が39,300円/m3、ヒノキ正角(柱材)が73,700円/m3となっており、スギ小丸太では、昭和55年の価格の約1/3に落ち込んでいる。(図2-2-7)
図2-2-7 林業就業者の状況
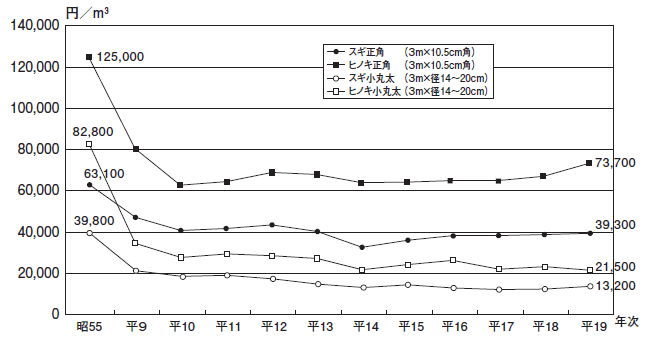
- (イ)林業担い手等の状況
- 林業経営体数は3,943経営体で、そのうち64%が保有山林面積10ha未満の小規模経営体となっている(2005年農林業センサス)。
林業就業者数は、17年国勢調査によると610人で、12年の6割にまで減少しており、65歳以上の就業者が4分の1を占め、他産業に比べて高齢化が進んでいる。一方、新規林業就業者数は、毎年20~40人台で推移しているが、その多くは他産業に勤務経験のある30代を中心とする年齢層から参入している。(図2-2-8)
「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、経営や雇用の改善を計画的に行う林業事業体として、森林組合など24事業体が知事の認定(認定事業体)を受けている。
図2-2-8 林業就業者の状況
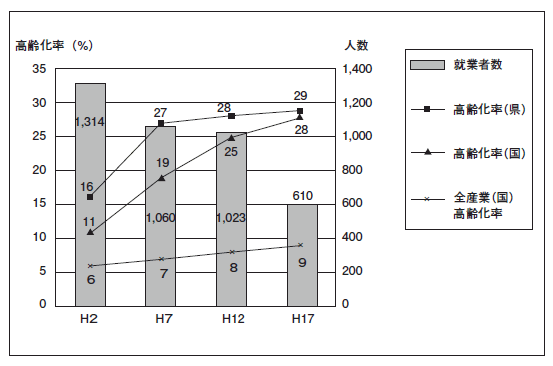
- (ウ)林業生産の基盤の状況
- 林業生産の基盤となる林道、作業道の状況は、それぞれ延長が2,375㎞、6,680㎞、密度が6.6m/ha、6.3m/haである。(表2-2-3)
高性能林業機械の導入(保有)台数は122台で、フォワーダが最も多く、次いでプロセッサが多い状況である。(表2-2-4)
| 区分 | 整備目標(平成46年度) | 現状(平成18年度末) | 達成率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 延長(km) | 密度(m/ha) | 延長(km) | 密度(m/ha) | ||
| 林道 | 2,375 | 10.6 | 1,467 | 6.6 | 62 |
| 作業道 | 6,680 | 29.9 | 1,393 | 6.3 | 21 |
(注)整備目標は、「栃木県民有林林道網整備計画(H10~H16)」における整備目標である。
| 機械名 | フェラバンチャー | ハーベスタ | プロセッサ | スキッダ | フォワーダ | タワーヤーダ | スイングヤーダ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保有台数 | 2 | 11 | 18 | 11 | 65 | 5 | 10 | 122 |
- イ 木材産業の現状
- 18年の素材供給量は638千m3となり、前年より122千m3増加している。供給の内訳は、自県材6割、他県材3割、外材1割で、大半が製材用である。(図2-2-9)
製材工場数は年々減少しているが、一部の大規模工場が規模を拡大していることなどから、製材品出荷量の減少傾向には歯止めがかかっている。さらに、人工乾燥材の生産は年々伸びており、18年は人工乾燥材率(製材品出荷量に占める割合)が30%までに達した。(図2-2-10)
図2-2-9 素材供給量の状況
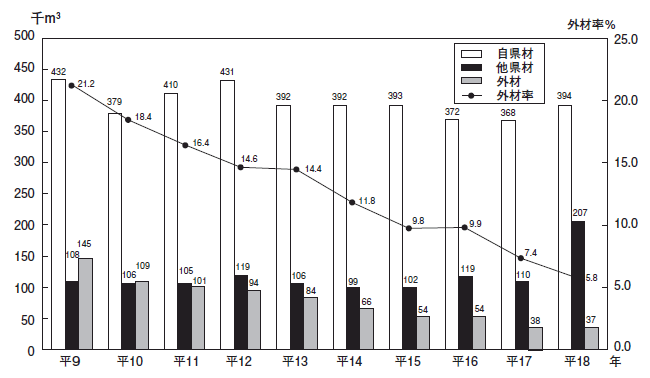
図2-2-10 製材品出荷量の状況
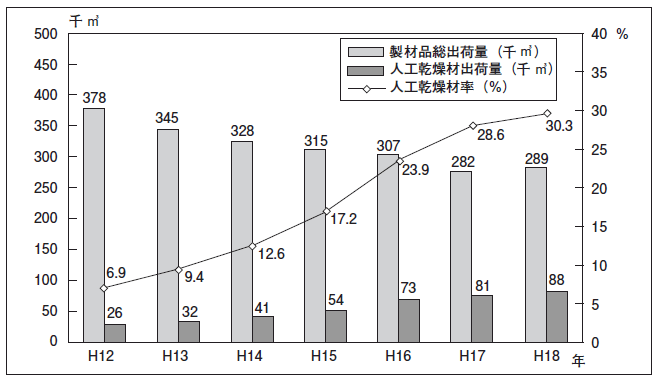
2 森林づくり対策
(1)森林の公益的機能の向上
- ア 間伐等森林整備の促進
- 森林の持つ公益的機能を持続的に発揮させるため、森林所有者への支援や県・森林整備公社による公的森林整備により間伐等の森林整備を促進しており、19年度は約5,005haの間伐を実施した。
また、造林、下刈り等の森林整備を約1,050ha実施した。(表2-2-5)
| 年度 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実施面積 | 4,000 | 3,311 | 5,103 | 4,881 | 5,005 |
(出典:森林整備課業務資料)
- イ 多様な森林の育成
- 森林の持つ公益的機能を持続的かつ高度に発揮させるためには、間伐の促進とともに複層林施業や長伐期施業、育成天然林施業、広葉樹林整備等による多様な森林の育成が重要である。
19年度は約125haの複層林整備、約724haの広葉樹林整備を含め、多様な森林の育成を図る目的で、約2,300haの森林整備を実施した。(表2-2-6)
| 年度 | H17 | H18 | H19 |
|---|---|---|---|
| 複層林整備 | 116 | 99 | 125 |
| 広葉樹林整備 | 679 | 682 | 724 |
| 長伐期施業 | 1,734 | 1,499 | 1,422 |
(出典:森林整備課業務資料)
- ウ 公的森林整備の推進
- 自然災害などにより公益的機能の低下した保安林においては、県が実施主体となる保安林整備事業等により森林整備を推進している。また、林道から遠いなどの条件により所有者による施業が困難な奥地の保安林以外の森林等においては森林整備公社が実施主体となり、スギ・ヒノキの間伐や広葉樹植栽等の森林整備を推進している。
19年度は県、森林整備公社で約2,060haの間伐や広葉樹植栽等の森林整備を実施した。
公益的機能の低下した保安林において、治山事業により、県が事業主体となって機能回復するための約660haの本数調整伐等の森林整備を行った。
また、生育不良な造林地や所有者による施業が放置され、公益的機能が低下した森林において、森林整備公社が実施主体となり約1,111haの間伐等の森林整備を行った。(表2-2-7)
| 年度 | H17 | H18 | H19 |
|---|---|---|---|
| 保安林整備事業 | 980 | 600 | 758 |
| 森林整備公社事業 | 1,356 | 1,133 | 1,111 |
(出典:森林整備課業務資料)
- エ 県民参加の森林づくりの推進
- 森林の大切さについて情報提供を行うとともに、森づくり体験講座の開催や公募による森づくり活動の実施など、体験活動を通して森林環境の保全に対する県民意識の醸成を図った。
また、ボランティアやNPO、企業等の上下流交流による協働水源の森づくり推進事業を実施するなど、県民参加による森林整備活動の促進を図った。(表2-2-8)
| 項目 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|
| 森林ボランティアの活動人数 | 450 | 543 | 663 | 744 |
- オ とちぎの元気な森づくり県民税の導入
- 公益的機能を有する森林を県民全体の理解と協力の下に守り育て、元気な森を次の世代に引き継いでいくことを目的とした「とちぎの元気な森づくり県民税」の20年4月導入に向けて、19年度は次の取組を行った。
(ア) パブリック・コメントの実施
19年3月30日から5月1日まで、とちぎの元気な森づくり県民税の導入について県民の意見を募集するため、パブリック・コメントを実施し、91名の県民から162件の意見が提出された。
パブリック・コメントに寄せられた意見については、県の考え方等を県のホームページ、県民センター等で公表するとともに、とちぎの元気な森づくり関連施策に反映させていくことにした。(イ) とちぎの元気な森づくり県民税条例の制定
県議会第290回定例会において、とちぎの元気な森づくり県民税条例が可決され、7月3日に条例を公布した。(ウ) 「とちぎの元気な森づくり県民税」の広報活動
条例公布後、県民協働の森づくりについて県民の理解を一層深めるため、森林の大切さや社会全体で森林を守り育てていくことの必要性について、とちぎ元気フォーラムやとちぎ県民だよりなどを通じて広聴・広報活動を継続的に実施した。また、市町の協力を得て、税の使い道等について各市町広報誌へ掲載するとともに、パンフレットの配布を行った。(エ) とちぎの元気な森づくり県民会議の設立
県民が主体となって進める“とちぎの元気な森づくり”を県民運動として展開していくための推進母体として、57の団体等で構成する「とちぎの元気な森づくり県民会議」を19年10月に設立した。(オ) とちぎの元気な森づくり憲章
本県の森づくりの基本理念などを定める「とちぎの元気な森づくり憲章」を20年3月に制定した。
図2-2-11 とちぎの元気な森づくり県民税で進める取組
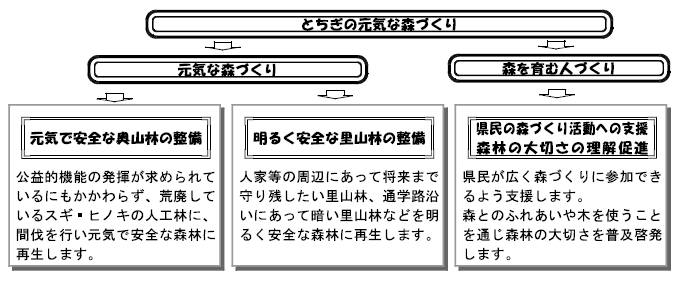
- カ 森林を支える林業・木材産業の振興
- 森林の持つ多面的機能の発揮には、持続的な林業生産活動の推進が不可欠であり、このためには「木を植え、育て、伐って利用し、また植える」という森林資源の循環利用を推進することが重要である。
(ア) 森林整備を支える人・システムづくり
林業後継者の育成や林業経営の改善などを図るため、19年度は林業普及指導員32人による普及活動を実施するとともに、林業普及推進事業により意欲的な林業グループの活動を支援した。
さらに、間伐など森林施業の集約化等によるコストの低減を図るため、森林整備地域活動支援交付金により森林情報活動等に支援するとともに、19年度は森林所有者に施業経費を提案することにより間伐を促進するため、間伐材生産経費積算プログラムの開発に着手した。
また、森林整備の中核を担う森林組合等林業事業体の新規就業者を確保育成するため、国の「緑の雇用対策事業」の活用促進を図りながら、栃木県林業労働力確保支援センターが行う林業カレッジ研修等を支援した。
さらに、林業労働災害を防止するため、作業現場の安全や安全意識の向上を図るための研修や巡回指導を支援した。(イ) 低コスト林業の基盤づくり
森林施業や木材生産の効率化を高めるため、19年度は林道7km、作業道84kmを開設するとともに、林道の改良、舗装を実施した。
さらに、林業作業の効率化、低コスト化を図るため、林業・木材産業構造改革事業により高性能林業機械の導入や栃木県林業サービスセンターが行う高性能林業機械の共同利用(リース事業)を支援した。(ウ) 県産材の安定供給と利用拡大
高品質な県産材を低コストで安定的に供給するため、木材産業等高度化推進資金や木材業振興資金を融資するほか、19年度は木材団体などと「原木流通合理化ガイドライン」を作成するとともに、林業・木材産業構造改革事業により人工乾燥施設や木材加工施設の整備を支援した。
また、県産材の利用拡大を図るため、一般消費者を対象とした「木造りの家ノウハウ講座」を開催するほか、県産材を利用した住宅の建築を進めるグループの活動、木材業団体が行う木造住宅コンクールの開催や柱材プレゼント事業を支援した。
さらに、「とちぎの元気な森づくり県民運動」の展開等による木の良さの普及など県産材の利用拡大に努めた。
(2)森林の適正管理
- ア 森林計画制度による森林管理の推進
- 森林計画制度は森林法において体系付けられており、国が策定する全国森林計画に即して、県が地域森林計画を、市町村は地域森林計画に適合した市町村森林整備計画を策定している。
地域森林計画は、民有林を対象とした10年を1期(前期・後期)とする計画であり、本県では県内を那珂川・鬼怒川・渡良瀬川の3つの森林計画区に区分している。(図2-2-12、図2-2-13))
19年度においては、21年度を初年度とする鬼怒川地域森林計画区上流(日光市)の編成を行った。
また、計画的な森林整備を図るため、森林計画図や森林簿、施業履歴など民有林に関する様々な情報について一元的に管理・分析する「森林GIS」を運用している。
図2-2-12 栃木県の森林計画区
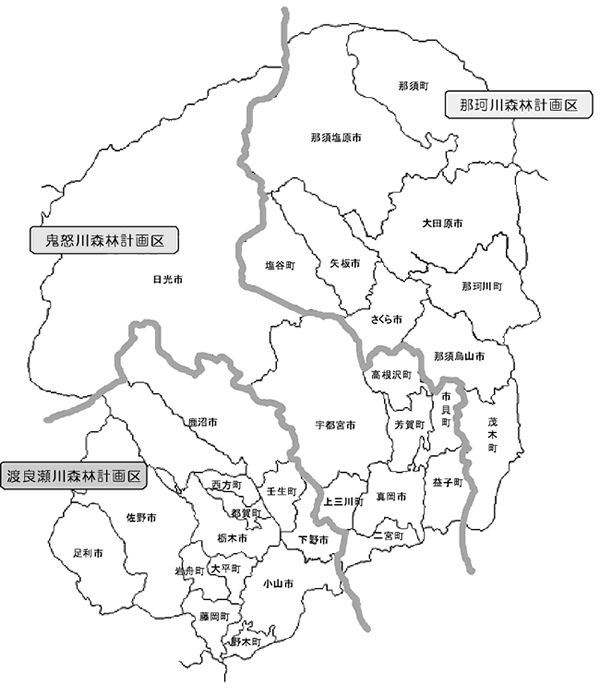
図2-2-13 森林計画区と計画期間
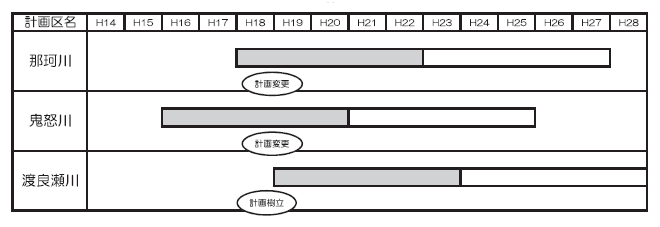
- イ 保安林・林地開発許可制度による森林の保全
- 保安林指定の拡大等により、森林の持つ公益的機能の高度発揮と森林の保全を推進した。
また、本県民有林の保安林整備(指定、森林整備、管理)の適正な推進を図るため、「栃木県保安林整備基本計画」に基づき、具体的行動計画である「栃木県第1期保安林整備実施計画」を19年度に策定した。
さらに、森林の有する公益的機能や環境との調和を損なうことなく、秩序ある開発行為を促すための林地開発許可制度に基づき、適切な許可と指導に取り組んだ。
- ウ 森林被害対策の推進
- 森林の病害虫等被害を早期に発見し、適切な対策を実施するため、市町村や関係団体等と連携して被害対策を図っている。
19年度は、松くい虫被害防除対策として、146haの森林で薬剤散布を実施したほか、約1,900m3の被害木の伐倒駆除等を実施した。
また、貴重な県民共有の財産である森林が一瞬で焼失してしまう森林火災を防止するため、山火事防止の普及啓発活動を実施している。
19年度は、3月15日の「栃木県山火事防止デー」に県内16箇所において山火事防止の普及啓発活動を実施したほか、広報車による巡回パトロールやテレビによる山火事防止CMの放送、ポスター・リーフレットの配布等を実施した。