第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策
第2章 人と自然が共生する潤いのある地域づくり
| 第2節 | 多用な自然環境の保全 |
1 自然環境の状況
(1)自然環境の状況
本県は、県北部に日光、高原、那須火山群からなる山岳地帯が形成され、湖沼、渓谷、瀑布や高層湿原等が原生林と調和した自然景観をなしている。また、地形、地質、気象など立地条件の特異性によって、南方系、北方系植物が混在して分布し、氷河期からの動植物が数多く生息するなど、特異種や貴重なもの、珍しい生態を示すもの等変化に富んだ自然の様相を呈している。
一方、中央部及び南部の平地帯は、経済活動の場として時代とともに変化してきたが、人間と自然との長いかかわり合いの中で存続している平地林等は、遮音、防火、憩いの場の提供等生活環境上計り知れない効用をもつ身近な自然として重要な意義を持っている。
(2)自然公園の指定状況
本県の自然公園は、総面積が約13万haであり県土の面積の約21%を占めている。県北西部の山岳地帯を中心とした地域は、我が国の代表的な自然公園である日光国立公園によって占められ、また、県内各地には、地域の特性を持つ8つの県立自然公園があって、それぞれ変化に富んだ自然景観を有している(図2−2−14)。なお、19年度に、新たに、尾瀬国立公園の公園区域の一部が栃木県内に指定(1,147ha)され、日光国立公園の那須地域においても公園区域が拡張(155ha)された。
これらの自然公園には、県の内外から、自然を求めて多くの人々が訪れている。
| (単位:ha) | |||||||||||||||||||||||||||||||
図2−2−14 自然公園の現状(19年度末)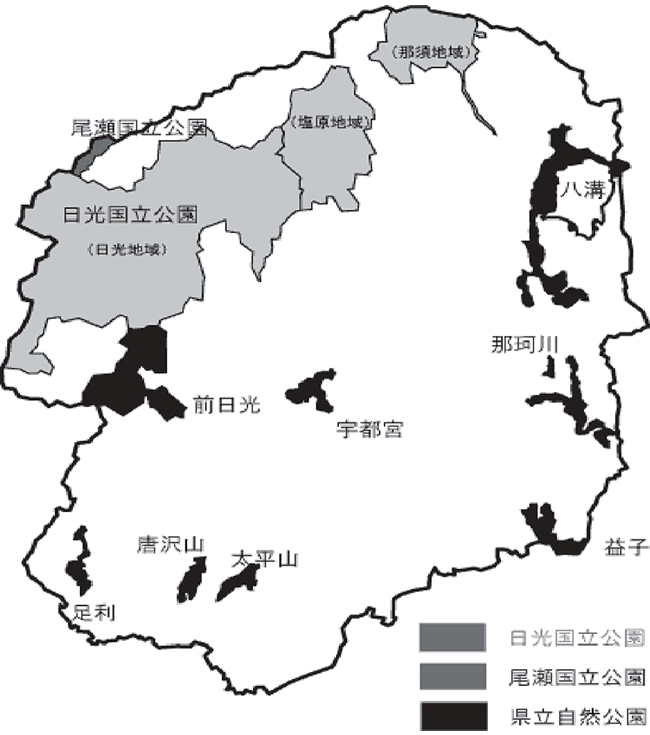 クリックで拡大します |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)日光、尾瀬国立公園の面積は本県分のみを計上した。 |
(3)自然(緑地)環境保全値域等の指定状況
「自然環境保全法」及び「自然環境の保全及び緑化に関する条例」に基づき、優れた自然環境を持つ地域を自然環境保全地域に、また、市街地周辺地及び歴史的・文化的遺産と一体となった良好な緑地を緑地環境保全地域に指定し、その保全に努めている。19年度末現在、国指定の自然環境保全地域1か所を含め、41か所5,355haを指定している。(表2−2−9、図2−2−15)
| 県自然環境保全地域 | 緑地環境保全地域 | 国指定の自然環境保全地域 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 |
| 26 | 4,672ha | 14 | 138ha | 1 | 545ha | 41 | 5,355ha |
図2−2−15 自然(緑地)環境保全値域等の指定状況(19年度末)
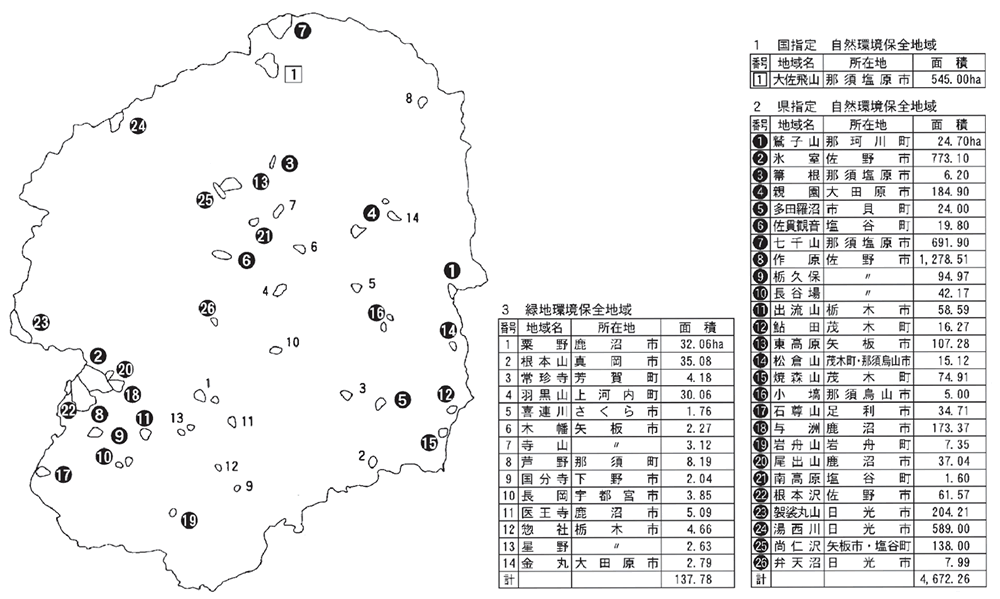
クリックで拡大します
(4)都市公園の整備状況
都市公園は、都市に緑とオープンスペースをもたらすことによって都市環境を良好なものとするとともに、児童、青少年の健全なレクリエーションの場や市民のコミュニケーションの場を提供するばかりでなく、大気汚染、騒音等都市公害を緩和し、災害時の避難場所として活用されるなど、多目的な機能を有する基幹的な生活基盤施設である。
本県では、20年3月末において、1,827か所2,547.81haの都市公園が整備されており、都市計画区域内の1人当たり公園面積は13.1m2が確保され、全国平均※の9.3m2を大きく上回る整備水準となっている。(表2−2−10) ※全国平均は19年3月末の値
| 種類 | 箇所数 | 面積(ha) | 種類 | 箇所数 | 面積(ha) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 1,460 | 210.40 | 特殊公園 | 13 | 82.05 |
| 近隣公園 | 111 | 184.54 | 広域公園 | 4 | 374.40 | ||
| 地区公園 | 61 | 314.85 | 緩衝緑地 | 13 | 35.79 | ||
| 小計 | 1,632 | 709.79 | 都市緑地 | 87 | 85.65 | ||
| 都市基幹公園 | 総合公園 | 26 | 357.86 | 広場公園 | 6 | 1.09 | |
| 運動公園 | 37 | 899.59 | 緑道 | 9 | 1.59 | ||
| 小計 | 63 | 1,257.45 | 合計 | 1,827 | 2,547.81 | ||
2 自然環境保全対策
(1)優れた自然の保全
- ア 奥日光地区の自然環境の保全
- 戦場ヶ原等の「奥日光の湿原」が本県で初めてラムサール条約湿地となったことを受け、環境省が立ちあげた戦場ヶ原湿原保全対策検討会のメンバーとして保全方針の策定に携わるほか、庁内関係課所に情報提供を行うなど、貴重な湿原の保護思想醸成に努めた。
奥日光地区においては、貴重な自然環境を保全するため、低公害バスの運行、植生回復対策(シカ食害影響調査)、移入植物(オオハンゴンソウ等)の除去(19年度ボランティア参加者約300名)等に取り組んだ。
| 年度 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低公害バス利用者数(人) | 115,566 | 128,406 | 120,356 | 106,615 | 116,071 |
- イ 自然(緑地)環境保全地域の保全
- 自然(緑地)環境保全地域に指定されている地域(図2−2−15)について、自然監視員による巡視、案内標識の整備、土地の形質変更の規制などにより保全に努めた。
(2)平地林・農地の保全
- ア 平地林等の保全
- 人里近くの丘陵部や低山地に広がる平地林と、田園のみどりは、農産物や特用林産物等の生産活動を通して、創出・保全され、私たちの生活に潤いと安らぎを与え、身近な緑として親しまれている。
身近な平地林等の役割や管理の重要性について、広く県民の理解を深めることにより、より多くの県民が平地林等に関心を持ち、住民参加による積極的な保全活動が展開されるよう、ボランティアグループ等による下草刈りや朽木の伐採等の活動を軸に市町村が行う普及啓発事業への支援を行った。(19年度実績 小山市、野木町) - イ 豊かな地域資源の保全・継承
- 農業農村のもつ豊かな自然、伝統文化等の多面的な機能を再評価し、豊かな生態系や美しい農村景観・伝統的農業施設等の保全・復元等を行っている。
なかでも、19年度から導入した農地・水・環境保全向上対策を活用して、農地や農業用水、さらには、生態系や景観などの農村環境の保全向上に向けた地域ぐるみの共同活動を266地区の約20,000haで促進した。(表2−2−12)
| 市町名 | 共同活動 | 営農活動 | 市町名 | 共同活動 | 営農活動 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区数 | 面積 | 地区数 | 水稲 | 地区数 | 面積 | 地区数 | 水稲 | ||
| 宇都宮市 | 24 | 1,475.57 | 藤岡町 | 1 | 45.68 | ||||
| 鹿沼市 | 3 | 116.63 | 岩船町 | 1 | 43.79 | ||||
| 日光市 | 10 | 1,029.73 | 1 | 41.37 | 都賀町 | 1 | 116.35 | ||
| 真岡市 | 1 | 43.64 | 矢板市 | 15 | 753.13 | ||||
| 益子町 | 5 | 359.19 | さくら市 | 6 | 599.64 | ||||
| 茂木町 | 7 | 158.64 | 塩谷町 | 31 | 1,478.11 | ||||
| 市貝町 | 2 | 79.21 | 高根沢町 | 5 | 691.69 | ||||
| 芳賀町 | 8 | 2,142.55 | 大田原市 | 42 | 4,272.05 | ||||
| 栃木市 | 1 | 44.94 | 那須塩原市 | 34 | 2,872.60 | 5 | 50.45 | ||
| 小山市 | 45 | 2,926.08 | 5 | 95.70 | 那須町 | 6 | 201.20 | ||
| 下野市 | 1 | 45.30 | 那須烏山市 | 4 | 195.68 | ||||
| 壬生町 | 1 | 90.59 | 那珂川町 | 6 | 298.56 | ||||
| 野木町 | 1 | 30.30 | 足利市 | 1 | 64.17 | ||||
| 大平町 | 1 | 161.32 | 佐野市 | 3 | 55.45 | ||||
| 計 | 266 | 20,391.79 | 11 | 187.52 | |||||
- ウ 田園自然環境保全・再生支援事業
- 19年度は、農業農村整備事業の実施等と併せ、住民主体による農村の自然環境保全・再生活動を実施する3地区を支援した。
19年度実施地区:小代地区(日光市)、文挟地区(日光市)、荒川南部地区(那須烏山市)
(3)都市地域の自然環境の保全
- ア 都市公園の整備
- 19年度も、都市環境の改善や公害、災害発生の緩和、レクリエーション需要等の多様なニーズに対応する都市公園の整備を促進するとともに、既開設公園についての適正な維持管理を推進している。
- イ 開発行為による良好な宅地化の推進
- 開発許可制度の適切な運用により、無秩序な宅地開発等を防止し、良好な市街地形成と都市地域の自然環境の保全に努めている。
(4)ビオトープの保全・創造
農村地域は、農業生産及び生活の場であるとともに、その豊かな自然環境は多様な生物の生活の場でもある。そこで環境に恵まれた農村空間(エコビレッジ)を形成することを目的に、水生生物保全のための施設整備、昆虫・野鳥等のための植栽等の整備を実施している。
(5)自然公園の適正な管理
自然公園については、指定の目的である自然の保護と利用の増進を図るための公園計画が定められ、これに基づいて、木竹の伐採、工作物の建築等の風致景観の現状を変更する行為を規制するとともに、歩道や休憩施設など利用のための施設整備を計画的に実施している。
また、公園利用者に対しては、自然公園指導員によるマナー指導やビジターセンターによる情報提供等が行われ、自然公園の適正な利用に寄与している。
さらに、奥日光の日光市道1002号線では、自動車の乗り入れ規制を行うとともに、代替交通手段として低公害バスを運行し、小田代原周辺の自然環境の保全を推進している。