第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策
第3章 地球環境の保全に貢献する社会づくり
| 第1節 | 地球温暖化防止対策の推進 |
1 温室効果ガスの削減目標と本県の排出状況
(1)温室効果ガス排出量の削減目標
我が国は、京都議定書において、20年(2008年)から24年(2012年)の第1約束期間に、温室効果ガス総排出量を基準年(2年、1990年)比で6%削減することとしている。
京都議定書目標達成計画においては、温室効果ガス排出量の削減目標として、基準年比−0.5%を掲げ、不足分となる量(5.5%)は、森林での吸収量(3.9%)と京都メカニズム(1.6%)で補うとしている。
栃木県の22年度(2010年度)における温室効果ガス排出量推計値は、約22,208千t-CO2と予測され、基準年(2年度、1990年度)比4,061千t-CO2(22.4%)の増加が見込まれている。
京都議定書における削減目標は、我が国全体で果たすべき国際的な公約であり、本県としても、地球社会の一員としてこの目標達成に向けて積極的に温室効果ガス排出削減対策を実施する必要があることから、京都議定書目標達成計画に定められた各種対策・施策を中心に地球温暖化対策を強力に推進するとともに、県民、事業者がさらなる努力を続けていくことを前提に、「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」において、温室効果ガス総排出量の削減目標を基準年比0.5%削減(18,056千t-CO2)を目標として設定している。(図2−3−1)
図2−3−1 温室効果ガス排出量の将来予測と削減目標
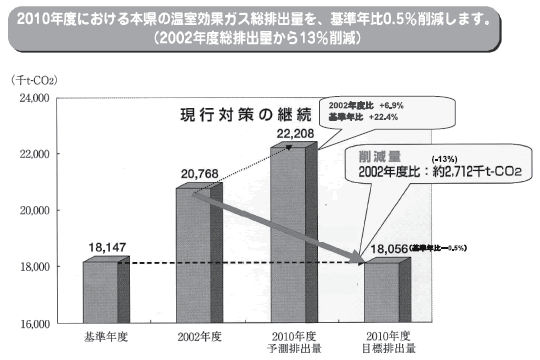
(2)本県の温室効果ガス排出状況
14年(2002年)度における本県の温室効果ガス総排出量は約20,768千t-CO2であり、基準年(2年(1990年)。ただし、HFCS、PFCS、SF6については7年(1995年))比14.4%増となっている。
14年度の本県における排出源別のCO2排出量の占める割合を全国と比較すると、製造業、運輸部門の占める割合が全国と比べて大きく、家庭、業務部門は小さくなっている。(図2−3−2)
本県が製造品出荷額で全国11位(18年)と有数の工業県であることや、乗用車保有台数が全国17位(18年)という本県の特性が表れている。
19年度(2007年度)の県における温室効果ガスの排出量は、推計の結果、19,685千t-CO2であった。詳細については、第3部第2章第1節(186頁)を参照のこと。
図2−3−2 排出源別のCO2排出量の占める割合(14年度)
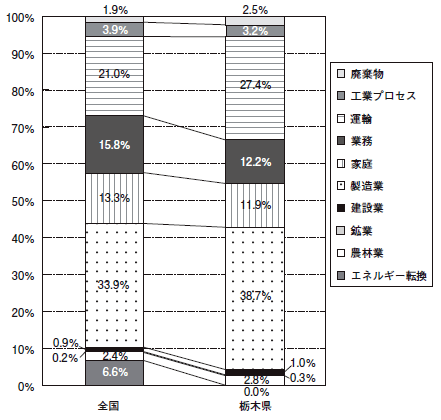
2 地球温暖化防止対策
(1)地球温暖化防止対策の総合的な推進
「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、19年度は、次のとおり地球温暖化防止対策を総合的に推進した。
- ア 地球温暖化防止活動推進センター事業
- 「地球温暖化対策推進法」第24条の規定に基づき指定した栃木県地球温暖化防止活動推進センターの自主事業との連携を図りながら、地球温暖化防止に向けた県民への普及啓発事業を委託により実施した。
- (ア)エコテックとちの環2008の開催
- 企業や団体によるリサイクル製品・省エネ機器など環境への負荷の少ない製品や技術の展示、活動の紹介、及び講演会の開催等を通して地球温暖化対策や循環型社会の構築を啓発する環境イベントを開催した。
期間:20年2月1日(金)〜2日(土)
会場:マロニエプラザ(宇都宮市)
主催:栃木県、栃木県地球温暖化防止活動推進センター、とちの環県民会議
出展企業・団体数:82企業・団体
講演:「エコドライブでCO2削減」
講師俳優保坂尚希氏
来場者:約2,000名 - (イ)地球温暖化防止キャンペーン「エコライフフォーラム」の開催
- 地球温暖化の現状や影響、さらに、防止するためには一人ひとりの取組が必要不可欠であることを普及啓発し、県民の環境にやさしいライフスタイルへの転換を促すため、講演会を開催した。
月日:19年12月1日(土)
会場:栃木県産業創造プラザ多目的ホール(宇都宮市)
主催:栃木県、栃木県地球温暖化防止活動推進センター、とちの環県民会議、
財団法人栃木県職員互助会
講演:「“地球を救え”〜ツバルから考えるSTOP THE 温暖化〜」
講師写真家/国際NGO Tuvaru Overview 日本事務局代表遠藤秀一氏
参加者:120名
- イ とちの環県民会議との連携
- 「とちの環県民会議」は、県民、民間団体、事業者、行政の各主体が相互に連携・協力するパートナーシップを確立し、県民総ぐるみで環境保全に取り組む組織で、「地球温暖化対策推進法」第26条の規定に基づく地球温暖化対策地域協議会を兼ねており、地域の特性に応じた地球温暖化対策の検討・実践活動を行っている。
とちの環県民会議と連携し、普及啓発事業を実施した。- (ア)とちの環県民会議総会記念講演会の開催
- 異常気象や気候変動に関するメカニズムに関する講演会を開催した。
月 日:19年5月19日(土)
会 場:とちぎ健康の森(宇都宮市)
主 催:栃木県、栃木県地球温暖化防止活動推進センター、とちの環県民会議
講 演:「エコ商品で地球を守る!!」
講師 株式会社カタログハウス取締役エコひいき事業部長 竹本徳子 氏
参加者:約200名
-
ウ 地球温暖化防止活動推進員の委嘱
- 地球温暖化対策の取組を推進するため、「地球温暖化対策推進法」第23条の規定に基づき、栃木県地球温暖化防止活動推進員を19年度は57名委嘱し、19年度末で合計90名の推進員が県内各地域で、地球温暖化の現状や対策の重要性についての普及啓発を実施した。
- エ 広報媒体を活用した普及啓発事業
- 地球温暖化防止啓発、省エネルギーキャンペーン等の周知を新聞、ラジオ等スポットCMにより行った。
- オ 環境演劇の開催事業
- ごみの減量化・リサイクルをテーマとした演劇を県内の小・中学校へ巡回公演(130回、約30,000人)し、次世代を担う子どもの意識の高揚を図った。
- カ 栃木県庁環境保全率先実行計画〈二期計画〉の推進
- 県では、持続可能な循環型社会の構築を目指し、より一層の環境に配慮した取組を推進するため、「栃木県庁環境保全率先実行計画〈二期計画〉」を17年3月に策定した。
19年度は、「電気使用量を抑制する」「ガソリン使用量を抑制する」の2項目を全庁重点取組事項として温室効果ガス削減の取組を行った。取組結果については、第3部第3章第1節を参照のこと。
(2)省エネルギー・エネルギー有効利用の推進
- ア 省エネチャレンジ大作戦
- 省エネ型ライフスタイルの普及・定着を図るため、家庭、学校、事業所単位により県民総ぐるみで省エネ活動に取り組み、その成果を顕彰する省エネチャレンジ大作戦を実施した。学校及び事業所部門では、削減率のほかに、「周知・啓発度」「定着度」「ユニークさ」「実行可能性」についても審査し受賞者を決定した。
取組期間:19年7月〜9月
取組内容:エネルギー使用量を前年同時期と比較して削減
参加者:家庭776・学校26・事業所134 全体:936 - イ 地球温暖化対策支援事業
- 事業者の地球温暖化対策を推進するため、温室効果ガス排出量削減に関する知識や技術を指導・助言できるESCO事業者等省エネルギー関連事業者や専門家を「地球温暖化対策アドバイザー」として県が登録し、県内事業者の要請に応じ派遣した。
19年度の派遣状況は、9件であった。
- ウ ESCO導入推進事業
- 県内の総合的・効率的な省エネルギー対策を推進するため、市町及び民間事業者等を対象とするESCO事業導入に関するセミナーを県立がんセンター(宇都宮市)において2回開催した。
- エ 省エネルギー住宅の普及拡大
- 省エネルギー性能を含む「住宅性能表示制度」の普及・促進により、適切な熱環境計画を行った省エネルギー住宅の普及拡大を図った。また、住宅の省エネルギー化技術者の養成を推進するため、(財)建築環境・省エネルギー機構との共催で、住宅建設業者等向けの「省エネルギー住宅の設計・施工技術講習会」(20年2月)を実施した。
- オ ESCO事業の推進
- 県自らの省エネルギー化に向けた率先行動の一環として、「栃木県ESCO推進マスタープラン」(18年2月)を策定し、モデル的にがんセンターにて18年度からESCO事業を導入し、19年4月から運用を開始した。
(3)新エネルギー・未利用エネルギーの利用の推進
ア 一般住宅用太陽光発電システム資金貸付
一般住宅用太陽光発電システムの設置に必要な資金の融資制度を17年6月から開始し、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及促進を図っている。(表2−3−1)
19年度の融資状況は、融資件数3件、融資額6,000千円であった。
| 対象者 | ○県内に居住する方(新たに県内へ居住する方を含む)で申込者本人又は同居の家族の所有である自宅(新築・既築)にシステムを設置する方 ○システムの設置工事に着手していない方 ※システム付きの建売住宅を購入する場合も対象となる。 |
| 対象額 | ○設置経費から他の公的補助金額及び公的融資金額を控除した額 |
| 限度額 | ○200万円 |
| 融資利率 | ○年1.7%(19年4月1日現在) |
| 償還機関 | ○10年以内 |
| 償還方法 | ○元利均等毎月返済方式(賞与時の増額返済の併用も可) |
| その他 | ○その他の条件(保証・担保等)は、取扱金融機関の定めるところ |
イ 太陽光発電の率先導入
県自らの活動によるCO2の排出抑制に取り組むとともに、太陽光発電システムの導入促進を図るため、学校や県民利用施設に大規模太陽光発電システムの整備を進めている。
ウ 新エネルギーに関する普及啓発
県民や事業者の新エネルギーに対する理解を促進するため、県が導入した太陽光発電施設やクリーンエネルギー自動車などを活用して積極的に普及啓発を行った。
また、天然ガス自動車の普及促進を目的とした「新エネルギーセミナー」の開催や新エネルギーの理解促進・普及のためのパンフレットを作成した。
(4)自動車からの二酸化炭素排出量削減の推進
ア エコドライブ普及啓発事業
11月を「栃木県エコドライブ月間」として、エコドライブキャンペーン及びエコドライブ講習会を開催し、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るためのエコドライブの普及啓発を図った。
エコドライブキャンペーン:11月3日(土)宇都宮市馬場通り
エコドライブ講習会:11月17日(土)さくら市氏家公民館
イ クリーンエネルギー自動車の率先導入
県として二酸化炭素(CO2)の排出抑制や大気環境の保全に取り組むとともに、クリーンエネルギー自動車の普及啓発を図るため、公用車にハイブリッド自動車4台・天然ガス自動車1台を導入した。
これにより、県のクリーンエネルギー自動車保有台数は79台となった。
ウ 自動車交通需要の調整
県と関係市町が策定した各都市圏の総合都市交通計画に基づき、都心部でのレンタサイクル(宇都宮市)や循環バス運行(栃木市)など、自動車交通需要の低減に寄与する交通需要マネジメント施策が展開されている。
エ 公共交通ネットワークの整備
本県は、自動車普及率や自動車免許保有率が全国上位にあるなど、「くるま社会」化が顕在化しており、県民の日常生活は自家用車に依存する傾向がますます強まる一方で、公共交通の利用者は減少に歯止めがかからない状況にある。この状況を改善するため、以下の取組を進めている。
- (ア)とちぎ公共交通ネットワーク形成基本指針の策定
- 本県の公共交通の活性化に向け、行政・交通事業者・住民等が連携しながら取り組むべき方向を示した「とちぎ公共交通ネットワーク形成基本指針」を策定した。
- (イ)子供向け副読本の作成
- バスや電車の乗り方や公共交通の役割等を記載した子供向けの副読本を作成し、子供に対して公共交通に関する啓発を行い、併せてバスの無料乗車券等を添付して、親子そろっての利用促進を図っている。
- (ウ)バス・鉄道利用デーの取組
- 毎月1日と15日を「バス・鉄道利用デー」と定め、通勤等で日常的に自家用車を利用している県民に対し、ラジオスポットによる呼びかけを行い、バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進を図っている。
- (エ)新交通システムの導入検討
- 19年度からは、宇都宮市が主体となり、宇都宮地域における新交通システムの成立性・実現性について、技術的かつ専門的な観点から検討に着手したところであり、県もこの取組を積極的に支援している。
オ 交通渋滞の解消、緩和による自動車交通の円滑化
体系的な道路ネットワークの整備や道路の拡幅、バイパスの整備、交差点の立体化等を推進し、渋滞の解消、緩和によるCO2の排出抑制を行っている。
(5)森林整備・緑化の推進と木材利用の推進
ア 森林整備、緑化の推進
森林は、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を光合成により吸収し、木材として炭素を長期間貯蔵、また、蒸散作用により気候を緩和するなど、地球温暖化を防止する上で大きく期待されており、これらの機能を高く発揮するため、森林の保全・育成や木材資源の有効利用を促進することが求められている。
また、都市部の緑化は、大気の浄化や気温上昇の抑制などの効果が期待されている。
19年度は、地球温暖化防止森林吸収源対策の着実な推進を目指し、県内民有林における間伐等の促進や荒廃した森林の復旧を図る治山対策を推進するなど健全な森林づくりに取り組んだ。
また、本県の森林による二酸化炭素吸収量の確実な確保を図るための県としての行動計画として「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」の部門プログラムである「栃木県地球温暖化防止森林吸収源対策推進計画」を策定した。
また、公益的機能の高度発揮が求められる森林の適切な保全を図るため、長期的な視点から保安林の適正な指定・森林整備・管理について方向性を示した「栃木県保安林整備基本計画」に基づき、行動計画となる「栃木県第1期保安林整備実施計画」を策定し、計画に基づく取組を進めた。
さらに、県土の緑化を推進するため、18年度を初年度とする「第4次栃木県緑化基本計画」に基づき多様な緑化施策を総合的かつ計画的に実施した。
イ 木材利用の推進
木材の持つ炭素の貯蔵効果を発揮するため、「県有施設の木造・木質化に関する基準」に基づき、県発注の建築工事や土木工事において積極的に県産材を利用したほか、県有施設における木材利用の重要性を再認識するとともに、県の取組に対する県民の理解促進を図り、具体的な目標を示した4か年計画「県有施設等における木材利用推進行動計画(平成19年〜22年度)」を策定した。
また、市町村・学校法人等の施設整備や県民の住宅建築における県産材利用を促進した。