第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策
第4章 環境保全活動への積極的な参加
| 第1節 | 自主的な環境保全活動の促進 |
1 自主的な環境保全活動の状況
(1)県民等の環境保全の取組
平成19年度に実施した県政世論調査の結果では、地球温暖化などの地球環境について約62%が関心があると答えているなど、県民の環境問題に対する関心は高まっているが、環境保全のための取組については、特に取り組んだことはない方が36%、エコライフなどに取り組んだ方が約34%となっている。(図2−4−1)
また、環境活動団体の活動が活発化してきており、団体による自主的な環境保全活動等が各地で開催されている。これらの活動の多くは、広く県民が参加できるものであり、団体の活動は、県民への活動機会の提供の受け皿ともなっている。
図2−4−1 平成19年度県政世論調査結果
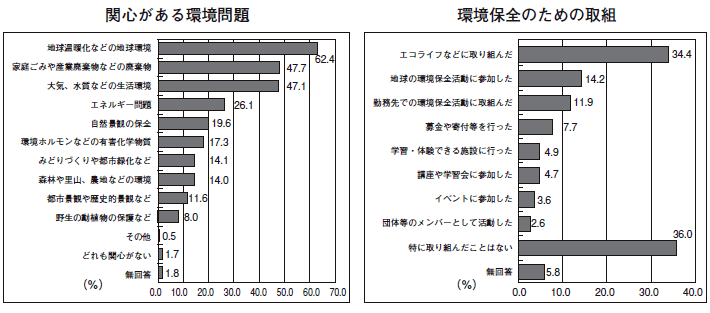
(2)環境マネジメントシステムの取組
企業が環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて自主的に取り組む、いわゆる「環境マネジメントシステム」は、今日の環境問題を解決していく上で大変有効な手法である。
8年9月には、その国際的な統一規格としてISO14000シリーズ(環境マネジメントシステム及び環境監査)が規格化された。また、16年11月にはISO14001の改正が行われ、環境への配慮に対する要求事項がより明確化された。
さらに環境省では8年より、中小事業者等の幅広い事業者が自主的に「環境への関わりに気づき、目標を持ち、行動することができる」簡易な方法を提供する目的で、環境活動評価プログラム(エコアクション21)を策定し、その普及を進めてきた。また、16年度には、エコアクション21の仕組みの見直しが行われ、新たな環境経営に対応するため認証登録制度に活用できるガイドラインへと改訂された。
近年、ISO14001の認証を取得する事業者等が増えてきており、20年3月末現在で、県内では363の事業者等が認証を取得している。また、「エコアクション21」も中小事業者等において取組が進んでいる。
(3)環境保全型農業の取組
農業生産の向上に、化学肥料や化学農薬の果たした役割は大きいが、一方でこれらの資材への過度の依存による環境への影響が心配されている。
また、消費者の安全・安心な農産物を求める声が高まる中で、環境保全に対する意識が強まっている。
こうしたことから、18年12月に策定した「栃木県環境保全型農業推進基本方針」に基づく4項目を柱として、農業生産を安定させながら、化学肥料・化学農薬の使用量を減らし、環境と調和した将来的にも持続可能な「環境保全型農業」の取組を推進している。
19年度末現在、環境保全型農業推進方針を策定している市町数は24市町(旧市町)であり、堆肥等を利用した土づくりと化学肥料、化学農薬の低減を一体的に行う農業生産方式を導入し、環境に配慮した農業に取り組む生産者(エコファーマー)は、20年3月末現在7,683名が認定されている。
2 自主的な環境保全活動の促進
(1)環境に配慮したライフスタイルの確立
- ア 環境保全団体との連携・協力
- 県民総ぐるみによる環境保全に向けた実践活動を促進するため、「とちの環県民会議」等の環境団体との連携・協力の下、各種普及啓発活動を推進している。
- イ 環境活動実践者への支援
- 県民一人ひとりの自主的な環境保全活動を促進していくためには、とちぎエコパートナーやとちぎエコリーダー、地球温暖化防止活動推進員等、地域におけるリーダーとして、自主的かつ積極的に様々な環境保全活動を実施している人材を支援するとともに、人材相互の交流・連携を促進していくことが重要である。このため、19年度は、以下の事業を実施した。
- (ア)とちぎエコパートナー制度の運営
- 県民の環境保全に関する知識を深め、県民と県との適切なパートナーシップの下、地域における自主的な環境保全活動を促進するため、地域住民に対する環境保全情報の提供や助言等を行う人材を登録する「とちぎエコパートナー制度」を運営している。19年度は、新たに30名を登録し、平成20年3月末現在で67名がとちぎエコパートナーとして活動している。
- (イ)環境活動実践者研修会の実施
- 地域において自ら環境保全活動や環境学習活動を実践している者に対し、環境の現状や環境問題に関する知識を深めるとともに、実践者同士の交流を深める機会を提供することにより、環境保全活動に取り組む人材や組織のネットワーク化を図ること目的として、研修会を開催した。
環境活動実践者研修会 19年11月11日(土) 於:総合教育センター27名参加
20年2月16日(土) 於:総合教育センター44名参加 - (ウ)パートナーシップだよりの発行
- 環境活動実践者に対し、様々な環境保全情報等を提供するため、パートナーシップだよりを発行した。(発行回数:7回)
(2)事業活動における環境保全活動の促進
- ア 環境マネジメントシステムの普及
- 環境マネジメントシステムの普及を図るためを図るため、19年度は以下の事業を実施した。
- イ 環境保全団体への助成等
- 事業者による環境保全への取組を促進するため、産業界における環境保全推進活動を行っている(社)栃木県産業環境管理協会が実施する事業に対して助成を行っている。
また、中小企業がISO14001の認証を取得するための経費について、環境保全資金による融資制度を設けている。
(3)環境保全型農業の推進
18年12月に策定した「栃木県環境保全型農業推進基本方針」に基づき、次の4項目を柱とした環境と調和のとれた農業を積極的に推進している。
○ 全ての農業者による農業環境規範の実践促進
○ 有機物資源を活用した土づくりの推進
○ 環境負荷を低減した農業生産の推進
○ 農業生産活動に伴う廃棄物の排出抑制とリサイクルの推進
また、環境保全型農業の普及啓発を図るため、生産者・農業団体等の取組の支援、消費者に対するPRを実施している。
19年度は、次の取組を行った。
ア 環境保全型農業に係る県推進指導事業
- (ア)エコファーマーの育成・支援
- 堆肥等を活用した土づくりと化学肥料、化学農薬の使用低減を一体的に行う農業生産方式を導入する生産者(エコファーマー)を育成し、土壌診断の実施や技術指導による農業生産方式の導入支援を実施している。また、啓発資料の作成や広報活動を通して普及啓発を行っている。
- (イ)化学農薬・化学肥料使用低減の推進
- 性フェロモン剤等の利用による効率的防除や土壌診断に基づく適正施肥等を推進するとともに、作物病害虫の生物的防除法の開発等の試験研究に取り組んでいる。
- (ウ)消費者交流事業の開催等
- 消費者・生産者双方の意識高揚と相互理解を促進するため、県民の日(6月)、農業試験場公開デー(9月)、とちぎ“食と農”ふれあいフェア(10月)等において、環境にやさしい資材、パネルの展示等を実施した。
また、環境保全型農業や食の安全等についての理解を促進するため、農業者と消費者を交えた講演会を開催した。
イ 堆肥の流通・利用促進
畜産部門と耕種部門の連携の下、堆肥の流通・利用の促進を図るため、県関係機関、市町、農協、堆肥センター等を構成員とする「栃木県堆肥利用促進協議会」を設立し、堆肥の生産技術の改善及び品質向上(堆肥共励会開催)、堆肥の流通・利用の促進、耕種農家のニーズの把握、堆肥の広域的な需給調整等の活動を行っている。
ウ 畜産経営の環境保全対策の推進
畜産経営による環境汚染問題は、経営の存続や畜産業の発展に重大な影響を与えることから、家畜ふん尿の適切な処理・利用により環境汚染を未然に防止し、畜産経営の健全な発展を図るため、「環境保全型畜産確立基本方針」に沿って、次のような畜産経営における環境対策の推進に努めている。
○ 家畜ふん尿の適正な処理と畜産農家・耕種農家の有機的連携による農地還元の推進
○ 家畜ふん尿処理機械・施設整備等の支援
エ 畜産経営の環境保全対策の指導
農業振興事務所ごとに県関係機関、市町、農協等の関係団体を構成員とする「地方協議会」を開催し、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排せつ物法)」の遵守に向け、次のような指導等を行っている。
○ 環境問題の発生状況等の実態調査
○ 畜産農家に対する環境保全意識の啓発
○ 畜産公害苦情・紛争処理に対する助言指導
○ 水質・臭気調査等の実施と調査結果に基づく農家指導
オ 環境保全に対する助成
適正な家畜ふん尿の処理・利用を推進するために、畜産農家が組織化し、又は畜産農家と耕種農家が連携して施設・機械等を整備するため次の畜産環境対策事業を実施した。(表2−4−1)
| 区分 | 資源リサイクル畜産環境整備事業 | バイオマス利活用フロンティア整備事業 | 畜産環境整備リース事業 (特別緊急対策) |
| 実施数 (件数) |
1市 (1) |
2市 (2) |
8市町 (14) |
カ 環境と調和のとれた生産技術の推進
化学農薬の使用を最小限に抑える総合的病害虫・雑草管理(IPM)を推進するため、総合的防除技術の開発や現地実証により、本県の実情を踏まえた環境にやさしい総合防除マニュアルを策定し、その普及を図っている。
○IPMマニュアルの普及啓発:水稲
○現地実証ほの設置によるIPMの実証:いちご、なし、トマト
また、土壌診断に基づく施肥や肥効調節型肥料の使用など、化学肥料の低減に繋がる適切な施肥技術の普及定着を図っている。
(4)行政の率先行動の推進 (注)詳細は、第3部第3章を参照のこと。
ア 県の自主的な環境保全活動
- (ア)栃木県庁環境保全率先実行計画に基づく取組
- 12年度に策定した「栃木県庁環境保全率先実行計画」に基づき、県の事務事業から排出する温室効果ガスの低減を図るため、環境保全活動(省エネルギー・省資源、廃棄物の減量等)を実施してきた。
17年度には、「栃木県庁環境保全率先実行計画〈二期計画〉」を策定し、引き続き取組を推進している。
また、18年度から県立がんセンターにおいてESCO事業を導入し、19年4月から運用を開始した。 - (イ)栃木県グリーン調達推進方針に基づく取組
- 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」及び「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、「栃木県グリーン調達推進方針」を13年7月から毎年度策定している。19年度は、17分類223品目について判断基準及び調達目標を定め、取組を実行した。
- (ウ)栃木県公共事業環境配慮指針に基づく取組
- 県の実施する公共事業について、より一層環境に配慮した取組を効果的、継続的に推進するため、19年3月に「栃木県公共事業環境配慮指針」を策定し、19年度から運用を開始した。
この指針では、県は、公共事業の実施に当たって、「栃木県環境基本計画」における4つの目標に即して環境配慮を行うこととしており、公共事業の種類ごとに環境配慮事項を示している。 - (エ)栃木県イベント環境配慮指針に基づく取組
- 県が実施するイベントにおける環境負荷の軽減等を図るため、19年2月に「栃木県イベント環境配慮指針」を策定し、19年度から運用を開始した。
具体的には、省エネルギー・省資源、廃棄物の発生抑制及びリサイクル、公共交通機関の利用等に関する環境配慮を行うこととしている。
イ 県庁のISO14001認証取得
県庁では、本庁、保健環境センター、宇都宮工業高等学校及び県北高等産業技術学校において、ISO14001の認証を取得している。
- (ア)本庁の取組
- 環境基本計画に基づく各施策や上記(1)ア〜エの取組をさらに推進するため、県庁(本庁)において「栃木県環境マネジメントシステム」を構築・運用し、20年3月14日にISO14001の認証を取得した。(登録番号:08ER・697)
a 取組経過 18年度 栃木県環境マネジメントシステム(EMS)の構築
環境方針の策定、公表【1月9日】19年度 EMSの運用開始【4月〜】
審査登録機関による審査を受審【1〜2月】
ISO14001の認証取得【3月14日】b EMSの概要 ○適用区域
栃木県本庁舎及び附属庁舎、警察本部庁舎
○主な実施事項
Plan(計画):環境目標、実施計画等の設定
Do(実行):環境活動の実践/職員研修の実施 等
Check(点検):運用状況の点検評価/内部監査の実施 等
Act(見直し):知事による総括評価/EMSの改定 等
○本県の特徴
- (イ)県保健環境センターの取組
- 県庁におけるモデルケースとして、12年10月27日にISO14001の認証を取得した。(登録番号:JSAE282)
a 適用区域
栃木県保健環境センター((財)栃木県環境技術協会及び(財)栃木県保健衛生事業団岡本水質食品検査所を含む)b 概要
保健衛生及び環境保全に係る試験検査等の事業活動において、省エネルギー、省資源、廃棄物の 適正管理・リサイクルの推進及び化学物質の適正管理の徹底などの環境保全活動に優先的に取り組むとともに、環境保全に関する調査研究、県民や事業者を対象とした環境保全への関心を深めるための事業を積極的に推進している。
18年10月27日に第2回登録更新となり、19年度の第2−1回の定期維持審査を経て、20年度は第2−2回の定期維持審査を受審、継続する予定である。