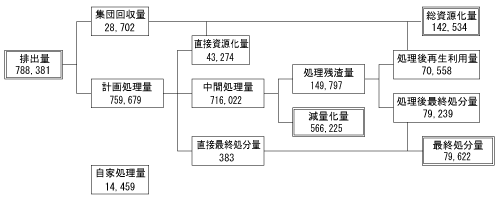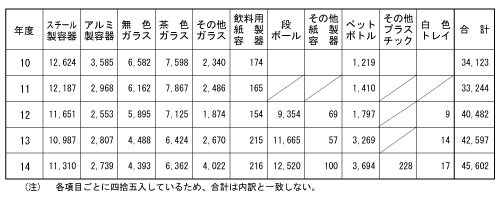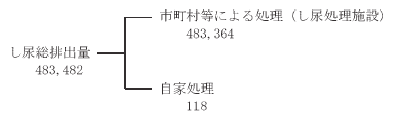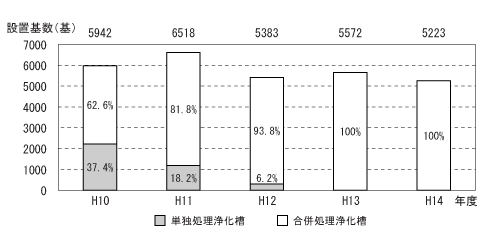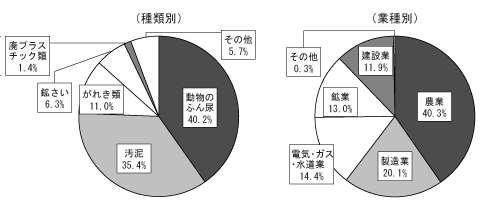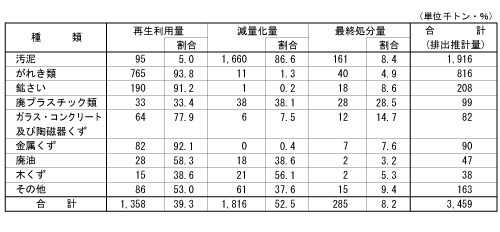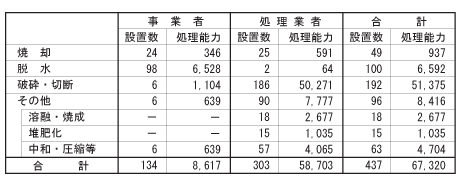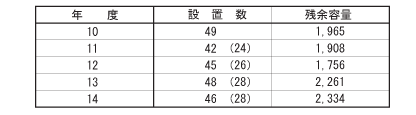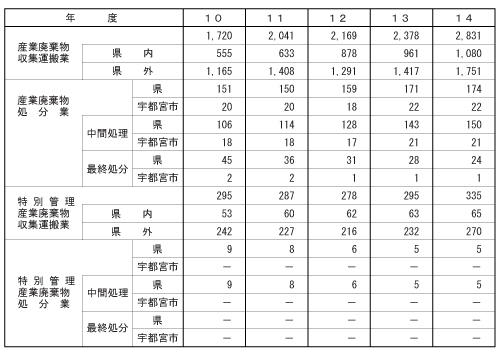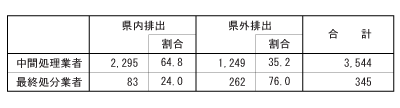|
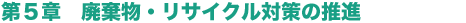
一般廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、市町村の固有事務となっている。
一般廃棄物は、家庭から排出されたごみ及びし尿が主体であり、収集されたごみ及びし尿の大部分は、市町村又は一部事務組合(以下「市町村等」という。)の処理施設で衛生的に処理されている。
14年度末におけるこれらの処理能力は、ごみ処理施設にあっては2,743t/日であり、し尿処理施設にあっては1,917kl/日である。
(1) ごみ処理
ごごみの総排出量は、年間約78万8千tにのぼり、集団回収された約2万9千tを除く約75万9千tが市町村等により処理されている。(図2−5−2)
図2−5−2 ごみ処理のフロー(14年度) (単位:t)
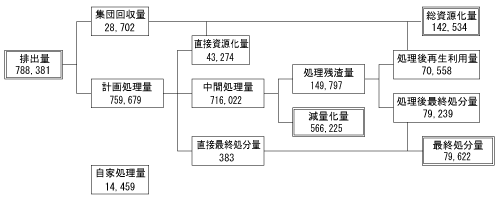
市町村等がごみ処理に要した年間の経費は、総額約385億円で、その内訳は、建設・改良費が約172億円(44.8%)であり、処理及び維持管理費は約204億円 (53.0%)となっている。
(2) 資源化・最終処分の状況
ごみの排出量788,381tのうち資源化された量は、市民団体等による回収で市町村が関与している集団回収が28,702t、市町村等から再生業者等へ直接搬入された直接資源化が43,274t、市町村等の中間処理施設における資源化が70,558tの合計年間142,534tであった。資源化されたものの大半は紙類、金属類、ガラス類で、全体の約9割を占める。
なお、排出量に占める資源化量の割合(再生利用率)は18.1%で、ここ数年頭打ちの状況にある。
最終処分量は79,622tで、排出量に占める割合(最終処分率)は10.1%で、この割合は年々減少している。(表2−5−1)
「容器包装リサイクル法」に基づく分別収集は、分別対象品目の差はあるものの県内全市町村で実施されており、45,602tが分別収集された。その他ガラス製容器、その他紙製容器、ペットボトルが増加傾向にあり、また、14年度は2市町でその他プラスチック製容器包装の分別収集が始まった。(表2−5−2)
表2−5−1 資源化・最終処分の状況
(単位:t)
| 年度 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 総排出量 |
725,987 |
731,053 |
757,362 |
771,078 |
788,381 |
| |
直接資源化量 |
− |
39,599 |
40,020 |
39,444 |
43,274 |
| 中間処理後再生利用量 |
103,318 |
63,935 |
69,323 |
70,324 |
70,558 |
| 集団回収量 |
30,576 |
27,885 |
29,100 |
30,485 |
28,702 |
| 総資源化量(率) |
(18.4%) |
(18.0%) |
(18.3%) |
(18.2%) |
(18.1%) |
| 133,894 |
131,419 |
138,443 |
140,253 |
142,534 |
|
最終処分量(率) |
(12.1%) |
(11.7%) |
(11.5%) |
(10.7%) |
(10.1%) |
|
87,808 |
85,490 |
86,989 |
82,541 |
79,622 |
(注)10年度以前は、直接資源化量は中間処理後再生利用量に含まれる。
表2−5−2 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量(単位:t)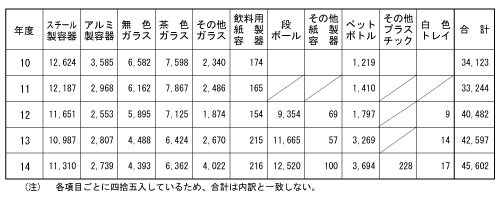
(3) し尿処理
14年度のし尿及び浄化槽汚泥の総排出量は483,482klであり、このうち483,364klが市町村の設置するし尿処理施設で処理されている。(図2−5−3)
図2−5−3 し尿処理の状況(14年度) (単位:kl)
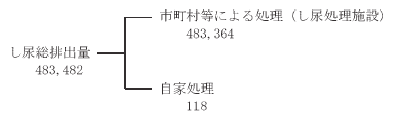
し尿処理に要した年間の経費は総額約73億円で、その内訳は、建設・改良費が約17億円(23.9%)であり、処理及び維持管理費は約53億円(72.7%)となっている。
(4) 浄化槽の設置状況
浄化槽は、毎年5〜6千基が設置されているが、13年4月から、し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽の設置が義務づけられ、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の新設ができなくなった。(図2−5−4)
図2−5−4 新設浄化槽設置状況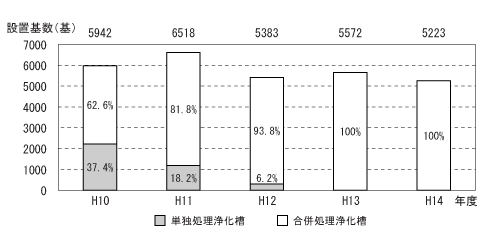
産業廃棄物は、事業活動に伴って排出される廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、汚泥、廃プラスチック類等20種類に分類されている。
産業廃棄物は、排出した事業者自ら処理することが原則であり、その処理を委託する場合には許可を有する業者に委託しなければならないこととなっている。
(1) 排出量と処理の状況
ア 排出量
1年間に産業廃棄物を1000t以上、特別管理産業廃棄物を50t以上排出する多量排出業者から徴収した実績報告等を基に推計した県内における14年度の総排出量は、約741万tである。
種類別では、動物のふん尿が約298万t(40.2%)で最も多く、次いで汚泥約263万t(35.4%)、がれき類約82万t(11.0%)、鉱さい約47万t(6.3%)、廃プラスチック類約10万t(1.4%)の順になっている。
業種別では、農業が約299万t(40.3%)で最も多く、次いで製造業約149万t(20.1%)、電気・ガス・水道業約107万t(14.4%)となっている。(図2−5−5)
図2−5−5 栃木県内から排出された産業廃棄物の推計量(14年度)
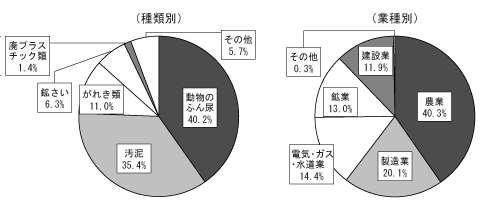
(注)各項目ごとに四捨五入しているため、合計は内訳と一致しない。
イ 再生利用率
品目毎の再生利用状況は、がれき類93.8%、金属くず92.1%が高い数値を示す反面、廃プラスチック類33.4%、木くず38.6%の再生利用率が低い。(表2−5−3)
農業・鉱業に係るものを除いた全体の数値は、10年度以降ほぼ同じ推移を示している。(表2−5−4)
なお、特に排出量の多い動物のふん尿については、従来から肥料(堆肥等)としての再生利用が行われてきたところであるが、一部で不適正な保管、処理が行われている。11年11月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が施行されたことにより、今後、堆肥としての利用と適正処理が一層促進されるものと期待される。
ウ 最終処分率
種類別では、ほとんどが10%未満だが、廃プラスチック類28.5%、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず14.7%については高い率となっている。(表2−5−3)
全体的には、10年度以降同じ率で推移している。(表2−5−4)
表2−5−3 産業廃棄物の種類別処理状況(農業・鉱業に係るものを除く)
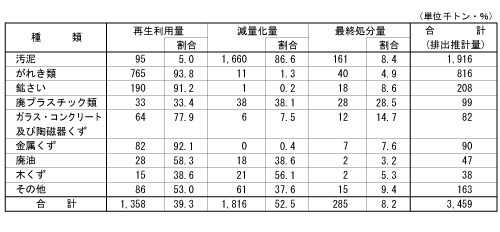
(注)1 この表は、11年度の実態調査及び14年度の多量排出事業者の実績値に基づく集計である。
2 各項目ごとに四捨五入しているため、合計は内訳と一致しない。
表2−5−4 産業廃棄物の年度別処理状況(農業・鉱業に係るものを除く)

(注)1 この表は、実態調査及び多量排出事業者の実績値に基づく集計である。
2 各項目ごとに四捨五入しているため、合計は内訳と一致しない。
(2) 産業廃棄物処理施設の設置状況
中間処理施設は437施設あり、事業者が設置しているものが134施設、処理業者が設置しているものが303施設である。事業者が設置しているのは、脱水施設98施設(6,528t/日)、焼却施設 24施設(346t/日)が中心となっている。処理業者は破砕・切断施設の186施設(50,271t/日)、焼却施設の25施設(591t/日)となっている。(表2−5−5)
安定型最終処分場は、14年度末現在46施設が設置されているが、残余容量があるものは28施設である。処理業者の報告等によれば残余容量は約233万m3であり、13年度末の約226万m3より7万m3増加した。
産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理施設等の設置にあたっては、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」に基づく事前協議及び廃棄物処理施設等協議会において、技術的な審査及び関係法令の調整を行っている。
表2−5−5 中間処理施設の設置状況
(単位:t/日)
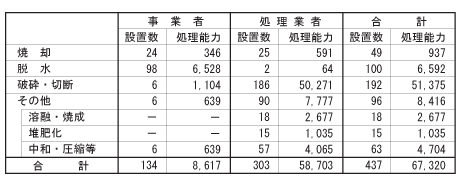
(注)事業者の設置数は廃棄物処理法の許可対象施設のみの数、処理業者の設置数は、許可対象外の施設数を含む。
表2−5−6 安定型最終処分場の設置状況 (単位:千m3)
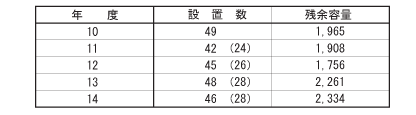
(注)11、12、13、14年度の設置数の( )書きは、残余容量のある処分場の数(内数)である。
(3) 産業廃棄物処理業の許可状況
産業廃棄物の収集・運搬、中間処理(焼却、破砕等)及び最終処分(埋立)の業を行おうとする者は、知事(宇都宮市長)の許可を受けなければならないこととされている。
15年3月末現在、栃木県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者は2,831業者で、そのうち1,080業者は、県内に主たる事務所を有する業者である。(表2−5−7)
また、栃木県内で産業廃棄物中間処理業の許可を有する者は171業者、産業廃棄物最終処分業の許可を有する者は25業者である。
(4) 産業廃棄物処理業者の処理実績
産業廃棄物処理業者の14年度の処理実績は次のとおりである。
ア 産業廃棄物処分業者実績
県内の中間処理業者が処理した産業廃棄物は約354万トンである。その内訳は、県内の事業者からの受託量が約229万トン、県外の事業者からの受託量が約125万トンとなっている。
県内の最終処分業者が処理した産業廃棄物は約34万トン。その内訳は、県内の事業者からの受託量が約8万トン、県外の事業者からの受託量が約26万トンとなっている(表2−5−8)。
イ 産業廃棄物収集運搬業者実績
産業廃棄物収集運搬業者によって県外から搬入された産業廃棄物は約115万トン(中間処理目的約102万トン、最終処分目的約13万トン)、一方、県内から県外に搬出された産業廃棄物は約64万トン(中間処理目的約59万トン、最終処分目的約5万トン)である。(表2−5−9)
表2−5−7 産業廃棄物処理業者の許可状況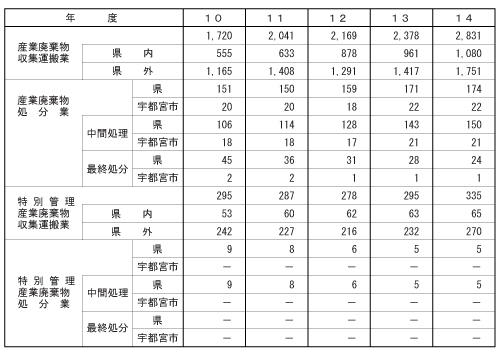
(注)1 収集運搬業については、県許可業者と宇都宮市許可業者のほとんどが重複していること
から、県許可業者数のみを計上した。
2 処分業については、県許可業者と宇都宮市許可業者数を計上した。
3 「県内」とは、主たる事務所が県内にある処理業者をいい、それ以外を「県外」という。
ただし、10〜11年度については統計処理の都合上、宇都宮市内の業者は県外に計上され
ている。
表2−5−8 処分業者の排出地域別処理実績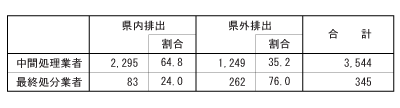
(注) 本表数値は産業廃棄物処理業者の実績報告に基づく。
表2−5−9 収集運搬業者の運搬地域別処理実績
|