第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策
第1章 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり
| 第6節 | 3Rの推進 |
1 廃棄物・リサイクルの状況
(1)一般廃棄物
ア 排出状況
18年度の県内の一般廃棄物(ごみ)の総排出量は約78万5千tと、前年度に比べ微減(約2千t)したが、ここ数年横ばいの状況にある。(図2−1−41)
図2−1−41 ごみの総排出量の推移 (単位:t/年)
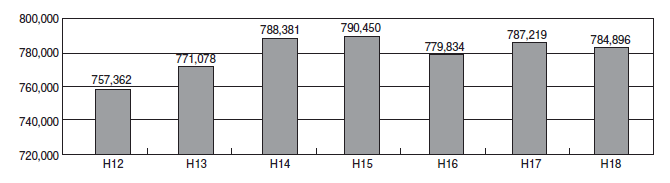
イ 資源化の状況
| (ア) | 18年度のごみの総排出量約78万5千tのうち資源化された量は、市民団体等による回収で市町村が関与している集団回収が約3万3千t、市町村又は一部事務組合(以下「市町村等」という。)から再生業者等へ直接搬入された直接資源化が約4万3千t、市町村等の中間処理施設における資源化が約6万6千tの合計年間約14万2千tであった。なお、資源化されたものの大半は紙類、金属類、ガラス類で、全体の8割を超える。(図2−1−42、表2−1−52) |
| (イ) | 「容器包装リサイクル法」に基づく分別収集は、分別対象品目の差はあるものの県内全市町で実施されており、約4万5千tが分別収集された。その他プラスチック製容器が増加傾向にあり、17年度は新たに延べ14市町で、無色・茶色・その他ガラス製容器、その他プラスチック製容器、飲料用紙パック、段ボールの分別収集が開始された。(図2−1−43、表2−1−53) |
図2−1−42 一般廃棄物の資源回収の状況及びごみの再生利用率の推移
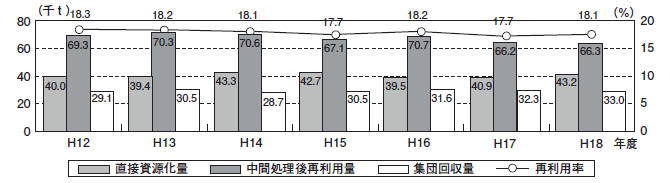
| 年度 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総排出量 | 757,362 | 771,078 | 788,381 | 790,450 | 779,834 | 787,219 | 784,896 | |
| 直接資源量 | 40,020 | 39,444 | 43,274 | 42,666 | 39,507 | 40,939 | 43,162 | |
| 中間処理後再利用量 | 69,323 | 70,324 | 70,558 | 67,070 | 70,688 | 66,179 | 66,263 | |
| 集団回収量 | 29,100 | 30,485 | 28,702 | 30,516 | 31,628 | 32,329 | 33,014 | |
| 総資源化量 | 138,443 | 140,253 | 142,534 | 140,252 | 141,823 | 139,447 | 142,439 | |
| 再利用率 | 18.3% | 18.2% | 18.1% | 17.7% | 18.2% | 17.7% | 18.1% | |
図2−1−43 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量の推移
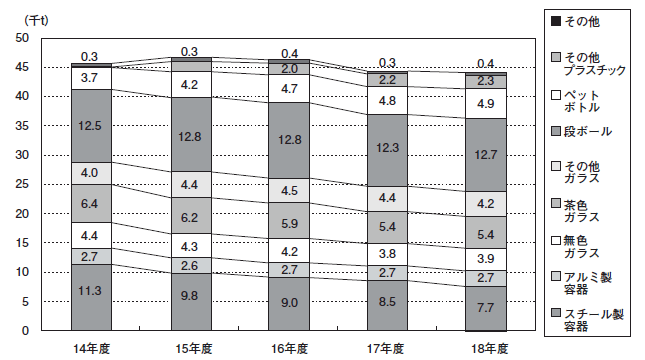
| 年度 | スチール製 容器 |
アルミ製 容器 |
無色 ガラス |
茶色 ガラス |
その他 ガラス |
飲料用 紙製容器 |
段 ボール |
その他 紙製容器 |
ペット ボトル |
その他 プラスチック |
白色 トレイ |
合計 |
| 14 | 11,310 | 2,739 | 4,393 | 6,362 | 4,022 | 216 | 12,520 | 100 | 3,694 | 228 | 17 | 45,602 |
| 15 | 9,806 | 2,601 | 4,275 | 6,208 | 4,435 | 206 | 12,752 | 117 | 4,212 | 1,973 | 23 | 46,609 |
| 16 | 9,039 | 2,722 | 4,169 | 5,931 | 4,511 | 212 | 12,839 | 125 | 4,742 | 2,032 | 22 | 46,344 |
| 17 | 8,504 | 2,746 | 3,829 | 5,432 | 4,376 | 181 | 12,307 | 124 | 4,776 | 2,248 | 20 | 44,542 |
| 18 | 7,685 | 2,694 | 3,883 | 5,436 | 4,245 | 206 | 12,672 | 141 | 4,940 | 2,347 | 23 | 44,271 |
(2)産業廃棄物
- ア 排出状況
- 1年間に産業廃棄物を1,000t以上、特別管理産業廃棄物を50t以上排出する多量排出業者から徴収した実績報告等を基に推計した県内における18年度の総排出量は、約906万t(17年度は約898万t)である。
また農業、鉱業を除いた産業廃棄物の排出量は、約401万t(17年度は約399万t)と推計される。(図2−1−44)
種類別では、汚泥が約374万t(41.3%)で最も多く、次いで動物のふん尿約298万t(32.9%)、がれき類約111万t(12.2%)、鉱さい約34万t(3.8%)、金属くず約19万t(2.1%)の順になっている。
業種別では、農業が約299万t(33.0%)で最も多く、次いで鉱業206万t(22.7%)、製造業約150万t(16.5%)となっている。(図2−1−44)
図2−1−44 栃木県内から排出された産業廃棄物の推計量(18年度)
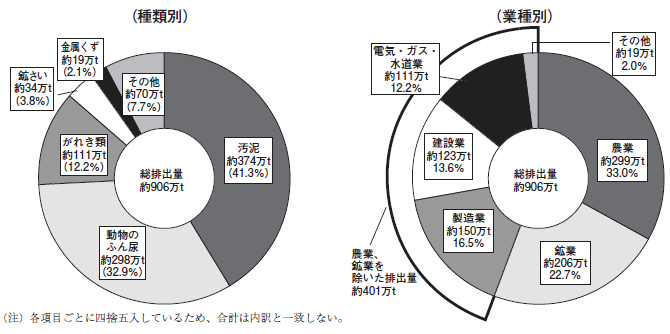
- イ 資源化の状況
- 18年度の再生利用率は53.6%であり、品目毎の再生利用状況は、鉱さい98.5%、金属くず98.2%が高い数値を示す反面、汚泥6.2%、廃プラスチック類44.0%の再生利用率が低い。(図2−1−45、表2−1−54) なお、特に排出量の多い動物のふん尿については、従来から肥料(堆肥等)としての再生利用が行われてきたところであるが、11年11月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が制定 され、16年11月1日から完全施行されたことにより、適正処理と堆肥としての利用が一層促進されることとなった。
図2−1−45 産業廃棄物総排出量と再生利用率の推移(農業・鉱業に係るものを除く。)
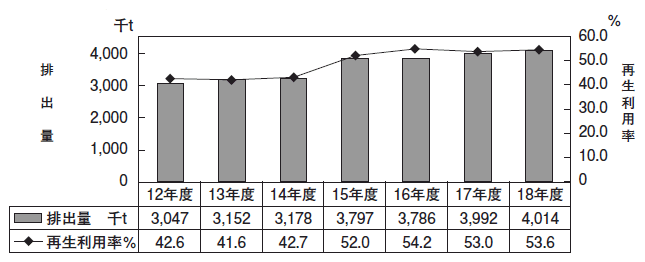
| 種類 | 再生利用量 | 減量化量 | 最終処分量 | 合 計 (排出推計量) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | 割合 | |||||
| 汚泥 | 106千t | 6.2% | 1,593千t | 92.9% | 16千t | 0.9% | 1,715千t |
| がれき類 | 1,079 | 97.7 | 5 | 0.4 | 21 | 1.9 | 1,105 |
| 鉱さい | 314 | 98.5 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 319 |
| 廃プラスチック類 | 51 | 44.0 | 39 | 34.2 | 25 | 21.8 | 115 |
| ガラス・コンクリート及び陶磁器くず | 68 | 79.1 | 0 | 0.2 | 18 | 20.7 | 86 |
| 金属くず | 185 | 98.2 | 0 | 0.1 | 3 | 1.8 | 189 |
| 廃油 | 35 | 54.4 | 28 | 44.0 | 1 | 1.6 | 64 |
| 木くず | 47 | 54.9 | 35 | 41.6 | 3 | 3.5 | 85 |
| その他 | 267 | 79.0 | 60 | 17.9 | 11 | 3.2 | 338 |
| 合計 | 2,150 | 53.6 | 1,716 | 43.9 | 102 | 2.6 | 4,014 |
| (注) | この表は、16年度の実態調査及び18年度の多量排出事業者の実績値に基づく集計である。 各項目ごとに四捨五入しているため、合計は内訳と一致しない。 |
図2−1−46 産業廃棄物の年度別処理状況(農業・鉱業に係るものを除く)
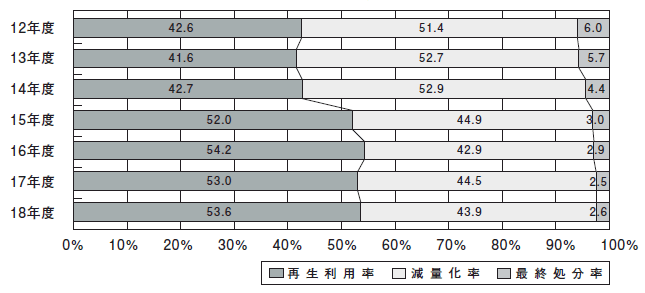
2 廃棄物・リサイクル対策
(1)循環型社会形成の総合的な推進
近年の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムやライフスタイルによって、廃棄物の増加や、これに伴う最終処分場の残余容量のひっ迫、不法投棄の増大、さらには地球温暖化など、深刻な環境問題が顕在化している。
この問題への対処として、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)のいわゆる「3R」を基本理念とし、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された「循環型社会」の形成が急務とされている。
このため、3Rを基本理念とする循環型社会の形成を今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向と位置付けた「循環型社会形成推進基本法」を始めとするリサイクル関連法が整備されている。
県では、本県における循環型社会形成の基本原則、役割分担、具体的な施策などを明示した「栃木県循環型社会推進指針」を15年3月に策定し、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。
(2)19年度におけるリサイクル関連法への主な取組
- ア 食品リサイクルへの取組
- 食品リサイクルに関わる施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、関係各課・各所の事業等取組状況等を集約し、今後の方向性について検討を行った。
- イ 建設リサイクルへの取組
- (ア)「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」における具体的施策の実施
- (イ)「再生材の利用基準」の改定(19年3月)
- 再生合材における再生骨材混入量及びエコスラグを使用する場合の混入量等を定めた。
- (ウ)普及啓発活動の継続実施
- 「建設リサイクル法」の周知徹底を図るため、各種啓発活動(リーフレット配布、講習会等)を実施した。
- (エ)現場パトロールの実施
適正な施行の指導を図るため、対象工事現場のパトロールを実施した。- 届出工事現場における分別解体の指導
- 未届工事の監視
- ウ 自動車リサイクルへの取組
- 17年1月に完全施行された「自動車リサイクル法」の適正な執行を図るため、自動車リサイクル法関連事業者(引取・フロン類回収・解体・破砕業者)に対して立入検査を実施し、指導を行った。 また、19年度は環境省からの依頼により、引取業者に対して使用済自動車のフロン類及びエアバッグ類に関する装備情報に対する調査及び指導を行った。 なお、一般ユーザーや関連事業者に対し、自動車リサイクル法の概要を周知するため、ポスターを掲示及びパンフレットを配布し、普及啓発活動を実施した。
| 種類 | 引取業 | フロン類回収業 | 解体業 | 破砕業 (破砕前工程のみ) |
破砕業 (破砕工程を含む) |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録・許可数 | 1,554 | 413 | 117 | 15 | 4 |
- エ エコスラグの有効利用促進への取組
- 一般廃棄物や下水汚泥から製造する溶融スラグ(エコスラグ)の品質基準や利用基準等を示す「栃木県エコスラグ有効利用促進指針」を20年3月に改定し、品質の確保されたエコスラグの有効利用を図っている。 県発注建設工事においては、アスファルト混合物の細骨材として利用できるよう「再生材の利用基準」を運用している。
(3)廃棄物の減量化・リサイクルの推進
一般廃棄物の質の多様化と量の増大に対応するため、ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発を進めるとともに、下水汚泥の資源化や建設副産物の再利用など各種の施策を行っており、19年度は次の取組を行った。
ア ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発
- (ア)マイ・バッグ・キャンペーンの展開
- 3R推進月間(10月)にキャンペーンを実施した。
- (イ)ごみ減量化・リサイクル演劇開催事業
- 次代を担う子どもたちのごみ問題に対する意識の高揚を図るため、ごみ減量化やリサイクルをテーマにした演劇を県内小中学校等で上演した。
演劇名:「田口さんとみょーな妖怪」
巡回公演:130回 約30,000人 - (ウ)ごみ減量化、リサイクル広報活動事業
- テレビ・ラジオのスポットCM等で県民にごみの減量化、リサイクルの推進について呼びかけた。
イ とちぎの3R推進支援事業費補助金
「栃木県循環型社会推進指針」で示した「とちぎの地域循環モデル」の構築促進と、本県における循環型社会の早期実現を目的として19年度に創設した。
19年度は1団体の取組(資源循環システム構築事業)に対して補助を行った。
- (ア)資源循環システム構築事業
-
事業内容: 廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用を推進し、持続可能な、新たな資源循環システムの構築を目的として実施される事業 補助対象者: 業界団体、2以上の事業者等で構成される協議会など 補助限度額: 1,500千円(補助率 1/2以内)
- (イ)普及啓発事業
- 事業内容:普及啓発事業
補助対象者:資源循環システム構築事業を採択を受けた者
補助限度額:500千円(補助率 1/2以内)
ウ 栃木県リサイクル製品認定制度
本県で発生した廃棄物等を原材料として製造されるリサイクル製品を「とちの環エコ製品」として県が認定し、その普及と使用促進を通して、廃棄物等の発生抑制と利用促進、リサイクル産業の育成を図り、本県の地域特性を活かした循環型社会の構築に寄与することを目的として16年度に創設した。認定は、実施要綱に基づく申請があり、同要綱に定める認定要件を満たした製品に対して行っている。(表2−1−56、2−1−57)
| 18年度末認定数 A |
19年度の認定状況 | 19年度末認定数 A+B+C-D-E-F |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規認定 B |
再認定 C |
認定辞退 D |
認定取消 E |
期間満了 F |
||
| 67 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 67 |
| 日用品 | 肥料 | 土壌改良材・ 緑化資材・培養土 |
造園材・ 園芸資材 |
建築用製品 | 路盤材 | アスファルト 混合物 |
盛土材・ 地盤改良材等 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 23 | 22 | 2 | 67 |
エ 下水汚泥の資源化
下水汚泥の有効利用を促進するため、下水道資源化工場を宇都宮市茂原に整備し、14年10月に供用を開始した。この工場は、県内の流域下水道及び公共下水道の終末処理場から発生する下水汚泥を集め、焼却溶融施設によりスラグを製造し、建設資材等として有効利用をするものであり、15年度から下水道管渠工事においてスラグの利用を開始している。
オ 建設副産物の再資源化
建設工事から発生するアスファルト・コンクリート塊等の建設副産物の再資源化・再利用を促進している。
18年度における栃木県内公共工事(県・市町村)の建設副産物の排出量及びリサイクル率は表2−1−58、表2−1−59のとおりである。
| 発注区分 | 建設発生土 (万m3) |
建設廃棄物 (万t) | |||||||
| コンクリート塊 | アスファルトコンクリート塊 | 汚泥 | 木材 | 混合廃棄物 | その他 | 計 | |||
| 公共工事 | 県事業 | 96.3 | 9.9 | 16.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 27.7 |
| 市町村事業 | 72.1 | 5.9 | 18.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 25.4 | |
| 計 | 168.4 | 15.9 | 34.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 53.1 | |
| 発注区分 | 建設発生土 | 建設廃棄物 | |||||||
| コンクリート塊 | アスファルトコンクリート塊 | 汚泥 | 木材 | 混合廃棄物 | その他 | 計 | |||
| 公共工事 | 県事業 | 94.3 | 99.8 | 99.9 | 60.1 | 68.0 (96.6) |
35.7 | 66.1 | 99.5 |
| 市町村事業 | 95.7 | 99.9 | 99.9 | 60.6 | 73.4 (96.6) |
33.3 | 90.9 | 99.4 | |
| 計 | 94.9 | 99.9 | 99.9 | 60.5 | 69.5 (96.6) |
34.5 | 85.3 | 99.4 | |
(注)表中の( )書き数字は、縮減(焼却減量等)を含めた数値である。
カ 栃木県グリーン調達の推進
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」及び「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、「栃木県グリーン調達推進方針」を13年7月から毎年度策定している。19年度は、17分類223品目について判断基準及び調達目標を定め、取組を実行した。
(4)バイオマス利活用の推進
バイオマスの現状と今後の利活用の取組方向や、県、市町村、県民、事業者等の役割などについて明らかにした「栃木県バイオマス総合利活用マスタープラン」に基づき、バイオマス利活用に関する県民などへの普及啓発活動を行った。
また、家畜排せつ物の有機質肥料としての流通・利用を促進するため、生産された堆肥の成分分析と生産履歴表示の促進等について支援を行っている。
さらに、バイオマスのエネルギー利用を促進するため、県酪農試験場に、家畜排せつ物や食品廃棄物から発生するバイオガスを電気エネルギー等に変換するバイオガス(メタン発酵)プラントを整備するとともに、メタン発酵後に発生する消化液の肥料利用技術の確立に向けた試験研究を実施している。
20年3月には、地球温暖化防止や原油高騰などを背景としたバイオ燃料への関心の高まりを踏まえ、県産バイオ燃料の実用化の推進及び関係機関等のバイオ燃料の取組を促進するため、「栃木県バイオ燃料実用化指針」を策定した。
このほか、県内の木材産業分野から発生する未利用木質残材の資源としての有効利用を進めるため、「栃木県木質資源循環利用推進指針」に基づき、木材乾燥用の熱源利用を図る木質焚きボイラー施設の設置及び周辺環境へ与える影響調査や検証への支援を行った。