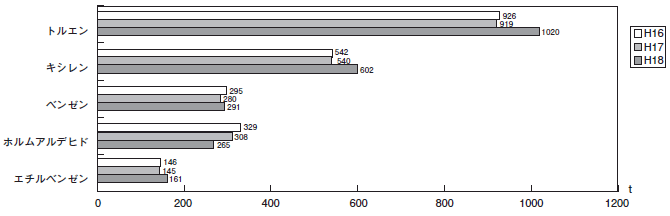第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策
第1章 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり
| 第5節 | 化学物質対策の推進 |
1 ダイオキシン類対策
(1)環境基準等
ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」により、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められている。(表2−1−43)
また、同法において、ヒトが生涯にわたって摂取し続けても許容される摂取量(TDI)は、1日当たりの摂取量として、体重1kg当たり4pg-TEQと定められている。
| 媒体 | 基準値 |
|---|---|
| 大気 | 年平均値 0.6pg−TEQ/m3N以下であること |
| 水質 | 年平均値 1pg−TEQ/l以下であること |
| 水底の底質 | 150pg−TEQ/g以下であること |
| 土壌 | 1,000pg−TEQ/g以下であること |
(2)環境汚染の現況
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気、水質、水底の底質及び土壌の汚染の状況について、常時監視を行っている。
19年度においては、大気16地点、水質(河川・地下水)90地点、水底の底質30地点及び土壌(一般環境)28地点でダイオキシン類の測定を行った。(表2−1−44)
| 調査対象 | 区分 | 調査地点数 | 測定結果 | 備考(調査地点数) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 | ||||
| 大気 (pg-TEQ/m3) |
16 | 0.016 | 0.13 | 0.043 | 0.046 | 県10地点、宇都宮市6地点 | |
| 水質 (pg-TEQ/l) |
河川 | 54 | 0..22 | 0.83 | 0.18 | 0.11 | 国2地点、県49地点、宇都宮市3地点 |
| 地下水 | 36 | 0.045 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 県29地点、宇都宮市7地点 | |
| 水底の底質 (pg-TEQ/g) |
河川 | 30 | 0.094 | 25 | 1.79 | 0.28 | 国2地点、県24地点、宇都宮市4地点 |
| 土壌 (pg-TEQ/g) |
28 | 0.096 | 99 | 6.0 | 1.9 | 県21地点、宇都宮市7地点 | |
ア 大気
19年度は、一般環境11地点、固定発生源周辺5地点の合計16地点で、年4回1週間の採取によるモニタリング調査を実施した。各調査地点の年平均値は、0.018〜0.073pg-TEQ/m3Nであり、全ての調査地点で環境基準(0.6pg-TEQ/m3N以下)を達成した。
10年度からの経年変化は、一般環境、固定発生源周辺とも減少傾向にある。(図2−1−34)
図2−1−34 ダイオキシン類濃度の推移(年平均値)
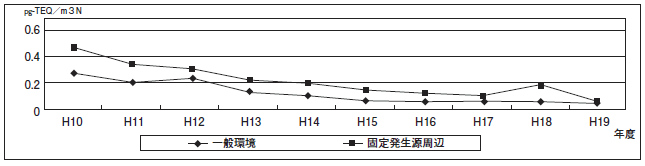
イ 水質
- (ア)河川
- 19年度は、54地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.022〜0.83pg-TEQ/lであり、全ての調査地点で環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成した。
- (イ)地下水
- 19年度は、36地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0. 045〜0. 048pg-TEQ/lであり、全ての調査地点で環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成した。
ウ 水底の底質
19年度は、河川30地点において底質の調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.094〜25pg-TEQ/gであり、全ての調査地点で環境基準(150pg-TEQ/g以下)を達成した。
エ 土壌
19年度は、一般環境28地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は0.096〜99pg-TEQ/gであり、全ての調査地点で環境基準(1,000pg-TEQ/g以下)を達成している。
(3)工場・事業場対策の推進
ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、常時監視と並行して「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく工場・事業場への立入検査を実施している。
表2−1−45 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設数(20年3月31日現在)
| (1) 大気基準適用施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 水質基準適用施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ウ 立入検査状況
- 19年度は、延べ107工場・事業場(県103、宇都宮市4)について立入検査を行い、ダイオキシン類の排出削減等について指導を行った。(表2−1−46)
県では12年度に県保健環境センターに測定施設を設置し、ダイオキシン類の検査体制を整備し、13年度から工場・事業場の行政分析を計画的に実施している。
行政分析の結果、19年度において、基準不適合施設が1件あり、改善対策を指導した。事業者が施設改善した上で、再測定した結果、排出基準に適合していた。(表2−1−47)
| 区分 | 実施数 | 備考(立入検査実施数) |
|---|---|---|
| 大気関係の特定施設を設置する工場・事業場 | 94 | 県91件、宇都宮市3件 |
| 水質関係の特定施設を設置する工場・事業場 | 13 | 県12件、宇都宮市1件 |
| 合計 | 107 |
| 区分 | 施設数(件) | ||
|---|---|---|---|
| 県 | 宇都宮市 | 合計 | |
| 大気実施数 | 21 | 3 | 24 |
| 不適合数 | 1 | 0 | 1 |
| 水質実施数 | 2 | 1 | 3 |
| 不適合数 | 0 | 0 | 0 |
- エ 事業者の自主測定結果
- 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者は毎年1回以上自主分析を行い、県(宇都宮市)に報告することが義務付けられている。
19年度の自主測定結果の報告状況は、19年4月1日〜20年3月31日の間に設置されていた施設(この間に廃止された施設も含む。)のうち、大気関係対象323施設(宇都宮市28)に対し242施設(宇都宮市22)、水質関係対象11事業場(宇都宮市3)に対し8施設(宇都宮市3)の報告があった。
19年度の報告結果については、排出基準超過が1件あり、改善対策を指導した。事業者が施設改善した上で、再測定した結果、排出基準を満足した。(表2−1−48)
表2−1−48 ダイオキシン類自主測定結果の報告状況(19年度)
| (1) 大気関係対象施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)( )は、宇都宮市の内数
| (2) 水質関係対象事業場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 | ( )は、宇都宮市の内数 |
| 2 | ダイオキシン類を含む汚水又は廃液の全量を下水道に排出したり循環使用することなどにより、公共用水域への排出がない特定事業場は、自主測定対象に該当しない。 |
2 化学物質管理対策
(1)背 景
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的として、11年7月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法)が公布された。
本法で定められたPRTR制度では、政令で定める354種類の化学物質(第一種指定化学物質)を取り扱い、かつ、政令で定める届出要件(業種、従業員数、取扱量)を満たす事業者は、1年間にどのような物質をどれだけ環境中へ排出したか、あるいは廃棄物としてどれだけ移動したかを県を経由し国へ報告することとなっている。
国はそれを集計し、家庭や農地、自動車などから排出される化学物質の量を推計し、合わせて公表することとなっている。
この制度により、事業者が、自らが排出している化学物質の量を把握することによって、化学物質排出量の削減への自主的な取組が促進されることが期待される。
また、PRTRデータを利用して、県民、事業者、行政が、化学物質の排出の現状や対策の内容等について、話し合いながら協力して化学物質対策を進めていくことが期待されている。
(2)環境中の現況
ア 大気環境
大気環境中における化学物質の存在量を把握するため、19年度は、有害大気汚染物質の優先取組物質(22物質)のうち、8物質について、県内8地点で月1回24時間の採取により、年間を通じて調査を実施した。(表2−1−49)
測定結果は、概ね環境省の全国調査結果による検出濃度範囲内であった。
| 物質名 | 年間平均値の濃度範囲 | 物質名 | 年間平均値の濃度範囲 |
|---|---|---|---|
| アセトアルデヒド | 1.4〜3.5μg/m3 | 酸化エチレン | 0.066〜0.10μg/m3 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.62〜0.94μg/m3 | ベリリウム及びその化合物 | 0.0094〜0.029μg/m3 |
| ベンゾ[a]ピレン | 0.12〜0.33μg/m3 | ホルムアルデヒド | 2.7〜3.8μg/m3 |
| クロム及びその化合物 | 1.3〜4.3μg/m3 | マンガン及びその化合物 | 11〜26μg/m3 |
イ 水環境
水環境中における化学物質の存在量を把握するため、19年度は、化学物質排出把握管理促進法対象物質の中から5物質を選定し、県内河川の31地点において調査を実施した。(表2−1−50)
測定結果は、概ね環境省の全国調査結果による検出濃度範囲内であった。
| 水系 | 河川名 | 地点 | ポリオキシエチレン アルキルエーテル(C12) |
2−アミノエタノール | ポリオキシエチレンノ ニルフェニルエーテル |
エチレンジアミン 四酢酸塩 |
| 那珂川 | 那珂川 | 恒明橋 | 0.07 | <1 | <0.01 | <2 |
| 那珂川 | 黒羽 | 0.03 | <1 | <0.01 | 4 | |
| 那珂川 | 川堀 | 0.01 | 2 | <0.01 | 5 | |
| 箒川 | 箒川橋 | 0.08 | <1 | <0.01 | 9 | |
| 荒川 | 向田橋 | 0.03 | <1 | <0.01 | 6 | |
| 余笹川 | 川田橋 | 0.32 | <1 | <0.01 | <2 | |
| 蛇尾川 | 宇田川橋 | 0.34 | 3 | 0.02 | <2 | |
| 内川 | 旭橋 | 0.36 | <1 | 0.08 | 3 | |
| 鬼怒川・小貝川 | 鬼怒川 | 佐貫 | 0.06 | <1 | <0.01 | 16 |
| 鬼怒川 | 鬼怒川橋 | 0.03 | <1 | <0.01 | 13 | |
| 鬼怒川 | 川島橋 | <0.01 | 3 | 0.09 | 19 | |
| 田川 | 明治橋 | 0.01 | 1 | <0.01 | 47 | |
| 江川 | 高宮橋 | 0.18 | <1 | 0.37 | 14 | |
| 五行川 | 高畦橋 | 0.11 | <1 | <0.01 | 10 | |
| 大谷川 | 開進橋 | 0.03 | <1 | <0.01 | <2 | |
| 赤堀川 | 木和田島 | 0.95 | <1 | 2.6 | 26 | |
| 田川 | 梁橋 | 0.16 | 2 | 0.06 | 86 | |
| 渡良瀬川 | 姿川 | 淀橋 | 0.29 | <1 | 0.39 | 7 |
| 黒川 | 御成橋 | 0.09 | <1 | <0.01 | 3 | |
| 渡良瀬川 | 葉鹿橋 | 0.24 | <1 | 0.21 | 19 | |
| 渡良瀬川 | 新開橋 | 0.25 | 2 | 0.83 | 51 | |
| 松田川 | 末流 | 0.19 | <1 | 8.5 | 44 | |
| 袋川 | 袋川水門 | <0.01 | 3 | 0.31 | 170 | |
| 旗川 | 末流 | 0.60 | 2 | 1.3 | 18 | |
| 才川 | 末流 | 0.41 | 2 | 0.05 | 10 | |
| 秋山川 | 末流 | <0.01 | 2 | 0.94 | 220 | |
| 出流川 | 末流 | 0.73 | 2 | 0.80 | 21 | |
| 三杉川 | 末流 | 9.1 | <1 | 0.75 | 13 | |
| 永野川 | 落合橋 | 0.15 | <1 | 0.20 | 33 | |
| 巴波川 | 巴波橋 | 0.11 | <1 | 0.29 | 34 | |
| 思川 | 乙女大橋 | 0.24 | <1 | 0.07 | 15 |
(3)リスクコミュニケーションの推進
県民、事業者、行政による化学物質に関するリスクコミュニケーションを推進するため、本県では、事業者や県民の代表者、学識経験者、行政から構成する「化学物質に係るリスクコミュニケーションのあり方検討会」を設置し、リスクコミュニケーションの進め方などに関する報告書を16年12月に取りまとめた。
19年度は、県民などを対象とした「化学物質セミナー-私たちの生活と化学物質・化学物質と上手につきあうために-」を開催した。
(4)PRTR制度による排出量の把握
ア 届出件数
「化学物質排出把握管理促進法」に基づく18年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出事業所数は、表2−1−51のとおりであり、本県は全国の約2.1%を占めている。
| 年度 | 栃木県 | 全国 |
|---|---|---|
| 16 | 753 | 40,341 |
| 17 | 804 | 40,823 |
| 18 | 878 | 40,980 |
イ 環境への排出量
18年度の県内の届出排出量と推計排出量を合わせた総排出量は、14,311t(17年度は14,943t)である。届出排出量は全体の56%(同56%)を占め、それ以外から排出される推計排出量は44%(同44%)であった。(図2−1−35)
届出排出量の内訳は、大気への排出99%(同99%)、公共用水域への排出1%(同1%)であった。
発生源別の内訳をみると、事業所(製造、販売、サービス業、農業等)からの排出割合が74%(同76%)、家庭から7%(同7%)、自動車等から19%(同17%)であった。
なお、これらの数値については、全ての事業者を対象としていないことや、推計により算出したものも含まれていることなどから、その精度に一定の限界があることに留意する必要がある。
図2−1−35 発生源別割合(届出・推計)(18年度)
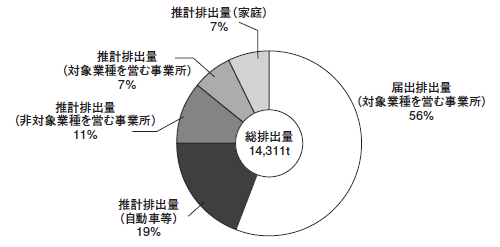
(ア)届出排出量
- a 大気への排出量
- 県内の事業所から届出のあった大気への排出量7,962t(17年度は8,287t)の上位5物質を図2−1−36に示す。排出量の多い物質の主な用途は次のとおりである。
(a)トルエン:塗料やインキの溶剤、ガソリン成分、合成原料
(b)キシレン:塗料の溶剤、ガソリン・灯油成分、合成原料
(c)ジクロロメタン(別名 塩化メチレン):金属脱脂の洗浄剤
図2−1−36 大気への排出量(届出)(16〜18年度推移)
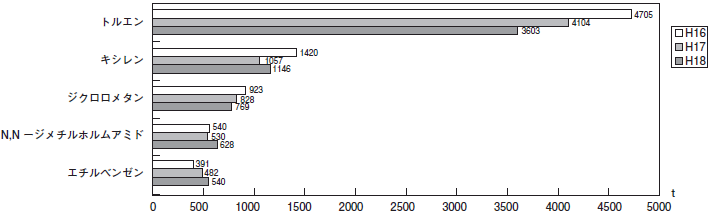
- b 公共用水域への排出量
- 県内の事業所から届出のあった公共用水域への排出量93t(17年度は86t)の上位5物質を図2−1−37に示す。排出量の多い物質の主な用途は、次のとおりである。
(a)ふっ化水素及びその水溶性塩:金属・ガラスの表面処理剤
(b)ほう素及びその化合物:ガラス添加剤、消毒剤
(c)亜鉛の水溶性化合物:乾電池、金属表面処理剤
図2−1−37 公共用水域への排出量(届出)(16〜18年度推移)
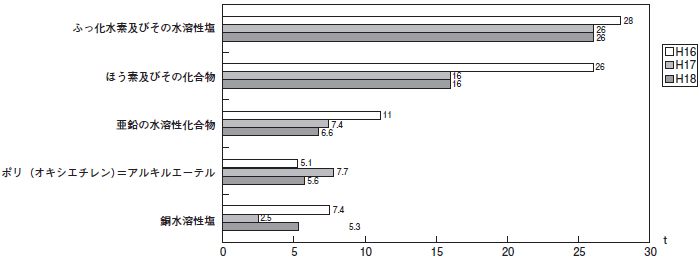
- c その他
- 土壌への排出及び届出事業所における埋立はなかった(17年度もなし)。
(イ)推計量
- a 届出の必要のなかった事業所からの推計排出量
- 届出要件(業種、従業員数、取扱量)を満たしていないために、届出をする必要のなかった事業所からの推計排出量2,605t(17年度は2,931t)の上位5物質を図2−1−38に示す。
排出量の多い物質の主な用途は、次のとおりである。
(a)トルエン:塗料やインキの溶剤、ガソリン成分、合成原料
(b)キシレン:塗料の溶剤、ガソリン・灯油成分、合成原料
(c)トリクロロニトロメタン:農薬
図2−1−38 届出の必要のなかった事業所からの推計排出量(推計)(16〜18年度推移)
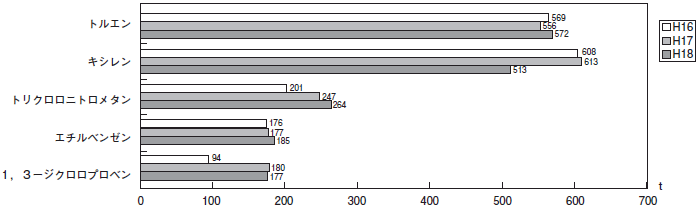
- b 家庭からの排出量
- 県内の家庭からの推計排出量967t(17年度は1,073t)の多い上位5物質を図2−1−39に示す。排出のあった物質の主な用途は、次のとおりである。
(a)ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル:界面活性剤(洗剤成分)
(b)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:界面活性剤(洗剤成分)
(c)p‐ジクロロベンゼン:衣類用防虫剤
図2−1−39 家庭からの排出量(推計)(16〜18年度推移)
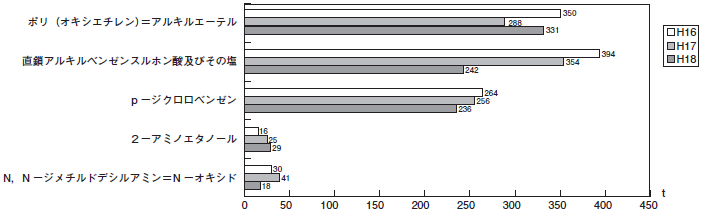
- c 自動車等からの排出量
- 県内の自動車等(自動車・二輪車・特殊自動車等)からの排ガスに含まれる推計排出量2,681t(17年度は2,565t)の多い上位5物質を図2−1−40に示す。
図2−1−40 自動車等からの排出量(推計)(16〜18年度推移)