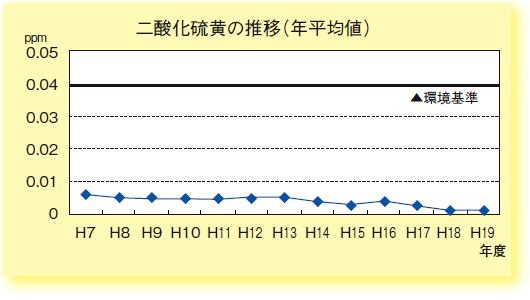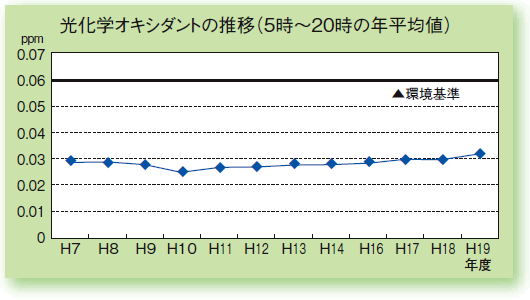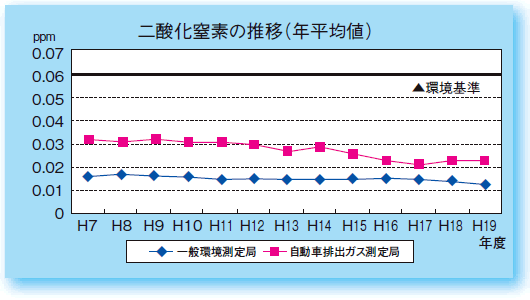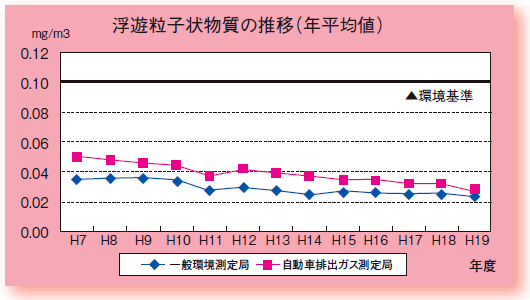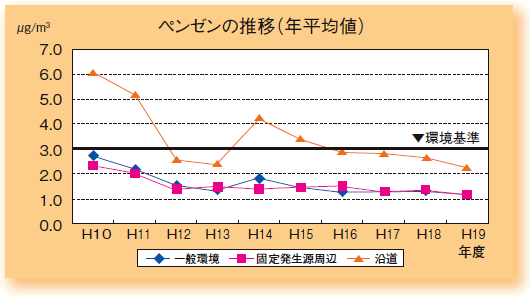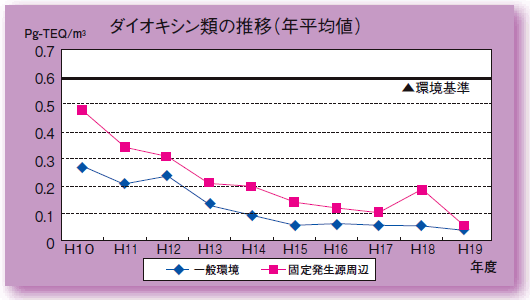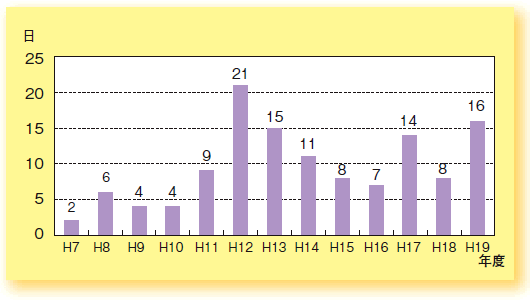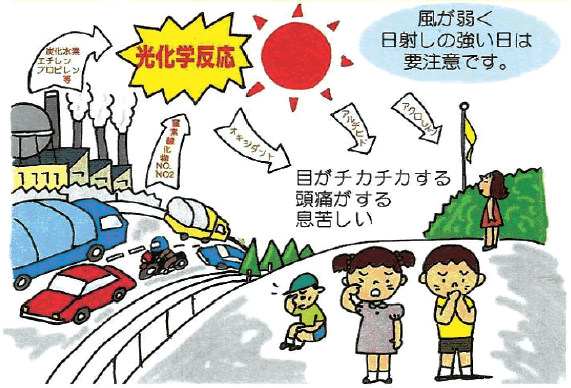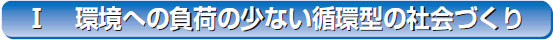
私たちは、これまで、自然から多くの資源を採取し、それを利用し、不用となった様々なものを自然の中へ排出することにより、社会経済活動を行ってきました。
しかし、今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会がもたらす環境への負荷の増大は、自然の持つ再生能力や浄化能力を超え、都市・生活型の公害や地球環境問題の発生を招いています。
このため、生産、流通、消費、廃棄等、社会経済活動の様々な段階を通じて、汚染物質や廃棄物の発生を抑制し、資源の循環的な利用を進めるとともに、廃棄物の適正利用を図ることなどにより、自然の物質循環に与える影響をできるだけ抑えた「環境への負荷の少ない循環型の社会づくり」を目指します。
1 大気環境の保全
1 大気環境の状況
- 県内の大気環境の状況は、概ね良好です。
- 環境基準が定められている10物質のうち、光化学オキシダント以外の物質については、すべての測定局で環境基準を達成していました。
- 光化学オキシダントは全国的にも環境基準の達成率は低い状況にあり、本県ではすべての測定局で環境基準を達成していません。
- 光化学スモッグの注意報発令日数は16日で、7月に1回、県南部で目やのどの痛みを訴える健康被害がありました。
大気の環境基準
人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及びダイオキシン類の10物質について環境基準が定められています。
○二酸化硫黄燃料中の硫黄の燃焼で発生し、ぜんそく等の原因になります。 |
○光化学オキシダント |
○二酸化窒素物が燃焼する際に、空気中及び燃料中の窒素から発生し、肺に害を与えます。 |
○浮遊粒子状物質大気中に長時間浮遊し、気道や肺に害を与えます。 |
○ベンゼン化学工業製品の合成原料などとして使われているほか、ガソリンにも含まれており、発がん性を有することが認められています。 |
○ダイオキシン類物の燃焼の過程などで生成する物質であり、環境中に広く存在していますが、量は非常にわずかです。 |
光化学スモッグ注意報発令日数の推移 |
光化学スモッグの仕組み |
2 大気環境保全対策
1 自動車排出ガス対策の推進
- 自動車排出ガスによる影響を把握するため、自動車排出ガス測定局で常時監視を行っています。
- 「エコドライブ」や「アイドリングストップ」の普及のため、県民への啓発や運輸関係業界・大規模駐車場設置者への呼びかけを行っています。
- ディーゼル自動車対策として、DPF等の粒子状物質減少装置装着に対し、融資を行っています。
- 奥日光でハイブリッドバスを運行しているほか、公用車に天然ガス自動車やハイブリッド自動車を計画的に導入しており、19年度には、5台を導入しました。
- 公共交通の活性化のため「とちぎ公共交通ネットワーク形成基本指針」を策定しました。
- 公共交通機関の利用促進のため、子ども向けに副読本を作成しました。また、毎月1日と15日を「バス・鉄道利用デー」と定めて呼びかけを行っています。
- 宇都宮市が取り組んでいる新交通システムの成立性・実現性の検討について、積極的に支援しています。
2 広域大気汚染対策の推進
- 二酸化硫黄、窒素酸化物等について、県内36カ所の測定局において常時監視を行い、大気環境情報システムにより測定データをリアルタイムで発信しています。
- 光化学スモッグによる被害を未然に防止するため、光化学スモッグ予報を関係市町、報道機関、協力工場等に通報するほか、緊急時には注意報などを発令し、県民への周知や工場に対するばい煙排出削減の要請を行っています。
3 有害大気汚染物質対策の推進
- 工業団地周辺など県内8地点でモニタリング調査を行っています。
4 工場・事業場対策の推進
- 工場などから排出される有害物質(塩素、塩化水素、ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素)については、「大気汚染防止法」による全国一律の基準に加えて、県の条例でより厳しい基準を定めて規制を行っています。
- 工場などに対して立入検査を実施するほか、ばい煙等の自主測定や結果の報告を求めるなど、施設の適切な維持管理が図られるよう指導しています。
- 吹付けアスベストを使用した建物等の解体時には、立入検査等により、適切な飛散防止措置等が図られるよう指導しています。