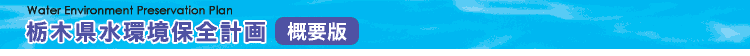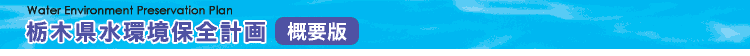|
県全域の年間降水量は約97億m3で、そのうち33%にあたる約32億m3が蒸発散し、12%にあたる約12億m3が地下に浸透し、55%にあたる約53億m3が河川に流出している。河川からの県外への流出量は、那珂川水系約24億m3、鬼怒川水系約17億m3、渡良瀬川水系約19億m3の計約60億m3で、群馬県からの渡良瀬川水系への流入量は約7億m3である。
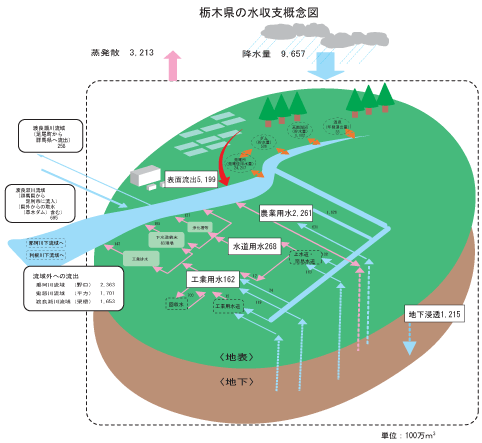
>>拡大<<
(1)河川
河川の有機性汚濁の指標であるBODの環境基準達成率の経年変化をみると、年によって変動はあるものの、県全体の水質は改善傾向にある。
(2) 湖沼
中禅寺湖は面積11.5km2、最大水深163m、湖水の滞留日数は約6年で、貧栄養湖に属している。過去5年間の状況を見ると、COD、全りんは環境基準を達成していない。
湯ノ湖は面積0.35km2、最大水深14.5mで、湖水の滞留日数は約30日で水深も浅く、富栄養化しやすい湖沼といえる。近年では、全窒素、全りんはほぼ横ばいで推移している。
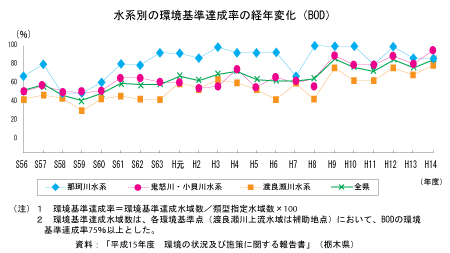
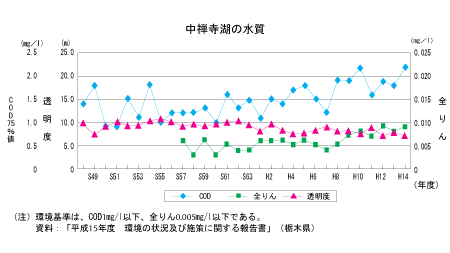
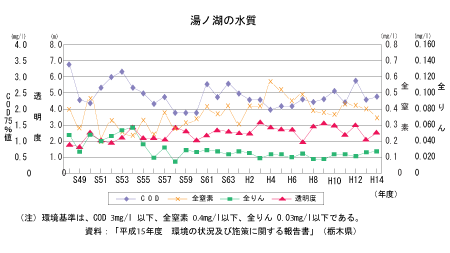
(3) 生活排水処理の状況
公共下水道、農業集落排水施設及び浄化槽等を合わせた汚水処理人口の普及率は、平成14年度末で63.2%と前年度末に比べ2.8%増加したものの、全国平均75.8%に比べ普及が遅れている。
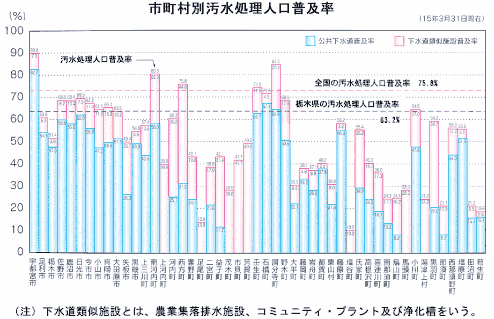
>>拡大<<
(1)土地利用の変化
本県の昭和50年と平成13年の土地利用の変化を県土の総面積に占める割合でみると、森林及び農用地面積が減少し、道路(一般道路、農道、林道)、宅地(住宅・工業用地等)が増加している。
(2)流域の保水性
那珂川(野口)、鬼怒川(平方)、渡良瀬川(藤岡)の3地点について、降雨日前日を100とした場合の降雨後の河川流量の変化を過去と比較した。那珂川では30年前と現在とで流出パターンがほとんど変化していないのに対し、鬼怒川及び渡良瀬川の下流では降雨後の流量が増加している。
森林や農地の持つ雨水の貯留・浸透力が減少し、道路、宅地の増加により不浸透域が拡大するなど、都市化の進展により、流域の保水性が低下している傾向がうかがえる。
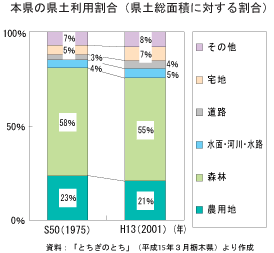
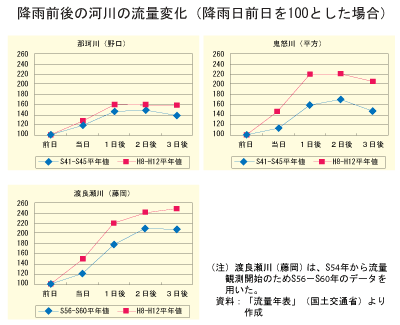
河川水辺の国勢調査(平成11年国土交通省)では、那珂川は29種、鬼怒川は34種、渡良瀬川は26種の魚類が確認されている。希少種では、ミヤコタナゴやホトケドジョウ等が確認されている。
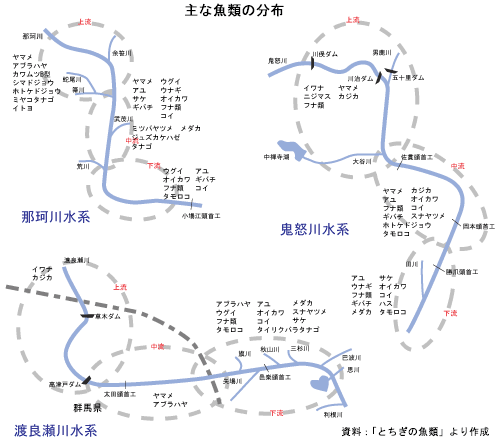
県内各地に、水に関わりを持つ神社や祭りなどが多くある。地域に根ざした文化として、まちづくりや水環境保全意識の高揚のため、保存、継承していくことが重要である。
|