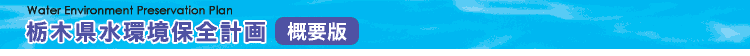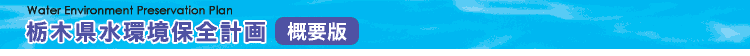|
(1)水循環の視点
水は、地表から蒸発した水蒸気が雨となって地表に降り、一部は地下水となり、一部は表流水となって川を流れ海に至るという循環を繰り返している。
この水循環が、自然の営みや人間の活動に必要な水量の確保のみならず、水質の浄化、多様な生態系の維持といった水環境を良好に保つための基盤となっているということを理解した上で、水環境の保全に取り組んでいくことが重要である。
(2)水環境を総合的にとらえる視点
水環境は、人や生物に普遍的な恩恵を与えるとともに、それぞれの地域で固有の価値を有し、固有の役割を担っている。また、人の暮らしや産業を支える基盤であるとともに、人にやすらぎを与えたり地域の文化の核となるなどの多面性を有している。このため、水環境を考えるに当たっては、水質、水量等といった構成要素を個々に独立してとらえるのではなく、全体として総合的にとらえることが重要である。
(3)流域を基本単位とする視点
水環境の保全のため、上流から下流への面的な広がり、表流水と地下水を結ぶ立体的なつながりを考慮し、流域全体を総合的にとらえるという視点が重要である。
また、私たち栃木県民は、水源県に暮らしているということを日々の生活の中で意識しながら、下流域にきれいな水を送るなどの責任を果たす必要がある。そして、水源県は、治水、利水、水源かん養等に重要な役割を果たしていることから、利益を享受する下流域の自治体等と一体となって流域全体の水環境の保全に取り組んでいく必要がある。
(1)健全な水循環を確保する
健全な水循環とは、生活や生産に必要な水の利用、水質の浄化、生物の生育・生息、気候の緩和等、自然の水循環がもたらす恩恵が基本的に損なわれていない状態をいい、この状態を将来にわたって永続的なものとしていくことが重要である。
(2)水環境への負荷を減らす
生活や生産活動から生じる排水等による汚濁物質を低減していくとともに、節水対策や循環利用、雨水・地下水のかん養などを総合的に進め、「節水型社会」を目指すことが重要である。
(3)生物多様性に配慮する
土地利用や社会基盤等の整備に当たっては、生物の生育・生息環境としての水や水辺の機能の保全、回復に配慮していくことが重要である。
(4)パートナーシップを築く
水環境の保全に関する取組を総合的かつ体系的に展開していくため、県民、事業者、民間団体及び行政等の関係者が、お互いの理解を深めながら、今日の水環境に関する課題と将来の目標に対して共通認識を持ち、相互に連携、協力して取り組んでいくことができるようパートナーシップを構築していくことが重要である。
水環境保全の理念の実現のため4つの基本目標を掲げる。
水質の保全を図るため、可能な限り水環境への汚濁物質負荷量を低減していくとともに、各般の取組を推進し、きれいで安全な水を将来に引き継いでいくことを目指す。
○公共用水域の環境基準(BOD)達成率
生活環境項目に関する環境基準の設定されている水域について、環境基準が達成されていない場合はその向上及び達成を目指し、達成されている場合は引き続き水質を良好に保つことにより、全県的な環境基準の達成率を上げる。
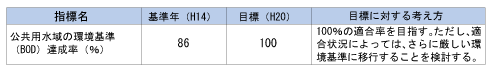
○汚水処理人口普及率
公共用水域への生活排水による汚濁物質の排出削減の観点から、公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の普及向上を目指す。
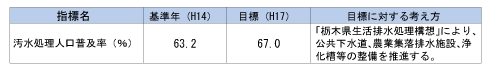
○水道普及率
一人でも多くの県民が安全で良質な水道水の供給が受けられるようにする。
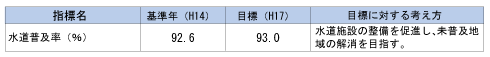
日常生活や事業活動において水の有効利用に取り組んでいくととともに、水源のかん養に重要な役割を果たしている森林、農地等の保全に努める。また、都市化の進展等により雨水の浸透域の減少した市街地等においても地下水のかん養に配慮したまちづくりを目指す。
○工業用水使用量(1日当たり)に占める回収水の利用割合
工業用水の使用量のうち、一度使用した水を再利用する回収利用(回収水)を進め、水道水や井戸水等から新たに取水する補給水の量を低減するなど、水の合理的利用を促進する。
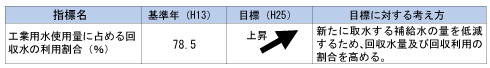
○保安林の指定面積
水源かん養機能を高めるため、水源地域の保安林の指定面積を拡大する。
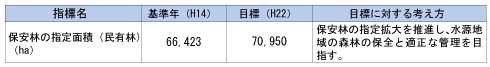
○水源地域における森林整備面積
水土保全林等については、適切な森林整備を進め、その機能の維持増進を図る。
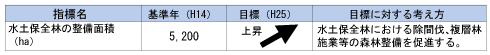
○平地林の整備面積
減少や荒廃等が見られる平地林を保全するため、地域住民と市町村の連携、協力により、平地林での下草刈りや休憩施設の整備等を進める。
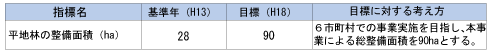
|
基本目標3 生き物が息づく水辺を守り、人々のふれあいを築く |
地域固有の動植物や生態系を保全しつつ社会基盤を整備し、次世代においても人々が水環境を身近なものと感じ、気軽に水と親しむことのできる場所として、地域の特性に配慮した水辺づくりを目指す。
○親水性のある水辺空間の整備面積
地域のまちづくりと調和したうるおいと安らぎのある水辺を創出する。
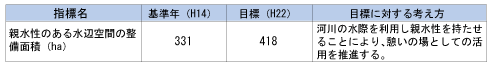
○自然公園等の地域指定面積
自然公園法、自然環境保全法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、県立自然公園条例、自然環境の保全及び緑化に関する条例、とちぎふるさと街道景観条例等に基づき、景観や自然環境の保全を図ることとした地域を適正に管理していく。
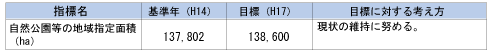
○メダカの生息地数
水辺生態系の健全性を確保していくことが重要である。このため、農村地域の魚類の象徴であるメダカを一つの指標として、今後の動向に配慮していく。
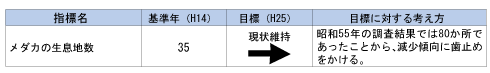
|
基本目標4 みんなが水環境づくりに参加する体制をつくる |
水環境を学ぶ機会の充実や水環境の保全活動に関する体制の整備に努め、県民、事業者、民間団体、行政等のすべての主体の参加と協働により、流域全体を考えながら足下から行動していくことを目指す。
○指導者の養成
自然と親しんだり、水環境の保全活動に参加する県民を増やすため、指導者の養成を行う。
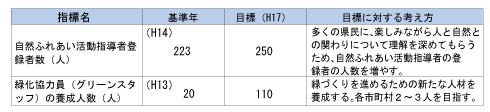
○森林ボランティア登録制度による活動件数
森林ボランティアによる活動に参加する県民を広報誌やホームページ等で募集する。
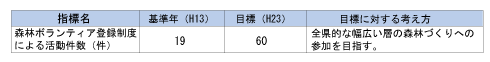
 |
 |
| 足尾の山の植林活動 |
河川清掃活動 |
|