重要なお知らせ
ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 住まいの相談について > 住宅のリフォームについて
更新日:2014年8月20日
ここから本文です。
住宅のリフォームについて
☆ 「安心してできるリフォーム」・「満足できるリフォーム」のポイントを紹介します ☆
最初に、『悪質な訪問販売をめぐるトラブルを防ぐには』どうしたらいいでしょう?
- 悪質な業者特有の巧みな口調やセールステクニックにだまされないようにする。
- おかしいなと思ったらはっきりと断わる。
悪質な訪問販売の実例
(1) 執ような訪問営業
- 頼みもしないのに、突然やってきて、断わっても何回も来訪。
- 勝手に工事図面まで持ってきて執ように契約を迫る。
(2) モニター大幅値引き中
- 自社製品による外壁のリフォームをすすめ、「いまなら期間中でモニターになれば費用は半額にする」と誘う。
(3) 不必要なサービス
- 屋根の改修工事の訪問販売なのに、「いま契約すれば玄関ドアの取替えをサービスする」ともちかける。
(4) 不安をあおる
- 「無料で耐震診断をします」といって上がりこみ、「補強が必要。修理をしないと地震のときに倒れる」と不安をあおられ、法外な額で契約させられたが、そもそも不要な工事だった
※販売目的を隠して消費者に接近する「点検商法等」への対策として、販売目的の訪問であることをまず明示することが法律で義務付けられました。
(5) 強引な契約方法
- 「今日中に契約したら半額。明日なら通常価格になる」と言い張り、午前零時まで居座られた。
もし契約してしまったら・・・
訪問販売による自宅での契約は、契約から8日間以内なら特定商取引法によって解除(クーリング・オフ)することができます。8日間以内であれば工事着手後でも解除できますが、手続きが複雑になるため、クーリング・オフ期間中は工事に着手させないようにしましょう。
長時間にわたる居座りなどによる強引な契約は消費者契約法によって取り消すことが可能です。県の消費生活センターや最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。
栃木県消費生活センター TEL 028-625-2227
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
(栃木県庁 本館7F くらし安全安心課内)
宇都宮市消費生活センター 028-616-1547
足利市消費生活センター 0284-73-1211
栃木市消費生活センター 0282-23-8899
佐野市消費生活センター 0283-61-1161
鹿沼市消費生活センター 0289-63-3313
日光市消費生活センター 0288-22-4743
小山市消費生活センター 0285-22-3711
真岡市消費生活センター 0285-84-7830
大田原市消費生活センター 0287-23-6236
矢板市消費生活センター 0287-43-6755
那須塩原市消費生活センター 0287-63-7900
さくら市消費生活センター 028-681-2575
那須烏山市消費生活センター 0287-83-1014
下野市消費生活センター 0285-44-4883
上三川町消費生活センター 0285-56-9153
芳賀地区消費生活センター 0285-81-3881
壬生町消費生活センター 0282-82-1106
野木町消費生活センター 0280-23-1333
那須町消費生活センター 0287-72-6937
那珂川町商工観光課 0287-92-1116
☆ 悪質な訪問販売の事例が「国民生活センター」のホームページ『悪質な「訪問販売に(外部リンク) よるリフォーム工事」にご用心』(外部リンク)に掲載されていますのでご覧ください。
1 リフォームの進め方
(1) 情報収集
- リフォームする部分を決める
- 必要な情報を集める
- 法律や規約などを調べる
(2) プランの検討
- 住まいの構造を知る(在来構法なのか、ツーバイフォーなのか など)
- 設備機器の適正な組み合わせを確認する
- 耐震性、省エネ性、バリアフリー対策など将来への備えについても考慮する
(3) 資金計画
- 大まかな見積りなどをもとに工事費の目安を把握する
- 固定資産税などリフォーム後の税金面の負担を確認する
(4) 事業者選び
- リフォームの工事内容にあった事業者を選ぶ
- 事業者選びは相見積りを取るなど慎重に行う
- 事業者の中に資格を持っている人がいるかも大きな目安になる
※ リフォームに関する代表的な資格
・ 増改築相談員(栃木県内に162人/全国で約13,400人)※公開希望者のみ
住宅建築の実務経験が10年以上のベテランの方で 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが企画したリフォームに関する専門の研修をうけ、考査に合格、登録した方です。
・ マンションリフォームマネージャー(栃木県内に5人/全国で約1,300人)※公開希望者のみ
マンションの特性とその制約を踏まえたプランの提案や、工事にあたって管理組合や施行業者に対して適切な指導・助言を行ないます。財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行なう試験に合格し、登録した方です。
(5) 見積り
- 項目ごとに材料や人件費などが出ているかを確認する
- 指定した製品が記入されているかを確認する
- 不明な点は納得がいくまで確認する
(6) 契約
- 必ず契約書を取り交わす
- 工事金額、工期、引渡し期日などを確認する
- トラブルが生じたときに必要な約款の規定を確認する
(7) 工事中
- 着工前には近隣へのあいさつを忘れずに行う
- 現場を見学し、進捗状況を確認する
- 工事内容の変更・追加があったときは書面で確認する
(8) 工事完了後
- 引渡し前に工事内容や使い方などを確認する
- 竣工検査は事業者とともに行なう
- 工事完了・確認書を取り交わし、きちんと保管する
2 リフォームのポイント
(1) リフォームのイメージ
・ メンテナンス
年月がたち、いたみが出てきた箇所の修繕、改修
(屋根のふき替え、外壁の塗り替え などが代表的)
・ ライフステージへの対応
家族構成の変動や高齢化などに伴う増改築、改修
(間取りの変更、部屋の追加、バリアフリー化 など)
・ グレードアップ
住まいの性能や快適性を高めるためのリフォーム
(設備の更新・新設、省エネ性能を高める改修 など)
(2) 注意したい法律について
・ 建築確認申請が必要か?
増改築などのリフォームを行なう場合には、地方公共団体や民間の指定機関に建築確認申請を行なう事が必要な場合があります。
・ 建ぺい率、容積率を超えないか?
地域ごとに定められた数値や隣接道路の幅員によって、建ぺい率、容積率が決まっています。リフォームで増築する際にもこの範囲に収まっていなければなりません。
・ マンションでは区分所有法にも注意!
マンションは専有部分と共用部分に分かれており、共用部分は勝手にいじれません。リフォーム工事をするときには、管理規約などを確認し、管理組合の承認を得ましょう。
・ シックハウス対策について
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるための規制を導入した建築基準法が平成15年7月に施行されました。
ホルムアルデヒドに関する建材の規制、換気設備の設置
クロルピリホス(シロアリ駆除剤)の使用禁止
・ 廃棄物の処理について
廃棄物処理法等に基づき、リフォーム工事から出た廃棄物は、元請業者(排出事業者)が処理することになっています。見積りの際などに、「解体・廃棄物処理費」が消費者の負担になることが明記されているか注意しましょう。
※ 以上の点は、見積りの際、業者に確認しましょう。
(3) 住宅の性能アップについて
リフォームの際に、「耐震性能」、「省エネ性能」、「バリアフリー性能」、「防犯性能」を向上させて、安心や快適性、住宅資産価値のアップについても検討してみましょう。
☆ 住宅性能向上のポイント
・ 現在の性能を把握する
設計の前に、現在どの程度の性能なのかを把握する。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略称:品確法)に規定された「住宅性能表示制度」では、既存住宅の性能表示ルールが定められ、住宅性能を測る「ものさし」が整備されています。こうしたルールを基に、現状を客観的に把握した上で目指す性能を設定することが重要です。
・ 性能の目標・ニーズを決める
現在の性能や家族のニーズを踏まえて、どの程度性能を向上させるか目標を設定する。
・ 目標に沿ったリフォーム計画を立てる
設定した目標を実現するため、リフォーム計画を立て、設計をすすめていく。
☆ 住宅性能の概要・リフォームの考え方
・ 耐震性能
わが国は、頻繁に地震の起こる”地震大国”です。震災は災害の中でも予想がつきにくく、家屋の倒壊などによる被害は甚大です。
地震はいつどこで起きるか分かりません。現在住まわれている住宅の耐震性能をしっかり把握し、適切な耐震補強を行なうことが必要です。
※構造の耐震性については、住宅性能表示制度で評価基準が定められています。その他、木造戸建住宅では 財団法人 日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の診断方法が広く用いられています。リフォームの際に、耐震性能を確認してはどうでしょうか。
・ 省エネルギー性能
「夏涼しく、冬暖かい家に住みたい・・・」 このために利用されるエアコンや床暖房には電気や石油等のエネルギーが必要です。住宅本体(構造躯体等)にエネルギー消費を少なくする対策を施せば、冷暖房等で制御する必要も少なくなります。このエネルギー消費を抑える対策の度合いが「省エネルギー性能」といえます。
※住宅性能表示制度においては、新築住宅を対象として評価基準が定められていますが、既存住宅でも竣工時の図面があり、断熱仕様等がわかる場合は、新築住宅の基準を準用し評価することも可能で、リフォームの際の参考情報としては有効です。
・ バリアフリー性能
日本は、世界有数の長寿国です。加齢、病気、怪我などにより身体機能が低下すると、歩行、立ち座りなど日常動作が負担に感じられ、転倒などの思わぬ事故に遭う恐れがあります。住み慣れた住宅で安心して暮らすためには、段差の解消や手すりの設置などバリアフリー化を進めることが重要になります。
※住宅における高齢者への配慮については、住宅性能表示制度で住宅の新築・既存を問わず評価を受けられます。リフォームの際には、まず、住宅の現状の使い勝手や家族のニーズに応じてリフォーム後の各部の性能を設定していくことが、有効です。
※国土交通省では、高齢者が居住する住宅において、加齢等に伴って心身の機能の低下が生じた場合にも、高齢者がそのまま住み続けることができるよう、一般的な住宅の設計上の配慮事項等を示した「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(PDF:4,441KB)を定めていますので、参考にしてしてみてください。
こちらも併せて、ご覧ください。
住宅のバリアフリーについて(住まいの情報発信局)(外部リンク)
・ 防犯性能
平成25年の住宅への侵入盗は約5万7千件となっています。
犯罪被害に遭わない普段の心がけに加え、住宅の防犯性を高め、泥棒に侵入されにくい住宅にすることが重要です。
侵入盗の大半は周囲の見通しが良かったり、侵入に手間取る家は避けるそうです。防犯リフォームは部分的に行うのではなく、住まいの中で防犯性の低い箇所を把握したうえで、その全ての防犯性を高め、泥棒が侵入しにくい住宅にすることがポイントです。
3 業者選びのポイント
- 最初は3~5社程度をリストアップする。複数の業者から見積りを取る「相見積り」で比較検討して、最終的に1社に絞り込む。
- 業者の住所を確認する。事業所と現場の距離は車で1時間以内が目安。対応がしっかりしているか、実際に行って確かめる。
- リフォームについて経験豊富で実績のある業者で、資格を持ち、専門業者の団体に加盟しているか確認する。
- 依頼する工事内容が業者の得意分野で、これまでの実績を喜んで見せてくれる業者であれば最適。
- 自社内に施行管理の体制があり、工事保証など施工後のフォローも十分に行なっていれば、工事後も安心できる。
- 明朗会計が一番。内訳明細がきちんと書かれた見積書でなければ、誠実な業者とはいえない。
4 見積書について
(1) 相見積りを取るときの注意点
- 各業者に同じ条件、希望を正確に伝えること
- 相見積りを取ることを業者に伝えること
- 提示された見積りを他の業者には見せないこと
(2) 相見積りの内容をチェック
- 見積り内容が、条件、希望にあっているかチェックすること
- 単価がわかりにくく「○○工事一式」と記載されているものは注意すること
- 総額だけを比較するのではなく、工事内容もチェックすること
(3) 次の見積書(例)について
- 「摘要(仕様)」欄に、希望した銘柄、仕様のものが使われているか
- 「単価・数量・時間等」欄で、「一式工事」でないと表現できない項目もあるが、数量や単価を出せるものが、「一式」になっている場合は注意すること
- 諸経費として記載がある場合は、どのようなものが含まれるのか確認する
- 廃棄物の処理方法や、費用について確認しておく
- 有効期限は、通常1ヶ月程度なので、あまり短期間が書き込まれていたら注意する
5 契約書について
(1) 次の契約書(例)について
- 住宅リフォーム工事請負契約書:発注が決まったら工事規模の大小に関係なく、必ず契約書を交わしておく
- 工期:工事開始のどのくらい前から受け入れ準備が必要かを確認する
- 請負者名:訪問業者によるリフォームの場合などは、しっかりと確認する。念のために、会社の登記簿謄本があれば、なお安心できる
- 請負金額:請負金額以外に、別途費用がかからないことを確認する
- 添付書類:見積書のほかに、「住宅リフォーム工事打ち合わせシート」と「住宅リフォーム工事請負契約約款」の2つの書類も必ず添付する
- 支払方法:高額の場合は分割して支払うのが一般的
6 工事完了・確認書について
※各書式(例)の詳細については、住宅リフォーム推進協議会(外部リンク)のホームページを確認してください。
【参考】
『平成17年度 住宅リフォーム実態調査』(抄 戸建て住宅) 住宅リフォーム推進協議会(外部リンク)
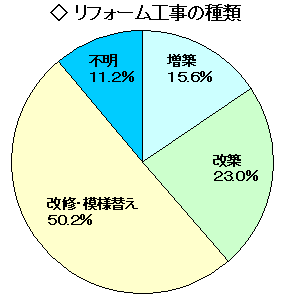
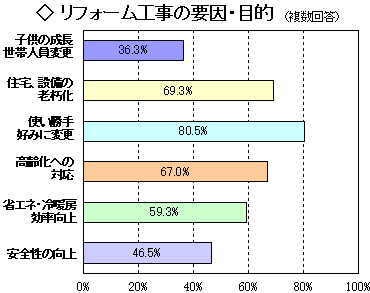
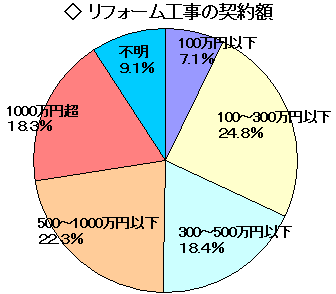
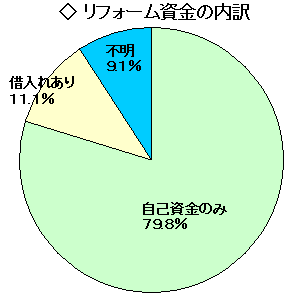
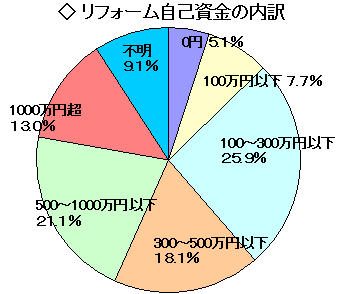

お問い合わせ
住宅課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2482
ファックス番号:028-623-2489