|
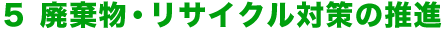
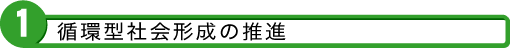
1 推進体制の整備
廃棄物による環境への負荷を軽減するためには、廃棄物の発生を抑制するとともに、ものを再使用したり、再生利用していく循環型社会を形成することが重要です。
県では、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、各部局が一体となった「栃木県循環型社会推進本部」を12年度に設置しました。
さらに、循環型社会の形成に向け広く県民の意見を各種施策に反映させるため、学識経験者・消費者・事業者等で構成する「循環型社会推進懇談会」を13年度に設置しました。
2 循環型社会推進ビジョンの策定
循環型社会形成の基本原則、役割分担、政策手法などを明示した「栃木県循環型社会推進ビジョン(仮称)」を策定することにし、13年度には策定のための基礎調査を実施しました。
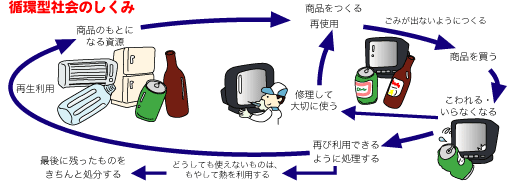
3 廃棄物処理計画の策定
県における廃棄物の減量と適正処理のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、一般廃棄物と産業廃棄物をあわせた廃棄物全般についての処理計画を13年度に策定しました。
(1) 計画期間
計画期間は、13年度を初年度として22年度を目標年度とする10年計画とし、中間年度である17年度に、それまでの実績を踏まえて見直しを行うことにしました。
なお、廃棄物処理施設の整備など中長期的な課題については、20年後も視野に入れた計画としました。
(2) 計画目標
県の将来人口、経済成長率の見込みや近年の排出動向に基づき、将来の排出量を予測し、これに対して、現状の減量水準、県民・事業者の減量努力、各種リサイクル法、必要な処理施設の整備動向等を踏まえ、以下のとおり減量目標を設定しました。
|
廃棄物処理計画の概要
○排出量の見込み
・生活系廃棄物 (平11) 54万t → (平22予測量) 55万t(+ 2%)
・事業系廃棄物 (平11) 339万t → (平22予測量) 421万t(+24%)
○減量目標(目標年度 平22)
△排出量を10%削減
・生活系廃棄物 (平22予測量) 55万t → (平22目標量) 50万t(△10%)
・事業系廃棄物 (平22予測量) 421万t
→ (平22目標量) 379万t(△10%)
△最終(埋立)処分率を半減
・一般廃棄物 (平11) 12% → (平22) 6%
・産業廃棄物 (平11) 9% → (平22) 5% |
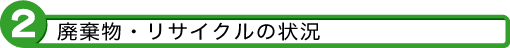
1 一般廃棄物の状況
一般廃棄物は主に家庭から出されたごみとし尿からなり、ほとんどが市町村などの処理施設で処理されています。12年度の本県のごみの排出量は約76万tであり、うち約73万t(96.2%)が市町村などで処理されています。
ごみ処理に要した年間の経費は約384億円で、その内、建設・改良費が約182億円、処理・維持管理費が約194億円となっています。
資源化が可能なごみについて、自治会などによる集団回収が約2万9千t、市町村などによる直接資源化が約4万t、市町村などの清掃工場における資源化が約6万9千tと、年間約14万tがリサイクルされています。
し尿(浄化槽汚泥を含む)の排出量は約50万sで、大部分(99.9%)が市町村などで処理され、残りが自家処理されています。
2 産業廃棄物の状況
産業廃棄物は、農業、建設業、製造業などの事業活動に伴って出される廃棄物であり、排出事業者が適正に処理する責任を負っていますが、一部には不適切な処理の事例も見られます。
12年度の県内の産業廃棄物の推計総排出量は約733万tであり、種類別にみると動物のふん尿が約306万tで最も多く、次いで汚泥が約244万tとなっています。
産業廃棄物の最終処分率は、再使用や再生利用による排出抑制や減量化が促進されており、ほとんどの種類で10%未満となっていますが、廃プラスチック類は28.2%、ガラス・陶磁器くずは18%と高くなっています。
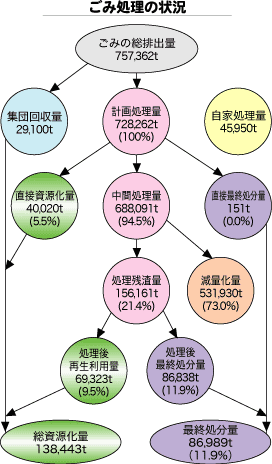
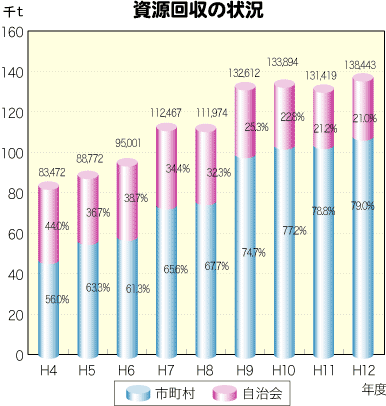
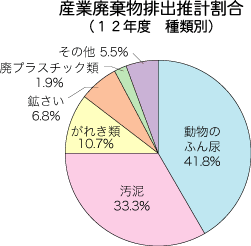
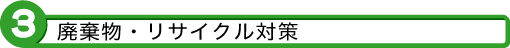
1 一般廃棄物対策
一般廃棄物の種類と量の増大に対応するためには、処理施設の整備促進と維持管理の充実、ごみ減量化・リサイクルの推進が重要です。
そのため、クリーンアップフェアなどのイベントやリサイクル演劇の開催、買い物袋を持参してレジ袋の削減を目指すマイ・バッグ・キャンペーンなどの普及啓発事業を実施しています。
また、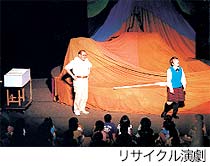 ごみ処理施設から出されるダイオキシン類を削減するために、燃焼管理の徹底や施設改造について市町村等を指導するとともに、「栃木県廃棄物処理計画」により、ごみ処理施設の広域的な整備を進めています。 ごみ処理施設から出されるダイオキシン類を削減するために、燃焼管理の徹底や施設改造について市町村等を指導するとともに、「栃木県廃棄物処理計画」により、ごみ処理施設の広域的な整備を進めています。
一方、各市町村では、「容器包装リサイクル法」に基づき、空き缶やガラス瓶、ペットボトルなどの分別収集が行われています。
2 産業廃棄物対策
廃棄物の排出事業者や処理業者に対して研修会の開催や事業 場などへの立入検査により、再生利用の促進、適正処理の指導・監視を行っています。 場などへの立入検査により、再生利用の促進、適正処理の指導・監視を行っています。
また、市町村と協力して不法投棄や不適正な処理を防止するための監視パトロールを実施するとともに、産業廃棄物処理施設周辺整備事業等により、処理施設の整備促進に努めています。
|